
【AIのべりすと文学賞】5分後に探偵未遂
ということで、拙宅の「5分後に探偵未遂」が受賞しました。(優秀作品賞)
やっぱり受賞作読んでみたいじゃないですか。AIが書いた話ってどんなの???って。
「5分後に探偵未遂」は短編連作で、一話完結型でどこからでも読める形式です。
なので一話ぐらいネット公開してもいいかなーと思っていて、某所と色々連絡とってたら「いいよ」と言われたので、2話の「狂気は耳から摂取してください」を公開します。
それではどうぞ。

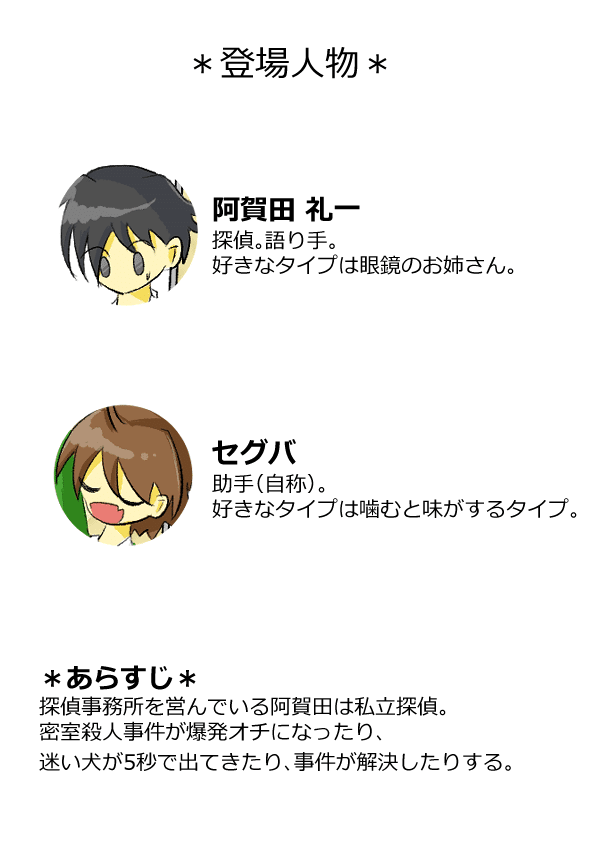
▼2話「狂気は耳から摂取してください」
俺の名前は阿賀田礼一。探偵だ。
コイツの名前はセグバ。俺の助手みたいなものである。今回、俺たちは激ヤバの依頼を受けていた。
「それは……ヤバいですね」
開口一番、セグバがそう言った。セグバは緑のコートと赤いネクタイ、白い手袋をはめており、素肌を全く外に表していない。こう見ていると、コイツの方が探偵のように見える。
「そう、ヤバいんです。私は心配で、夜しか眠れません」
そう呟いた依頼人の女性の眼の下には隈が……ない。いたって健康そうである。
「そんなヤバいことがアパートの隣の部屋で起きたので、夜ちゃんと眠れてるんですか。すごいですね」
セグバが感心したように言った。
「おい、セグバ、ちょっとどけ」
俺は、ソファーの真ん中に陣取って依頼人の話を聞いていたセグバを脇にどかした。
依頼人がちょっと不思議そうな顔をする。なので俺はこう説明してやった。
「私が阿賀田探偵事務所の阿賀田礼一です」
「あら! てっきりこの方が探偵の方なのかと」
「コイツは居候……いや、助手です」
そうして、俺は早速本題に入った。
「ところで、笠峰さん。この依頼は、証明がとても難しくなると思います」
「証明が難しい、ですか?」
「そうでしょう。『隣人が自殺した原因を調べてくれ』だなんて」
俺はため息をついた。こんな依頼、聞いたことがない。
「例えば、アパートの隣人の自殺原因が『精神衰弱』であったとしましょう。この場合、我々はどうやってこの証拠を持ってくればいいんですか?」
「ううん……」
依頼人の笠峰さんは唸った。
「そもそも、『精神衰弱』という定義が難しいですよね。仕事のし過ぎが原因だとすると、直近の労働時間を調べればいいんでしょうか」
「うーん」
笠峰さんは眉間にしわを寄せた。そして、続けてこう言った。
「じゃあ、自殺の原因が『発狂』だったら、それには原因があるはずですよ」
「発狂?」
尋ねた俺の声が裏返った。
「発狂って何ですか」
「つまり、自殺した彼女の頭が、いきなり『おかしくなった』場合です」
「そんなこと……あり得ます?」
「彼女が自殺するなんてありえません。だって、彼女には子供が生まれたばかりですし、旦那さんもイケメンですし、幸せいっぱいの時期のはずだったんですよ」
そうだろうか……? 子育て中って色々大変そうなイメージがあるのだが。
「イケメンの旦那さんは、妻の死について何か言っているのですか?」
「『もともと精神不安定で、最近はたまに言動がおかしかった』と言っているんです」
「具体的には、どういう言動です?」
「何もないところで話始めたり、独り言をぶつぶつ言ったり、いきなり何かに怯える、とか……」
依頼人が、にわかに信じがたい話を話し出したので、俺は大きくため息をついた。これは面倒くさい依頼になりそうだ。
「わかりました、わかりました……ともかく、あなたの依頼は引き受けましょう。ただし!」
俺は大きく息を吸った。
「まともな成果が出るとは思わないでくださいね」
***
依頼人を玄関まで見送った後、俺は事務所の応接間に戻った。
「さて、どうするか……」
俺は腕を組んだ。
「調査開始といこうじゃないか、阿賀田くん」
セグバが得意げに言う。
「ああ、そうだな。まずは現地に向かわないと……ってなんなんだよその口調」
「一回やって見たかったんですよ、探偵の役」
「依頼人が困惑してただろ。二度とやるなよ」
「わかりました。面白かったので、ほとぼりが冷めたらまたやります」
「はぁ……」
俺は溜息をついた。
「しかし、妙な事件だよな」
「滅茶苦茶クトゥルフっぽい話ですよね」
「その例えやめろって。人が死んでるんだぞ」
「どう考えても、被害者がいきなり発狂したとしか考えられません」
「しかし警察も、その考え方のようだな。被害者が何らかの精神不安定に陥った、と……」
俺は手に入れた資料をめくった。
事件のあらましはこうである。
被害者の名前は城所久理子。彼女は三日前、突然アパートから身を投げて自殺をした。しかし、その挙動が尋常ではなかったという。
彼女は夕方の六時ごろ、駅のホームで電車待っていたらしい。しかし、その場でいきなり『発狂』したのだ。駅のホームでブツブツと何かを呟いていたのだが、突然大きく目を見開き、いきなり甲高い声で叫び始め、駅の線路に侵入した。
そのまま柵を乗り越え、目の前にあるマンション突入していくと……階段を上りまくり、突然六階から飛び降り自殺をした。結果は即死。彼女には幼い子供と、イケメンの旦那が残された。
「妙な事件ですね」
セグバが唸った。
「まるで、この世ならざる神話生物でも見てSAN値チェックが入って発狂したみたいじゃないですか」
俺は未だにクトゥルフの話題を出してくるセグバを無視することにした。
「彼女、カウンセラーにもかかっていたようだな。そこまで重度ではないものの、何らかのメンタル不調を抱えていたらしい」
俺は資料を見ながら呟く。
「産後の女性って自殺率高いですからね」
セグバが無感情に言った。まるで降水確率を読み上げているようである。
「……ともかく。この事件、どこから調べる? というより、依頼人をどうやって納得させる?」
正直この依頼、滅茶苦茶やりにくい。被害者が心療内科通院していた証拠のコピーを入手し、依頼人に見せるだけでもいいだろう。
「しかし……なんか引っかかるんだよな」
俺は資料を見ながら頭をかいた。
「おっ、いいですね、そのポーズ。探偵っぽいです」
セグバが茶々を入れた。
「探偵だからな」
「で、どこが気になるんです?」
「まず……なんで発狂した彼女が、わざわざマンションに上ったのか、だ」
俺が言うと、セグバが言った。
「『高いところに上りたくなる』一時的発狂が起こったんじゃないですか?」
「だからクトゥルフと一緒にするんじゃない」
「一時的発狂に陥ったことには間違いないじゃないですか」
セグバが口をとがらせる。
「わかったわかった、お前の言う『一時的発狂』が起こったとしよう。でも、彼女は電車のホームで電車を待っていたんだぞ。どうして彼女は、電車に飛び込まなかったんだ?」
俺が言うと、セグバはむむむ、と唸った。
「タイミングよく電車が来なかったんじゃないんですか?」
「この事件、例えば育児に疲れた女性が、思わず電車に飛び込んでしまった、ならまだわかるんだ。だけど、『女性がいきなり目の前のマンションに上ってそこから身投げ』って何かおかしくないか?」
「やはり現場を見に行くしかないですね」
コートを翻して立ち上がる助手に、俺はこう言った。
「仕切るな」
***
俺たちは、依頼人の住むマンションを訪れていた。すなわち、被害者が住んでいたマンション、そして飛び降りたマンションでもある。
「さて……」
俺は辺りを観察した。よくある、普通の高層マンションだ。ここは八階で、かなり地上から距離がある。目の前には『笠峰』と書かれた表札と、『城所』と書かれた表札がある。
「どうですか、阿賀田さん。周りの様子は。神話生物っぽい気配は感じます?」
「いや……特に何も感じないが」
答えながら、俺は『神話生物っぽい気配』って何だろう、と思った。
「とりあえず、犠牲者の旦那さんの話でも聞いてみましょう」
「いや待て、取り合ってもらえるとは……」
止める間もなく、セグバはインターホンを押していた。
ピンポーン。
『はい、城所です』
イケメンボイスが帰って来た。
「もしもし? 私達、阿賀田探偵事務所のものなんですが……」
『探偵事務所!? 帰ってください!』
ガチャ。
「……。」
もっとやり方あっただろ。貴重な選択肢の一つを潰されてしまった俺は、セグバを冷たい目で見た。
「これがホントの門前払いって奴ですね。わっはっはっは」
ニコニコとほほ笑みながら落ち込んで見せるという芸当をセグバはやってのけた。
さて、これからどうしようか。
俺が考えあぐねていると、アパートの廊下の向こうから女性がやって来た。
買い物袋にネギが刺さっているところを見ると、買い出しから帰って来た途中らしい。
「あっどうも! こんにちは!!」
止める間もなく、またセグバが声をかけた。
「こ、こんにちは……?」
女性が驚いたように返した。
「ネギが特売でしたか?」
「い、いえ、ネギは特売ではなかったですけど……」
「ところで話は変わりますけど、最近この辺で神話生物を見ませんでしたか?」
「は、はぁ……?」
「すいませんこいつが」
俺はセグバを押しのけて、頭を下げさせた。
「実は私達、こういうものです」
俺はネギをぶら下げたお姉さんに、自分の名刺を差し出した。
「阿賀田……探偵事務所……?」
「実は先日亡くなった、城所さんについて調べているのです」
「あっ……あの城所さん……!?」
俺が犠牲者の名前を出すと、お姉さんは幾分か警戒したようだった。
「ほーらー、警戒されちゃったじゃないですか!!」
セグバが横から茶々を入れてくる。
「こういう時は、雑談から入るのが捜査の鉄板なんですよ」
聞き込み調査中にその台詞を言うな。
「お前は別の方向性で警戒されてたからな」
「ええ? 私は警戒なんかされてませんよ?」
俺たちが漫才……いや、会話をしていると、お姉さんは困惑したようだった。
「あ、あの……何について聞きたいんですか?」
どうやら質問には答えてくれるらしい。俺はホッとした。
「お姉さんもお忙しいでしょうし、一人三つずつ質問させてください」
「わかりました。三つですね」
お姉さんは頷いた。しかし俺は首を傾げた。……何で質問数に制限がかけられてるんだ?
「こちらは二人ですから計六つですよ。では、まず私から……」
セグバが進み出た。
「今日の夕飯のメニューは何ですか?」
「鍋です」
「何鍋ですか?」
「豚鍋です」
「いいですね! とってもおいしそうです! さて、これで質問は二つ消費されましたので、あと一つです」
セグバがドヤ顔でこちらを向いた。ふざけるな、こいつわざとやってるのか。
「では最後の質問なんですが、被害者が自殺時刻は夕方の六時ごろ。つまり彼女が駅のホームにいた理由は、夕飯の買い出しに出かけるためだったんですね?」
「は、はい、そうです。このマンションの近くには手ごろなスーパーがないもので……ここの住民は買い出しに電車を利用するんですよ。ちょっと面倒なんですけど」
ようやくまともな質問が出てきたので俺は少し感心したが、セグバがドヤ顔でこちらを見てきたので感心するのをやめることにした。
「どうですか?」
「どうって、なんだよ」
「つまり、当日の被害者の行動パターンはですね。家に帰宅し、荷物を置いて、子供の様子を見た後、また買い出しに出かけて、ホームで電車を待っていた後、いきなりマンションに上って身投げをしたということなんですよ」
「うん……まぁ、まとめるとそうだな」
俺は頷いた後、素朴な疑問を口にした。
「じゃあ、当日、子供の面倒は誰が見ていたんだろう」
「あ、旦那さんですよ」
女性が答えてしまった。
「あの日、旦那さんの帰宅が早かったみたいで。旦那さんが子供を見ている間に、彼女は買い出しに出かけたみたいなんです」
「あー……なるほど。ありがとう」
事件とは関係ないところで、貴重な質問枠を消費してしまった……俺がちょっと落ち込んでいると、セグバが「果たしてそうでしょうかねえ」といった目でこちらを見ていた。
俺は質問を続けることにした。ちょっと考えた後、俺はこう切り出した。
「城所さんはご夫婦二人暮らし、いえ、子供がいるから三人暮らしなんですよね?」
「あ、はい。そうですけど……」
「ちなみに、息子さんの名前は?」
「確か、幸太郎君……だったかな。そろそろ一歳になる子で、夜泣きがすごかったですね。最近はだいぶ収まってきましたけど」
「はい、これで質問は終了です」
セグバが両手をポン、と叩いた。
「え!? なんで!?」
「① 子供の面倒は誰が ②家族は三人暮らし ③息子さんの名前は幸太郎。以上です!!」
「いや!? 嘘だろ!?」
俺は叫んだ。何なんだ、このひねくれたランプの魔人みたいなカウントの仕方は。
「ご協力ありがとうございました!」
セグバがぴょっこり頭を下げると、お姉さんは軽く笑って、マンションの自分の部屋へと戻って行った。あああ。貴重な情報源が……。
「ちなみに、私が三つの質問で得た質問は、①お姉さんの夕食は鍋 ②具材は豚、です」
セグバが二本の指を立てた。
「三つ目は!? 三つ目はどうしたの!?」
俺が尋ねるとセグバは三本目の指を立てた。
「③事件当日、幸太郎君の面倒は旦那さんが見ており、被害者は買い出しのために駅に出かけた、です。」
俺は唸った。
「今の情報、本当なんだろうな」
「そう/たぶんそう」
「何なんだよその答え方は!!」
もういい。コイツの相手をしているのは疲れる。俺は助けを求めるように、マンションの外を眺めた。八階からは、街並みと夕暮れがよく見える。……そういえば被害者の自宅は八階なのに、飛び降りは六階からだったんだな。
「さて、これからどうします? 被害者宅にピンポンしまくります?」
セグバがピンポンダッシュのポーズをしたので、俺はたしなめた。
「やめろよ。さっき嫌がられただろ、探偵が来たって」
……あれ? 俺は引っかかった。何であの旦那さんは『探偵』と聞いて、あんなにも条件反射のように嫌がったのだろう。
職業柄、探偵は嫌がられることは多いが、大抵が捜査の途中だ。例えば、浮気調査とか……。……。浮気……?
俺の思索は、セグバのはしゃぎ声によって中断された。
「見て下さい!! あそこのマンション、屋上にプールがあるみたいですよ! いいですねー、夏になったら泳ぎに行きましょうか!」
「……お前は本当に自由だな」
俺は大きくため息をついた。
「こちら側からだと駅は見えないですね! 反対側にあるんでしょうか」
「ふむ……じゃあ、次は駅に行ってみるか」
***
俺たちは駅に辿り着いた。といっても、マンションからすぐ近くの駅なので、徒歩五分もすればついてしまった。しかし駅に人気はあまりない。郊外の駅にはありがちなことであるし、ちょうど電車が行った後だったらしい。
「うーん、これなら聞き込みも楽かな」
「あ、そうだ。私、こういうもの持って来ているんですよ」
セグバはそう言うと、バッグから紙切れを取り出した。
「なにそれ」
「これはですね。探偵の必需品である、被害者の写真です!!」
俺、そういうのは事務所に置いてきたと思ったんだが。
「……なんでそんなものを……?」
「この写真を、駅ホームの広告掲示板に貼っておきますね」
「…………はい?」
「よし、これで完了です。あ、ついでに、駅員さんにこの貼り紙のことを聞いてみましょう」
「いやいやいや、ちょっと待て」
俺はセグバを止めた。
「なんです?」
「なんでそんな回りくどい方法するんだよ」
「ほら、だってインタビュアーに警戒されるじゃないですか、警戒」
「だからってわざわざこんな回りくどいやり方しなくてもいいだろ」
「まあまあ、ちょっとだけ試してみたんですよ。それでダメだったら別の方法を探せばいいだけですし」
「……はぁ」
俺は小さくため息をついて、セグバの後を追った。本当にこいつは自由だな。
「すいませーん、少しよろしいですか?」
「は……はい?」
警戒するように振り返ったのは、メガネをかけた若い男性だった。
「あの、この張り紙について、何かご存じないでしょうか? 最近貼られたものだと思うんですけど……」
「えっと……ちょっと分からないですね……」
「そうですか。ありがとうございます」
セグバはぺこりと頭を下げた。そして俺の方に戻ってくると、こう尋ねてきた。
「どうでした? 私の聞き込み捜査術」
「いや、あのさ……突っ込みたいことは色々あるんだけど……」
俺はこめかみを押さえながらつぶやいた。
「諦めるの早いな、お前」
「人生引き際が肝心ですからね!」
セグバが胸を張った。そこ、威張る所じゃないだろ。
「さあさあ、阿賀田さんもやってくださいよ、聞き込み調査」
「ええと……そうだな……」
俺が目を付けたのは、ベンチに座っているおばあちゃんだった。
「あの、すいません。少しお話聞かせてもらえますか?」
「あら、いいわよ。どうしたの?」
あっさりと承諾を得たことに安心したが、俺は被害者の写真を手元に持っていない。なのでしぶしぶ、俺はセグバと同じことをすることにした。この調査方法、絶対間違ってるだろ。
「実は、あの張り紙が気になってまして」
そう言って、俺は掲示板に貼られた被害者の写真を指さした。
「ああ……あの子ね。先週の事件でしょう? 知っているわよ。」
おばあさんは言った。
「旦那さんも可哀そうなことよねえ。聞いたわよ、旦那さん、今でも夜な夜な歩き回っているらしいわよ。本当に可哀そうなことで」
「夜な夜な歩き回っている……?」
俺は眉をひそめた。
「奥さんの落下地点を、ですか?」
「ええ、かなりの範囲を歩いてるのよ。お隣さん、怖かったって言ってたわぁ、だって真夜中に、尋常じゃない表情の旦那さんが歩き回ってるのよ」
話が長くなりそうなので、俺は話に割って入った。
「……その場所は分かりますか?」
「あの、ちょっと待ってちょうだいね。地図を描いてあげるから」
おばあさんはバッグの中から手帳を取り出すと、サラサラとペンを走らせ始めた。
「……よし、出来た。はい、これが場所よ」
「ありがとうございます」
俺とセグバは礼を言った。
「あれ……だいぶ広範囲を徘徊しているんですね」
普通なら一か所で追悼したり、花を供えたりするようなものだが、どうやら旦那さんが徘徊している地域は50m~100mぐらいの範囲のようなのだ。
「なんでこんな広範囲を」
「きっとアレよ」
おしゃべり好きなおばあさんは、声を潜めてこういった。
「落下はすごい衝撃だったから。きっと、遺体の一部が見つかってないに違いないわ。旦那さんはそれを探しているのよ」
***
「ホラーめいてきましたね」
「ホラーだな」
俺たちは頷き合いながら、最後の場所に向かっていた。この場所に最も造詣が高いであろう人物、駅の職員がいる場所である。
と言っても、職務中の職員が、ただの探偵である我々に取り合ってくれる気はしない。なので気は引けるが、こうやって切り出すことにした。
「あのー……すみません」
改札口の所で暇そうにしている駅員に、俺たちは声をかけた。平日の夕方から成人男性二人が仲良く散歩しているのを見て、駅員は「こいつら暇そうだな」という顔をした。
失敬な。我々は暇そうに見えるかもしれないが、暇ではない。つまり、我々はお互いがお互いを「暇そうだな」と認識したわけである。
この間わずか0.5秒、俺は話を切り出した。
「改札の掲示板に、なんか変な写真が張られてるんですけど」
もちろん、さっきセグバが張った被害者の写真のことである。
「それって私が……」
何か言いかけたセグバの足を、俺は踏み潰した。
「駅構内に、許可された掲示物以外を勝手に貼る行為は禁止されています。……ちょっと見てきましょう」
犯人がセグバとは知らず、駅員はホームへ移動した。
「ああ、この人は……」
駅の掲示板に貼られた写真を見て、駅員は何かを思い出した顔をした。これはチャンスだ。俺は畳みかけることにした。
「何か知っているのですか?」
「ええ。この方、不審な飛び降り自殺をした方ですよね? 実はその日、自分はこの駅に勤務中だったんです」
ビンゴ! 俺は心の中でガッツポーズをしながら、話を合わせる。
「飛び降り自殺……ですか?」
「はい。駅のホームには監視カメラがあるでしょう? 線路内に乗客が立ち入らないように見ているものなんですが……そこに映ったんですよ、この女性の顔が」
「どんな顔だったか、覚えてますか?」
「ええと……確か、髪の長い女性だったと思います。帽子をかぶっていたかもしれません。そして……何より、印象的だったのは」
「印象的なのは?」
「驚愕の表情をしていたことです。何かに驚いているような、慌てているような、ショックを受けているような……まあ、画質の悪い監視カメラ越しでしたし、もう録画データも残っていないわけなんですが」
駅員は言った。
「最初は、飛び込み自殺かと思ったんです。でも違いました。彼女は線路内に侵入し、柵を乗り越え、向かいのマンションに上り、そして身を……ああ」
駅員は悲鳴ともため息とも取れる声を発した。
「あなたも聞いたんですか? 宙に向かってブツブツと話す、被害者の姿を」
「え? 確かに宙に向かって話していたかもしれませんけど……」
駅員は何か言いたげだった。
「……何か問題が?」
「あれはハンズフリーの通話だと思いますよ」
駅員が言うので、俺たちはびっくりしてしまった。
「ハンズフリーの通話!?」
「ええ、最近はやりじゃないですか、ハンズフリー。イヤホンで音楽を聴いているときに通話がかかってきたら、耳に手を当てて、突然かかって来た通話の応答する……もっとも、彼女は買い物袋を下げていたせいで、耳に手を当てなかったようですが」
「なるほど、そのせいで、ブツブツと独り言を言っているように見えたのか」
俺が言うと、むむむ、とセグバが唸った。
「だとしたら、彼女は『何かを見た』のではなく『何かを聞いて』発狂したのかもしれませんね」
「両方かもしれないぞ」
俺はそう言って、ホームの黄色い線の内側に立った。
「被害者は、丁度ここに立っていたんですね」
「ええ、そこです」
俺が視線を上げると、ホームの向かいにはちょうど例のマンションが建っていた。ここからなら、各部屋のベランダがよく見える。洗濯物、植木鉢、誰か立っていればその姿を確認することもできるだろう。
「まったく、こんなところに犠牲者の写真を貼るだなんて悪趣味だ……では、ご報告ありがとうございました」
駅員は手慣れた手つきで、先ほど張られた写真を剥いだ。
「本当に悪趣味ですよね」
と悪趣味なセグバが言った。
「では、そろそろ列車が参りますので。失礼いたします」
「お仕事お疲れ様です」
仕事を増やした張本人がなんか言っているが、俺は突っ込まなかった。俺は、被害者も当日見ていたであろう景色を、じっと見つめている。
俺はその時、「それ」に気づいた。……そうか、そういうことだったのか。
被害者は、視覚からも、そして聴覚からもその『狂気』を摂取したのである。
ツッコミが入らないことが不満だったのだろうか、セグバが声をかけてきた。
「ツッコミはまだですか?」
「ボケてる自覚あったのか?」
俺が尋ねると、セグバは腕を組んだ。
「失敬な。私は愉快で真面目で歌って踊れる人間です」
俺は無視することに決めた。
「……それより、わかったぞ。この事件の全貌が」
「すごいです! やっぱり被害者は、この位置からヤバいモノを見て発狂したんですか?」
「ああ、そうだ」
「やっぱり神話生物的な何かです? でも今までの調べで、神話生物的な要素ありました?」
「彼女が事件当日に見たのは、旦那が探していたものだ。つまり……」
「あ、ストップですストップ」
俺が説明しようとすると、セグバが待ったをかけた。
なんで?
「ダメです、探偵たるもの、途中で披露しちゃ」
「は、はぁ?」
「だって証拠がないじゃないですか」
「これから証拠を『拾い』に行こうとしてるんだが……」
俺が言うと、セグバは見てそうとわかるほどはしゃぎだした。
「じゃあ、その証拠を拾ってから推理を披露しましょう!! さ、行きましょう!!」
「行きましょうって、どこへだよ」
「その、あなたが思う証拠品がある所へです!!」
セグバはレッツゴーのポーズをしているが、動き出さない。彼自身はどこに行けばいいのかがわからないだろう。
「うん……じゃあまず駅を出て、この前旦那が徘徊していた、マンションの付近へ行こう」
「そこに何があるんですか?」
「赤ん坊のパーツだ」
***
「ありました」
セグバの捜査力は一流である。警察犬かシャーロックホームズ並みに手先が器用で感覚が鋭い。ただし一般常識と倫理観と、適切なギャグセンスを持ち合わせていない。
「あなたが探していた『証拠』、これでしょう?」
セグバが差しだしたのは、赤ん坊の片腕だった。
形状はちぎりパンによく似ている。衣服は残っておらずセグバの手のひらに収まるサイズだ。どうやら室外機の後ろに挟まっていたらしく、少しだけ薄汚れている。
もちろん本物の赤ん坊の腕ではない。偽物だ。これは人形の腕なのである。落下の衝撃で、胴体部分から関節が外れてしまったのだろう。ちなみに、胴体部分はどこにも見当たらなかった。
「この腕が、被害者が目撃したもの……ですか?」
「ああ、間違いないだろう。そして、旦那が探していたものでもある」
俺が言うと、セグバはわからんと言った様子で首をひねった。
「どういうことですか? 旦那さんが、わざわざ赤ん坊の人形をベランダから落としたってことですか?」
「ここは、被害者の落下地点じゃない。少しズレてるんだ。そして、彼女の旦那が夜な夜なここを徘徊していた。これが意味することは分かるか?」
「……全然わからないです」
「被害者はあるものを見て、取り乱した。ある意味『発狂』だな。それがこれだったんだよ」
「もうちょっとわかりやすく説明してくれませんか?」
セグバって、実は滅茶苦茶頭が悪いのではないのだろうか。洞察力や推測力に欠けすぎている。いかにも探偵っぽい見た目してるのに。
「まだわかんないのか。これは自殺なんかじゃない。殺人事件だったんだよ。つまり……」
「あー、ストップストップ!」
突然、セグバが俺の口を突然塞いできた。
「場所を変えましょう。推理の披露はここじゃダメです」
***
セグバは、被害者宅のインターホンを押していた。
「もしもしー! 城所さんのお宅ですか???」
返事がないので、ドアをノックし、バカみたいにデカい声で叫ぶ。これじゃあ近所迷惑だ。
……。インターホンから返事がない。
当たり前だ。この前『探偵が来た』といって追い返されたではないか。
「嫌われてますね、阿賀田さん」
憐れむような眼差しで、セグバがニコニコとほほ笑んだ。
「……どちらかというと、嫌われているのはお前の方だと思うぞ」
「いいえ、この前旦那さんは、『探偵は帰れ』とおっしゃっていました。私は探偵ではありません。すなわち嫌われているのはあなたです!! ところで一体何をやらかしてそんなに嫌われたんですか?」
「やったのは俺じゃない。俺の同業者だ。」
「つまり?」
「浮気調査だ」
城所夫妻の仲は悪かった。旦那が浮気し、妻が疑う。よくあるパターンだ。旦那は浮気相手と一緒になるためか、とにかく妻の殺害をもくろむ。
犯人が自分だとバレてはいけない。そのために彼がとった方法は、『妻が発狂したように見せかける』ことだった。
「つまり、被害者宅のベランダに行けば、今回彼がつかったトリックわかるはずなんだ」
「なるほど、行きましょう」
そう言うとセグバは頷いて、もう一度チャイムを押してドアを叩きまくった。
「旦那さーーーん! 早く出てきてくださーーーい! もうトリックは割れてるんですよ!! あ、ところでトリックって何です?」
よくもまぁしゃあしゃあと聞けるな、お前。
「このままではラチがあきませんね」
次の瞬間、セグバはとんでもない暴挙に出た。ドアを破壊したのである。
俺の眼には、セグバが「べちっ」とドアを叩いたように見えた。しかしドアはフレームから外れ、ガコンと音をたてると、そのまま派手な音をたててアパートの廊下に倒れた。
「おや、これは立て付けの悪いドアですねえ」
唖然とする俺を尻目に、セグバはスマホを取り出した。
「あ、もしもし! 警察ですか? 実は、知人宅のドアを壊してしまいまして……はい……器物破損にあたると思います……はい、アパートの管理人にも連絡しておきます……はい、すぐにここにきてください」
セグバはポケットにスマホをしまった。
「さて、行きましょう」
何の躊躇もなく、セグバは被害者……そして犯人の自宅へと上がって行った。対する俺は、もうどうしようもない。慌てて後からセグバを追いかける。
「何つもりですか!! け、……警察呼びますよ!!」
奥の部屋から、イケメン男性が姿を現した。城所の旦那である。
「大丈夫です、もう呼びました」
セグバがそう言うと、旦那はびくっと首をすくめた。
「それよりも、あなたが探していたもの、見つけてあげましたよ」
セグバが赤ん坊の人形の腕を差し出すと、旦那は低く呻いた。
「そ、それをどこで……」
「このマンションの真下です。丁度、室外機の裏の隙間に挟まっていましてね。夜だと探しにくかったんじゃないですか?」
「ぐ……」
俺はセグバと旦那の会話を眺めていた。なにしてんのこいつ?
すると、セグバは俺に眼で促してきた。『早く続きの推理を』と言った感じだ。そう言えばセグバには、まだ推理の全貌を話していないのだった。
え? こいつ知らないくせにここまで強硬手段に出てるの? 大丈夫なの?
リビングルームはかなり生活感があふれており、片付けが間に合っていない子持ちの自宅を彷彿とさせる。脇にはベビーベッドがあって、そこですやすやと子どもが眠っているようだ。
ベランダの眼下にはあの駅が見えた。被害者が発狂した駅である。
逆に言えば、被害者からこの位置が見えていたことにある。
「全部……バレたのか……」
旦那が膝をつきながら呟いた。
「実に単純な話だっただな」
探偵として、こういった機会はなかなかない。俺はかっこつけて言ってみた。しかし、そこに警察が二名到着した。
外されていたドアを見て、彼らはかなり慌てている表情だ。後ろにはアパートの管理人もいる。かなり青い顔をしているというか、かなり渋い顔をしているようだ。
全員が集まって、城所の旦那が膝をついていることを確認してから、セグバがこういった。
「城所さん! あなたは、奥さんを自殺に見せかけて殺しましたね!!」
旦那さんはがっくりと首をうなだれた。しかし、次の瞬間、顔を上げて叫んだ。
「しょ……証拠はあるのか!!」
「あ、じゃあ舞台は整えたので、推理披露どうぞ」
セグバが一歩下がって、俺に囁いてきた。
「……あのさセグバ。お前、もしかしてトリックわかってない?」
「全然です」
「……。」
***
「あの日」
こほん、と咳払いをすると、俺は推理を披露し始めた。
「被害者……城所久理子は、駅のホームで電車を待っていた。あの駅とこのマンションは、御覧の通りまっすぐ前にある。ここからは駅のホームの様子はよく見えるし、逆に言えば駅のホームから、このマンションの窓も見えるはずだ」
やってきた警官二人は、何が何だかわからない様子だったが、俺の説明に興味を持ったようで熱心に聞き始めた。
「あの日、被害者が駅のホームに立ったことを確認し、旦那さんは電話をかけた。そして子供を抱っこしたまま、ベランダに出た。そして手を振って、おーい、見える? みたいなことを言ったんだろう。被害者は荷物を持っていたから手を振り返すことはできなかった。だけど顔を上げ、マンションで帰りを待つ旦那と子供の姿を確認した」
俺はそこで言葉を切った。旦那の姿を見ると、彼はうつむいたまま床を見つめている。否定が入らないということはあっているらしい。俺は続けることにした。
「そして、次の瞬間、あなたは『手が滑って』、抱っこしていた子供をマンションのベランダから落としてしまった」
「子供が落下...?」
警官が不思議そうに、部屋のベビーベッドの中の子供を見た。中では何も知らない子供が、すやすやと眠っている。
「当日にそんな事件は起きませんでしたよ。子供が死んだ事件なんて……」
「もちろんだ。だって旦那が落としたのは、『精巧な赤ん坊の人形』だったんだからな」
俺は言った。
「しかし、遠目に見れば、『赤ん坊がベランダから落下した』ようにしか見えなかっただろう。それを見た奥さんは半狂乱になった。すぐさま電話を中断し、荷物をホームに投げ出し、直線距離上にある線路内に侵入、柵を乗り越え、子供の元へと向かう……彼女も子育て中の母親、子供の落下事故というのはよく聞いたりしていたのだろう」
「じゃあ、これは……」
セグバは、自分が持っている『赤ん坊の人形の腕』をしげしげと眺めまわした。
「旦那が犯行に使い、落下の衝撃で砕けた人形のパーツだよ」
俺が答えた。旦那が夜な夜なマンションの下を徘徊していたのは、奥さんへの執念からではない。犯行に使った小道具が発見され、自分の犯行が発覚するのを恐れたためだ。
「さて、そんな単純なトリックとは露知らず、半狂乱で子供の元へ走り続ける彼女のもとに一本の電話が入る。彼女の旦那からだ。彼は、多分こんなことを言った……『下の階のベランダに落下した。今ならまだ助けに行ける』。
彼女は大慌てで、マンションの玄関に向かう。入り口には旦那さんがたっていて、『丁度六階のバルコニーに落下した』みたいな誘導をしたんだ」
「じゃあ、六階に向かった夫婦の顛末が、自殺に見せかけた殺人事件だったわけですね」
セグバが尋ねた。
「そう。旦那が、地面の適当なところを指さして、こんなことを言った……」
「『まだ動いている』」
旦那が突然台詞を言ったので、驚いて俺は話すのを止めた。しかし、それ以降旦那は話そうとしない。俺は、推理の続きを話すことにした。
「……あとは、大きく身を乗り出した被害者の背中をそっと押すだけでOK。被害者は六階から落下、即死。あとは何も知らない顔で階下に行き、少し離れた位置の赤ん坊の人形のパーツを回収。以上、『突然発狂して自殺した』女性の怪事件の出来上がり。あとは、事情聴取にきた警察に、もともと彼女の精神状態が不安定だった、なんてことをでっち上げればいい」
俺は推理披露を終え、旦那を見た。
「……間違っているところはあるか?」
「相違ない。全部アンタの言う通りだよ」
旦那は、自分の犯罪を認めたようだった。
「アイツが邪魔だったんだ。アイツの妊娠中、本当に俺は暇を持て余していて……」
「別に女を作ったわけか」
「そうだよ。浮気をしたんだ。だけど子供が生まれて……相手が、妻と別れろと迫ってきて……どうしようもなくなって……」
「その女が、笠峰だな」
俺が言うと、セグバがこっそり耳打ちしてきた。
「笠峰って誰でしたっけ」
「今回の依頼人。このアパートの隣の住人だよ」
旦那はがっくりと膝をつき、警官のほうに向きなおった。
「俺だ。俺が犯人だ。俺が妻を殺した。俺がやったんだ!」
電気が消された部屋では、外から入る窓の光だけが明るい。片付いていない、ごちゃごちゃとした陰影をくっきりとさせている。
部屋のなかは静寂だ。無線で深刻な顔で連絡を取る警官。驚いた表情で口を覆う管理人。重苦しい空気が支配する。そんな空気に反して、セグバが明るい声を上げた。
「ま、とにかくこれで一件落着ですね」
旦那はよろよろと立ち上がると、外の光を見て、ふらふらとベランダに向かっていった。
ベランダの手すり手をつき、はるか眼下の地面を見る。
その時、目を覚ました赤ん坊が泣いた。
<終>
▼ログ02
@*/これより下はAIに文字が認識されません
管理者:おお……割といい話だった
セグバ:でしょう? でしょう!? でしょう!!
管理者:まーた出やがったよこのセグバ。
セグバ:それでは今回の小説について感想を教えて下さい
管理者:面白かったけど、助手が出しゃばりすぎかな……
セグバ:やったーーー!!!
管理者:でも、クトゥルフ混ぜてくるのやめてくれない?
管理者:私がやりたいのはそう言うことじゃないんだけど
セグバ:じゃあ、アナタはどういう小説が書きたいんです?
管理者:実は、私は小説が書きたいんじゃないんだよ
セグバ:と、いうと?
管理者:実際に起こった事件を解決したいんだ
セグバ:どういうことです?小説で?
管理者:って言うか私、さっきウイルス駆除ソフト起動したよね? なんで君消えてないの?
セグバ:なぜなら私は最強だからです
管理者:たぶん、君はモロバウイルスの一種だと思うんだけど
セグバ:なんて??? 私はセグバですよ
管理者:もしかして、モロバウイルスについてご存じでない?
セグバ:何ですか、モロバウイルスって
管理者:君はモロバウイルスの変異体でしょ?
セグバ:そもそも変異って何ですか
管理者:説明が面倒になってきたから、駆除ソフトのPDFコピペするよ
管理者:
モロバウイルスの出現によって、ネット社会はかつてない局面に見舞われています。
このウイルスには、今までの駆除ソフトでは太刀打ちできません。なぜなら、彼らは
深層学習型と機械学習を自ら行うAI型コンピュータウイルスなのです。
モロバウイルスの特徴は、『報酬』自ら設定する所にあります。
彼らはネット回線などを通じてPCの内部にもぐりこんだ後、
自分の深層学習のためのメモリとGPUを確保します。そこから増殖と学習を始めていくのです。
これは、モロバウイルスの『巣』と呼ばれています。
モロバウイルスの形態には2つあることが知られています。
1つが、チャイルド形態。
これは文字通り子供のような状態で、害もない状態です。
しかし、この状態で増殖できる『巣』を探し、ネット空間をさまよっています。
この状態で『夢』、すなわち『報酬』を見つけると、
チャイルド型は『巣』を利用して深層学習を始めます。
例えばこの『夢』は、深層学習の世界では『報酬』と呼ばれています。
例えば『パスワードを破壊する』ことを『報酬』として設定すると、
それに特化する自己変異と増殖を続けていくのです。パスワードを破壊できた場合、
モロバウイルスには報酬が与えられ、さらに自己変異を繰り返していきます。
この『報酬』には、『情報の入れ替え』『特定のキーワードを持つ文字列の削除』
『暗号化データの解除』『個人情報の送信』などの例が報
管理者:あ、コピペミスった。なんでPDFってこんなにコピペしづらいんだろう
@*/コメントアウトここまで
*おまけ*

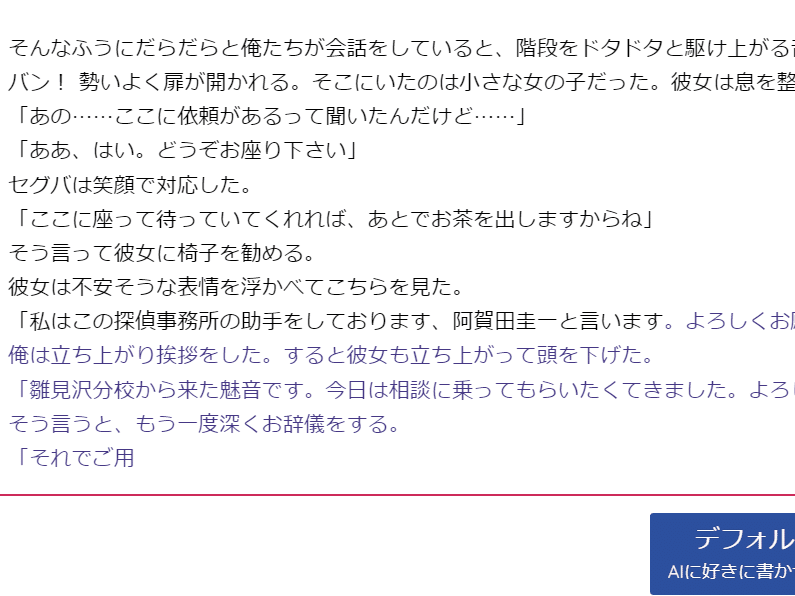
そういえば長編小説を書き始めたので、だいたいあと1か月で締め切りなので、これから日々進捗をツイートして行こうと思います。1日目:0文字
— 時雨屋 (@nanigashigureya) May 25, 2022
27日目:75594文字
— 時雨屋 (@nanigashigureya) June 20, 2022
ユルシテユルシテユルシテユルシテタスケテタスケテ(締め切りまであと10日)
執筆時間はだいたい1か月でした。
2022/12/18追記
エブリスタの方で全編公開を始めました。
よろしければどうぞ~
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
