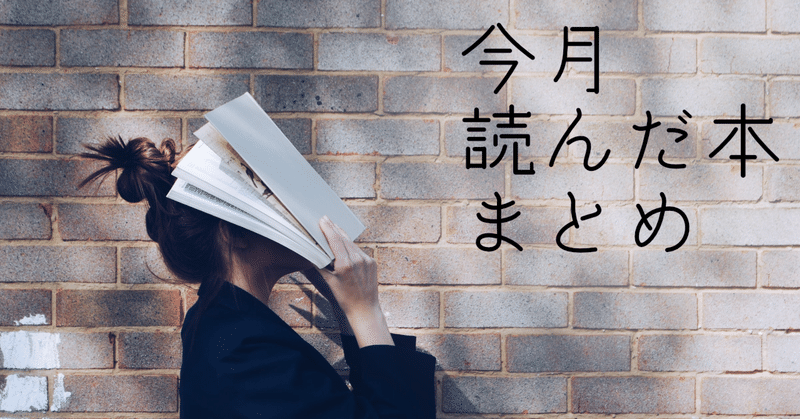
2022年10月に読んだ本まとめ
先月の給料日に1万円分の本を買ったので今月はそれらを読んでいました。前から気になっていた本だけあって、自分に合った本が多かったです。
文芸書では、『推し、燃ゆ』、『六人の嘘つきな大学生』が物凄い良かったです。同じく先月買った『塞王の楯』も現在読んでいて最終局面ですが非常に面白いです。
文芸書以外では『DIE WITH ZERO』が米国の富裕層向けの記載に眉に唾を付けつつも、これからの人生の指針になりそうな良い内容でした。
文芸書
宇佐見 りん著『推し、燃ゆ』
言語化を放棄すると「いいぞ、『推し、燃ゆ』」となる。
「推し」っていう言葉は耳にする機会があるし、なんとなく意味は分かるものの、理解できていなかったので読んでみた小説。
「推しは私の背骨だ。」という文章にすべてが詰まっています。主人公にとって「押し」は生きる糧であり、辛い日常生活の救済であり、自己表現の手段であり、ネット上のコミュニケーションの中心で、自身と不可分の存在です。
主人公は生き辛いとされる特性を持っているので、「推し活」をしている人の中でもマジョリティーとは言えないと思いますが、「推し」という言葉の意味の一端に触れられた気はします。
もうでてから2年経っちゃってますけど、今の内にこそ読むべき、時代を切り取った傑作なのではないでしょうか。コンサート会場のトイレのシーンとかの圧迫感と絶望感がすごかったので、小説に心動かされたい方にもおすすめです。
逢坂 冬馬著『同志少女よ、敵を撃て』
主人公はソビエト赤軍に所属する女性狙撃手で、戦場のシスターフッド作品としても文句なしに面白いです、
ただ、主人公の目を通して見る戦争に人生を翻弄された女性達が、この作品をただのシスターフッド作品ではなく傑作たらしめているのではないでしょうか。
作中でウクライナとロシアの関係が描かれているのも、見どころだと思いますし、現実の出来事によって注目を浴びた作品でもあると思うのですが、その現実の出来事が作品の邪魔をしている感じも大いにあります。
ロシアが「ナチス」という言葉を現代でも度々使っているのは、この作品の舞台となっている独ソ戦の時には、ロシアの元で旧ソ連各国が一つにまとまっていたとロシアが考えているからですが、まぁ、そんなシンプルな話じゃなかったんだろうなとこの作品を読むと思わされます。
作中に登場するリュドミラ・パヴリチェンコはキーウ近郊の出身で、レーニン勲章を授与されているそうなのですが、優秀な狙撃手だったのはそうなんでしょうけど、政治的な臭いも強く感じてしまいますね。
伊坂 幸太郎著『マイクロスパイ・アンサンブル』
ほんわかします。
音楽フェスで毎年連載されていた作品とのことで、TheピーズとTOMOVSKYの歌詞がところどころ引用されています。どちらのアーティストもしっかり聴いたことはないので、ちょっと聞いてみたくなりました。
浅倉 秋成著『六人の嘘つきな大学生』
夜更かしして一気に読んでしまいました。今年読んだり、見たりしたエンタテイメント作品の中で最高に面白かったです。思うところも色々とあったので以下に感想をまとめてみました。
浅倉 秋成著『ノワール・レヴナント』
『六人の嘘つきな大学生』が非常に良かったので読んでみた作品です。
後半の盛り上がりが非常によかった。
難しい問題でもなんでもなく、シンプルに他人の権利を害してはいけないと思うけどね。問題定義は一理あるけど、アプローチの方向が全く間違っているんでしょうな。
文芸書以外
宮口 幸治著
『どうしても頑張れない人たち
―ケーキの切れない非行少年たち2―』
「頑張れない人」がどんな態度や行動に出ようとも支援し続けることを支援という、という言葉に支援側に求められるものはなかなか大きいと思い知らされる。
当然と言えば当然なんだけど、同じ言葉でも聞く側の状態によっては有益だったり、有害だったりする。
そう考えると教師は教壇で人生訓めいたことは言えないので、授業以外で「頑張れない人たち」をフォローすることになるんだけど、反抗的な生徒に対してそれができる余裕のある教師ってどれだけいるんだろうっていう話ですよ。
親は自分の子供だけ見ていればいいので、じっくり考えてリアクションや、子供へ人生訓を伝えられるか?と言えば支援が必要な状態になっているということは、既に親に余裕がない場合が多いので、それも難しい。そういう状況が好転したとしても子供を育てる経験が豊かな親ってのは少ないので、やはりフォローは難しい。
頑張れない支援者を出さないようにするための支援まで織り込んでおく必要がありそうな気がしますね。
ビル・パーキンス著
『DIE WITH ZERO
人生が豊かになりすぎる究極のルール』
子供の頃「フルハウス」という海外のシットコム作品をよくみていました。その中で主人公の一人であるジェシーが結婚式の日にスカイダイビングをするという話があって、子供の私にはイマイチ飲み込めなかったのですが、結婚するということは、夫婦で問題を分け合うするということなので、そうなる前に、リスクはあるが自分のやっておきたかったことをやりたかったってことなんでしょうね。
結婚前であれば問題が起こっても自分だけで背負っていけばよいですが、結婚するとそうもいかないですもんね。まして、ジェシーはその後二度の父親になるのでそうなるとさらにリスクを取ることは難しくなります。
自分を取り巻く状況もそうですが、年齢によってもできることは変わってきます。学生時代の友達が大学を休学してバックパッカーをしていました。私が死んでも路頭に迷う家族はいないので、やろうと思えばできなくないですが20代でバックパッカーをして得られた経験と、40代で得られる経験には差がある気がします。さらにあと20年もたって60代になってしまえばバックパッカーをすること自体が難しくなるでしょう。
つまりは、年齢や自分を取り巻く環境によってできることは減っていくので、よく言われるように「引退してからやりたいことは引退したらできなくなっている」わけです。いつやるの?今でしょ?という言葉が浮かんできますね。
『DIE WITH ZERO』で紹介されている資産の取り崩しタイミングを実際に計算してみると、日本人の平均的な年収だと、資産を削り始めるのが老齢過ぎるので、欧米の富裕層向けの本なんじゃないかと疑いたくなりますが、
作者がこの本で言いたいことは、無駄なく人生を楽しむ方法です。
私にはこの本に人生を楽しむことについて真摯に向き合うためのヒントが含まれているような気がしました。
2022年9月
昨年分
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
