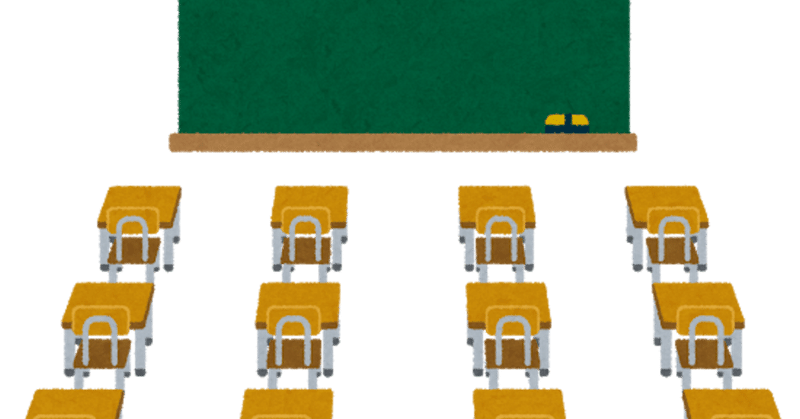
知る人
生徒宅、もしくは各自治体が指定した施設で行われるオルタースクールでのオンライン授業の環境がようやく世界的に整備されたといえるタイミングで、正式に世界の共通言語がクリンゴン語に決定した。人口の激減によるアメリカの没落。イギリスの事実上の消滅。英語以外を母国語とする多くの国からの反発。理由は様々だが、最終的にはその時点で一番大きな力が働いたのだろう。これにより、ほぼすべての生徒がそれまで目にしたことのなかった人工言語を新たに学びながら学校に接続することとなった。
学校というものは既に概念に近くなっていた。かつてその象徴としてあった校舎は移動者のための簡易宿泊施設や経済貧困者のための福祉施設になっていた。校舎としてその姿が見られるのは月に一度、基礎教育カリキュラムのオンライン授業で背景として選択できるフリー素材でのみだった。
新しいことの始まりと問題はセットだ。今回の言語設定における一番の問題は、生徒でなく教師側に起こった。言語学習において発達途上である生徒たちと違い、教師たちのある意味では完成された言語中枢では新たな言語を習得することが容易でなかったのだ。教師の間違いを生徒たちがからかい、いじめのような形になるグループも少なくなかった。もちろん、生徒たちが教師に言葉を教え教師が勉強内容を教えるという美しい双方向も存在したが少数だった。この問題は最終的に、世界のおよそ六十五パーセントもの教師が辞職するという事態に発展した。
授業で使う言語が決まった時点で世界の教育はQGY(qo’ ghojmoH yejHaD=世界教育機関)というUNESCOの後継機関に引き継がれることになっていたが、この教師の大量辞職によって各国からのクレームが舞いこんでいた。QGYは慌てて教師を募集したものの、これまでの惨状を見て教師になりたいという者などいない。最終的に世界の物流、小売りを牛耳っていた企業がpegh ngemと屋号を変えQGYを買収し、pegh ngemの従業員が突如教師になることになった。
pegh ngemの教育は画期的だった。全世界で共通して、六歳から十六歳までの生徒にpegh ngemの仕事内容に沿った教育を行ったのだ。受注、在庫管理、出荷、配送。生徒たちは従順に学び、規定のghoj Huch(学業報酬)を受け取り、その多くがエスカレーター式にpegh ngemを就職先に選んだ。それは当然の流れだった。新しいことを覚えなくともなくこれまで以上の給料がもらえるのだ(ghoj Huchが度々人権問題として話題になる程の額だったとしても)。
メーカーによって製造された商品はpegh ngemが回収しpegh ngemの倉庫に入れられ、受注があった商品をpegh ngemが発送しpegh ngemのジェット・トラック便によってエンドユーザーの元に届けられていた。問屋なんてシステムはとうに無くなっていたし、もう十年もすれば製造もpegh ngemがやるだろうと囁かれていた。
だが、終わりは突然だった。pegh ngemの倒産。数時間前までフル稼働していたpegh ngemは星の爆発のように倒産し、それからずいぶんと遅れて世界中の九割以上の物流が途絶えた。いったいいつpegh ngemが倒産したのか、正確な日時は誰も知らなかった。pegh ngemの代表取締役である人物は既に消息不明となっていた。全ての資産を持ち出し雲隠れしたとも噂されていたが、真相はわからない。世界は彼の行方を追うことよりも、既に社会インフラと化していた巨大企業の代わりを探さなくてはならなかったがそれは困難だった。
pegh ngemが倒産し、世界中の学校が停止した翌日。残っていたpegh ngemの公式ホームページにて小売り周りの業務ついてはこれまで下請けとして働いていた多くの企業が引き継ぐことが表明された。その下に並ぶのは名だたる大企業ばかりだ。ここまでは専門家の予想と同じだった。ただひとつ違ったのはpegh ngemが担っていた教育関連の業務については全てUOHACHIが引き継ぐ、との文章だ。見慣れないその単語に世界は戸惑った。検索エンジンとSNSのトレンドワードにその単語が踊った。
UOHACHIは日本の職人文化とオタクカルチャーを融合させたアート集団だった。秩父多摩甲斐国立公園内に作られた、スーパーマーケットに見立てた巨大インスタレーション空間の中で作品を展示していた。発足当時は日本が国としての起死回生をかけて打ち出した、過去に例をみない予算規模の文化支援によりかろうじて作品を発表し極一部において評価を得ていたもの半年も経たずに支援は打ち切られた。
UOHACHIは当時の代表の決断により小売業を主とする企業に転向し、店舗をそのままに食料品を中心としたスーパーマーケットを営むようになった。その頃、実店舗をもつスーパーマーケットは他になかったためUOHACHIは小売業の収益の他に体験可能な文化として有料で店舗を開放することで、かろうじて経営を存続していたのだ。
pegh ngemの代表取締役はかつてのUOHACHIの大ファンで、とりわけ全身に入れ墨を施した美少女フィギュア『vay mu’adD be’Hom』シリーズのファンであった。pegh ngemが教育業務を小売業者であるUOHACHIに引き継いだ理由は、規模の大きなファン活動の一貫だったのかもしれない。一方、UOHACHIの代表は困惑していた。pegh ngemから送られてきた帳簿データを何度見返しても、教育部門単体での収益に黒字がなかったのだ。理由は明白で、教育業務での赤字を小売業としての経営でペイしていたためだった。
おいおい、とUOHACHIの代表は呟いた。明日にでも、いや、今夜にでもpegh ngemが雇用していた従業員つまり教師たちがなだれ込んでくるだろう。給与を下げることは難しいし、辞めてもらうにしても払う退職金がない。それに世界中の生徒たちはどうする? 送られてきたメールには事細かな教育資料が添付されていたが、それを実現する設備も人材もUOHACHIにはなかった。男は一本の電話を掛けた。それは、彼の幼馴染であり自然保護団体の代表である男性へのものだった。
地球の歴史は大地と生物の歴史である。その両輪によって地球は豊かな星となっていった。だが、ある分水嶺を越え生物は地球にとって害悪でしかなくなってしまった。人類はこの地球の未来ために、ゆるやかに滅びるべきである。というのが非営利の過激派自然保護団体SuD tera’の教育指針だった。知識を欲していた生徒たちは、新しい教えを新しい常識として吸収していった。かつてpegh ngemの従業員兼教師だった者たちはSuD tera’に出向し、無給で活動することとなった。そしてすぐさま全員が逃げるようにSuD tera’を去っていった。
だがそのSuD tera’もほどなくして解散となる。その経過と顛末はシンプルだ。自分の娘が自殺させられそうになっていることに気が付いたある母親がSuD tera’の代表の自宅に突入したのだ。母親は軍人でもあった。当時、義務教育を終えた十七歳以上の約三十パーセントが性別にかかわらず各国の軍に所属していた。彼女は代表の男を外に連れ出し、仲間の操縦するヘリに乗せた。途中、腕を縛られたまま男が女性に対して罵詈雑言を浴びせたが、彼女は始終無言だった。ヘリを火口の斜め上でホバリングさせるよう仲間に頼むと、女性は男に尋ねた。
「愛する自然の一部になりたい?」
男は泣きながら首を横に振った。火口に飛び込むというのは、彼がSuD tera’で教えている自然への還り方のひとつだった。
この事件をきっかけにして、学校という概念は急速に世界から消えていった。クリンゴン語の電子辞書からもその単語は消え、代わりに助ける場所を意味するtaH lanが学校の意味として使われるようになっていった。生徒たちは自宅もしくは各自治体が指定したオルタースクールをそのまま利用した。教師は各地域の大人が有志で務めた。ボランティアとして持ち回りで教える地域もあれば、一人の者が長く続けるうちに自然と通貨や食事でのカンパが発生る場合もあった。それで生活ができる者も出てきた。
子どもたちは算数を学び、第一言語であるクリンゴン語の他に第二言語として自分が生まれ育った地域の言葉を学んだ。ここ数十年の歴史はテキストと画像でリアルタイムに記録されていたし、ここ数年のことであれば生徒たちも自ら体験していた。
それ以前の歴史や経済、どうして虹は七色なのかといったもっと詳しいことを知りたい者は、クリンゴン語で世界にアクセスし専門の教師に教わりその家の経済状況に応じた報酬をchuH Huchと呼ばれ自由に金額を選び送ることができるシステムで教師に届けた。授業のあとのフリータイムで気の合った友人ができれば、個別に設定したルームに集まり会話したりゲームをしたりした。不思議なことに、ギリギリのところではあるけれどそれらはひとつの大きな教育の流れとして成り立っていた。
更に何年も経ち、子どもたちが大きくなるにつれ教師を目指す者が増えていった。第二言語を教えることが人気だったが、自分の専門分野を伸ばし、専用チャンネルを作り、誰かになにかを教えながらお金を稼ぐということが当たり前になっていった。生活と地続きのものとして教師と教育があった。
さらに時が経つと教師という言葉も生徒という言葉もなくなり、ただSov nuvpu’=知る人、という言葉だけが残った。学校という言葉もやがて忘れられ、なにかを教わるために行く奇妙な場所=Huj.lanとして歴史のデータベースにその名を残すのみとなった。
いくつかの国がなくなり、それをまたいくつかの国が自分のものとしていった。そんななかで、どの国からも奪われず、誰からも忘れられた土地があった。三つの国の境にある小さな土地だ。老人が建物を作っていた。どこかからか集めた資材を使い、慣れない手つきで建物を作っていた。通りがかった人はそれを笑ったが、老人が手を止めることはなかった。稀に男の足元にパンを置いていく者もいた。だが、男はそれに気付かず作業を続けていた。ある朝、ひとりの子どもが男の不在を確認した。建物だけが残されていた。建物は四角を組み合わせたような不格好な姿で、入り口の上部に大きな時計が付いていた。子どもにはそれがなんだかわからなかったが、昨日友だちになった子をここに誘ってみようと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
