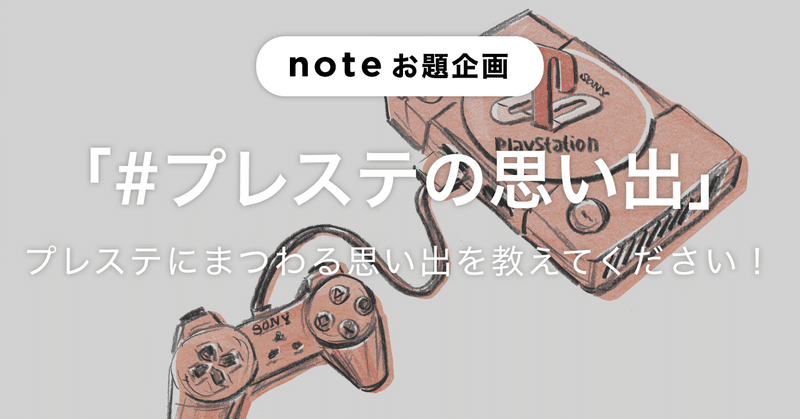
かつて、PSPは俺たちの青春を公転する惑星だった。
「ぎゃああああ!」
深夜。閑静な住宅街の一室。叫んだのは俺だった。
「なんだ!?どうした!?」
Yは手もとのPSPに俯かせていた顔をあげて俺を見る。それから「がははははは!」と笑い出した。
「おい!夜中だぞ!母さんに怒られるから静かにしろよ……って、げはははははは!」
Sも最初の勢いを失って笑いだす。それから「ああ、ちょっとまて!そのまま!飛び散るから!動くな動くな!」と言った。
笑えないのは俺だけだ。ふたりから震える指でさされた俺は、空中でぴたりと静止した頭を支える首筋を震わせながら、お気に入りの白いPSPを布団のどこかに投げ出して「とにかくタオルください!タオル!」と懇願する。
Sが部屋のクローゼットからタオルを引っ張り出して俺に投げた。Yが近くにきて「くさっ!」と言うなりまたそばで転げまわった。
「でもよく床にこぼさなかったな。そこだけは褒めてやる。」
Sは言って、自分のPSPを手にした。彼は本体の後ろに金文字の龍のシールを貼っていた。普通にダサかった。
「じゃ、俺は先に一狩りしてくるわ。」
「ぼくも」とYが言って、またPSPの画面のなかへと帰っていく。
『そこに枕があると思いこんで倒した頭の先にはなぜか食べ終えたカップラーメンの残り汁があってまんまとうっかり豚骨のぬるま湯に入湯した話』を、エピソードトークとして週明けの学校で部活仲間に披露しようと俺は考えた。失敗は成功の出汁だ。これは美味しくなるぞ。ひひひひひ……頭くさっ!
「ほら、はやく来いよ!エリア5にリオレウス見っけたぞ!」
「よっしゃあ!俺の頭の匂いを嗅がせてやる!背脂に頭の皮脂が混じった超豚骨級の一撃必殺だ!」
「やめろー!ぼくに頭をなすりつけるなー!うわ、くっっっさ!」
「こやし頭!こやし頭!」
後日、Sは母にこっぴどく怒られた。
春も夏も秋も冬も夜も朝も昼も金曜日も日曜日も、狂ったようにゲームをやっていた。中二。『モンスターハンター ポータブル』が発売された年だった。
「今日はどうする?うちでやる?それともまたSん家?」
週末になれば決まって徹夜でゲームをした。部活終わりの放課後。3人の帰り道。俺は言った。
「いや、たまにはYの家とかよくね?この前のバカ騒ぎで親にしっかり怒られたから、さすがに2週連続は勘弁。」とS。
「うちは無理だって。親が厳しいからね。」とY。
「じゃ、うちにするか。親に電話してみるわ。ま、聞くまでもないけどさ。」
実際、ふたつ返事だった。『べつにいいよ』。いつもとおなじ返答。
「オーケーだと。飯食って、9時でいっか。ほんじゃ、またあとで。充電器を忘れないように。」
別れてひとりで帰る週末の12分の道のりが、俺は好きだった。オレンジの陽が射すころはとくに。濃い影と、サッカーボールに見立てた小石を蹴りながら帰る道のり。もし石をなくしたら俺は死んでた。あるいは白線の外を歩いたら死んでたこともあった。
先のことなんてなんにも考えていなかった。
PSPが盛り上がりを見せていたとき、平成の初頭に生まれた若者たちは青春時代を生きていた。
俺はたしかにゲームが大好きだった。だがゲームだけが好きなわけじゃなかった。テニスをするのも好きだったし、女の子とメールをするのも好きだった。勉強以外はなんでもござれだ。身軽だった。どこにも所属せずに、囚われていないと思っていた。それがカッコいいと。「なかのくんは雲みたいな人だ」と役者志望の男が恥ずかしげもなく俺に言った。俺は恥ずかしかった。そうでありたいと思っていたから。いわばキャラ付け。自由な男。そのためには、どこへでも行けてしまえる必要があった。PSPは相棒だった。一緒にどこへでも行けた。くだらないカーストの垣根を越えて、だれとでもゲームをすることができた。モンハン、みんゴル、鉄拳。ゲームは越境した。いともたやすく。
ふとした拍子にイジメにあった。
従兄が札付きの悪というだけで威張っていた間抜けな男が、俺の気ままな振舞いに目をつけた。差別主義者のクソ野郎だった。「あのケニア野郎」と奴がハーフの男子に言った。「うるせえ」と俺は反射的に言ってしまった。言ってから、あっ、と思った。手遅れだった。
俺は半月自宅に引きこもった。自由は死んだ。ゲームをやった。ゲームしかやらなかった。とことん上達した。夜が来て朝が来た。その繰り返しのなかで。
学校に戻っても俺の居場所はとことん窮屈だった。だれも話しかけようとしなかった。当然だ。なぜなら「奴の従兄は悪名高い不良」で、俺はそいつに目をつけられている。いまとなっては笑える話。でも当時はそんなに愉快でもなかった。俺の友達はどこにいったんだ?遠巻きに日常を見ていた。さらにゲームにのめりこんだ。輪をかけて勉強はしなくなった。部活は行かなかった。なんの意味もない。ならゲームのほうがマシだった。
あるとき、入学のその日からそのときまでずっとクラスメートに見離されているIという男子が突然話しかけてきた。放課後だった。
「なかのくんってゲーム好きなの?」
「好きだよ。」
「よかったらうちに遊びこない?ゲームいっぱいあるんだ。」
「行くよ。」
俺は彼の家にお邪魔した。たしかにゲームはあった。でもそれらはすべて古いゲームだった。初代プレイステーション。俺たちは遊戯王のゲームをやった。彼は強かった。俺は退屈した。
「PSPとか買わないの?」
「買ってもらえないよ。このプレステもうちの親のおさがりみたいなものでさ。」
「そっか。いつか買ったらモンハンとかやろうな。」
「やろう。やろう。」
俺はいつの間にか周囲の連中の環のなかに戻っていた。Iとは2度と遊ぶことはなかった。
I。8年後。彼は自殺した。葬儀の報せが来た。行けなかった。行けるわけがなかった。「いつかPSPでゲームをしよう」なんて都合のいい言葉で突っぱねた思い出に連れられて悔み涙を流すような浅はかさを自分に許すことができない。最後のお別れとやらの一瞬の時間で青白い顔に語りかけるのか?「君とまたゲームがしたかったな。」しゃらくせえだろ、そんなの。
PS3が発売されたとき、高校生になっていた。徐々に他人の家に集まるということも減った。オンラインでつながり遊ぶことが主流になってきた。
「そんじゃ、今日9時に○○サーバーで。」
「おう。」
もう徹夜でゲームなんてだれもしなかった。それぞれの日常へと着実にむかっていた。将来があった。うつつを抜かしてばかりいるのは終わりだった。みんな前を向いていた。もう手のなかに収まるサイズのビジョンにとどまりはしなかった。社会へと出ていくために。いつまでも俺ばかり愚図のままで。
寂しかった。けれどもそれもすぐに慣れた。スカイプ。画面越しの友達の背中。電源を切れば暗いテレビ画面のなかには俺ひとりの姿しかないことも。
大人になるにつれ、ゲームで遊ぶ機会は確実に大胆に減った。「大人になればゲームなんてやらなくなる。いまのうちだけだ。」耳が痛くなるほど聞いたセリフだった。その通りになった。20代の前半。ゲームなんてやらなかった。PS3は映画を再生するための機械になった。大学を出て、ひとり暮らしをはじめた。働いた。人付き合いをした。酒を飲んだ。悪くなかった。まずまずの日常。それで十分だった。そのはずだった。PS4は買わなかった。
だがいま、俺の手もとにはPS4がある。今年になってようやく買った。
徹夜でゲームに夢中だったあの頃とはずいぶん変わった。俺も、俺以外も。現実と見まがう圧倒的な世界のなかを冒険することは楽しい。いまの子どもたちはこれを当りまえに遊んでいるんだな。ゲームを持ち寄って深夜の公園でカップ麺を食べながら合間合間に好きな女子の話とか将来の話とかしながらそぞろな心でゲームをしないのかな。意味もなく登山して頂上でやるゲームは普段の数倍楽しいね、なんて馬鹿げたことも言ったりしないよな。それもまたきっと絶対に素敵な青春なんだろう。青春はダイヤモンドだ。いついかなる場所でも、だれのものでも美しい。
この文章を書いたのは深夜の散歩の最中。俺は自分の精神状態を台無しにしたばかりに地元へ強制送還されていた。田舎の、星がよく見える場所。
公園のブランコに腰かけて、せいいっぱい思い出を引き出してみた。笑えるくらいにゲームばかりがあった。まるで俺自身がゲームの周りを回転しているみたいだな、なんて。
いまはもう回転する力を失ってしまっただろうか?かつての友人たちはもうこの町にはいない。S、Y。帰省すれば彼らもこの公園にやってきて、まだそう遠くもない昔の思い出に想いを馳せたりするだろうか。俺を記憶しているかな。豚骨スープでカピカピになった髪を、一緒に倒したラオシャンロンを、一緒に育てた競走馬を、サッカーチームを、記憶しているだろうか?
この町の月は綺麗だ。いまも。
うちへ帰ろう。買ったものの、まだ手の付けていないゲームがいくつもある。消化しなければならないゲームが。
そんなことがあるなんて昔の俺は思いもしなかった。手の付けていないゲームなんて。ゲームするための時間が足りないなんて。それに、消化しなければならないゲーム?
勘弁してくれ。
くだらない話。はははハハハHAHAHA。
笑えるうちに終わりにしよう。
そうそう。そう遠くないうちにPS5が出るという話もあった。俺もいよいよ30才に迫るころだ。どんなゲームが出るだろう。どんな体験が?
やっぱりどうしようもなく、性懲りもなくワクワクしている自分がいる。でもそれは素晴らしいことかも。気になるゲームが発売するまでの時間って強い引力があるから。引き寄せられることの心地よさ。発売日をおもえば退屈な日々も耐えられる。蹴飛ばせる。いざ封を切って遊びクリアすれば、またそのうち新たな気になるゲームが出てくる。そこへ向かっていく。手にする。遊ぶ。クリアする。クリアしたゲームはつのっていく。これからも。そのたび思い出話も増える。やればやるだけ増えていく。増える。生きた証拠だ。その人生が良かれ悪しかれ、とにかく。生きる。続く。
それらを数珠つなぎにして輪を作り、いつか首にかけて晴れがましく白い陽光の下を飛びだすタイミングが来たら、そのときは、全部ひっくるめてもなお誇らしげに笑うことができるといいのだけれど。
なんつって。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
