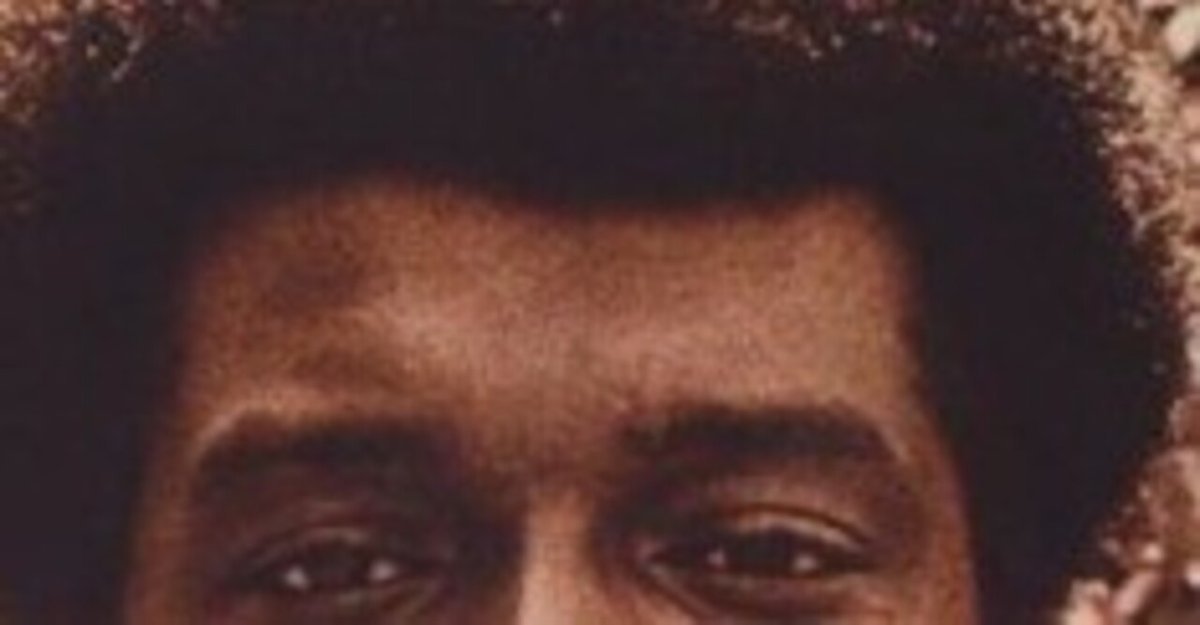
70年代ベストアルバムランキング30位〜21位
前回の記事はこちら。
30位 Can/tago mago

クラウト・ロックの代表的バンド。日本人ヴォーカルを迎えての1枚。クロいものとは違う奇妙なグルーヴが渦巻いており、トリップ感がすごい。とはいえ、ヴァイナルでいうC面、D面は実験的というか前衛的というか難解。
意識高い系の人たちが好きそう。通好みというか、「canをいいと思える自分かっこいい」と思ってそうで苦手(偏見)
29位 Ceazer fraizer/'75

gangstarrやcommonの元ネタでお馴染み。あの時代の下世話なオルガン・ジャズ・ファンク。これ系の音がこの時代は山のようにあり、純粋なジャズファンからは徹底的に無視されていた模様。後のレア・グルーヴのムーヴメントの中で評価をされた1枚。
①④のようなジャズ・ファンク、メロウでポップな③など魅力的。gangstarrネタの④からスティーヴィー・ワンダーの⑤の繋ぎがなんか好き。
まあこれだけソウル、ファンク色が強いと純粋なジャズ・ファンには無視されて当然か。
28位 Tower of power/live and in living color

ベイエリアの白黒混合バンド。ホーン・セクションがリトル・フィートやヒュール・ルイス・アンド・ザ・ニュースのライヴやスタジオ音源に参加しているので、ロック・ファンにもお馴染みか?当時シカゴとかと並んで「ブラス・ロック」と紹介されていたらしいが、ロックではなく、完全なファンク、ソウル・グループ。
タワーのライヴ盤は2013年に出た1974年のラジオオンエア用音源が最高だが、それは発掘盤なのでこちらを。
76年なのでヴォーカルがレニー・ウィリアムではないが問題なし。ロッコとガリバルディの手数の多い複雑なリズムが最高のグルーヴを生み出す。代表曲の③と⑤が熱すぎる。特に後者は30分近い演奏。全員のソロ回しが終わり、後半に唯一紹介付きという待遇で長いソロをとる鍵盤はチェスター・トンプソン。ブラック・ジャズからリーダー作も出している。
タワーは「back to oakland」から「in the slot」あたりはどれも名盤で選ぶのが難しかったので無難にライヴ盤選んでしまった。順位はもっと上で良かったと後悔している。
27位 Sly&the family stone/ fresh

普通ブラック・ミュージック、特にファンク好きならスライはもっと上位に来てしかるべきなのだが、私には正直良さがよくわからない。
冒頭のリズム・ボックスにアンディ・ニューマークのドラムが被さってくる所など鳥肌モノだし、次曲のミッド・ファンクも最高である。とまあ曲によっては好きだけどアルバムとしてはどうなのかなあ。意味不明なキーボード音が入ってきたり、ロックっぽくしたいのか、中途半端な作りの曲があったり。絶賛される前作も同じような感想。
しかし名盤ほど理解するのに時間がかかるとも言われる。最初はイマイチだったけど聴きこむうちに…ってパターンは自分も経験がある。そう思い、思い出しては聴き、うーん、わからん、と棚にしまわれ、しばらくしてまた聴いてみて…ということをもう20年以上やっている。なんやかんや結局こうやって聴き続け、振り回され続けて行くのであろう。それもある意味名盤の証なのかも。
26位 Weldon irvine/in harmony

ニーナ・シモン楽団のディレクター的立場で活躍したり、ホレス・シルヴァーに楽曲を取り上げられたりしていたのに、ジャズの正史にはほとんど出てこず、レア・グルーヴやヒップ・ホップ界隈に大人気の鍵盤奏者。名盤も多いのに。ジャズ・ファンもいい加減なものである。
初っ端からクラヴィネットが荒れ狂うジャズ・ファンクだが、後半はピアノでのストレート・アヘッドなジャズも聴け、ストラタ・イーストらしい黒さも。
RCAからリリースされた「sinbad」でドン・ブラックマンがヴォーカルを取る「i love you」は最高のメロウ・ナンバー。どの作品から聴いても問題なくかっこよい。ただ「ジャズ」として聴くと理解できないと思うけど。
25位 Earth,wind&fire/S.T

「セプテンバー」や「ファンタジー」ばかりが有名なので、派手なディスコ・グループと思われているかもしれないが、ワーナー時代の初期2枚は、どす黒いジャズ・ファンク、後年とは違う怪しいアフロセントリックな音が満載でとんでもなくクール。
モーリス・ホワイトがラムゼイ・ルイス・トリオにいたのは有名な話しだが、他のメンバーが在籍していたというファラオス(pharaohs。ファラオ・サンダースとは関係ない)と言うグループも、発掘盤含めて最高のブラック・グルーヴをぶちかましている。
24位 Funkadelic/standing on the verge of getting it on

パーラメントとほぼ同メンバーの別働隊。パーラがファンク、ファンカがサイケ・ロックと言われるが、ここでは初期の混沌としたサイケ感が減り、かなり整理されたブラック・ロック。
Pファンクはとにかくメンバーの出入りが激しいうえクレジットも適当なので、わからないことが多いが、本作の鍵はエディ・ヘイゼルと言って良いのでは。①、②やタイトル曲で爆発するギターが堪らん。ロイ・ハーグローヴがRH factor名義でディアンジェロが歌いカヴァーした③の怪しげメロウな感じもナイス。
その後はツアーもPファンク名義になり、初期メンバーもどんどんいなくなり(気まぐれに参加しているけど)パーラとの境界線が曖昧に。「One nation under a groove」がファンカの最高傑作と抜かす輩がいるが、あれは「Pファンク」という集合体としての名盤ではあると思うが、もはやファンカデリック名義としての体は成していないと思う。
23位 Rolling stones/exile on main street

チャーリー・ワッツを失っても転がり続ける最強のジジイども。
ベガーズ・バンケット以降のアメリカ最深部への旅が生んだ大傑作。発売当初は散漫と言われていたらしい。まあ長いし。
いろんな物をパクり適当で無責任にやっていたらこんなのができたというロックの最良のお手本。
ネットリしているのはミックのヴォーカルだけではない。⑤なんてこの時期のストーンズにしかできないスワンプ・ロックでしょ。⑮の疾走するミック・テイラーのスライド・ギターがヤバイ。
ロックなんて適当でうるさくて汚くて無責任なものよ、でもそれでいいの。それが魅力なんだから。コンプライアンスの時代、演る方も聴く方もそれがわかってないわよね(おネエ)
22位 Delaney&bonnie&friends/motel shot

白人ながらスタックスとの契約を勝ち取った事もある夫婦デュオ。クラプトンやレオン・ラッセル繋がりで名前は知られているかもしれないが、「ロックの名盤」みたいな企画にもほとんど取り上げられない人達のマイナー盤。
タイトル通りツアーのオフステージ、モーテルでのセッションをイメージしたアコースティックなサウンド。スタックスと契約できるぐらいなので歌はなかなかにソウルフル。ピアノやアコギのシンプルな演奏でゴスペル的な雰囲気も。参加メンバーも当時の彼らを支えていた豪華なメンツ。
ザ・バンドと並んで、ジョージ・ハリスンやエリック・クラプトン、デイヴ・メイスンらUKのビッグネームをアメリカン・ルーツ・ミュージックに誘った二人なのに後年の扱いは地味そのものでかわいそう。辣腕レオン・ラッセルにバック・メンバーを根こそぎ引き抜かれてしまったのもツイてなかった。
派手さはないけどいい歌といい演奏、「佳作」って言葉が合うのかな。
21位 Grateful dead/american beauty

ドラッグまみれでサイケな音を垂れ流していたバンドが前作に続き自身のルーツ・ミュージックに立ち帰った作品。とはいえドラッグ臭は完全には払拭できておらず、しかしそれがザ・バンドのようなルーツ・ロック・バンドとは違う味を醸し出す。
コーラスも演奏も上手いのか下手なのかわからんゆる〜いグループだが、スタジオ盤なのでまとまりはある。歌いたくなるメロディ・ラインも素晴らしい。個人的にも思い出が沢山詰まった1枚である。今も全曲歌えるからね。
ブート(このバンドにブートレグという概念はないかもしれないが)含め天文学的な数のライヴ音源が世に出回っているが、オフィシャルのものはどれもクオリティが高く、live/deadとdead set、europe'72が好きかな。全部聴いてないので偉そうな事は言えないけど。
とはいえグルーヴとか超絶技巧を期待できるバンドではなく、お酒でも飲みながらぼんやり聴くと心地良いトリップ感が味わえる。ドラッグはダメ、絶対!
ミッキー・ハートがリズム・デヴィル名義の作品やザキール・フセインと組んだティガ・リズム・バンドもパーカス好きには堪らん。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
