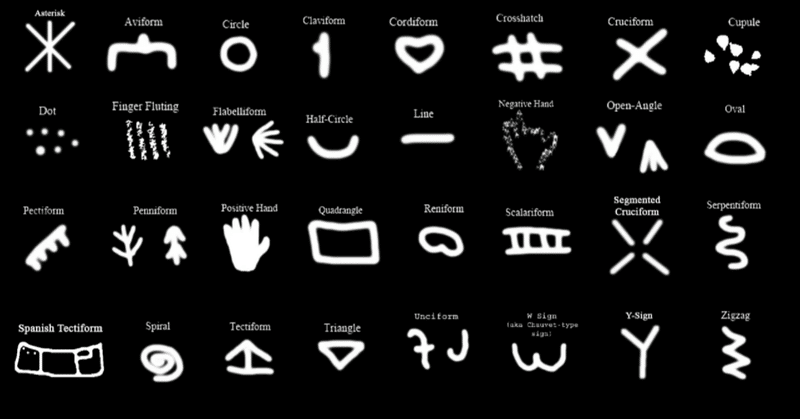
文字的世界【17】
【17】神の語、純粋言語─読まれない文字を読むこと・続
ベンヤミンの言語論については、かつて「韻律的世界」の第29節で、「音(声)のオノマトペ」すなわち「擬音語」に対する「形(字)のオノマトペ」すなわち「擬態文字」の話題を取りあげた際、細見和之著『ベンヤミン「言語一般および人間の言語について」を読む──言葉と語りえぬもの』からの“孫引き”のかたちで言及したことがあります。
ベンヤミンが「言語はいかなる場合でも、伝達可能なものの伝達であるだけにとどまらず、同時に伝達不可能なものの象徴でもある」とし、また「名前…がたんに伝達する機能のみならず、伝達機能と密接に結びついた象徴的機能をも有していることは、きわめて確かなことである」(「言語一般および人間の言語について」第25段落)と書いたことを受けて、細見氏は次のように述べていました。
「「名前」が「伝達機能と密接に結びついた象徴的機能をも有している」というのは、当然のことと思われるかもしれない。しかし、これがやはりかなり特異な発想であることを…確認しておきたい。ランプを例にとれば、まさしく「ランプ」という名前・呼称に、伝達不可能なものとしてのランプの精神的本質の「象徴」を見て取ろうとする態度だからである。ここで「ランプ」という音ないし文字はランプを指すたんなる記号であってはならない。「ランプ」という音はランプという存在の、いわば‘擬音語’であり、さらには擬態語、‘擬態文字’でなければならないのである。
この傾向をもっとも顕著に示しているのが、一九三三年に書かれた「類似したものについての試論」であり、その続稿ないし改定稿として成立した「模倣の能力について」…である。そこでベンヤミンは、そもそもすべての音声言語を擬音語として理解する方向を示すとともに、文字を「非感性的類似の貯蔵庫」…と呼んでいる。擬音語が外的に理解しやすい「感性的類似」にもとづくのにたいして、擬態語は、…そのままでは類似を見て取ることのできない「非感性的類似」にもとづいているのである。そして、文字が「非感性的類似の貯蔵庫」であるということは、すべての文字はそもそも擬態文字であるということだ。」
話がいきなり後期に飛んでしまったので、元に戻します。ベンヤミンの初期言語論と言えば、まず細見本のタイトルにある「言語一般および人間の言語について」(1916年)[*]、そして──山口裕之氏が『ベンヤミン・アンソロジー』の「訳者解説」で、「初期の言語論の思想的ヴァリエーションである」とした──「翻訳者の課題」(1922年)の二篇に極まります。ここでは、前者から「創造する神の語」を、また後者から「純粋言語」の概念を(「読まれない文字」の原型として)切り出しておきたいと思います。
◎神の語
ベンヤミンは「言語一般および人間の言語について」において「事物の言語=存在の言語」/「人間の言語=認識の言語(名づける言語)」/「神の語=創造の語」の三層構造にもとづく言語論を展開し、その最終第26段落で「言語についての純化された概念」を次のように語っている。
「ある存在の言語とは、その存在の精神的本質が自己を伝達する媒質[Medium]である。この伝達の途切れることのない流れが、自然全体を通って、もっとも低次の存在から人間にいたるまで、そして人間から神へと流れている。人間は、自然と自分の仲間に対して、(仲間には固有名で)与える名を通じて、自己自身を神に伝達する。そして、自然に対して人間は、自分が自然から受け取る伝達に応じて名を与える。というのも、自然全体もまた、名もなき黙した言語に、つまり創造する神の言葉の残滓で満ちているからだ。この神の言葉は、人間のうちに認識する名となって、また、裁きを行う判決となって人間の上に漂いつつ保たれてきた。自然の言語は、歩哨がそれぞれ次の歩哨へと自分自身の言語で伝えていく、ある秘密の合言葉に喩えることができる。しかし、合言葉の中身はその歩哨の言語そのものなのだ。あらゆる高次の言語は、低次の言語の翻訳である。それは最終的に明晰なものとなって、この言語運動の統一体である神の言葉が展開してゆくまで続いてゆく。」(『ベンヤミン・アンソロジー』35頁)
──水が自ら熱を帯びることによって熱を伝達する媒質であるように、言語は自ら名・固有名もしくは合言葉となって、自然の事物あるいは人間(話し手)の「精神的本質」を伝達する。この媒質としての言語の流れを通じて伝達されるものは言語そのものであり、低次から高次へと向かう言語運動において翻訳されるのは(意味や事象内容といった実質ではなく、いわば形式としての)言語そのものである。
◎純粋言語
ベンヤミンは「翻訳者の課題」の第11段落で、翻訳の能力について次のように語っている。
「究極の本質を意味から解放すること、象徴するものを象徴されるものそのものにすること、形成されたもののかたちで純粋言語を言語運動へと取り戻すこと、それが翻訳のもつ力強い、そして唯一の能力である。純粋言語は、もはや何も意図せず、何も表現しないが、表現を欠いた創造的な言葉となって、あらゆる言語において意図されたものそのものである。この純粋言語のなかで、最終的には、あらゆる伝達、あらゆる意味、そしてあらゆる志向が一つの層に達する。そこではそれらがすべて消滅すべく定められている。そして、まさにこの層から、翻訳の自由が、新しいより高次の権利を得ると確信されることになる。」(『ベンヤミン・アンソロジー』105-106頁)
(文中の「象徴するもの」とはいわゆる「音象徴」やオノマトペ(擬音語、擬態文字)がその典型だろう。また「形成されたもののかたち」は文字以前の〈文字〉である“フィギュール”もしくは生まれたての《文字》の新鮮な“姿”を思わせる。)
ここで先達の議論を援用する。宇波彰氏は『記号的理性批判──批判的知性の構築に向けて』において次のように論じている。以下(「哥とクオリア/ペルソナと哥」第13章の“再利用”)はその概要。
──ベンヤミンはつねに「事実的なものが理論である」というゲーテの教えに忠実であった(ボルツ)。
そのベンヤミンは「翻訳者の課題」で次のように書いている。「いかなる詩も読者に、いかなる美術作品も見物人に、いかなる交響曲も聴衆に向けられたものではないのだ。」ここでベンヤミンは、テクストが受け取るひとのために存在するのではなく、それ自体で価値を持つといっている。このようなベンヤミンの思想と深い関係があるのは、彼の純粋言語(reiner Sprache)の概念である。純粋言語は、「もはや何ものをも意味せず表現しない」(「翻訳者の課題」)。それは意味を持たず、表現もしていない言語であるから、もとより伝達の手段ではなく、したがってそれを「解釈」することは最初から不可能である。
純粋言語という考え方には、ヴォーリンガー(『抽象と感情移入』)の影響がある。ヴォーリンガーは、感情移入、つまりミメーシスを原理とする芸術を否定した。ミメーシスに代わる原理が「抽象」である。それはいかなる「表象」とも断絶した、リーグルのいう「芸術意欲」に基づく芸術の原理であった。
ベンヤミンは『ドイツ悲哀劇の根源』で、ヤコブ・ベーメの「永遠のことば、神の響き、神の声」ということばを引用している。「神の声」は表現や伝達を目標としていない純粋言語であり、人間の堕落以前、バベル以前の「アダム語」である。芸術家はときにこのような「言語以前の言語」を用いた作品を作る。たとえば、ジジェク(『幻想の感染』)はシューマンの「フモレスケ」について、「声にならない〈内なる声〉にとどまる、声による旋律線」云々と書き、ラカン解釈のキーワードのひとつである「到達不可能なものとしてのル・レエル」(the impossible-real)という概念を使って説明している。
地上の人間は「神の声」をなんとか聞こうとする。そのときに考えられる手段が、アレゴリーである。「アレゴリカーの手のなかで、事物はそれ自体ではない他のなにかになり、それによってアレゴリカーは、この事物ではないなにかについて語ることになる。」(『ドイツ悲哀劇の根源』)ここでベンヤミンが「事物」(Ding)といっているのは、パースの「対象O」(記号連鎖のプロセスにおいて最初に存在する解釈の対象)であり、「なにかほかのもの」といっているのは無限に継起する記号S、S'、S''…である。(そしてベンヤミンの「アレゴリー」とは文字である。)
[*]柿木伸之氏は『ベンヤミンの言語哲学──翻訳としての言語、想起からの歴史』のなかで、ベンヤミンの「言語一般および人間の言語について」とウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』(1918年完成)が「一つの世界の崩壊を印づける出来事と言うべき第一次世界大戦を目の当たりにしつつ書かれたことは、覚えておいてよいことと思われる」(95頁)と書き、以下「ヴィトゲンシュタインとベンヤミン、あるいは像と名」の議論を展開している。
《このとき二人は、言語が経験から乖離して世界に応える力を失い、それゆえに空虚な記号と化して蔓延っている危機的な状況に立ち向かいながら、世界に応答しうる言葉の在り処を、言語の本質に求めているのである。ヴィトゲンシュタインが言語を、「語りうるもの」を明晰に表現する「像」と規定したのに対し、ベンヤミンは、「語りえないもの」に言葉を与え、世界の現実として語り出すような「名」であることのうちに言語の本質を見て取っている。さらに、そうして名づけるという言語の根源的な働きは、彼にとっては翻訳にほかならない。言葉を発するとは、翻訳することなのだ。》(『ベンヤミンの言語哲学』101-102頁)
また、中井秀明氏は「ベンヤミン「翻訳者の使命」を読みなおす(2)――ウィトゲンシュタインの中動態」において、ウィトゲンシュタインの「論理形式」を「アウラ」に見立てている。
《こうしてベンヤミンは、「命題」において「論理形式」が「示される」というウィトゲンシュタイン的事態を、「言語」において「言語的本質」が「精神的本質」を「語る」という事態に読み替えたのである。あるいは、語ろうとしても同語反復にしかならないもの――「語り得ぬもの」――を、特定の語り手ぬきに、言語において自動的・自発的・不可避的に「語られてしまうもの」として語った。言語が語るのだと。
「諸言語」は「それらが言おうとしていることにおいて互いに親近的な関係にある」という「翻訳者の使命」の表現で、この「言う(Sagen)」は、以上見てきたような意味での「語る」の同義語として考えなければならない。つまり、「言語による伝達」ではなく「言語における伝達」の意味で。「諸言語によって人間が言おうとしていること」の比喩ではなく「言語それ自体が言おうとしていること」の字義で。この「言う」において語るのは、文字通り言語であって、人間ではない。言語から垂直に浮き上がるアウラとしての「論理形式」について、ベンヤミンは語っているのだ。》[http://d.hatena.ne.jp/nakaii/20121022/1350885571]
──ウィトゲンシュタイン(1889-1951)とベンヤミン(1892-1940)、この二人の同時代人が言語というフィールドにおいて切り結ぶ関係は途方もなくスリリングである。私の個人的関心を言えば、そこにハイデガー(1889-1976)を、さらに萩原朔太郎(1886-1942)や折口信夫(1887-1953)、九鬼周造(1888-1941)といった面々を加えることで、言語と言語による表現をめぐるある“連関”が見えてくる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
