
[推理小説] 少年ナイフと完熟レモン 第一話 5分の1の行方
☆7つのノートにまたがってますが、小説は最後まで無料で読めます (最後のノートは投げ銭式です) 目次はこちら その1はこちら
その4 井上君は推理する
ゲーム脳なんてうさんくさい言葉が流行るくらい、世の中じゃゲーマーってのはバカの代名詞みたいに思われてる。でも、ゲームをやってる奴が勉強できないのはバカだからじゃない。勉強をしないからだ。
ことに格ゲーにおいてはバカじゃうまくならない。ほら、負けるとチンパンジーみたいにムキになってボタンを叩いてくる奴とかいるだろ?そういうやつは、上達は絶対しない。負けようが勝とうが、試合にはゲームを解析する情報が詰まってて、頭のいいやつなら次はあれを試してみようという想像で頭がいっぱいになるんだ。
たとえば、攻撃は、距離やタイミングによっては必ず反撃を受けてしまうものがある。これを確定反撃、略して確反、もっとカジュアルに言うとお仕置きとかいう。まともに格ゲーをやりたければ、いろいろなキャラに対し、確反に使える技を自分で開発していかなきゃならない。
相手が確反があることを知ってれば、その射程圏内で攻撃を出すのはやめる。同じように考えてみたらどうだ。昼休みに見たように、ここからは冷蔵庫の中まではっきり視界に入る。
「あのさ、さっきから見てたかどうか聞いてきたけどさ。先輩は逆に調理実習室は丸見えだってわかってるわけじゃん。例えば、店員の前で万引きする?」
スポンジに手を出しているところを見られたら、確定反撃だ。そんな行動、普通の神経だったらとらない。
「えー、店員の前でやるからおもしろんじゃないですか?」
うん、聞かなかったことにしよう。語感に実感がこもってるのは無視しよう。綾野さんが現役のシーフでないことを祈るばかりだ。こいつに小野先輩をひどいとか言う資格があるかどうかは一旦おいておいて、一度気になると、とことんまで調べたくなるのが格ゲーマーの性だ。
「あのさ、最初から気になってたんだけど。普通カットって、デコレートしてからしない?」
「井上君知らないの?横にカットしないとクリーム挟めないんだよ」
汐澤さんがたしなめるような口調でそう言った。知っとるわ、そんなこと。
「違う違う、横じゃなくて縦。5分の1にカットする方。先に切ったんだろ?」
「今日はデコレーション大会しようってことで、カットしたやつを、みんなが自分の持ってきた材料でデコレートしたんだよ」
そう言いながら、夏木さんが再び肩をタッチする。この人はやたらと人の肩に触りたがるんだな。まったく。
「あ、あとさ。ケーキはゴミ箱に捨てられたりしてたわけ?」
「いいや、調理実習室のゴミ箱にはケーキらしきものは何もなかった」夏木さんが言う。「生ゴミ用の三角コーナーとかにもなかったなあ」
「じゃあ、その先輩はケーキをどこにやったんだよ」
「他の教室のゴミ箱に捨てたのかもしれません」
杉山さんがうつむいて残念そうに言う。ケーキを捨てるという行為は想像してしまうと、そりゃ結構残念だ。でも、ちょっと落ち込み過ぎてて、こちらが辛くなる。
「ほら、北棟の教室は普段は全部鍵が掛かってるだろ。わざわざ渡り廊下をわたってこっちまで捨てにきたの?それってすごくめんどくさくない?」
「食べたんじゃないですかあ?」綾野さんがいう。
「『お前らの焼いたスポンジなんて、いるかー』っていいながら、バクバク食べるわけ?すごい矛盾してるじゃん」
「偶然ケーキを冷蔵庫でみつけて食べたかもよ。普段、偉そうなこと言ってたから恥ずかしくて言い出せないとかありそうじゃない?」
夏木さんが言った。この子はさっきからオレの肩にずっと手を置いている。ほんとまったく、いいんだけどさ。うん、いい。
「でも、切り落としたケーキの端が冷蔵庫に入ってるんじゃないの?」
固い部分を切り落とそうって汐澤さんたちが言っていたのを確かに聞いてた。昼休みにこの子らが全部切り落とし部分を食べちゃってない限りは、それは冷蔵庫にあるはずだ。なにしろ、調理部のゴミ箱にケーキらしきものはなかったんだから。
「え?」汐澤さんは驚いた顔で固まる。そんなに驚かなくてもいいでしょ。
「だからさ、つまみ食いするならそっちの方に先に手をだすでしょ」
「えー、やだー」汐澤さんが眉をひそめる。
「井上君、休み時間に私たちのこと盗み聞きしてたんだ」

オレの体の中の時間が、止まった。
「ちょっと、違うって」
上ずった声が出る。ていうか、何も違ってない。まずった。固い部分を切り落とすとか休み時間に言ってたのを覚えてて、つい言ってしまった。
「あたしたちに興味あったの?かわいいね。今度一緒にティラミス作る?」
夏木さんが肩の上に置いた手にぎゅっと力をこめる。
「作らねーし」オレは肩をカヌーのオールのようにまわして、手を振り払った。再び後ろのデュエリストたちと目が合う。なんか蔑んだ目で見てくるし。
「ほら、ちょっとさ。話戻そうぜ。そんで放課後、誰がはじめにケーキが欠けてるの見たの」
「もういいよ。なんか話し方が理屈っぽくて、飽きちゃった」
再び髪をいじくる。その度に桃っぽいシャンプーのにおいがする。オレは汐澤さんの雰囲気を見てわかってしまった。
こいつらは真相が知りたいわけじゃない。そんなめんどくさいことじゃなく、ただ単に小野先輩の悪口を仲間内で言い合えれば満足なんだ。なんだよそれ。
「オレが言いたいのはさ。その小野先輩がやったって決めつけはどうよってこと。みんなケーキのことが気になって、休み時間だってチラチラ調理実習室を見てたわけでしょ?それで誰も小野さん見てないわけだからさ」
汐澤さんがため息を漏らす。
「ていうかさ、なんであなたうちの部に興味持ってくるの?関係ないでしょ」
「もしかして、小野さんのこと好きなんですか」
綾野さんが、不意打ちまがいの発言をしてくる。上目遣いで笑いをかみ殺して見てくる。オレはつい、反射的に語気を荒げて叫んでいた。
「あんなブス、好きになるわけねーだろ」
「あー、怒ったあ。ムキになるのが怪しいよね。なんか小野先輩のこと知ってるしい」
どちらにしろ、そういうことにされるのかよ。これじゃハメじゃないか。どんなクソゲーだ。
それになんでオレまで、咄嗟にあいつのことを拒否するようなことを言うんだ。あいつは、そう、いいやつなのに。
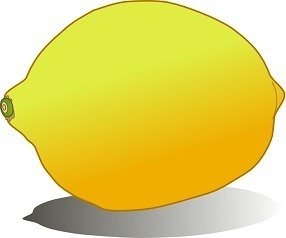
かわい目の女子たちにわいわい囲まれるという、自分の学生生活にあまりなかった現象は、あっという間にしぼんで消えていった。
「井上君、あたしらこれからガスト行くんだけどさ。一緒に来て話さない?名探偵なんちゃらみたいにさ、ケーキ紛失事件といてよ」
夏木さんはまた肩の上に手を置いてきた。
「オレ、金ないからさ。無理」
なんか、反射的に断ってしまう。
誰が言うとでもなく、あいつら全員が教室の扉に向かって歩き出した。
あいつらはきっと、今日の出来事をはっきりさせずに、明日を迎える。そんな面倒なことをする気がないんだ。本当にあったことがこの世から蒸発して、いわれない憶測だけがこの世に残ってく。
だからといって別にいいだろ。実際、調理部なんて関係ないし。自分の人生だって、曖昧なまますませてはっきりさせなかった物事なんて山ほどある。人生なんてそんなもんなんだ。
で、一体誰を納得させてるんだ。
そのとき急に杉山さんがこっちを向いた。そして小動物のようにとことこと近づいて来て言った。そしてオレの顔を見上げて言った。
「あの、スポンジを放課後はじめにスポンジ見たのは私と、汐澤先輩と夏木先輩です」
オレがきょとんとしてると、杉山さんは続けた。
「私たちが調理台で手を洗ってる間、夏木先輩が冷蔵庫から持ってきてくれたんです」「さっき聞いてくださったときに、答えてませんでした。ごめんなさい」
申し訳なさそうな顔で謝られると、こちらも謝ってしまう。
「いや、オレの方こそ面倒くさいこと聞いてごめん」
自分でも気持ちの悪いくらいジェントルな話し方で、杉山さんにそう言った。やっぱりこの中で唯一、話ができそうだ。
そっか、結局は犯人は先輩か。杉山さんの話す状況で、だれかがスポンジを食べたり捨てたりする余裕はなかっただろう。先輩が性格までブスだったということを思うと、心臓の一部が鉛になったような痛みを覚えた。
杉山さんはぺこりと頭を下げて、調理部の群れにまぎれて教室を出て行った。
「ありがとね、杉山さん」彼女の背中にそう声をかけた。
また後ろからまたデュエリストたちが白い目を送ってくる。特にロン毛メガネが、ほとんど睨みつけるような眼差しをオレに向けていた。なんだよ、女子に優しくしたっていいだろ。そんなんだからお前らはいつまでたってもブラックマジシャンガールとしか絡めねーんだよ。
心の中でそう悪態をついた瞬間、謎が解けた。事件の答えが目に飛び込んできたんだ。
そのロン毛眼鏡が「用事あるから外すわ」と立ち上がったとき、カードを四人に配っていた男が、余ったカードの山を他のカードの山の上に一枚ずつ置く。これだ。5分の1のケーキはここに消えたんだ。
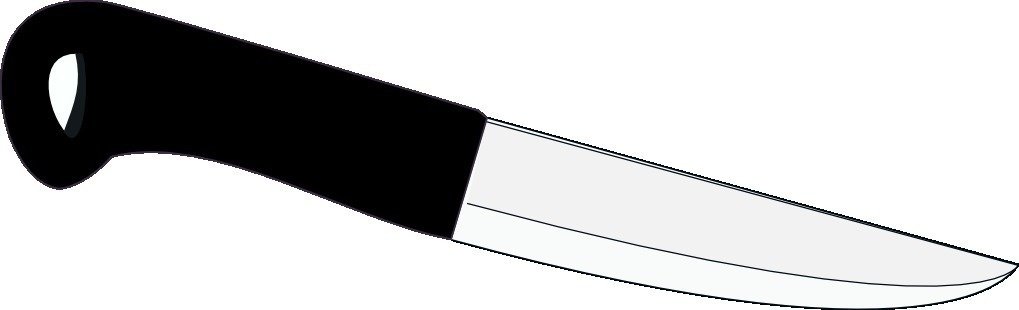
その5はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
