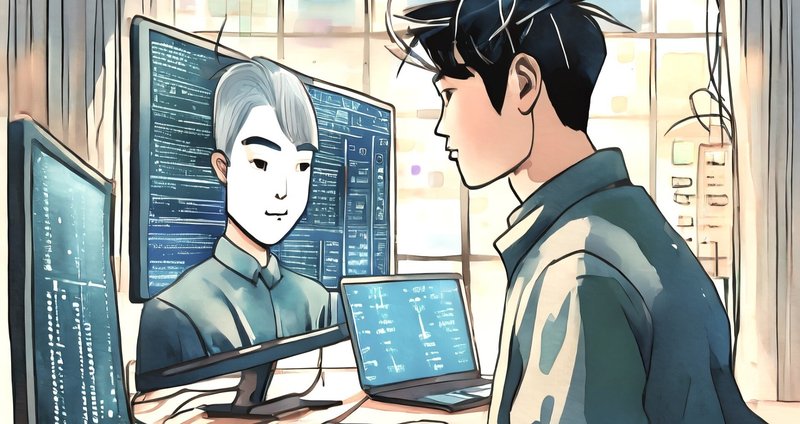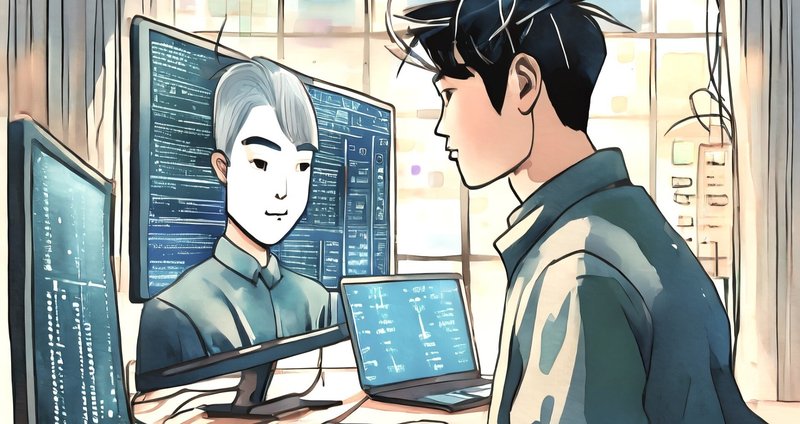[AI中山]をオンライン会議に参加させた話⑤[最終話]AIを使うか,使わないか
オンライン会議に、自作のAI画像を参加させた「実験」から学んだことを通して「生成系AIを使ってみた」について語る話の5回目(最終話)です。
「自分の身代わりAI」が誰でも作れる時代に
前回、「AIか人間かがほとんどわからないAI」がいずれできるだろうと書きました。「AI中山4号」ではまだ無理でも、この進化のスピード感から考えるに、2年後には確実に、僕の身代わりになれる「AI中山 5号」は完成するでしょう。
そして、今の僕のように1からプログラミングしなくても、写真