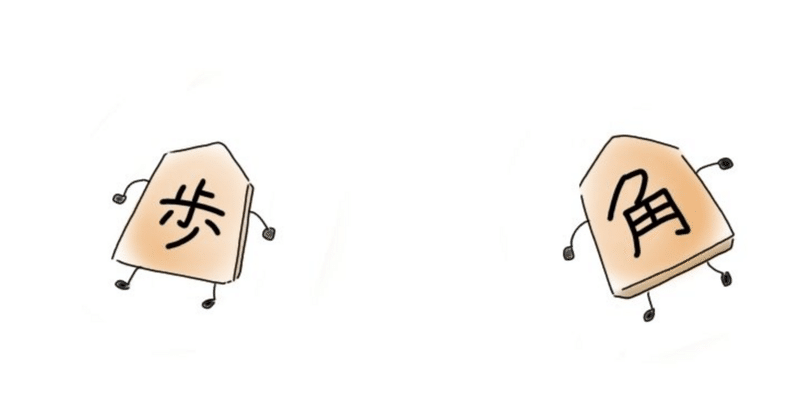
日本一時帰国の際のコミュニティへの参加方法について考える(2)
前回に引き続いて、日本に一時的に滞在する子どもたちにとって、現地の学校への聴講体験以外で、どのような「コミュニティへの参加」方法があるか、次男(当時4歳)の経験を例に、考えてみたいと思います。
ある日の夕方、放課後に学童としても機能している児童館に行った時のことでした。長男(当時6歳)が聴講していた小学校の真向かいにあり、長男の同級生も学童に参加していたので、私たちが訪れると、あっという間に長男の周りに人だかりができました。
最初は圧倒されていた次男ですが、児童館にあった様々なゲームの中から、アメリカの自宅でも慣れ親しんでいた「どうぶつ将棋」を見つけた途端、目が輝き始め、周りの子ども達と対戦して遊び始めたのです。滞在先の母の家にはゲームがあまりなかったため、このような遊びへの渇望も後押しになったようでした。普段はあまり日本語を話すのに自信がなさそうにしていた次男が、私の元を離れて、初めて出会った子達とゲームを介して果敢に話しかけて行く様子を見るのは、とても嬉しいことでした。
私自身、恥ずかしながら、元々将棋に深い関心や知識があったわけではなく、我が家の「将棋」との出会いは偶然でした。アメリカ在住の大切な友人が、日本で姪っ子さんがハマっていたという「どうぶつ将棋」をプレゼントしてくれて、まずはそこからのスタートでした。その後、公文の「スタディ将棋」を購入して、実際の駒の動きを確認しながら遊ぶようになりました。
アメリカでは、チェスは子どもにも大人にも人気がありますが、コロナ禍のステイホーム期に、より若い世代の競技人口が拡大したそうです。子どもたちも、現地校でチェスのルールを習い、友達と対戦したりする機会があるようです。一方、将棋は、アメリカでは競技人口が少なく、ニッチなゲームではありますが、"Japanese Chess"といえば、将棋を知らない相手にも、割と簡単に理解してもらえるという利点があります。
そして何より、前述の例のように、我が家のような継承日本語家庭の子ども達にとっては、日本に一時帰国した時に、老若男女問わず、いろいろな方と即座に交流できるきっかけになるのが大きな魅力だと思っています。
この児童館での一件の後、もっと日本にいる間に将棋を介したコミュニティに参加できないかと探したところろ、市内の国際交流会館で行われていた、子ども、あるいは外国人を対象とした将棋体験クラスを見つけて、行ってみることにしました。シニアのボランティアの方から、みっちり将棋の指導(駒の置き方、挨拶の仕方など、基本的なルールやマナー。長男に対しては、棋譜の書き方の指導)をしていただき、今まで自己流でやってきた我が家にとって親子ともども、良い学びの経験となりました。
特に、幼稚園の体験などを行わず、ほとんどの時間を家族と過ごしていた次男にとって、自分が好きで慣れ親しんでいるゲームを介して、自信を持って新しく出会った方と交流できたことは、ポジティブな成功体験となったと思っています。
また、余談ですが、将棋の駒に書かれた漢字も幾度となく目にするたびに、自然と身についたようで、「これが金、あれが銀」だとか、兄弟間でワイワイ話していました。また、個人的には、将棋の駒やルールに基づいた慣用表現(金が成ることから、「成金」など)が多々あるという発見も興味深く、今後、子ども達がこのような表現に出会った際にも、理解が深まるきっかけになればとも、少し期待しています。
さて、アメリカに戻った後も、子どもたちは引き続き「どうぶつ将棋」のゲームアプリを使って、練習したり、オンラインでの対戦も楽しんでいます。今後も、ゲームとしての将棋をサポートしつつ、メディアミックス戦法で、将棋をテーマにしたアニメや漫画などにも発展させていけたらと考えています。
何らかのご参考になれば幸いです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
