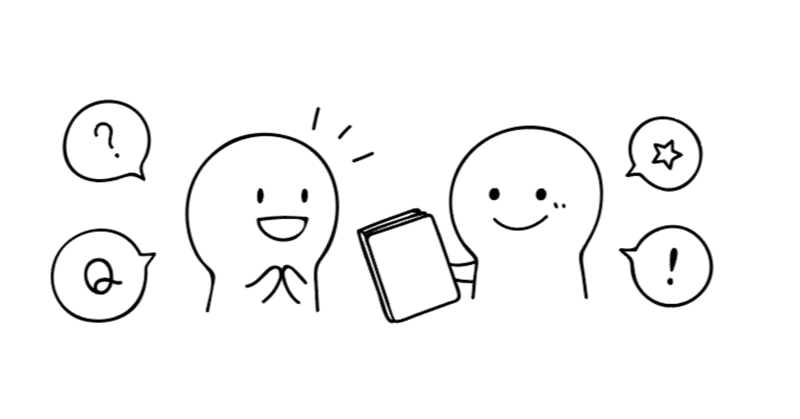
クラシック音楽の演奏家は、数百年前の音楽を現代に伝えるインフルエンサーでありアンバサダーだと思う。選ばれるクラシック音楽家になるためのセルフマーケティング講座第0回
こんばんは。名古屋クラシック音楽堂(@nagoyaclassicca)です。今日はクラシック音楽の歴史を離れて、演奏家や音楽家の皆さんに役立つお話をしたいと思います。
以前、名古屋クラシック音楽堂のTwitterで、フォロワーさんにどんなツイートに興味があるかアンケートを取りました。
【フォロワーの皆さまへアンケートご協力のお願い】
— 名古屋クラシック音楽堂 (@nagoyaclassicca) June 21, 2020
いつも当アカウントをフォローいただき、ツイートにいいね!&リツイート大変ありがとうございます!
このアカウントでクラシック音楽のどんなテーマのツイートがされたらいいと思うかアンケートを取りたいと思います
ご協力のほどお願いします!
その中で、「演奏家・音楽家のための集客&マーケティング術」にも多くの票をいただきました。今回はその第1回目の記事となります。
クラッシック音楽の演奏家は、数百年前の音楽を現代に伝えるインフルエンサーでありアンバサダーだと思う。
今日のnoteのタイトルにもなっているのでくどいようですが、このテーマから始めたいと思います。
インフルエンサーとかアンバサダーとかなんだか今風なキーワードを出しました。しかし考えれば考えるほど、このキーワードがしっくりきます。
本題に入る前に2つのエピソードをご紹介します。
1829年メンデルスゾーンがバッハの「マタイ受難曲」を100年ぶりに復活演奏し、バッハの再評価につながった。
バッハの「マタイ受難曲」は、1727年4月11日、ライプツィヒの聖トーマス教会において初演されました。
1750年にバッハが亡くなり忘れられた存在になっていた「マタイ受難曲」をメンデルスゾーンは復活上演をし、この名曲が現在まで演奏し続けられています。
メンデルスゾーンが14才の時に彼のお祖母さまからクリスマスプレゼントとして「マタイ受難曲」のバッハ自筆稿の写本をもらったという記録も残っています。
リストは歩くカバー系Youtuberだった?
もうひとつ、「ラ・カンパネラ」で有名なリスト。この曲の正式名称は、『パガニーニの「ラ・カンパネラ」の主題による華麗なる大幻想曲』
パガニーニのヴァイオリン演奏を聴いて大きな衝撃を受けたリストが「自分はピアノのパガニーニになる!」と決意し、自らの技術を磨き上げて作り上げた曲だと伝えられています。
天才的なピアニストであり作曲家でもあったリストは、「ラ・カンパネラ」のように他の著名な作曲家の作品をピアノ作品に数多く編曲しています。
これは、当時都市部で流行っていた大きな編成を必要とする交響曲や協奏曲を、ピアノ曲に編曲して自分の地方公演で演奏することで、地方に住む人にも都市部の流行曲を伝えていたといわれています。
現在のようにインターネットはおろか、録音技術もない時代に過去の名曲を時代を超えて、物理的な距離を超えて聴衆に伝えるには生で演奏するしかありませんからね。
現代を生きる演奏家がクラシック音楽を演奏する意義とは?
そろそろ本題に入りますね。メンデルスゾーンは100年という時代を超えた名曲を再演し、リストは過去や同時代に生きた名作曲家の主題をピアノ変奏という形で多くの聴衆に伝えました。
現代に生きる演奏家・音楽家の皆さんは、普段の演奏会でご自分が取り上げるプログラムにどんな意義をお持ちでしょうか?
過去その時代においては盛んに演奏された名曲も、演奏家が取り上げない作曲家や曲は埋もれていきます。
では、定期演奏会やコンサート・リサイタルで、どの作曲家のどの曲をプログラムとしてとりあげるかってとても重要だと思います。
そして、どんなポリシーで演奏会のプログラムを組み立てるかは、演奏家・音楽家個々人のアイデンティティにも関わってきます。
演奏されなければ、時間とともに忘れられていくのがクラシック音楽という再現芸術の特徴でもあり、無限にある楽譜からどの曲を、なぜプログラムに取り上げたか聴衆に伝えていくのも演奏家・音楽家の役割だと思います。
今日のnoteの元ネタにTwitterでこんなことをつぶやいていました。
正解はないのかもしれないけど、現在の演奏家に求められるのは
— 名古屋クラシック音楽堂 (@nagoyaclassicca) June 29, 2020
YouTubeの配信、演奏会のプログラムでどの作曲家のどの曲を取り上げるか
ここにアイデンティティが求められてる気がします
演奏家はクラシック音楽におけるインフルエンサーでありアンバサダーである
最近よくそんなことを考えてます
現代に生きるクラシック音楽演奏家は、ある意味すべからくインフルエンサーでありアンバサダーである
— 名古屋クラシック音楽堂 (@nagoyaclassicca) June 26, 2020
数百年前に書かれた作品を演奏することは、今に生きる人へ、その作曲家が描いた世界観を伝える役割を持っていると言えなくもない
そんな気がします
名古屋クラシック音楽堂はTwitterもやっております。

名古屋クラシック音楽堂のTwitterでは、毎日クラシック音楽に関するニュースや、演奏会・ライブ配信などの情報をシェアしています。ぜひフォローお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
