
「地域を次世代につなぐモビリティ共創拠点」、キックオフ!
車は混みそうだし、電車で行くのもだるいなぁ…
今日は疲れちゃったから、玄関まで誰か送ってくれたらいいのになぁ…
「移動」って、実は結構ストレスだったりしませんか。
今回は、移動問題なんとかならないかなー😩、と感じている方に読んで&聴いていただきたい内容です!
3月28日火曜日、名古屋大学では「地域モビリティ」をテーマにする大きなプロジェクトがキックオフシンポジウムを行います。
ちなみに、このプロジェクト、JST科学技術振興機構が提供する「共創の場形成支援プログラム」通称COI-NEXT(シーオーアイ・ネクスト)に採択され、始まったばかりのプロジェクトです。COI-NEXTは、人と社会と大学が変わることにより、共創の場をつくることをコンセプトに掲げています。
プロジェクトの正式名称は「地域を次世代につなぐマイモビリティ共創拠点」。いったいどのように移動問題を解決しようとするプロジェクトなのか、プロジェクトリーダーの森川高行教授に伺いました。どなたにもご参加いただけるキックオフシンポジウムの見どころについても教えてもらいました。
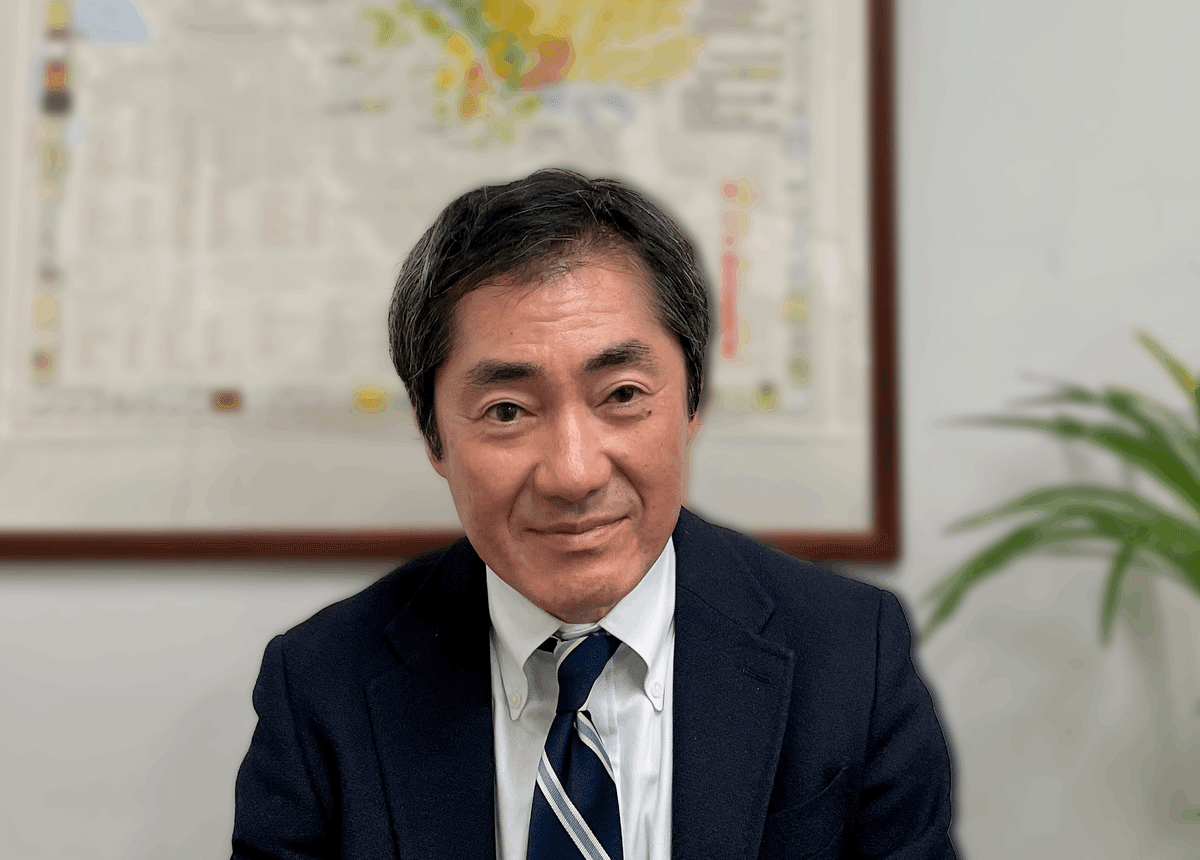
(名古屋大学未来社会創造機構/大学院環境学研究科)
インタビューを、以下から音声でお聞きいただけます。
──「地域を次世代に繋ぐモビリティ共創拠点」の中にある「マイモビリティ」という言葉について教えてください。
マイカーという言葉は皆さんよく使われると思うんですけれど、”マイモビリティ”は初めての言葉だと思います。これ作った言葉なんです。これはモビリティ、つまり移動手段のことなんですが、移動手段をですね、自分ごとと考えて、移動の問題を自分たちで解決していこうということです。マイカーを含んで、公共交通機関なんかも自分たちで守っていく、そういう概念を「マイモビリティ」といっています。
──このプロジェクトでは、ビジョンとして「みんなの行きたい、会いたい、参加したいを叶える超移動社会」と掲げていいます。“みんな”とは誰のことで、“超移動社会”とはどんな社会をイメージされているのでしょうか?
“みんな”は本当に文字通り“みんな”なんですけれども、特にフォーカスしていますのが、車を使わない人。これは運転免許持っていない、車を使えない人と、それから運転免許を持って車もあるんだけれど使いたくない人。これ合わせて“車を使わない人”といっています。こういう人たちにも自由な移動の機会を与えようと。
そして超移動社会って、これもね、作った言葉なんです。“超伝導”という言葉がありますね。電気抵抗がゼロになって電流が中に流れるような物体のことですけども、これになぞらえまして、移動の抵抗、つまり移動に関わるストレスのようなものが極めて小さくなって、人々がストレスなく自由に移動できる社会を“超移動社会”といっています。
──超伝導の考え方を使ったのは、おもしろくてわかりやすいですね。
そうですね。ちょっと言い過ぎなんですけど、ストレスはゼロにはなりませんので…。
──今回のプロジェクトの前身として、2013〜2021年に、「人がつながる “移動”イノベーション拠点」が行われていました。これは大きな成功を収めたということですが、今回のプロジェクトでは前回達成したどのようなことを活かして、今後どのようなことを新しく取り組んでいかれるのでしょうか?
前身のプロジェクトは高齢者を対象にしていたんです。やはり高齢者は、車を運転できない人が多く、そして段々健康に問題を抱えていく人も多くなっていくということで、高齢者を対象に外出の機会、そして外出の手段を与えて、社会参加して元気になっていただくと、こういうプロジェクトだったんです。もちろんその過程で様々な移動の新しいサービスとか、高齢者にも乗りやすい自動運転車などを開発してまいりました。
今回のCOI-NEXTでは、その移動サービスを作った成果、それから自動運転車、こういうものも活用しまして、対象を高齢者だけではなく若い世代、子育て世代にも対象を広げて、より誰に対してもどこに住んでいても自由な移動を提供できて社会参加の機会を広く与えていこうと。このような拡張になっています。
──そうしますと、様々なライフステージの人、例えば“子ども”としましょうか…、“子供”がモビリティを実現するというと、どういったイメージを持たれていますか?
そうですね、子どもさんがマイモビリティを自ら作るというのはちょっと難しいかもしれません。けれども、ご両親と一緒に、例えば地域の公共交通に積極的に乗っていく、そしてその公共交通の乗り方を勉強して自分1人でも乗って行けるようになるとか。地域の公共交通を乗り育てていく、乗り守っていくという点でも、子どもさんでも参加できるんじゃないかなと思います。
──子を持つ親としても、安心安全な子どものマイモビリティがあれば非常に便利だなと思いました。このプロジェクトは10年間の計画とのことですが、10年をどのように進めていくのでしょうか?
このプロジェクトは2022年度から2031年度までの10年間、年間約2億円の予算を国の方からいただくという規模感ですね。
そして10年間を大体3つのフェーズに分けまして、最後の3年ぐらいでは、いわゆるPOC(Proof of Concept / 概念実証)といいますか、それまで考えてきたことを、社会で本当に役に立つかというような実証実験を行うと。そのような計画になっています。
──どのような組織が参画しているのですか?
私どものCOI-NEXTは、地域共創分野といいまして、地域の課題を解決するということになっておりまして、地域の自治体に幹事自治体として入っていただくことになっています。私どものプロジェクトでは名古屋市と春日井市が幹事自治体です。その他、自治体としましては愛知県と岐阜市です。民間企業としましては、純粋な意味での企業ではないんですけれども、中部経済連合会。個別の企業としましては、JR東海、名古屋鉄道、ヤマハ発動機、KDDI、KDDI総合研究所、日建設計総合研究所に入ってもらっています。
その他、研究組織としましては岐阜大学、愛知県立芸術大学、東海大学。国系の研究所としまして、産業技術総合研究所が入っております。
──今リストアップしていただいた企業組織を聞くだけでも、非常に大きなプロジェクトとお察しします。3月28日にはキックオフシンポジウムが行われるということですが、どのような内容を予定されているのでしょうか?
実は、このプロジェクトは今年度(2022年度)から始まっておりますけれども、実質始まったのは昨年(2022年)の11月からということで、今回のイベントはキックオフのイベントということになります。ということで、我々のこの10年間の計画…どんなことをやっていって、どんなことが達成できそうかということを皆さま方と共有します。また聴衆の皆さまからいろいろフィードバックをいただいて研究計画に役立てていこうと考えています。
──イベントのポイントや見どころ、聴きどころを教えてください!
そうですね。研究全体がどういうことをやるかというお話をしますけれども、その中にはとても夢が膨らむような、新しいモビリティのお話も出てくるかと思います。例えば、私なんかが若い頃SFで出てきたような乗り物。具体的に言いますと、小さな車が自動運転で家の前から出ていって、それが幹線道路に入るとくっついて、みんなで一体になって走って、また最後にはバラバラになって個別の目的地になっていく…というような新しいモビリティができないだろうかと。こういう構想についてもまたお話したいと思っています。
──特におすすめしたいのはどのような方ですか?
まず自治体の方ですね。地域の公共交通また移動の問題が最近課題になっておりますので、対応される方にもちろん聞いていただきたいです。また民間企業の方で、特にモビリティ系や情報通信系や電気系の方ですね。何か新しいモビリティを作って開発して社会に実装したいと考えてるような企業の方にもぜひ聞いていただきたいと思います。
──多くの方に参加していただき、新しい発見やインスピレーションが生まれるといいですね。
はい、そのように考えていますのでぜひ多くの皆様にご参加いただければと思っています。
──森川教授、ありがとうございました!

◯関連リンク

「地域を次世代につなぐマイモビリティ共創拠点」ホームページ
https://mymobi.mirai.nagoya-u.ac.jp/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
