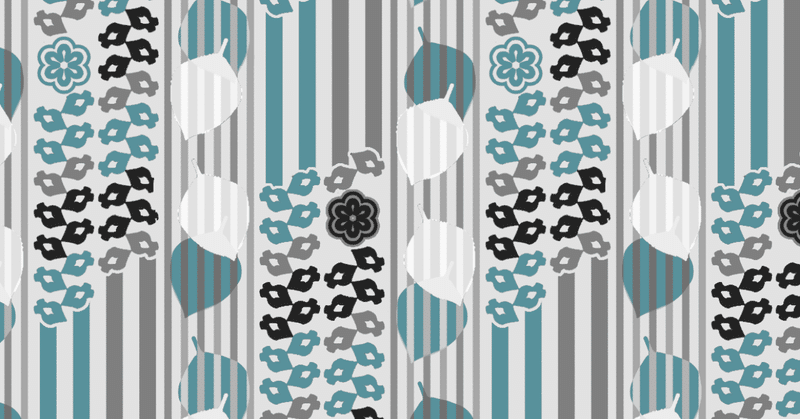
幻想生物大事典(3)一角獣‐凍てつく月の解ける随に(上)‐
――そのままだと、そのうち凍りついてしまうわよ――
幼い頃の両親の離婚が原因で男性不信になった少女、純子。
ある日出合った見知らぬ女性の一言が、彼女を幻想の世界へ引き寄せていく。
架空の女子校を舞台にした、オムニバス連載の3作目。よろしければお付き合いを。
画像は柴桜様制作『いろがらあそび8』作品No.51をお借りしています
⇒https://www.pixiv.net/artworks/70493328
◆本編
人間って、何だかんだ言っても四足(よつあし)の獣なんだな、と砂月純子(さつきじゅんこ)は冷やかに思った。
「さっきから、何を見てるの?」
そう言って、傍らの友人がひょいと彼女の視線を追う。
「別に……」
その瞬間、電車がガタンと大きく揺れ、純子の声はかき消されてしまった。鋭い初夏の西日が瞼を刺す。
彼女の視線の先にいたのは、少し離れたロングシートに腰掛け、ぴったりくっつき合って談笑している高校生らしいカップルだった。
夕方の帰宅ラッシュ直前で混雑していたためか、立っている純子たちの視線に彼らは気づいていないようだった。もっとも、仮に車内が空いていたとしても、二人が気づくことはなかっただろう。見るからにお互いの、二人だけの甘い世界に浸りきっている様子だった。
それを見とめた友人が、目を見開いて言った。
「あれ、あの男の人……確か先月、あんたに声かけてきた人じゃない。青嵐(せいらん)高校の1年生だっけ」
そう言いながら、無遠慮にカップルをじろじろ見ている。そして、くつくつと忍び笑いを漏らしながら囁いた。
「……うわあ。隣の女の制服、うちの高等部のだよ。やだあ。わっかりやすい『ブランド狙い』じゃない?やだやだ、きっも」
そう言うが早いか、にやにやと笑って純子を小突く。
「ほらあ、また取られちゃったよ。あんたがいつまでもぐずぐずしてるから」
「別に。こっちは興味無いし」
純子はつんとそっぽを向いて、手元の携帯に目を落とした。丁度、続きが気になっていた電子書籍の「続刊入荷のお知らせ」が、プッシュ通知で画面に表示される。
「また、そうやって強がるんだから。……ほんとはさ、ちょっとおしいことしたなー……とか、思ってんじゃないの」
見るからに底意地の悪い笑みを浮かべながら友人が切りこむ。それを冷たく一瞥して、純子は端末画面の購入ボタンをタップした。
「全然。……順子、あんまり騒ぐと向こうにばれるよ」
すると友人の順子は、大げさに口を尖らせながら言った。
「うちのクラスの級長様は、ほんっとお堅いなあ。もうすぐ夏休みだよ、遊びたいとか思わないの?」
「別に」
純子のにべもない返答を聞くなり、順子は大きな溜息を吐いた。
「別に、ねえ」
そして一呼吸置いてから、一気に小声でまくしたてた
「いっつも、その調子。……大体なんなの、そのだっさい眼鏡。ほんとは裸眼で平気なんでしょう?それで男半分くらいは逃してるよ」
顔は怒っているように見せていたが、彼女の眼が笑っているのを純子は見逃さなかった。二人にとって、それはどこか儀式めいた、お決まりの言い合いに過ぎなかった。
「いいでしょ、別に。それに、眼鏡のひとつふたつで態度の変わる男ってなんなのよ。まるで人を物みたいに」
「何言ってるの。彼氏彼女なんて季節ものの服やアクセサリーと大して変わらないんだって。シーズンが来たら適当に選んで楽しんで、用事が終わって飽きたらポイして、また次のを探す。世の中の大概の男と女なんてそんなものだよ」
あまりに露骨な物言いに、思わず鼻白みながら純子は顔を上げた。
「それ、誰の受け売り?」
一瞬躊躇うように黙った後、順子は答えた。
「えっと……。うちのお姉ちゃん」
「……順子。そういうの、『知ったかぶり』って言うんだよ」
小さく溜息を吐いてから、純子は携帯に視線を戻す。その途中、ちらりと先ほどのカップルを見やった。
冷房が効いているとはいえ、人の熱で涼しいとは決して言えない車内で、これでもかという程ぴったりとくっつき合っている。いつか互いに冷めるときがくるとは分かっていても、見ているだけで暑苦しいな、と純子は心の中で呟いた。
「ギリシャ神話の月の女神って、処女だったんだって」
不意に順子が言った。その顔には、面白がっているような、それでいてどこか皮肉っぽい笑みが浮かんでいる。
「それがどうしたの」
少しむっとして返すと、友人は口の端を吊り上げて言った。
「純子みたいだね」
そのとき、カップルの更に向こうに、同じように寄り添い合う、見慣れた顔と見慣れぬ顔とに気がついた。彼女は、心の中で深く大きな溜息を吐いた。梅雨明けの蒸し暑さの中で、彼女の胸の奥だけが、冬の夜のように冷えきっていた。
-------------------------------------------------
玄関のドアを開けた純子は、廊下の電気が点いていることに気がついて目を見張った。この時間に、家に人がいるのは珍しい。
もしかして空き巣じゃないかな、などと冗談半分に怪しみながら、恐る恐る進む。灯りの漏れるリビングのドアをそっと開けると、奥のキッチンで料理をしている物音と匂いとがした。首を伸ばして見ると、母の澄江が料理をしている。
「ただいま」
純子がそっと声をかけると、少し間を置いてから澄江が顔を上げた。
「お帰り」
素っ気なくそれだけ言うと、再び俯く。何となく落ち着かない気持ちになりながら、純子は言った。
「珍しいね。母さんがこんな時間に家にいるの」
母が大黒柱である純子の家では、平日の夕方、彼女以外の人間がいることはめったにない。彼女の覚えている限り、母がこんな時間に家にいたのはたった一度だけだ。
そのときのことを想い出して、お腹の辺りがきゅっと縮まるような感覚を、純子は覚えた。と同時に、先ほど電車の中で見かけた二人連れが脳裡を過ぎる。
そんな彼女の気持ちになど気づかぬ様子で、ことも無げに母が応える。
「ちょっとね。仕事が思ったより早く片付いたの」
「ふうん」
そう言いながら、いつもなら、早く終わっても、仕事の付き合いだの社外の勉強会だので、帰りを遅らせるくせに、と内心反論しながら、純子は適当に相槌を打った。ふと、思いついて言葉を繋ぐ。
「そう言えば、さっき電車の中でお父さんを見たよ」
「そう」
母の返事はそれだけだったが、彼女の包丁を下ろす手が一瞬止まったのを純子は見逃さなかった。
「知らない女の人と一緒だったよ。また、違う女(ひと)だった」
「そう」
お得意のポーカーフェイスのまま、母は淡々と玉ねぎを刻んでいった。テレビの声と、鍋の中でコトコトと何かが煮える音だけがリビングに響く。
わけも無く虚しい気持ちに駆られて、純子は母から顔を背け、テレビの画面へと目を移した。不意に、母が言った。
「今さらそんなこと聞かされたって、興味も無いし意味も無いのよ。私にとってはもう、とっくに他人なんだから。……あなたにとっては、まだ『父親』なのかも知れないけれど」
にべもない母の言葉に、純子は黙ってリビングを飛び出し、二階の自室へと向かった。自分がなぜ、母にあんな報告をしようと思ったのか、彼女にもよく分からなかった。
「もうすぐ準備ができるわよ。着替えたらすぐに下りてきなさい」
冷静な母の言葉が、純子の背中に突き刺さった。
-------------------------------------------------
心が冷め切っている、という感覚に気づき始めたのは、中学校に上がって間もなくのことだった。
同級生たちが、「好きな人」や「憧れの人」の話で盛り上がっていても、何が楽しいのか理解できなかった。
――どうせいつか、壊れるのに。裏切られるのに。
いつしか、そんな思いが胸の底に巣くうようになっていた。
純子の両親は、とうの昔に離婚していた。原因は父の浮気だ。もともと女好きで飽きっぽかった純子の父が愛人をつくったのは、結婚して半年もしない頃だったという。
彼の女癖の悪さは、母が純子を産んでも直らなかった。母はそんな父に愛想を尽かして、とうとうある日、離婚届を突き付けて家から追い出したのだ。純子が小学校の2年生に上がったばかりの春先だった。
離婚届に判を押して家を出ていく時、父が純子の方へ腕を伸ばした。彼女はその手を拒否して傍らの母にしがみついた。目の前に差し出された父の手が、とつもなく汚ならしいものに思えたのだ。
純子の気持ちを微塵も理解していないらしい父の薄ら笑いが、気持ち悪くて仕方なかった。少し戸惑ったようにこちらを凝視する父の眼差しと、居間を後にする後ろ姿とを今でも覚えている。
友人たちの「恋バナ」に耳を傾けていると、いつもその時の記憶が蘇る。すると、まるで冷たい薄絹で身体を包まれているような心地になるのだ。
そんな彼女にとって、自分に近づく男は皆、うす汚い獣に思えた。実際、彼女が少しでも拒絶する様子を見せると、誰も彼も、すぐに身を翻して他の女の子にすり寄っていく。父だって、母と別れた後も近くの町に住んでいるようだったが、見かける度、違う女性を連れていた。
薄絹は、年を重ねるごとに少しずつ、厚く、重く、冷たくなっていった。それは、彼女を覆う鎧のようにも思えた。いつしか、それを心地良く感じるようになっている自分自身に、純子はとうに気がついていた。
-------------------------------------------------
「男は皆オオカミだよ」
ふと聞こえた言葉に、純子は思わず振り向いた。見ると、自分と同じ制服を着た同い年らしい少女が二人、道端で話し込んでいる。
よく見ると、どちらも知っている顔だ。塾へ行くため私服に着替え、列に並んでバスを待つ純子に、彼女たちは気がついていないようだった。
歌い古されたJポップの歌詞のような台詞に思わず反応してしまったことが恥ずかしくて向き直る。
「違うよ。男は皆、ユニコーンなんだよ」
先に発言したらしい少女に向かって、もう一人の少女が言い返す。すると、一方が怪訝そうな声で言った。
「何それ、どういうこと?」
「えっとね……」
そこから先は到着したバスのエンジン音にかき消された。後ろ髪を引かれながら、純子はバスに乗りこんだ。
――男は皆、ユニコーンなんだよ――
その言葉が、やけに耳に残った。昔、ハロウィンの仮装用に買ってもらったユニコーンのマスクを思い出す。
ユニコーンなんて綺麗なものなんかじゃない。皆、ハイエナだ。純子は心の中で叫んだ。首筋に当たる日差しはじりじりと肌を焼いているのに、心の中は冬の朝のように張り詰めていた。
* * *
気がつくと、窓の外はすっかり暗くなっていた。塾の講義が終わった後、自習室で一人、その日の授業の復習をしていたのだ。見回すと、他の生徒たちは全員帰った後だった。慌てて帰り支度をして自習室を飛び出す。
この塾には夜、幽霊が出るともっぱらの噂だった。自習室で頭から血が流れている子どもを見たとか、階段を脚の無い男の人が上り下りしていたとか、数え上げるとキリが無い。純子自身はオカルトの類をあまり信じていなかったが、それを差し引いても、夜のビルテナントはどことなく気味が悪くて落ち着かなかった。
玄関ホールまでやって来たところで、勢いよく誰かとぶつかった。
「すみません!」
とっさにそう言って、相手を見た。そこにいたのは、すらりとした茶髪の女性だった。
季節外れの真っ赤なロングブーツに、上品なワンピースを身にまとい、ほんのり香水の良い匂いを漂わせている。おおよそ、中高生の通う学習塾の関係者とは思えない人物だった。その顔にどこか見覚えがあるような気がしたが、どこで見たのか思い出せなかった。女性は、切れ長の瞳で純子の顔を珍しそうにじろじろと眺め回した後、どこか愉快そうに言った。
「あなた、そのままだと、そのうち凍りついてしまうわよ」
「え?」
――こんな暑い時期に?――
言葉の意味を飲み込めず、純子はただ突っ立って女性の顔を見つめた。
「あ、まだ残ってる子がいた」
背後から、聞き慣れた声が上がった。純子のクラスを担当している臨時講師の女性だ。
「もう、玄関の鍵を掛けるから、早く帰って……」
そう言いながら純子の方へ近寄って来たが、その向こうにいる女性を見とめると、1オクターブ高い声で叫んだ。
「わあ、もういらっしゃったんですね。すみません」
そして、受け付けの窓から事務所の中へ向かって声を張り上げる。
「塾長、いらっしゃいましたよ。『チェシャ猫』のヤナガワさん」
「え、もう? ちょっと、まって」
奥から塾長の声が返って来た。やがて、受け付けから恰幅の良い塾長が顔を覗かせた。
「やあ、お早いですね、いつもいつも、すみません」
「いいえ。こちらこそ、御贔屓にしていただいて……」
純子を蚊帳の外に、塾長たちは事務的な話を始めた。講師が、憮然としている彼女に気づいて帰るよう促す。女性に先ほどの言葉の真意を問い質したい気持ちはあったが、しぶしぶ塾を後にした。
-------------------------------------------------
玄関のドアを開けた純子は、その瞬間、中から出てきた人物と思いきりぶつかった。目の前がチカチカして、思わずよろめく。
「ごめんね、大丈夫?」
ぶつかった相手は、そう言って彼女を抱き止めた。その低い声とがっしりした腕に、純子は血の気が引くのを感じた。相手は見知らぬ男だ。
「やだ、純子じゃない。ごめんなさい、この子がこんなに早く帰ってくるなんて……」
男の背後から母の声が聞こえる。母の知り合いらしいことに、純子の緊張は幾分緩んだ。
おそるおそる顔を上げて、更に腰を抜かしそうになった。相手の顔は人間のものではなく、額に一本角が生えた馬のそれだったのだ。
ユニコーンだ、と純子ははっとした。思わず、腕を振りほどくのも忘れて見入ってしまった。と、「ユニコーン」の口が動いた。
「君が純子ちゃん?」
マスクや安っぽい特殊メイクとは到底思えないような、リアルな動きだ。目が釘付けになったまま、純子は無言で頷いた。
「『はい』ぐらい言いなさい、失礼でしょう」
母の嗜める声はほとんど耳に届いていなかった。
「いいよ、澄江さん。……初めまして、純子ちゃん。お母さんの同僚で、スギモトと言います」
「スギモト……?ユニコーンじゃなくて?」
混乱した頭で口走った言葉に、「ユニコーン」と母が顔を見合わせて笑った。スギモトという男の人は、純子に「またね」とだけ声を掛けると、そそくさと帰ってしまった。
「何、あの『馬面』の人」
「馬面って……。ほんとうに、失礼な子ね。どう見ても人間の顔でしょう。誰に似たのかしら。だから言ったでしょ、同僚のスギモトさんだって」
「何で、同僚の人がこんな夜分に、家に上がり込んでいるの」
もともと人付き合いの良い方ではない母が自宅へ上げるなんて、よほど気に入っているとしか思えなかった。何となく嫌な予感がしたが、純子はそれ以上詮索しなかった。人の顔が馬の顔に見えるなんて、今日の自分はどうかしている。
母に続いて玄関に入ろうとした時、急に足がもつれて転んでしまった。見ると、膝から下がカチコチになっていて、まるで凍っているみたいに冷たかった。短く悲鳴を上げた純子だったが、次の瞬間には、足は元通りになっていた。
――そのままだと、そのうち凍りついてしまうわよ――
塾で出合った女性の言葉が蘇った。純子は慌てて、さっきの男の人の顔がユニコーンに見えたのも、足が凍ったように感じられたのも、全て自分の見間違いや思い違いだと言い聞かせた。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
