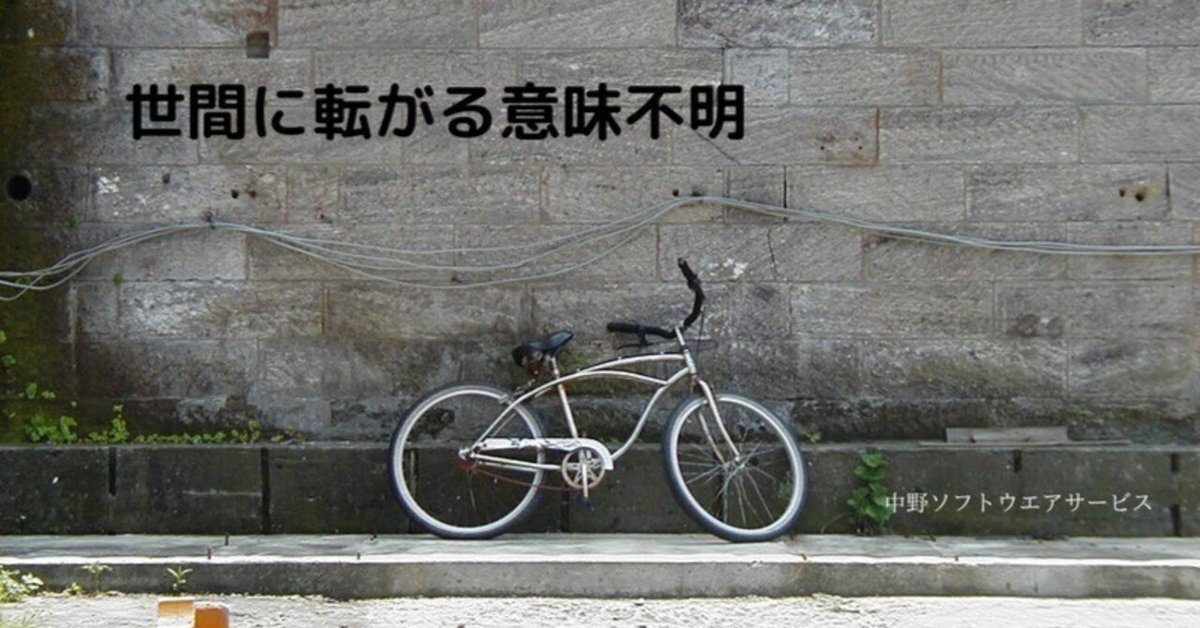
世間に転がる意味不明:めちゃくちゃなライドシェア議論(何を俎上にあげるのかの混乱)
まぁ、独り言なのだが「なんで問題を混ぜてしまうんだ」とう感が拭えない「ライドシェア問題」についてコメントです。
■「タクシー不足」と「タクシーの運転手不足」は違う
そもそもの発端は「2024年問題」であったはずであるがいつの間に「タクシー運転手不足」という問題がクローズアップされ「ライドシェア問題」に発展している。しかし、論点がかみ合わない。
その最たるものは「タクシー不足」と「タクシー運転手不足」の問題である。
そのため、下記の様な話が出てくる。
○「タクシーが全然足りない」という声は、そもそも本当なのか? 現場で上がる疑問の声、ライドシェア礼賛社会を再考する
2024.4.29
コロナ禍などの影響で、多くのドライバーがタクシー業界を去った。しかし、状況が落ち着いた現在、
「タクシードライバーは儲かる」
という情報がネット上を飛び交い、業界の門を叩く人が増えている。筆者(二階堂運人、物流ライター)は現役ドライバーでもあるが、ある大手タクシー会社では、1か月で100人近い新規採用者があったという。
公的機関によるドライバー数の最新統計はまだ確認していないが、特別区・武三地区のドライバーはかなり増えているはずだ。しかし、世間やメディアの認識は
「タクシー不足」
なのである。
https://merkmal-biz.jp/post/65093
統計データで把握できる情報としては「乗務員数」や「タクシー台数」の推移であり、これは確かに減っているのは確認できる。
http://www.taxi-japan.or.jp/pdf/toukei_chousa/jyuugyouin_suii.pdf
(その他 http://www.taxi-japan.or.jp/content/?p=article&c=575&a=15 参照)
しかし、遊休のタクシー台数などは分からないのでタクシーの稼働率などは分からない、
そもそも「タクシー不足」はどう考えるべきなのかの議論がされていない。
松本から少し田舎になる駅では駅前のタクシー会社にはヒトすらいなかった。
佐賀県の鳥栖に出張に行ったときに、駅前のタクシープールで30分ほど待たされたことがある。タクシーは一定程度の台数しかなく一巡したら返ってくるまで待たなければならない。
岩手県の大船渡に赴いたときには駅前に数台のタクシーがいたが客など誰もおらず、当然流しのタクシーなども見かけない。
タクシーの配置では
・流し(道路上を当てもなくさまよう)
・待機(駅のタクシープールで客が来るまで待つ)
・送迎(お客様からコールがあったら行く)
となるが、圧倒的に「人を乗せていない」時間が主である。
一時的に待ちとなる乗客が発生するが常態化されるわけではない。と思う。
しかし、タクシーに関して需要と供給に関するデータが不在である。
そうした中で「タクシー不足」はどう考えるべきであろうか。
■あるべき姿のデータが無い中での政策決定
「乗りたいと思ったときに乗れること」の充足率が一つの指標として考えられる。
したがって、特定の地域で
・乗りたいと思っているヒトが何人いるのか
・その時にタクシーが捕まるまでの時間はどのぐらいか
が最低限の情報になるだろう。
当然、時間帯や季節なども配慮しなければならない。また、過疎地、地方都市、観光地などでは状況が異なるからデータを混ぜてはならない。
しかし、こうしたデータを見ることはない。そうした場合、単に「タクシー不足」という曖昧な状況認識でなんとなくの政策が混乱を招く。
○タクシー規制緩和は失敗?自民党が『タクシー事業適正化・活性化特別措置法改正案』【争点:アベノミクス】2013年08月17日
安倍首相が官房長官だったときに行われた“タクシーの規制緩和”が、再び規制強化に戻されようとしている。タクシーの台数を減らす『タクシー事業適正化・活性化特別措置法改正案』の全容が8月16日に判明した…
タクシーの規制緩和(改正道路運送法)は、2002年に行われたもの。東京ハイヤー・タクシー協会のWebページにある『タクシー参入規制緩和とその後の実態』には、下記のような緩和が行われたと書かれている。
安倍首相が官房長官だったときに行われた“タクシーの規制緩和”が、再び規制強化に戻されようとしている。
タクシーの台数を減らす『タクシー事業適正化・活性化特別措置法改正案』の全容が8月16日に判明した。47NEWSによると、この法案は自民党がまとめたもので、1台当たりの売り上げが落ち込む都市部のタクシー事業者に対し、台数減らしを事実上義務付ける内容だとされる。
https://www.huffingtonpost.jp/2013/08/16/taxi_n_3771401.html
観念的に、「空車のタクシーが常に目の前にある」状況が望ましいとして竹中平蔵が規制改革を進め、タクシー運転手の苦境があるから台数の制限を設けるという安倍首相の思いつき政策が発せられてしまう。
しかし、こうした政策はどんな意図があったのかを正確に知ることは出来ない。なぜならば、例えば空車率などのデータを交通センサス並みに獲らない限り「タクシー不足」と言われる状況の変化など分からないからだ。タクシー会社やタクシー運転手、不満を持つ人々の声しか情報を得られない以上、不満解消でしか政策評価が出来ないとしたら、それは単なる人気取りでしかないからだ。あるいは、そこに漁夫の利をえるという石もあるかもしれない。いずれにしろ、朝令暮改のような政策ではその意図は分からない。
■解決したい対象はタクシー会社の窮状なのかタクシー運転手の窮状なのか
こうした思いつきの政策で振り回されるのは当然国民ではあるが、直接的にはタクシー業界であり、それを利用する乗客であろう。そうした政策は遠い過去のことではないのでトラウマになっている人々もいるのだと思い出させる。
○規制緩和が打撃「仙台」タクシー、今も残る傷の深さ
2002年の構造改革がもたらした台数急増の苦悩
2022/12/28
「昔の仙台は、タクシー運転手にとってはいい環境でしたね。1回の隔日勤務で5万円近くは稼げる市場があったんです。ところが、規制緩和により台数が爆増したことにより、営業収入は一気に3万円以下まで落ち込んだ。台数が増えたということは、それだけタクシーを利用する人が多い街だったということですが、需要と共有のバランスが一気に崩れてしまったんです。当然運転手は食えなくなり、生活は激変した。今なお、当時の流れを引きずっており、需要に対して供給過多の状態が続いています」
https://toyokeizai.net/articles/-/642308
ここで明らかなことは、タクシー不足ではない。タクシーの供給過多とタクシー運転手の収入の減少であろう。
全国的に見てタクシーの運転手や運転可能なタクシー台数の減少はあるだろうが、少子高齢化、地域の過疎化などを配慮すると全国規模でのタクシーの不足は"印象的"なものではないかと思う。
タクシー運転手の給与が上がらない以上、もっと稼ぎのよい職業に流れるのは当然であり、タクシーの運転手不足は必然であろう。2024年問題は関係ない。
■ライドシェアという安易な方策
ライドシェアという解決策は何を生み出すのかと言えば、自己管理で運行されるタクシーが増えるというだけで有り、一人頭の稼ぎが増えると言うことにはすぐには結びつかない。ましてや、新たな稼ぎがどこの馬の骨とも分からない奴らに渡るのはタクシー会社としては容認出来ないだろう。
○ライドシェア全面解禁なら「血みどろの戦いに」 タクシー業界トップ
2024/5/31
一般ドライバーが自家用車を使って有料で客を運ぶ「ライドシェア」でIT事業者などの参入を認める全面解禁を巡り、タクシー業界が猛反発している。約20年前のタクシー規制緩和が、激しい競争と賃金の低下を招いた苦い記憶ゆえだ。
https://mainichi.jp/articles/20240531/k00/00m/020/095000c
しかし、同じ記事の中で「 ただ、地方を中心に足りていないです。(都市部でも)雨の日は足りていないと自覚しています。雨や花火大会などのイベント時にライドシェアの台数を増やせるよう、国土交通省にお願いをしています。」というのはあまりにも自己都合であろう。
こうした「シェアビジネス」あるいは「格安ビジネス」がメインストリームになったことはない。確かにLCCなどはそれなりに市民権は持っているものの、少なくともビジネスや家族での旅行でLCCなどはそれなりは使わない。提示に発着すると言うことが補償されないからだ。
同様に民泊なども使用しない。安さだけを求めるならカプセルホテルやネットカフェを使う。いわゆるペンションなども使わない。蓋を開けてみなければ分からないという博打をうつきはない。
結局のところ、「安心」「安定」を担保されないビジネスには限界がある。ましてや日本型ライドシェアはタクシー会社が運営する。運賃は普通のタクシー料金並みだと聞く。わざわざ劣化したサービスを使う必要は無い。そうしたことを想起させる記事もある。
○京都のライドシェア、実際どう? 「ライドシェア車両と知ってキャンセルする人も」
2024/05/30
週末に乗務している一般ドライバーの男性(63)は「乗客のいない時は四条通や河原町通を中心に走りながら待つが、配車指示がすぐ入るので忙しい。大きなトラブルはないが、ライドシェアの車両と知ってキャンセルする人もいる」と話す。同じく一般ドライバーの中尾秀樹さん(50)は「実際の目的地が事前の指定と違う乗客もしばしばいて困ることもあった」と振り返った。
https://maidonanews.jp/article/15285180
■食い散らかされる情報
何を解決したいのかにより、あらかじめKPIは決定される。何かしらの活動の成否は、あらかじめ設定されたKPIへの達成度合いにより判断される。それがなければ、多くは結果を都合のよいように解釈するか、とりとめの無い事象を取り上げる。
下記の様な発言に対して土台となるデータも解決すべき課題も合意されていなければ、ただの言いっぱなしになる。
○日本版ライドシェアは「普通免許」でできる「バイトのタクシー」的な位置づけ! 料金もタクシーと同じで積極的に利用する理由はナシ
現状では、営業できる時間帯はかなり限られていますので、実質は普通免許で運行するタクシー会社雇用のパートタイマー・ドライバーといったところです
https://www.webcartop.jp/2024/06/1367825/
何を解決できて、何が解決されないかをコントロールできない限り、同じ状況が複雑化されるだけである。
合掌!
2024/06/05
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
