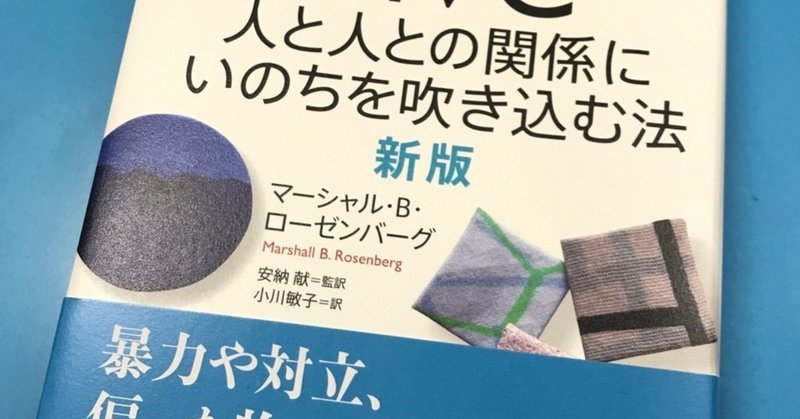
適切な感情表現はできていますか?_NVC論_vol.3
NVCって?→ Nonviolent Communication
NVCの基本
① 観察
② 感情
③ 必要としていること
④ 要求
今回は②の感情についてまとめたいと思う。
評価を交えずに、相手の行動を観察し、それに対して自分がどう感じるかのかを率直に述べる。自分の感情を適切に表現することは円滑なコミュニケーションに欠かせない。
では、なぜ自分の感情を表現する必要があるのか?
まぁそれは愚問である。
まったく感情を示さない人とコミュニケーションを取りたいと思う人がいるだろうか。ということだ。
きっとあなたにもそんな経験があるのではないだろうか?
話しかけても
「楽しいのか」
「つらいのか」
「怒ってるのか」
相手がどんな感情なのかが分からなくて、不安になったことがあるだろう。
感情をうまく表現してあげることで、はじめて相手は安心感や魅力を感じることができる。
相手の感情が見えるからこそ、人間関係の次の一手を進めることができるのだ。
しかし、多くの人はこの感情表現が非常に苦手である。
たとえば「私はあの人がすごいと感じる」という言葉は一見して、その人の感じていることを表現しているかのように思える。
ところが「〜と感じる」という言葉は、自分の感情を表現しているのではなく、相手を評価している表現方法になる。
「すごいと感じる」
というのは、相手が自分より上の立場にあるという評価でしかないのだ。
もし、これを適切な感情で表現するのであれば、すごいと感じたあとの感情を考えなければならない。
多くの人は「すごいと感じる」と発言した裏にある本当の自分の感情を表には出さない。
「すごいと感じる」
という表現の裏には、必ず「悔しい」や「安心する」といった自分の感情があるはずなのだ。
感情があるはずなのに、人はその感情を決して表に出さないようにしている。無意識のうちに。
なぜ、感情を出さないのか?
いや、感情を出せないといったほうが適切であろう。
感情を出せない原因の1つは「教育」である。
私たちは幼い頃より、学校教育で、自分の感情を表に出さない教育を受けてきた。
自分よりもまわりの人を大切にすることが一番であるという道徳教育は、自分がどんなにつらくても、まわりにそれを知られないことが美徳であるという偏った概念を生む。本当はやりたくないのに、怒られるのが嫌だから、自分に嘘をつきながら任務を遂行する。
その結果、感情を素直に表現することは恥ずかしいことであるというプライドの高い、常に論理的であろうとする人が出来上がってしまう。
自分の心の中の、本当の弱さを外に出せずに「〜と感じる」という評価を交えた擬似的な感情表現に頼ってしまうことで、対立しなくてもいいところで、まわりの人と対立してしまう
という状況が生まれる。
本当は、自分がどう思ったのかが重要であるはずなのに、相手のせいにするような発言を連発する。これでは円滑なコミュニケーションは成り立たない。
感情表現が出来なければ、練習するしかない。
自分の弱さを少しずつでも打ち明けていくことで、ちゃんと自分の感情は表現できるようになる。
「あなたはわたしを怒らせる」
▼
「わたしはイライラしている」
「なんで私を理解してくれないの?」
▼
「私はあなたに気遣ってもらえると、とても嬉しい」
自分のありのままの感情を表現することは、最初は恥ずかしいかもしれない。
しかし、自分の弱みをさらけ出すことのできる人に、なぜか魅力を感じるということはないだろうか?
人と人とが親密な関係を築くには、弱みを相手に知ってもらうということから始まるのかもしれない。
最後に、話が脱線するが、これからの時代は、自分の弱みを出せる人がリーダーになるに違いない。ひと昔前は、ワンマンでプライドの高いリーダーが活躍したが、多様性が求められるこの時代には、そういったリーダーは淘汰されていく。
自分から弱みを見せ、それを補ってもらえるような関係をうまく築ける人たちが、多くの人の共感を生み、リーダーとなっていくのであろう。
▼参考にした本
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。いただいたサポートは、高校生と地域貢献をするのための活動費用として使わせていただきます。
