
会報14号掲載記事公開「中島敦と芥川龍之介」…『山月記』と『羅生門』を中心に(講演要旨)
1992年発行の「中島敦の会」会報第14号は、中島敦没後50年特集でした。
教え子の回想や小論文などのコンテンツが掲載されました。
その中から、「敦の会」で行われた講演をまとめた記事を公開します。
中島敦を語る上で、なにかと比較される芥川龍之介について、敦文学の研究者が語りました。
※30年以上前の講演ですので、現在の中島敦研究とは状況が異なっていることをふまえて、ご覧ください。
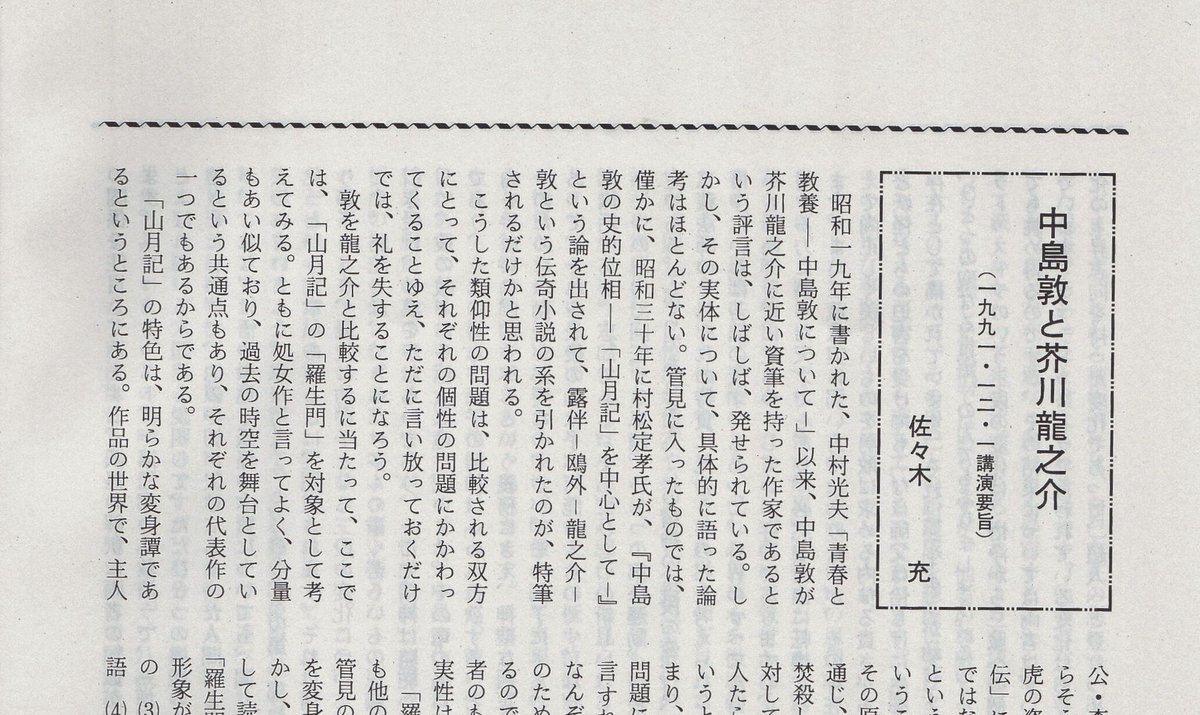
中島敦と芥川龍之介(1991年12月1日講演要旨)
講演者 佐々木充
千葉大学教授(当時)。「中島敦」「中島敦の文学」(桜楓社)など著した。
敦と龍之介 『山月記』と『羅生門』
昭和19年に書かれた、中村光夫「肖春と教養— 中島敦について」以来、中島敦が芥川龍之介に近い資筆を持った作家であるという評言は、しばしば、発せられている。しかし、その実体について、具体的に語った論考はほとんどない。管見に入ったものでは、 僅かに、昭和30年に村松定孝氏が、『中島敦の史的位相—「山月記」を中心としてー』 という論を出されて、露伴ー鴎外ー龍之介ー敦という伝奇小説の系を引かれたのが、特筆されるだけかと思われる。
編集注※管見(かんけん)自分の見識、考え方が狭いこと。自分の考えを謙遜して言うときに使うことば。
こうした類仰性の問題は、比較される双方にとって、それぞれの個性の問題にかかわってくることゆえ、ただに言い放っておくだけでは、礼を失することになろう。
敦を龍之介と比較するに当たって、ここでは、「山月記」と「羅生門」を対象として考えてみる。ともに処女作と言ってよく、分量もあい似ており、過去の時空を舞台としているという共通点もあり、それぞれの代表作の一つでもあるからである。

「人間」「人間の志」に重きをおいた変身譚『山月記』
「山月記」の特色は、明らかな変身譚であるというところにある。
作品の世界で、主人公・李徴は、確かに虎に身を変えている。
自らそう言明するだけでなく、確かに二度その虎の姿を見せる。
そしてこれは、素材「人虎伝」における設定であって、敦のオリジナルではない。
ということは、素材における変身という非現実性を、敦は全面的に肯定したということになる。
ではどこが違うかというと、その原因である。
「人虎伝」では或る女性と通じ、それをその家族が防害したので一家を焚殺した、というそこに原因を見ているのに対して、「山月記」では、周知のように、詩人たらんとしてその望みがかなわなかったというところに、原因を見ているのである。
つまり、「山月記」は、人間における「志」の 問題に、作の質を変換しているのである。
換言すれば、<おのれに相応しく生きることのなんぞ難きや>という人間のアポリアの表現のために、変身という非現実性が機能しているのであって、李徴の哀しみは、ただちに読者のものとなる。
そのとき、変身という非現実性は、一転、正当性を獲得するのである。
編集注※アポリア 解決の糸口が見いだせない難問

下人・老婆(人間)が獣になる変身譚として『羅生門』を読む
「羅生門」は変身譚ではない。下人も老婆も他の動物に姿を変えることはない。
これも管見の限りにおいてだが、これまでこの作品を変身譚として読解した例はないと思う。
しかし、私は、「羅生門」をほとんど変身譚として読んでよいのではないかと、考えている。
「羅生門」には、いろいろなレベルでの動物形象が頻出する。
(1)動物比喩
(2)動物そのもの
(3) 朱雀大路や鴟尾といった動物を含む熟語
(4) 「まるで弩にでも弾かれたように」とか「かみつくように」という動物の姿態の動きを思わせる表現。
これらが、舞台・羅生門 の内外に配されているのである。
羅生門とは、 まさに、<生き物>をからめとる門なのである。それゆえ、解雇された下人は、<喪家の犬>として羅生門に引きよせられて来るのであり、「犬のやうに」捨てられることを予想し、やがて「猫のやうに」「守宮のやうに」と比喩されるのである。
他方老婆は「猿のやうな」「鶏の脚のやうな」「肉食鳥のやうな」等々の比喩で示され続ける。
楼上でのこの二人の争いは、人間同士の争いというよりも、 動物の戦いの気配が強い。
げんに、下人は、楼上にのぼる梯子を「這ふやうにして」「体を出来る丈、平にしながら頸を出来るだけ前へ出して」…つまり、一匹の四足獣としてのぼっていたし、老婆は「猿の親が猿の子の虱をとるやうに」死骸の髪の毛をぬいており、「弩にでも弾かれたやうに」飛び上がり、「肉食鳥のやうな、鋭い眼で見」…いろいろな動物のイメージをとるのである。
そして最後、下人は「噛みつくやうに」老婆にものを言い、その着物を奪い、「足にしがみつかうとする老婆を蹴倒し」、「またたく間に急な梯子を夜の底へかけ下り」る。老婆は、「つぶやくやうな、うめくやうな声を立てながら」「梯子の口まで、違って行」き、「そこから、短い白髪を倒にして、門の下を覗きこ」む。下人はまさに俊敏な四足獸として夜の闇の中に消えて行くのであり、 ダメージを受けた老婆は、ずるずると身を引きずってまるで傷ついた蛇の執念を示す。
作品の世界の現実としては、下人も老婆も変身などしていない。しかし、このように動物イメージを次々に重ねられると、ちょうど 古典和歌における修辞法のひとつ——縁語のように、もう一つ、蔭のイメージを読者の脳裡に生成させる。老婆は傷ついた蛇のごとき生き物となり、下人は俊敏な獣――たとえば 虎になるのだ。
獣化する人間(下人)のその後が「李徴」
そのように見てくれば、「羅生門」の最後の一文「下人の行方は、誰も知らない。」は、 「山月記」の第一段落目の最後の「その後李徴がどうなったかを知る者は、誰もなかった。」 に重なると見えてこよう。つまり、「山月記」 冒頭のこの一段は、「羅生門」一編の要約と いった趣になっているのである。第二段落目から、その後のストーリーが始まる。つまり、 「羅生門」の下人の「行方」を、われわれは、「山月記」の李徴に見出すことが出来るのであり、そのような形で、敦は龍之介を継いだのである。
しかし、敦は単に龍之介を引き受けたのではない。奇異譚を好んだ龍之介は、分身小說までは書いたが、変身小説にはおよばずに他界した。「山月記」という変身小説を書かねばならなかった中島敦は、明らかに、芥川龍之介を、踏み出したのである。( 了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
