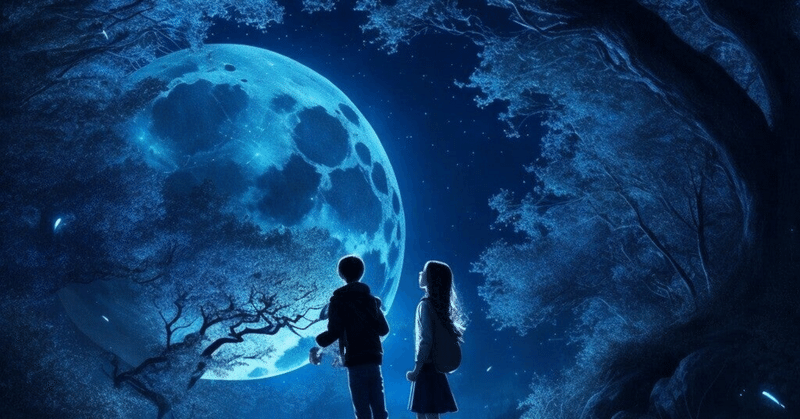
⑤攫われの姫君と、聖騎士の忘れ形見
馬が走り出し、大きな行商人用のゲートへ向かう。
聞き覚えのある男の声が聞こえると、そこにはラルケの姿があった。
ラルケはこちらに気付くと、ウインクのつもりか、両目をギュッと閉じた。
「逃げ切れればいいのですが……」
エリーはそう溢したが、そればかりは俺もわからなかった。
門を出てからは街道を進む。
車輪が小石を蹴飛ばす度に荷馬車は跳ねる。
荒野の真ん中に舗装されている街道がまるで線を書いた様に伸びている。
「どうやら、追っ手は来ていないみたいだね。アルマさん……無事だといいけど」
「そう……ですわね」
不安そうなエリーを他所に俺は謎にワクワクしていた。
勿論馬車に乗るのが初めてだったということもあるが、昨夜は夜だったこともあり、実感がなかったが、初めて世界に飛び出したんだという冒険感がそうさせていた。
「どうかした?」
エリーの視線に気付いた俺はそう訊くと、エリーは少し黙った後に話し始めた。
「……いえ、その剣に見覚えがあって」
「そうか、元は王都の騎士が持ってたやつって言ってたし、見たことくらい無きにしもあらずか」
しかし、エリーはそのまま考え耽ったまま黙った。
街道を走り続ける荷馬車が急に停まったのは、それから暫くしてからのことだった。
「どうしたんですか?」
俺たちが乗ってる荷馬車の馭者に訊ねる。
「いや……よくわからねぇが、前が停まったからよ」
「休憩はもう少し先の地点でしたわよね?」
「……何かあったのかも。行ってみよう」
「あ、ちょっと」
俺は勢い良く荷馬車を降りて先頭のジェフの元へ向かった。
が、そこは凄惨な光景が広がっていた。
「……あれは」
「まさか……魔物ですか?」
「おい!下がってろ!」
ジェフが俺たちを抑え込む。
そして魔物の攻撃を大盾で凌ぐ傭兵だろうか。その姿が見えた。
とても倒せるといった状況でも、事態が好転する様子もない。その戦闘はまるで、自分自身を盾にしてただ単純に時間を稼いでるだけ、ジリ貧の状態だった。
「おい……あまり長くは持たないから、早く逃げてくれ」
傭兵の男は苦しそうにそう言う。
熊の魔物。
魔物は、生まれつき魔導石を体内に持った、またはそれを捕食して取り込んだ動物が、魔力に触れることによって凶暴化する。どちらかといえば事象に近い。
「私、初めて魔物を見ましたわ……」
心なしか、エリーは呼吸を荒くして話す。
俺は、興奮から来るものなのか、不安から来るものなのかわからない動悸を感じていた。
「いいからお前達は乗ってた荷馬車に戻れ!」
「でも……」
「でもじゃねぇ!全員やられるわけには行かねえんだ!」
「では、あの方は……」
傭兵はその報酬で雇い主の身を護るのが役目。
それで命尽きようとも、その役目を果たす。忠誠を信念に戦うのが騎士ならば、傭兵はそれを報酬、つまりは金に忠誠を誓うといったところか。
「サイモンは元王家直属の騎士団所属だったんだ。そんな簡単にやられるタマじゃねえ」
「サイモン……サイモン・ワイルダーですか?」
「知ってるのか?」
「ええ……聖騎士団所属の騎士でした。ただ、聖騎士団は団長が居なくなってから暫くして解散したと聞きます」
「お嬢ちゃん、やたら詳しいじゃねえか」
聖騎士団がどれほどの物なのか、俺はにわからないが、とにかく、王家直属というくらいだから強いに決まってる。
「それでも……防戦一方じゃどうにもならない……」
不思議な感覚だった。まるでエリーをあの行列から連れ出す時に似た感覚。
体が勝手に、しかも何倍もの速さで動く感覚。
俺は気づけば手にしていた剣を抜き、魔物に斬りかかろうとしていた。
剣術は父さんからみっちり仕込まれた。
大丈夫、相手はカカシと思えばいい。
サイモンが引き付けている分、動きも少ない。
「ちょっと、ルカ!」
エリーの叫び声が耳に入るが、頭の奥までは届かなかった。
そして、その場がスローモーションに見え、それに対して俺は普通の速さで動くようだった。
一太刀目が魔物の喉元を切り裂き、大量の血飛沫が俺に降り掛かる。
間髪入れずに心臓を一突き。
ぐったりした魔物が、その場に倒れ込んだ。
「……ルカ?」
エリーが俺をまるで化物を見るような目で見る。
「あなたまさか……」
エリーが何かを言いかけたその時、俺の意識はまるで世界が反転したかのようにぐるりと回り、闇に包まれた。
そして、変な夢を見た。
父さんが、魔物と戦っている。そして、その心臓から魔導石を取り出して……。
赤子にその魔導石を埋め込む。
おそらく学者達が、その子を取り囲み猟奇的な視線を送る。
何かの実験だろうか……。
傍では泣いている母さんの背中を父さんが摩っている。
一体何だ、これは?
夢と気付いたのは、誰に触れられないし、誰も俺の存在に気づかなかったから。
そうでなければ、現実と区別がつかないくらい、変な夢だった。
そして、気がついた時には、宿屋のベッドの上だった。
「俺は……一体」
「よかった。気が付きましたのね」
エリーが安堵の表情を浮かべて駆け寄る。
「イテテテ……ここは?」
体中が痛い。怪我でもしたのだろうか?
痛みの種類が違う。これは筋肉痛だ。
俺には少し重い剣を振ったせいだろうか?
それとも……。
「ボスウェルの街ですわ。無理が祟った……といいますか、まだ力に慣れていないのですね。あなたが使ったのは魔導の力。あなたも、生まれ持って魔導石を体内に有しているのですか?」
「魔導石を? それってかなり低い確率でしかないんじゃなかったっけ?」
「ええ、ですから驚いているんです。もしやとは思っていましたが、まさか……」
エリーは自分の左胸に手を当てる。
「実は、私も心臓に魔導石を持っています……。家族からは少し距離を置かれているのはーえそれが理由です」
「エリーが? 魔導の力を?」
「実は、魔導の力を持つ者同士は惹かれ合うらしいのです。ですが、腑に落ちない点が一つあります……。魔導石は生まれ持って心臓に溶け込むような形で存在します。そして成長と共に、多少の個人差はあるとは言え、その力も大きくなって行くのです。ですから、年齢の近いあなたはと私は、同じくらいの力があるはずですが……あなたからは微弱な波動しか感じなかった」
「……つまり、俺の力が未熟だってこと?」
「いえ、まるで今まで眠っていたものが、覚醒したかのような……でもそんな事例の存在は私自身、そうであるから色々調べてはいるんですけど、どんな文献にも載っていませんでした」
俺は自分の胸に手を当てる。今までと何ら変わりもない体。
だけど内から来る違和感がずっと蠢いていた。
モヤモヤに似た何か、そこに隠れているものに今は見ないふりをした。
よろしければサポートいただければやる気出ます。 もちろん戴いたサポートは活動などに使わせていただきます。 プレモル飲んだり……(嘘です)
