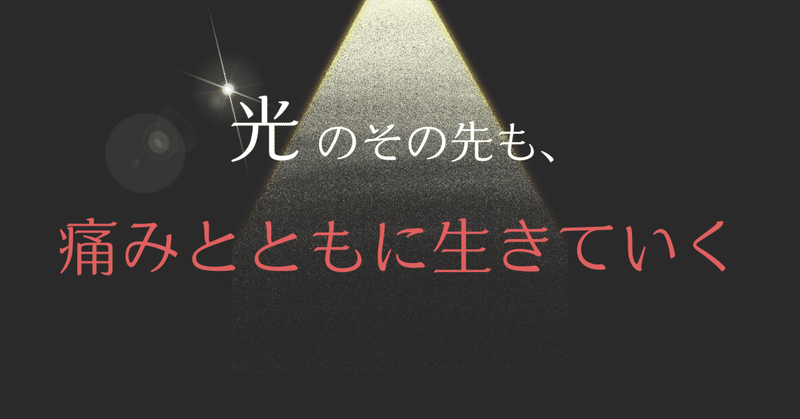
七本キメラ作
その一年間のことを、私は激しい胸の痛みと共に思い出す。いや、胸が痛み出すと同時にその時のことが思い出されると言った方がいいだろうか。それは比喩表現でもなんでもなく、本当にじくじくと胸が締め上げられるのを感じるのだ。
痛みが襲ってくると、私は俯いてそれをやり過ごす。下を向くと、自分の赤毛が視界に入ってくる。
私は半ば眠るようにして、過去の記憶が奔流のように押し寄せてくるのに身を任せた。
*
私は、すこぶる要領の悪い生徒だった。勉強、運動、芸術、なにをやらせても駄目。自分自身は一生懸命に取り組んでるつもりなのだが、結果がどうしても伴ってくれなかった。呆れる教師の溜息を何度耳にしただろう。それでも真面目な態度が評価されていたようで、見放されることだけはなかった。
高校は、家から通える一番低いレベルのところを受験した。それでもギリギリで受かったようなものだったが、この場合は『家から通える』ということが一番重要だった。電車に乗れば高校を選択する幅を広げることもできたが、過保護な親はそれを許さなかったのだ。私自身も特に将来の夢というものはなかったので、親の言うことに従った。
そんな風だったからか、それまで友達という存在ができたことはない。赤毛という身体的特徴が周囲から人を遠ざけていたからかもしれないし、あまりにも鈍臭い人間性がクラスメイトを呆れさせていたからかもしれない。親以外の身近な人たちはいつも私を遠巻きに見ていて、一定の距離を乗り越えてきてくれる人はいなかった。自分から積極的に交流を図っていけたら一番よかったのだが、気を遣わせてしまうというのがわかっていたので──そしてその空気感が何より苦手だった──誰とも関わらないことを選んだ。
私にとっての友達はただ一人。一年間という短い時間を共にした、あの子だけだ。
二年生の春、隣のクラスに転入生がやってきた。高校での転入生というのは珍しく、その姿を一目見ようと廊下にまで人だかりができて、ちょっとした騒動というか、お祭り騒ぎのようになっていた。どんな子かなと私も思ったけれど、賑やかな輪の中に入っていく勇気はなかった。だからその転入生の人となりを始めに知ったのは、周囲で交わされる噂話からだった。
──黒髪のイケメン。成績優秀で、授業中にどんな難問を当てられても必ず正解を答えている。さらにスポーツ万能で、体育の時間では輝かしい成績を叩き出している。口数は少なく、社交的な性格ではない。ミステリアスな感じが素敵。
ざっとこういう感じだった。話を聞いた限り、私とは何もかもが正反対な人だと思った。黒髪の彼と赤毛の私。なんでもできる彼と何もできない私。その人が無口なのだとしても、きっと自然にクラスメイトからの信頼を集めて、周囲に溶け込んでいくだろう。そう思える。
結論から言ってしまうと、その人物が私の生涯でのただ一人の友達なのだが──その子との出会いというのは、少々特殊なものだった。
五月、ゴールデンウイーク明け。保健委員会に所属している私は、保健室から取ってきたトイレットペーパーを女子トイレに補充しているところだった。時刻は昼休み。校庭でドッジボールか何かに興じている男の子たちの声が、微かに開けられた窓から入ってきていた。
補充はこんなものでいいか──そう思って踵を返すと、ちょうど一人の男子が入ってくるところだった。そう、男子。
硬直した。学ランを着たその人はこちらに見向きもせず、平然と個室に入っていこうとしている。肩につかないほどの黒髪、すらりと長い手足。涼しげな瞳。どう見ても男の人。間違えて入ってきてしまった天然か、それともわかってて突入してきた変態か。できれば前者であることを願った。
私はもうパニックになってしまって、ぴくりとも動けなかった。だけど自分が手にトイレットペーパーを持っていたことに気づくと、思い切ってそれを投擲した。何故そんなことができたのかわからない。スポーツテストのハンドボール投げでも壊滅的な点数を叩き出した私だったけれど、トイレットペーパーは男の人の側頭部に吸い込まれていく。
だけどその人は片手で、瞬きもせずにキャッチしてしまった。凄いと思ったけれど、それどころではない。彼は無言で私に向き直る。こうして真正面から見ると、私とその人には似ているところが一つもなかった。黒髪黒目で背の高い彼と、赤髪青目で短身な私。感情の読めない瞳に射竦められるのを感じたけれど、とにかく私は勇気を振り絞って言った。
「こ、ここは女子トイレです。男子トイレはここを出て右です」
彼は無表情のままだった。瞬きを一つして、こちらに一歩近付いてくる。私は反射的に後ずさった。
「俺は男じゃない」
涼やかな声だった。私は言葉の意味を咄嗟に呑み込むことができず、混乱した。
男じゃない? でも学ランを着ているからには男性に違いないはず。だけど整った顔立ちはよく見て見ると中性的で、声も男の人のそれほど低くなかった気はする。何が何だかわからなくなってきた。
返事ができないでいる私に、その人は自分のポケットから小さなカード──学生証を取り出した。そして表面、顔写真が貼り付けてある方を私に突き付けてくる。そこには所属と氏名、そして性別も記されていた。
雄 飛誠(ゆうひ まこと)、一年六組、女……。
全身から血の気が引いた。顔写真から恐る恐る視線を移し、目の前にいる彼──いや彼女、雄飛さんの顔を見やる。写真と同じく無表情。怒るでも呆れるでもなく、じっと私を見つめている。
なんてことをしてしまったんだ。人の性別を一方的に決めつけただけでなく、あろうことか顔めがけてトイレットペーパーを投げつけてしまっただなんて。
「ご、ごめんなさい! 私、その……パッと見てわからなくて、本当にごめんなさい」
「別にいい」
身体をくの字に折り曲げた私に対して、ぴしゃりと打ち据えるような口調だった。雄飛さんは学生証をポケットにしまうと、トイレットペーパーを持ったまま個室に入った。
足の先から頭のてっぺんまで、羞恥で熱くなる。そのまま同じ場所に立っているのも申し訳なくなって、雄飛さんが出てくる前に急いで教室に戻った。
恥ずかしい、みっともない。もしや今の光景を誰かに見られてはしないだろうか。いや、重要なのは私のことより雄飛さんの気持ちだ。性別を間違えられたのだから、不快になったことは間違いない。別にいいとは言ってくれたけど、あれは額面通りに受け取っていい言葉じゃない。
そんなことをつらつらと思った私は、ひどい自己嫌悪に陥りながら廊下を早足で歩いた。
週明け、ちょっとしたお菓子の詰め合わせを目の前に差し出された雄飛さんは、突然のことにやや困惑しているようだった。急に目の前に妙な赤毛の女が現れたと思ったら、食べ物を差し出された……さしずめそんなことを感じているのかもしれない。
「あの、この前のお詫び……失礼なことをしてしまったから」
私がそう付け加えると、雄飛さんの眉間の皺が僅かに深くなった。私は焦った。いちいちこんなことで菓子折りを渡すなんて、迷惑な奴だと思われただろうか。いやそれ以前に、こういうものをあまり食べないのかもしれない。ろくに好みを聞かず、失礼だっただろうか。
「えっと、甘いもの嫌い? ごめんなさい、だったら別の……」
「いい。貰っておく」
手を引っ込めかけた瞬間、雄飛さんの手が伸びてきて、菓子折りをパッと受け取った。私は目を瞬かせつつも、小声でお礼を言った。
これで用は済んだ──この前の粗相を謝ることができたのだが、周囲を見回した私はふと、六組の生徒たちが物珍しそうなものを見るような目でこちらに視線を注いでいるのに気が付いた。「珍しい組み合わせだな」──表情がそう物語っていた。馬鹿にするような雰囲気ではなかった、と信じたい。
雄飛さん、イコールこの春に来た転入生なのだが、彼女はクラスの中心にいるような雰囲気ではなかった。私の目には、自ら一人でいることを選んでいるように見えた。周りに壁を作り、一定の距離以上は決して立ち入らせない。そんな頑なさすらあったような気がする。周囲の女の子たちとは違う雰囲気、そして突出する才能が、雄飛さんの近くに人を寄せ付けなかった。
この時はこれで話が終わったのだが……私は既に、雄飛さんに惹かれていたのかもしれない。いや、惹かれたなんていう綺麗なものではなかっただろう。私が持っていないものを持つ彼女に近づいて、自分の未熟さを打ち消せやしないかと、浅ましい考えを抱いていたのだと思う。
だから私は、誰もいない非常階段のところで一人でお昼を食べている雄飛さんを見つけた時、すぐさま「一緒に食べない?」と口にしていた。そこにはもはや懇願の意すら含まれていたかもしれない。
雄飛さんは私を邪険に扱うことはしなかった。「好きにしろ」とだけ言って、菓子パンを咀嚼し始める。私は少し距離を開けて座り、膝の上で母親の作ったお弁当を広げた。
会話はちっとも続かなかった。雄飛さんの言葉は簡潔で、必要最低限の情報しか内包されていない。だから私もどうやって話を広げればいいのかわからなくて、黙ってしまう。そもそも雄飛さんは一人になりたくてこの場所に来ているのに、私が来て邪魔になりはしないだろうか。そう思われていたとしても「もう来るな」と言わない雄飛さんの優しさに、私は甘えていた。
だけどそんな日が続くと、私はずっと昔から雄飛さんと親しかったのではないかと思うくらい、自然に会話することができるようになっていった。雄飛さんも、相変わらず無口ではあったけれど、少しずつ話してくれるようになった。一体どうして私を受け入れてくれたのか、その理由は最後まで聞けずじまいだった。
廊下で会えば挨拶をする。昼休みには一緒にご飯を食べる。そんな風にしていつの間にか、「誠」「環」と、下の名前で呼び合うようになった。
ある日、こんなやり取りをした。
「あのね誠、よかったらこれ食べて」
小ぶりな弁当箱を差し出すと、誠は自分が手に持っていた焼きそばパンとそれとを見比べた。
「今日の分の昼飯はある」
「えっと、違うの。お節介かもしれないんだけど、誠っていつもお昼はパンでしょう? だから栄養が偏っちゃったらいけないと思って、お弁当作ってきたんだけど、ほら……」
私はゆっくりと、蓋を開けてみせる。中を覗き込んだ誠は「なるほどな」と言いたげな表情で少しだけ眉を上げた。
それは今朝、私が母と一緒に作ったお弁当だった。しかし当然、不器用な私が料理などできるはずがなく。母の手を借りながらでさえも、失敗作を生み出すことしかできなかった。おまけに盛り付けのセンスも壊滅的なものだから、どうしようもない出来になってしまっている。母は「作り直そうか」と言ってくれたけど、遅刻ギリギリの時間だったということもあり、私はその失敗作を鞄に押し込み、半泣きになりながら家を出たのだった。
「この綺麗な煮物はお母さんが作ったやつだから、これと、白ご飯だけ食べて」
だけど誠は私からお箸を受け取ると、迷わず茶色い塊──あれは確か卵焼き──を切り分け、口へ放り込んだ。私は目を見開く。じゃりっ、という、およそ料理を咀嚼した時に出るものではない音が漏れてきたけれど、誠は眉一つ動かさず、
「腹に入ったら一緒だろ」
そう言った。美味しいとお世辞を言うのでも、不味いと吐き捨てるのでもない。ただ黙々とおかずを食べている。私はその姿をしばらく呆然と見つめていたが、やがて自然と頬が緩んでいくのを感じた。
誠のこういうところが好きだった。変に人をおだてるようなことをしない。人や物に対して口汚く罵ることもしない。自分自身をしっかり持っているような、芯の強さがあった。
「お前、自分の分の昼飯は」
「え?」
急に問いかけられた私は我に返り、首を傾げる。
「この弁当は俺にやるために作ったんだろ。お前の分の飯は別であるんじゃないのか」
「あ」
あ、と言った口のまま固まる。頑張って弁当を作る、ということだけを考えていたので、誠と私二人分の用意が必要だということをすっかり忘れていた。
誠は、そんな間抜けな私に対して何も言わなかった。焼きそばパンを器用に二つに割って、片方を私に差し出してくる。私はしばらく目をぱちくりとさせていたけれど、慌ててお礼を言って受け取った。
私たちはお弁当とパンを半分ずつ分けて食べた。菓子パンを食べるのは随分久しぶりで──添加物が多いものはあまり口にしないよう、母から言われていた──こんなに美味しいものだったのかと、心の中ではしゃいだ。
これが友達という間柄なのか、と自覚すると、単純な私は飛び上がりそうなくらい嬉しくなった。だけどやっぱり一定の距離を置かれている感じはあって、それは彼女のパーソナルスペースなのだろうと思い、私も引かれたラインを超えることはしなかった。とにかく誠が私のことを受け入れてくれたのが、何よりもありがたいことだと思った。
できれば夏休み、そうじゃなくてもどこかの休日に、一緒に少し遠くまで遊びに行けたら。そう思えど、しかし誘うことはできなかった。
「おかえり環。危ない目には遭わなかった?」
これは家に帰った私を出迎えてくれる母の、お決まりの台詞だった。これだけを聞けば、「優しい母親」という印象だ。母は実際に優しい。優しすぎて、息ができなくなるくらい。
門限は17時。学校の用事で遅くなる場合には必ず連絡を入れること。極力一人で外に出かけないこと。出かけた時には一時間ごとに母へ連絡を入れること。これが私に課せられたルールの、ほんの一部。私はそれに従っている。母が悲しむくらいなら、私が我慢すればいい。
だけど過去に一度だけ、どうしても反抗したくなって無断で門限を破った。20時頃に帰宅した私を待っていたのは、母からの平手打ちだった。
母は私の肩を揺さぶりながら泣き叫んだ。どうして連絡を入れなかったの。私がどれだけ心配したと思っているの。環がいなくなったら私はどうすればいいの。私の気持ちを考えたことがあるの。
近隣から苦情が来るくらいのヒステリーぶりだった。私は泣きながら何度も謝り、二度と決まりを破らないことを誓った。
父は私が生まれる前に、病を得て他界している。愛する人を失った悲しみを、母はもう二度と味わいたくないのだろう。たった一人の家族である私をなんとしても守りたいと、少し過剰になってしまっているだけだ。
母の徹底ぶりは、もう一つの要因も絡んでいる。私が十年前、誘拐されたことがあるという事実だ。十年経った今でも昨日のことのように思い出せる。きっと赤毛という珍しい見た目が、犯人の目を引いたのだろう。薄暗い倉庫に漂う臭い、私の腕を掴んできた男の手の強さ。「一億持ってこい」と電話の向こうの相手──私の母に怒鳴りつけていた、その剣幕。あの瞬間、私の命に一億円の価値がついたのだと、震えながらもそう思っていた。一億円がどれほど大きい金額かは、六歳の私にはよくわかっていなかった。その男はすぐに逮捕され、刑務所に収容された。
自分の身は自分で守る──といっても限度がある。母はできるだけ私を家から出さないようにして、私のことを守ってくれているのだ。だから……友達と遊びに行きたいとか、そういうわがままは言ってはいけない。母を悲しませたくないから。
思い切って誠のことを母に話してみた。成績優秀スポーツ万能で、いつも私のおしゃべりに付き合ってくれている、と。そうすると母は喜んで「一度うちに連れていらっしゃい」と言ってくれた。私はその言葉通り、夏休み中に誠を家へ誘った。ひょっとしたら断られるかもしれないと思ったけれど、誠は了承してくれて家にやってきた。
Tシャツにジーパン、黒いキャップという出で立ちの誠を見た母は、目を丸くした。
「誠さんって、男の子だったの?」
「ううん、女の子だよ」
私が答えると、母は誠の頭からつま先に目を通して「そう」と曖昧に微笑んだ。その表情の裏にどんな思いが隠されているのかは、上手く読み取れなかった。
私の部屋に移動した誠は、母が用意してくれたお菓子をつまみながら「いい母親だな」と呟いた。私は一応それに同意した。
「うん、まあ。優しいんだけどね。ちょっと過保護っていうか」
私に課している厳しいルールのことについては言わなかった。
「過保護になる気持ちも、まあわかる」
「どういうこと?」
「それだけ見てて危なっかしいってことだよ」
「ひどい!」
私が抗議すると、誠は口の端を少しだけ持ち上げて笑った。この頃にはもう、こんな風に冗談を言い合えるようにもなっていた。
「誠のご両親はどんな人?」
「母親は他に男を作って出ていった。父親は単身赴任でいない」
何気なく質問したことを後悔した。私は俯いたまま、しばらく何も言えなくなった。自分だって片親なのに、どうして家族のことを質問してしまったのか。
「じゃあ一人で住んでるってこと? 面倒を見てくれる人は……」
「いない。親戚づきあいはほぼゼロだ」
学費は市の支援制度を利用して工面しているようだった。
一人だと楽でいい。誠は半ば自虐的にそう言った。私は同情するようなことはしなかった。誰もかれも、与えられた環境で生きていくしかないのだ。
誠が私のお姉さんだったらな、と思った。そうしたら母もこんなに私に対して過保護になることはなかったかもしれない。
二学期が始まった頃、誠との仲が深まっていくと同時に、母からの干渉も強くなってきた。日が暮れるのが早くなってきたから……にしては、少々鬼気迫りすぎているように感じられた。
委員会の仕事でどうしても遅くなってしまった時は──それでも玄関をくぐったのは17時を数分過ぎた時刻だっただろう──こっぴどく叱られた。母を悲しませたくないと思いつつも、私はさすがに鬱屈感を感じ始めていた。
母がそうなった理由を、私はダイニングテーブルの上に置かれていた一枚の書面で知った。母がうっかりしまい忘れたらしい。
どうやら私を誘拐した犯人が、間もなく出所してくるようだった。日本の法律では、子供を誘拐して身代金を要求した罪というのは、十年ほどでひとまず清算されるらしい。母からしたら犯人には一生獄中にいてほしかっただろうが、法の下ではそういうわけにもいかない。
私も私で、犯人が世に出てくることに対して、怖くないと言ったら嘘になる。だけどその人もしっかり刑務所の中で罪を償ったのだから、釈放されるのは当然のことだろう。私たちの前には二度と現れないだろうし、どこかでまっとうに職を得て社会復帰してくれればそれで十分だ。
「もし俺がどうしようもない人間だったらどうする」
それはショッピングモールからの帰り道、誠が電車の中でぽつりと漏らした一言だった。
母に必死で頼み込んで、誠と二人で遠出するという休日を勝ち取った日だった。連絡は一時間ごとにする、17時までには必ず帰ってくる、人通りの少ない場所には行かない。そう約束した上で、母はお小遣いを持たせてくれて私のことを送り出した。家の前で私をじっと見送るその表情には、最後まで不安が張り付いていたけれど。
ゲームセンターでクレーンゲームに悪戦苦闘し、美味しいと評判のクレープを食べ、ウィンドウショッピングを楽しみ、そしてお揃いのキーホルダーを買った。普通の学生からしたらありふれた休日だろうが、私にとってはかけがえのない思い出となった。
しかし誠は始終、いつもより元気がなかった。あまり感情を表に出さない誠だが、雰囲気の微妙な変化がわかるくらいの付き合いが私たちにはあった。私に振り回されて鬱陶しいと感じたのかもしれないと思ったけれど、怖くて聞けなかった。
そんな帰路での一言だった。誠は窓の外、前から後ろへ流れていく風景に目をやったまま、それきり口を閉じる。
聞き返せるような雰囲気ではなかった。そもそも誠からこんな抽象的な問いかけをされたこと自体が初めてだった。だけど沈黙の時間を作ってはいけないと思い、私は身を乗り出すようにして誠に問い返した。
「どうして? 誠はどうしようもなくなんかない。背が高くて勉強も運動もできて、私にないものを全部持ってて羨ましい」
「俺なんかを羨ましがらない方がいい」
突き放すような口調ではなかった。淡々と事実を述べているような、平坦な声だった。
本当に体調が悪いのかとも思ったけれど、電車を降りる誠の足取りはしっかりしていて、顔色も普通だった。結局それから会話は生まれず、駅で別れた。
そして──自分を羨ましがらない方がいいと言った誠の真意を、私はそれから間もなく、最悪の形で知ることになる。
十月。吹く風がからりと乾き始めた季節、私は速足で帰路を急いでいた。鞄につけた、誠とお揃いのキーホルダーが揺れている。17時が近い。日が落ちるのもどんどん早くなってきている。
交差点を右に曲がった私は、ふと見知った後ろ姿を見つけて立ち止まる。誠だった。こんなところで会うなんて奇遇だな──そう思って声をかけようとした時。
誠が相対しているその人の姿を見て、ヒュッ、と、喉の奥で悲鳴が鳴った。
街灯に白く浮かび上がった顔。高い鷲鼻に、はっきりとした形の瞳。そして──顎にある大きなほくろ。それは見間違えようもない、十年前に私を誘拐した人物だった。時を経て老け込んだように見えるが、絶対にそうだという確信があった。
「──その人はだめ!」
考えるより先に、私は駆け寄って誠の手を掴み、道路を駆け出した。いつもはどうしようもないくらい鈍足なのに、この時は人生最速で走ることができた。
遠くへ逃げなければ、それだけを思って走った。だけどすぐ体力に限界が来て、角をでたらめに三つ四つ曲がったあたりで力尽きた。手を膝に置き、ぜえはあと息を整える。
「環」
誠の、色のない声が鼓膜を震わせた。誠に自分の名前を呼ばれるのが私は何よりも好きだったけれど、今はそれどころではない。誠の手を掴んだまま、勢い込んで必死に説明した。
「あの人、私を十年前に誘拐した人なの! だから、だから誠が連れ去られちゃうと思って、私……」
そして、口を閉じる。
その時の誠の表情を、どう形容したらいいだろう。世界の終わりを間近で見たような、最愛の人が目の前で撃ち殺された時のような。絶望と困惑と、そして少しの後悔が入り混じったその顔は、見ていられないくらい悲痛なものだった。
「親父」
血の気の失せた唇が動く。誠は全身をわなわなと震わせながら、低い声で言った。
「親父なんだ──つい最近出所してきた」
その瞬間、世界から色が消えた。そして失われた色は、二度と元に戻ることはなかった。
そこから誠とどんな会話をしたのか、どうやって帰ったのか、まるで覚えていない。気が付いたら私は自室のベッドの上に倒れ込んでいた。内臓をごっそり抜かれてしまったかのような絶望と虚脱感があった。どうしよう、と思ったけれど、私が何かをどうにかすることなんてできないのだった。
噂というものは、やっぱりどこからか漏れるものなのだろう。狡猾な悪魔のような存在がいて、そいつが吹聴しているのではないかと思うくらい、誠のお父さんの話は瞬く間に広まっていった。
──雄飛の親父は誘拐犯らしい。身代金目的で子供を誘拐したみたいだ。家族が出所してきて、今どんな気持ちなんだろうな。
さすがにその時の被害者──もとい私のことまでは流布されなかったが、私は毎日怯えながら暮らしていた。犯人が出所してきたことに対してではなく、誠ともう話せなくなるのではないかという不安に対してだった。そしてそれは現実になった。
噂は当然、私の母の耳にも入った。母は怒り狂った。よりによって出所してきた人間が、すぐ近くにいることに。そしてその子供が、自分の娘と親しくしていたという事実に。これは全くの偶然のことだったのだが、母にとっては偶然だろうが必然だろうがどうでもよかったのだ。私の両肩を掴み、血走った目でこう言った。
「あの子とは今後一切付き合うのをやめなさい。これは貴方のためを思って言っているの。わかるでしょう? 貴方に危ない目に遭ってほしくない」
母のためを思えば、私はここで嘘でも頷いておくべきだった。わかったよお母さん、誠とはもう関わらないよ、だから安心してね、と。
「だいたいああいう子は少しおかしいのよ。女なのに男みたいな恰好をしてるような人間とは、本当は関わらせたくなかった。犯罪者の子供はやっぱり、どこかしらが捻じ曲がっているものなのね」
だけどその言葉だけは許せなかった。
瞬間的に頭に血が上った、と思った時にはもう遅かった。私は生まれて初めて母に暴力を振るった。力いっぱい突き飛ばして、母の身体を壁に激突させたのだ。
「誠は誠だよ。誠の服装も喋り方も、お母さんがあれこれ指図するようなことじゃない。私の大事な友達をそんな風に言わないで」
私を見上げる母の顔は絶望の色をしていた。絶対に自分を裏切らないと思っていた存在に口答えされたのだ、その反応としては当然だった。
ここで母が烈火のごとく怒ってくれていたら、その後の色々な結果が変わっていたのかもしれない。私はそれに反抗して、自分に巻き付いている鎖を引きちぎれたのかもしれない。
だけど母は泣きついてきた。私の足に縋り付いて、身も世もなく、全身全霊で、「見捨てないでくれ」と懇願してきたのだ。それは大の大人が見せるにはあまりにも不憫な姿だった。
私にできるのは母を宥めることだけだった。私はどこにも行かないから、だから泣かないで、と。必死で声をかけながら、私の目にも涙が滲んでくるのが分かった。自分は何をやっているのだろう、という呆れからくる涙だったのかもしれない。
だけど結局、それから私は誠と会話をしなかった。
お昼休み、いつもの場所に誠が来なくなったのだ。屋上へ続く階段、校舎裏など、誠が行きそうな場所をくまなく探したのに、その姿はどこにも見えなかった。私から必死で距離を置こうとしているようだった。私と関わらないようにしてくれているのだ、と思っても、そんなのはちっとも嬉しくなかった。私は前みたいに、一緒に他愛もない話をしたかった。
授業の間の休み時間、隣のクラスに行って誠に話しかけ続けた。しかしどう訴えかけても、誠から返事が来ることはなかった。まるで私の姿が本当に見えていないかのようだった。周囲の、腫れものを触るような視線が突き刺さってきても、私は必死で呼びかけ続けた。
だけど結局その行為も無駄だとわかると、私はぱったりと誠に関わるのをやめた。そうせざるを得なかった。数か月かけて築き上げてきた友情は、呆気なく無かったものになった。
どうしてこうなってしまったのだろう。どこから間違ってしまったのだろう。こんな思いをするくらいなら、誠と友達にならない方がよかったんじゃないだろうか。どんなに後悔しても、時間は前に戻ってはくれない。
私は誠の姿をできるだけ視界に入れないようにして、学校生活を送った。あのキーホルダーは引き出しの奥にしまわれた。
年明けのある日。母はがん検診に出ていたので──誰が来ても絶対に玄関を開けないよう、きつく言い含めていった──家には私一人だった。
ただただ空虚な日々が続いていた。誠という支え──友人を失った私は、気力という気力をすべて失っていた。勉学もおろそかになり、留年の危機が迫っていたが、それを気にするほどの元気もなかった。
自室のベッドに寝転がり、眠るでもなく無為に時間を潰していると、階下のインターホンが鳴った。母の忠告が耳の奥に蘇らなかったわけじゃなかったけれど、脳死のようになっていた私はふらふらと階段を下りて行った。
そうしてモニターに映った人物の姿を見て──驚愕する。
「誠!」
思わず叫んで、身体をあちこち家具や壁にぶつけながら玄関に向かい、勢いよく戸を開ける。
そこには、生気のない誠が立っていた。私服はよれていて髪はぼさぼさ、目の焦点はかろうじて結ばれているものの、強い風が吹けば倒れてしまいそうなくらいに頼りなかった。
「どうしたの?」
声をかけても返事はない。久々に誠に会えたこと、そして家を訪ねてきてくれたことへの喜びは、ただならぬ雰囲気に打ち消された。
とにかく誠を家に上げた。母が帰ってくるかもとか、そういうことは考えなかった。
飲み物を出しても、誠は口をつけなかった。本当に、ただそこに存在しているだけといった風だった。
長い時間が過ぎた。時折家の横を車が通過していくほかは、何の音もしなかった。
「お前が」
そうして紡がれた誠の台詞は、ひどくひび割れているように聞こえた。
「お前が……自分を誘拐した男の家族と関わりたくないと思ったから避けてたのに、来てしまった」
「そんなの関係ない! 私は誠と一緒にいたい!」
言葉に被せるように言うと、誠は顔を歪めて拳を握り締めた。爪が白くなるくらい、固く、強く。
「年度が変わると同時に引っ越す。今までずっとそうやって転々としてきた」
私は息を呑み、誠の拳に手を重ねた。そうすることで少しでも誠のことを繋ぎ止められればいいと思った。
それから誠は堰を切ったように、今までのことを話し始めた。
犯罪者の子供というレッテルを張られ、小学校時代はどこへ行ってもいじめられたこと。教師たちからも腫れもの扱いされたこと。自分だけで生き延びられるように、必死で勉強して身体も鍛えたこと。アルバイトをして金銭を稼ぎ、早く自立するつもりだったが、父親のことが知られると例外なく辞めさせられたこと。
その苦労を、悔しさを、悲しみを、私は想像することができなかった。容易に想像していいものではないと思った。誰もかれも、与えられた環境で生きていくしかない。そう頭ではわかっているのに、こんなのはあんまりだ。
「どうしようもない奴だよ、俺の親父は」
誠はどこも見つめず、感情を殺した声で言う。
「自分の子供を性処理の道具にした挙句、食うに困って誘拐に走るような、どうしようもない人間だ」
息を抜かれたような沈黙が降りた。
誠が男装をして、男性の口調で話していたのは、自衛のためだったのだ。自分を少しでも強く見せることで、かろうじて自尊心を保っていたのだ。
こんな地獄があっていいのだろうか。どうして何もしていない誠が、こんな目に遭っているのだろうか。誠はきっと、父親から逃げて私のところへ来たのだ。その逃避が根本的な解決には何もならないとわかっていても、私を頼ってやってきた。
たまらなくなった私は、腕を伸ばして誠を抱きしめた。こうして触れてみると、誠の身体は心配になるくらい細かった。
誠ははじめ、恐る恐るといった様子で身を預けてきたけど、私が腕に少し力を込めると抱きしめ返してくれた。
「誰かにこうされたのは生まれて初めてだ」
その声は今まで私が聞いた中で一番──そして多分、誠自身の人生の中でも一番、穏やかな色をしていた。
「何回でもしてあげる。私は絶対、ずっとずっと誠の味方」
私たちは口づけを交わした。どちらからともなくそうしていた。泣きそうなくらい温かい触れ合いだった。
お互いに鎖で縛られた一人ぼっちの私たちは、この一瞬だけ、小さな結び目で繋がった。
誠の唇の柔らかさを感じながら私は、この世界が瓶の底だったらよかったと思った。そうしたら瓶を逆さまにして何度でも、誠との楽しい時間を再生することができただろう。
誠はその後、町から去っていった。先生曰く、退学したとのことだった。それ以上は何を聞いても教えてくれなかった。
犯人とその子供が遠くへ行ったことにより、母のヒステリーは少しだけ収まった。だけど私に課せられた今までのルールが撤廃されることはなかった。
最初はどうしようもなく辛くて、誠の声を、立ち姿を、唇の感触を思い出すたびに泣いていた。それでも時の流れというのは温かく残酷なもので、少しずつ少しずつ私の中の記憶を洗い流していった。それに伴って誠を思い出す頻度は次第に減っていった。
いつか私がおばあちゃんになった時、この一年の記憶をどういう感覚と共に思い出すのだろう。そんなことを考えながら私は時を重ね、大人になっていった。
*
胸の痛みが引いていく。私は顔を上げた。
あの口づけは多分、思春期特有の複雑な感情から生まれるそれだったのだと思う。特に女の子同士の友情は、時に疑似恋愛的な要素を生むこともあると聞いたことがある。
彼女のことを思い出す回数は少なくなったが、彼女と過ごした記憶の全ては、脳に刻み込まれている。だから街を歩いているときに、無意識で彼女の面影を探してしまう。
私たちは無意識に、互いが持つもの──自分が持っていないものを渇望し、惹かれ合っていたのだ。友情とも愛情とも違う、ほんの少しだけ歪な関係。だけど私と彼女は紛れもなく友人であって、その短い時間は私にとっての宝になっている。
二人の人生は、多分もう交わることはない。だけどきっとそれでいい。
彼女が何にも縛られることなく、自分らしい姿で生きていてくれたら、それ以上に嬉しいことはないと思う。
了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
