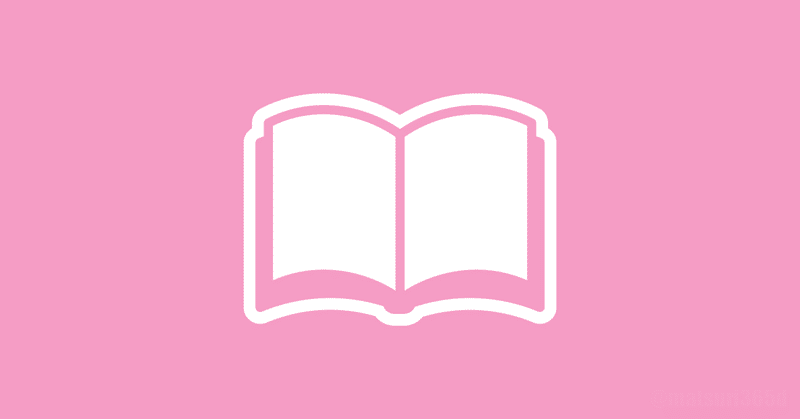
卒論を再定位したい
論文を書くということ
最初に前提というか、背景を共有したい。
論文や研究のあり方は学問分野によって違うし、先生によって方法論も異なる。そのうえで、自分の関わる人文・社会学系の分野を念頭において書く。
個人差こそあるが、論文は概ね以下のような構成で書かれる。
①問題提起&関心の在り処を示す
②先行研究や事例の整理、紹介
③データ
④考察や主張
⑤まとめ
①②ではその研究の意義や面白さを伝えることが大事になる。
というのも、研究は「こんなことを考えました!」だけだと成り立たない。
その学問分野や、取り扱うテーマ、関連する話題の蓄積があることを示した上で、新しい視点や研究対象、データを取り入れて、新しい何かを見出すことによって初めて成立する。
だから、先行研究を紹介しながら整理することを通して、「今までこんなことが分かってる、こんな調査がされている」ことを示して、だから「俺の研究はここに焦点を当てるから面白いんだ!すげーんだ!」「まだわかってないから意義があるんだ!」ってことを説明する。
論文を通して議論する概念や、説明に使う用語の意味や定義を整理する。
こうした学術的な背景と同時に、記事や資料を使って、その研究対象を取り上げるに至った社会的・歴史的背景を示す。
この作業があって初めて研究、論文としての意義が生まれるし、それがなかったらもはや作文でしかない。(少し過激派。)
だから先行研究は大事で、一般的に卒論指導の最初に文献を沢山読みなさいと言われるのはそういうこと。
そうして示した研究の意義を前提に、分析するデータや事例を紹介して、先行研究で示した点を踏まえた考察をする。
そして、その論文で「明らかにしたこと」と「まだ明らかにできていないこと/今後発展させる余地」を示して、論文は完成する。
アカデミックに馴染みのない人は驚くかもしれないが、論文の「限界を示す」ことはめちゃめちゃ重要。情報リテラシーの無い人が論文や調査報告書の「~~はまだわからない」みたいな文言を切り取って批判しているのも、専門家は断言して言い切ることがあまりない(からわかりにくい)と言われるのも、この作法が少なからず影響していると個人的には思っている。(とはいえ、その作法を無くすべきとは微塵にも思わんが。人類が長年培ってきた知こそが学問だし、新奇性あっての研究だから。)
卒論は論文とは違う!?
とまあ論文はそういうもので、研究者が書いて学術誌に投稿する論文は字数の上限が定められている。だから、研究者は特に自分の議論に必要なものを厳選してまとめて記述して論文を書く。
たまに「〇〇も知らんの?w」とか「こんなのあるよ」とか「人の話ばっかりして自分の話しない」とか、学生がそんな愚痴を吐いたり、リプが飛んだりしているけど、基本的には字数の都合で書いてないだけ。
そして、他の専門家が内容を精査した論文(いわゆる「査読論文」)は信頼度が高く、査読の無い論文は一定の意義がありつつも、扱いには気を付けないといけないものになる。
新しいテーマや概念、面白い知見として査読の無い論文を参照することはあっても、色々ちゃんと確認しないといけない。逆に査読論文や、それが掲載されている、分野を代表する雑誌から論文を参照していると、論文の質は自ずと高まる。
一方で、卒論は字数の下限が定められている。
卒論の先行研究は、もはやしっかり勉強したことをアピールしながら字数を稼ぐパートでもあるし、データも多ければ多いほどいい研究になる。
先行研究の重要性を散々書いておいてあれだけど、ぶっちゃけその辺を気にせずに、テキトーに書いても卒業はできる。
データの質もそこまで精査されない。
というか、その辺を厳密にしたら8~9割の学生は卒業できないと思う。
SNSで無造作によく流れてくる「卒論アンケート」も、とてもじゃないけどちゃんとした論文には使えない代物だしね。
まあそんな感じなのよ。
卒論をしっかり書くと2~3万字で足りるかどうかって次元になるのだけど、今や多くの大学が7000~1万字の文章を、サンプルが異常に偏ったデータを使って書いていたらOKって感じにしているのが、(少なくとも日本の)大学生が書く卒論というわけ。
でね、個人的にはその卒論のあり方そのものを否定する気は全くないのだけど、一方で、学問のエッセンスを最低限学ぶことができるのが卒論だというわけで。
それをちゃんとやらずに卒業した人は、学位があっても「学問を学んだ」とは言えないし、専門性をもって物事を判断できるかは怪しい。
企業が専門性を気にしない、評価しない一因にもなってる気がする。
それどころか、専門性を評価できず、取り入れることのできない企業/人事が大多数を占めて、日本経済が停滞する一因でもあるように思える。
だから卒論をしっかり書いて、最低限のエッセンスを掴んで、社会に出てほしいと思ってしまう。大学で仮にも学問を学び、アカデミックな文章を書く以上は。
ちなみに、うちの大学では指導の時に「○○学の論文を書くか、選んだテーマの専門家になれ」と言われる。そして「自分が面白いと思うものを楽しく書け。いやいや、無理やり字数を埋めた文章は読んでて苦痛でしかない」と言われる。
特に理系ではそうだと思うが、研究室で代々受け継がれている研究の一部を担って、それを卒論とするパターンも多い。一方で、人文・社会科学系の分野では、研究の方法論がその分野であれば基本的に、テーマを自由に選んで、興味のあることを探究できる。
だからこそ、先生の専門性と学生の専門性は一致することの方が珍しいわけで、だからこそ面白い論文かどうかは一瞬でわかるし、そのテーマの専門家であることが、ちゃんとした卒論には求められる。
「何がおもしろいの?」って散々詰められた意味が最近やっとわかってきたけど、結局は(理系を含めた)どの分野でも、書いてる人間が面白いと思って研究しないとつまらないし、何の意味も生まれない。
そういう意味で、ほとんどの学生が書いている卒論は論文でもないし「卒論」でもないと言えるんじゃないかなって思っている。
卒論の質って能力を測るいい指標なのでは?
でもね、ここからが本題なのだけど、卒論の質って実はめっちゃいい指標なんじゃないかなって最近考えてる。
起業するなら、採用者の研修を「いい卒論を書くこと」にして、卒論の出来によって初任給に差をつけようと思うレベルで。(その場合は当然、高卒や卒論の無い学部・校種は考慮する。)
理由はいくつかあるのだけど、「ちゃんとした卒論」を書くために必要な能力って、これからの時代に仕事をするうえで必要な力だと思うんよね。
箇条書きすると、
①情報を収集・選択する能力がわかる(課題特定&情報処理能力&市場調査)
②論理的で説得力のある文章を書けるかがわかる(簡単に見えて難しい複雑な思考力&マーケティング)
③新奇性を創出、説明できる(問題解決&イノベーション)
④フィールドワーク、調査系の研究であれば行動力や実行力が測れる
⑤関心に対してどこまで深めて突き進めるのかがわかる(探究心&忍耐力)
⑥アカデミックな専門性とまでいかずとも、興味関心に基づいた専門性(というより個性?)がわかる(新規事業設計やモチベーション管理)
あくまでも全て仮説だけど詳しく書くと
①情報を収集・選択する能力
情報化が進んで変な情報、偏った情報が溢れた世界で、妥当性が高くて信頼できる情報を取りに行ける。そして手段や目的に適した形に、情報を整理したり、取捨選択できる。
これは先行研究と考察を見れば明らかで、アカデミックという限定的な領域での話にはなるけど、情報の質と参照先が重視されるアカデミックの分野でそれができるのであれば、情報を精査する能力はかなり担保できるはず。
この能力があれば、組織の成長戦略を描いたり、自社の強みを理解したうえで市場調査をして新規事業を開拓したりする時に、変なデータに踊らされることなく、質の高い分析をしたうえで勝算の高い戦いに持ち込める可能性が高まる。
②論理的で説得力のある文章を書けるかがわかる
結局商品が利益を生むことができるかは直観や感情的な要素が大きいけど、再現性を高めるためには、普遍的な領域に持ち込んで発展・応用させるためには、やはりロジックが必要。
また、様々な関連することを踏まえたうえで、一つの主張、論証をするために筋の通った長い文章を書くことは、想像以上に難しい。
かなりの思考力と論理性がないとできる作業ではない。
こうした作業をするために必要な複雑な思考力は新しい価値を生み出す、届ける時にものすごく大きな力になる。
特に、課題解決が価値・ビジネスになる時代に、課題がどんどん複雑になる時代には、柔軟に物事を深める思考が必ず必要になる。
そして、(少なくとも就職する前に)こうした文章を一人で書く経験は、基本的に卒論しかない。
書いてて疲れてきたし、思いのほか長くなってきたからここらで具体的な仮説を書くのはやめるけど、、、
要するに、(日本企業の事業・仕事の設計や整理は結構遅れて、その段階に到達していないことも多いのだが)今の、これからの時代に事業として、ビジネスとして、複雑な課題を解決し、価値を創出するために、社内の組織経営や、顧客への価値にイノベーションを起こすために必要な能力と、卒論を「ちゃんと」書くことで身に付く能力は、大枠で見るとかなり共通する。
当然、論文が書けることと仕事ができることが直接的に一致するわけではないし、個人差はあるけど、枠組みとして、土台として求められるものは非常に似通っている。
となると。
個別具体の仕事のスキルやノウハウは働き始めてから学べば十分なわけで。
企業の研修である程度身につけられる短期的な能力は採用してから研修すればいいわけで。
それ以上に重要な、深く長期的に物事を見て、考えて、動き、それを形にする能力は卒論を読めば大体わかるし、卒論をちゃんと書けば育まれる。
それならば、卒論をちゃんと書かせた方が、内定者研修をするよりもコスパの良い学びにもなるし、労力もかからないし、学術的にも企業にとっても、本人にとってもいい成長機会になるんじゃない?
そして、卒論が最終的にビジネス(というより不安定な社会を生きていく?)ための力になるならば、コピペと繰り返しによる字数稼ぎを駆使して書く駄作文としての「卒論」なんて辞めて、ちゃんとした卒論を書くのがいいじゃん?
となると、卒論の見方は変わってくるはず。
そういう意味で卒論を再定位したいという話でした。
大学も、学問も、ビジネスも、自身の将来も、それが積み重なって社会をダメにするような卒論なんてやめちまって、ちょっとぐらい頑張ってみようぜ。
なんてことを、ビジネスと人文系の学問の両輪を回そうとしている大学院生は思うのでしたとさ。
