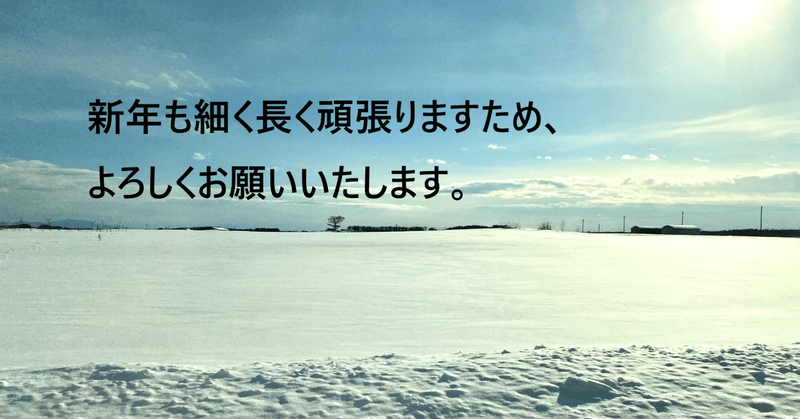
新年挨拶+弘大フィル定期演奏会
新年、あけましておめでとうございます。
noteを始めてからまだ2か月しか経っていませんが、
継続的に発信できていること、そして
ありがたくも私たちの記事を読んでくださっている方がいること、
感謝しかありません。
本当にありがとうございます。
2021年最後には、弘前大学フィルハーモニー管弦楽団の第51回定期演奏会が開催され、学生より案内をいただいたため、応援にかけつけました。

演奏曲目は「大学祝典序曲」(J.ブラームス)、「スラヴ行進曲」(P.I.チャイコフスキー)、「交響曲第5番」(A.K.グラズノフ)でした。
普段授業でお会いしている学生も、ここではいつもと顔が違い、団の中で大切な役割を担っている姿に心動きました。
コロナと演奏活動の共存はまだまだ課題が多いのですが、それでもこうして定期演奏会が開催され、お客様に見守られながら演奏ができたということはいかに貴重なことだったか、きっとすべての学生が実感し、そこからの学びも多かったことと思います。本当にお疲れさまでした。
グラズノフの作品を指揮された今先生がご挨拶のときにおっしゃっていたことの中に、"学生の本分として勉学に励むこと、そして勉学に励むために生活をすること、生活をするためにアルバイト等をしてお金を稼ぐこと、こうしたことと感染症対策とを並行しようとすると稽古がいつも以上に大変で、人も十分に集まれなかった"という旨のお言葉があったと思います。
やもすると、演奏の良し悪しだけで見ると決して上手な演奏ではなかったと思われた方への配慮ともとれますが、演奏=上手は音楽の条件ではありませんし、あまたある評価軸の1つでしかないことを伝えたいとされていたのかもしれないと個人的には受け取りました。
演奏を眼前としたときに、なにをみとるか。みとれるものは本当はいくつも存在するのに、みとりたいものばかりを見てしまい、これが音楽なのです、と言い切ってしまうようになると、自ら音楽の全体像を見えなくすることにつながり、音楽の豊かさとはかけ離れていく危険性もあります。
信念と真実は分けて考えること、そうすることで音楽の学びがさらに広がるのかもしれません。
そんなことを、今先生のお言葉から考えていました。
さて、新年の弘前は、
ふわっふわの雪が数十センチの高さに積もり、
気まぐれかつ容赦なく、雪が降りつけてきます。
この記事の最後は、
道端で見つけた気合の入った雪だるまと
ウミネコの写真で閉じたいと思います。
新年も何卒よろしくお願いします。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
