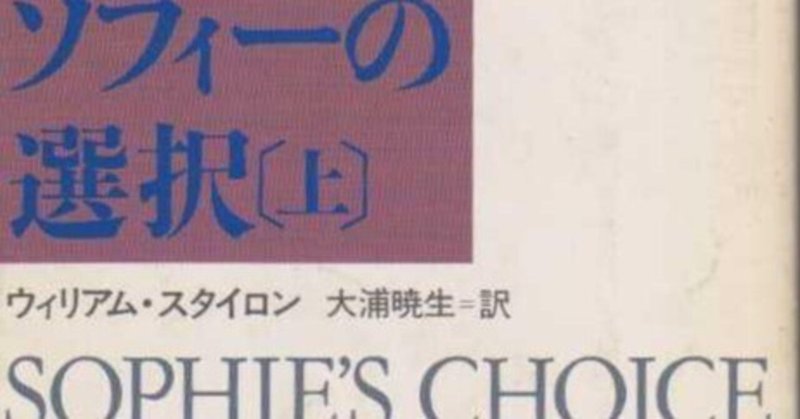
「ソフィーの選択」と出生前診断の選択
正月休みに読んだ本です.
「ソフィーの選択」(上・下)ウィリアム・スタイロン
1947年のブルックリン,美しいポーランド人女性ソフィーとユダヤ人ネイサンの愛が「ぼく」の目から語られる.第二次世界大戦のアウシュヴィッツ収容所を生き延びたソフィーは,身の毛のよだつような経験の数々を片時たりとも忘れたことはない.小説の題名はその中でも最悪の経験を指している.小説の最後に近いところになって,ソフィーは自ら許すことも忘れることもできないある「選択」について告白することになる.
(以下ネタばれ注意)彼女とふたりの子どもたちの息子のヤンと娘のエヴァは,列車に乗せられてアウシュヴィッツに運ばれた.到着してすぐに,強制収容所に行くか,そのままガス室送りになるかの選別が行われていた.人々を選別していたのはナチス親衛隊の軍医であった.
軍医はソフィーに選択の「特権」を与えてやろうと言う.ふたりの子どものうちひとりは残してもいい,もうひとりはガス室送りだと.すなわちどちらをガス室送りにするかかをここで選択しろというのだ.ソフィーは「あたしには選べません」と嘆願するが,今ここですぐに選べなければ子どもはふたりともガス室に送られてしまう.ついに「女の子の方を連れていって!」と叫んでしまった.そしてこのひとこと,すなわち自ら下した生死の選択がその後のソフィーの心を凍らせ,あらゆるときに彼女につきまとい続け,最後には彼女を破壊し尽くしてしまった.
これはまさに強いられた「選択」である.そしてここで周産期医療におけるある倫理的問題との類似性により,われわれは愕然とさせられてしまうのである.出生前診断を受けた結果,「選択」をつきつけられた両親たちの多くが,「こうするしかなかった」という確信ではなく,「こうだったかもしれない」,「こうすべきだったかもしれない」という思いにずっととらわれ続けられている現状がある.産むと決めた両親も,産まないと決めた両親も,また積極的な蘇生と集中治療を選択した両親も,積極的な治療をせずに看取りを選択した両親も,選択したことに深く傷ついている.その決定を自ら下したという罪悪感を長い間抱えて生きている人も多い.
ソフィーも,出生前診断によって選択をせまられた両親も,選択を下さなければならないという自覚によって極限まで追い込まれるということはいったい何を意味しているのだろうか? それはそもそも選択不可能なものに対して「選択」を強いているのではないか? 一般に「選択」や「自己決定」は,自分自身の意志で行うことにより自らの生を充実させるためにあるだろう.しかし「あれかこれか」はそれぞれの相対的価値を評価して選択できることが前提であり,もしそれが絶対的な価値をもつであれば選択は不可能である.原理的に不可能であるものを現実として強制されるところに,われわれの心に癒しがたい傷を残すのである.
出生前診断における「選択」とは,これは見せかけの「選択」に過ぎないのだろうか? それとも「選択」そのものにこの難問は不可避に存在するのだろうか? そしてその解決への道筋は? またいつもの堂々めぐりに陥りながら,それでも現実にはその決定を行わざるを得ない毎日が続く.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
