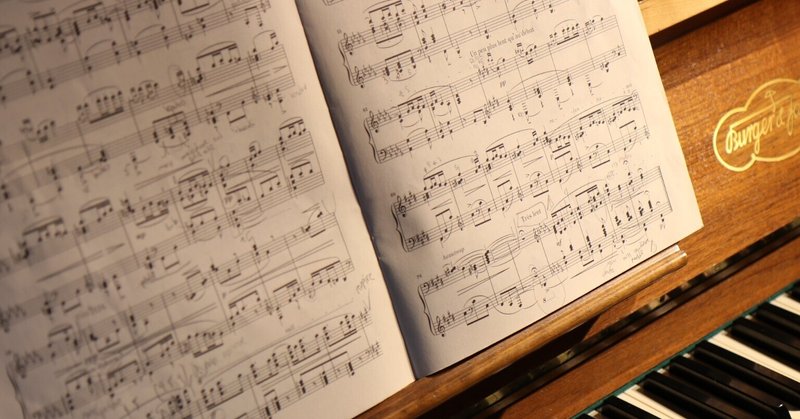
【文例あり】声喩・オノマトペについて解説【音の表現辞典に学ぶ】
声喩・オノマトペについて、文例を交えながら解説します。
参考文献は中村明氏著『音の表現辞典』です。
声喩・オノマトペとは【擬声語と擬態語】
《声喩》は、オノマトペを使って感覚的に伝えようとする修辞法です。
《声喩》は、一般的に「擬声語」と「擬態語」の二種類に分けられます。
しかし、これらの用語は別の意味で用いられることもあります。
オノマトペの由来
もともとの語源は、古代ギリシャ語の「onoma(名)」と「poiein(作る)」が融合してできた「onomatopoiia(オノマトポイーア)」に由来します。
英語では「onomatopoeia(オノマトペア)」、フランス語では「onomatopēe(オノマトペ)」となり、日本では「オノマトペ」と云われることが多いですが、「オノマトピア」「オノマトペア」と云われる場合もあります。
擬声語と擬態語の違い
擬声語は、音声や音響の比喩表現を指します。
そのうち、人間の発する声や動物の鳴き声などを模写した比喩表現を「擬声語」、自然の物音を模写した比喩表現を「擬音語」と呼び分けて、区別する場合もあります。
それぞれの例は下記の通り。
擬声語:「ワンワン」「キャッキャッ」「ニャーオ」「チュンチュン」
擬音語:「ガチャン」「ドンドン」「バタン」
擬態語は、
人や動物の動作を表す「擬容語」
物質の状態を表す「擬状語」
人の心情を表す「擬情語」
に細分されることもあります。
それぞれの例は下記の通り。
擬容語:「にやにや」「のろのろ」「もじもじ」「すいすい」「ぴょんぴょん」
擬状語:「ぴかり」「きらきら」「さらさら」「がちがち」
擬情語:「いらいら」「くよくよ」「じりじり」「どきどき」「わくわく」
さらに擬声語と擬態語を一括したこの種の音マネことば全体を「擬音語」と総称する場合もあります。
このように、「擬音語」が自然の物音を表す比喩表現の呼び名である一方、音マネことば全体の総称でもあるなど、擬声語と擬態語関連は用語が錯綜しているわけです。
声喩・オノマトペの効果TOP3
声喩・オノマトペを使うことで得られる効果について説明します。
「TOP3」と題しましたが、例のごとくランキング感はありません(笑)
効果1:訴求力が増す
声喩・オノマトペを商品のキャッチコピーに巧く取り入れることで、顧客の購買意欲をかき立てることができます。
たとえばサラダのキャッチコピーに
シャキシャキ
パリパリ
とあればより新鮮さが伝わってきます。
煮込み料理にしても、ただ「長時間煮込みました」と言われるよりか、
ことこと煮込みました
と言われた方が手間暇かけて作った感じが出ますよね。
「ぽってり濃厚カスタードクリーム」とした方がより濃厚な味わいを期待させますし、「ふわとろオムライス」とした方が素人には難しい職人技をイメージさせます。
効果2:わかりやすく伝える
声喩・オノマトペを日常会話に巧く取り入れることで、他者に物事をわかりやすく伝えることができます。
たとえば、「塩を振っておいて」と言われるよりも「塩をパラっと振っておいて」と言われた方が
「パラっとならこのくらいかな?」
というイメージは容易ですよね(この表現が指示として適切かどうかは怪しいですが──)。
この辺りは小説の表現でも似たようなことが云えます。
「ぼかぼか殴る」よりか「ぽかぽか殴る」の方が、迫力の点で劣るので。
大して痛くないのだろうなぁ~とイメージできます。
効果3:オリジナリティを表現する
声喩・オノマトペを文章に巧く取り入れることで、オリジナリティを発揮することができます。
くすんだガラス板に指先を持っていってほとほととたたく
ここでは指先とガラス板の接触音を「ほとほと」という珍しいオノマトペで表現しています。
中々目にしないオノマトペゆえ印象に残りますね。
バグパイプみたいなのをパオパオと吹いてかどづけしてまわる山から降りてきた羊飼い
何となく日本人に馴染みの薄い、異国の音色感が伝わってきます。
父親の武骨な手が箱の中から取り出し卓袱台の上へ置くと、その果物はぼってりとした音を立て、室内の静けさを際立たせた
擬音語ではなく、「ぼってり」という擬態語によって厚みのある音響を描出した例。
「『ぼってり』という感じの音を立てる果物ってなんだろう。リンゴや苺ではなさそうだな……」
と読者の想像力を掻き立てます。
ちなみに正解はメロン。云われてみると、感覚的に納得できます。
声喩・オノマトペを作品に取り入れる上で大事なこと
ことオノマトペは"巧く"取り入れることが大前提です。
取り入れれば取り入れるほど、質を高めるものではありません。
北方謙三先生は『ミステリーの書き方』のなかで「擬音は基本的には使わない」と述べております。
小説でもっとも大事なのは描写なんだ。
描写の背後に作家のきちんとした人間観や生命観がある。そういうものをしっかりと表現したいと思っている。記号や擬音は本質的なものではない。
声喩・オノマトペに対するスタンスは作家によって異なるでしょうが──。
個人的には取り入れることで作品がより良くなる確信があるなら取り入れるくらいの感じで良いのではないかと考えております。
今回はそんな感じ。
ここで紹介した内容が、あなたの今後の創作活動を彩る一助となれば幸いです。ではまた~。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
