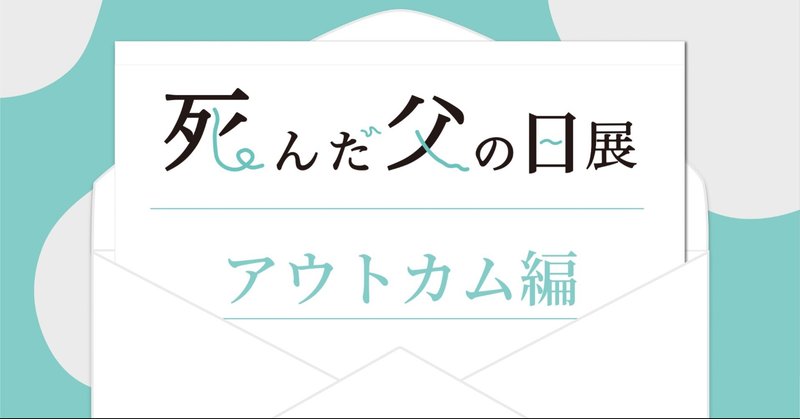
死んだ父の日展2021を振り返る〜アウトカム編〜
こんにちは、変化にもっと優しくなりたいむじょうの前田です。
6月9日〜20日の11日間、開催した「死んだ父の日展」の振り返りです。
設計編・分析編・アウトカム編の3編に分けて公開しています。
まだ設計編・分析編をご覧になっていない方はこちらを先にお読みください。
死んだ父の日展2021の応募終了後、20名の方にヒアリングをさせていただきました。ヒアリングから見えてきた、死んだ父の日展のアウトカムを整理します。
アウトカム① グリーフケア
父が亡くなった当時は、父の事を忘れようと思っていた。本当に忘れ始めると、今度は忘れてしまうことが怖くなった。今回、手紙を書くなかで忘れかけていたことを思い出せた感じがして救われた。(30代女性)
いろんな人のお父さん宛のお手紙を読んでいて、自分と同じような思いをした人がいると知ることができた。日常的に話す内容じゃないから、こういう機会に他の人の経験が知れると、寂しさが和らぐ。(40代女性)
辛いことにはかわりない。でも、冷静になれた。他の人の手紙もあり、客観的になれた。(20代女性)
今は父を亡くして1ヶ月なので悲しみが大きいが、亡くしてから時間が経っているであろう方の手紙を読んでいると、「いつか私もそういう気持ちになれるかな」と希望が持てた。(30代女性)
このような声をいただきました。
グリーフケアに取り組む団体で行われるプログラムでも、故人宛に手紙を書くワークや、自身の死別体験を話したり、他の方の死別体験を聞く時間があるります。
グリーフケアに関連する書籍には悲しみを癒すための行為として以下のようなアドバイスが書かれています。
1.他者の悲しみの体験について知る
2.故人にできたことを思い出す
3.今の気持ちを誰かに話す
4.気持ちを手紙に書く
5.体によいことをするように心がける
6.周りの人の助けを受け入れてみる
7.遺族会などの集まりに参加する
参考:古内耕太郎・坂口幸弘共著「グリーフケア」毎日新聞社 坂口幸弘著「悲嘆学入門」昭和堂
これらのうち、1.2.3.4は死んだ父の日展を通じて体験できることでした。
想いを言葉にして発散する。
手紙を書いて整理する。
手紙を展示して客観視する。
他者の手紙を読み共感する。
他者の気持ちを知り、死別との付き合い方の参考にする。
これらの体験が「グリーフケア」というアウトカムを生んだと考えられます。
アウトカム②教育
死んだ父の日展に掲載されている手紙を読んだら、人が死んでしまうことの悲しみがよくわかると思う。小学生の子供がいるが、子供にも読ませたい。 人に「死ね」って言ってしまう子供がいるけれど、この手紙を読んだらそんなこと言えなくなるはず。(30代女性)
このような声をいただきました。
死ぬことの重みを、お手紙という子供にも馴染みのある形で伝える可能性を秘めていると、この方のお話を聞いて思いました。
他には
小学生の時「今日は父の日なのでお父さんにお手紙を書きましょう」という授業があったが、私は父を5歳で亡くしているので父がいなかった。その時間はすごくしんどかった。父がいる、という前提で学校の授業が組まれてしまうのは仕方ないが、いない人もお手紙を書けるようにしてくれていていい企画だと思った。(30代女性)
「父がいる、という前提で学校の授業が組まれてしまうのは仕方ない」というお声については、「配慮に欠ける学校だ!」という意見もありそうですが、20年以上前のことで D&I的な考え方も薄い時代の話しである、という補足をさせていただきます。
お父さんがいるのは当たり前ではない、ということを小学生の時から理解する機会になる、というのは大きな教育的価値だと感じました。
教育的価値を生む、というのは企画段階では想定しておりませんでしたが、企画を通じて生まれたアウトカムです。
アウトカム③生へのスポットライト
私の父は昨年亡くなったが、父が亡くなる前にこれを読めたら良かった。父を亡くした人の後悔が書かれていて、生きているうちに何をしようか考えるきっかけになったと思う。(40代女性)
父が生きているうちに死んだ父の日展のメッセージを読んでおきたかった、というお声をいただきました。
応募者ではなく、観覧者の方からもご感想をいただきました。
父は今元気だけど、最近父に冷たくしている。死んだ父の日展のお手紙を読んでいて、今生きている時間は貴重なんだなと、父と過ごせる時間を大事にしようと思った。(10代女性)
お父様がご存命の方からは、いま父が生きている時間を大切にしようという気持ちになったというお声をいただきました。
本展示会が生の尊さを再認識する機会になった、というのは1つのアウトカムと言えそうです。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
振り返りを通じて、来年の改善点が浮き彫りになってきました。
今後も死をテーマにした企画を立ち上げて参りますので引き続きよろしくお願い致します!
こちらのフォームにご登録いただいた方には、死んだ父の日展2022の応募開始時にメールにてご連絡いたします。是非ご登録ください。
また、今回の応募者様からのご要望を受け、死んだ母の日展2022の開催を計画しております。ご関心をお持ちの方は、こちらのフォームにご登録ください。死んだ母の日展2022の応募開始時にメールにてご連絡いたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
