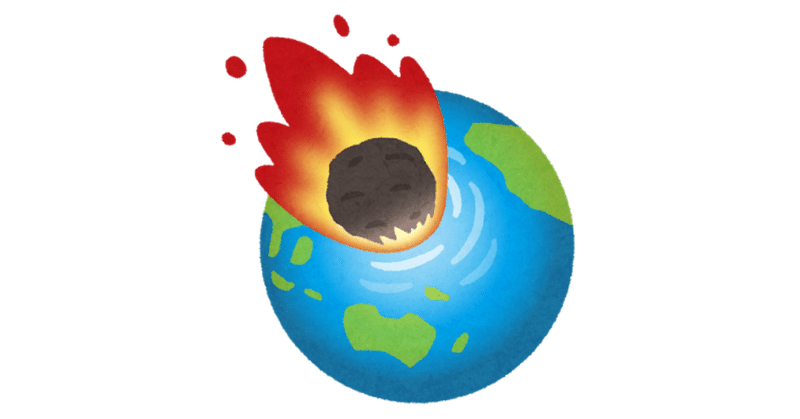
落ちた隕石を見物に行く
「ヤジウマ愛好会」のみんなで、先だって、町中に落ちた隕石跡へ出かける。
「だって、わたしたちヤジウマだもんねえ」会長が全員に向かってにこっとうなずく。わたし達は声を合わせて、「ねーっ」と答えた。
総勢30名、週に1度、会長の高田早苗さんのうちに集まる。彼女は主婦歴20年、そして町内の重鎮でもある。界隈のイベントは、まず高田さんを通してから話し合われることが常となっていた。
「で、あの隕石では、いったい何人くらいの方が犠牲になったわけ?」会員の1人が尋ねる。
「あら、やだわ、奥様ったら。そんなうれしそうな顔で言うものじゃなくてよ」銀縁眼鏡の、いかにも教育熱心そうな女性がたしなめた。
「そうよ、まるで面白がってるみたいで、不謹慎じゃないの」さらに別の者も話に加わる。「それに、あなた。あの件では、どなたも亡くならなかったんですのよ。なぜって、ほら。あとちょっとでぶつかる、ってところで、急に風船みたいにゆっくり落ちてきたって言うじゃない」
「ああ、そうそう。聞いたわ、わたしも。たまたま近くに住んでたって人がいるの。その人の話では、目の前のお宅のレンガの煙突に当たりそうになったんだって」
「いいえ、違うわ。わたしが聞いたところでは、その煙突はコンクリート製だったそうよ。それに、実際はぶつかって欠けてしまったって話よ。ま、どのみち隕石はその家を押しつぶしてしまったんだけどね」
「それでも、逃げ出す暇があったのは幸いだったわねえ。家はぺしゃんこになったとしてもさ」
「ほんと、ほんと。世の中ってば、いつ、何が起こるかなんて、まったく予想もつかないじゃないの。恐ろしいことだわね」
わたしは口を挟む機会もなく、ただうんうん、と耳を傾けていた。
「隕石が地面にめり込んだときのこと、あなた、覚えてらっしゃる?」
「そりゃあ、もう! だって、聞いてちょうだい。あれは忘れもしない、夕方の5時きっかりだったわ。あたし、煮物の下ごしらえをしていたわけよ。そうしたら、いきなり家中がどどどどーって揺れ始めるじゃないの。てっきり、隣の家のバカ息子が、またいつものようにタイコを叩き始めたんじゃないかってね」
「ああ、あそこの息子さん? 去年、大学を出た後、働きに出もせず、ぐうたら遊んでるそうじゃない。そうそう、あんた、あれはタイコじゃなくて、ドラムっていうんだってよ。若者の間で、はやってるらしいの」
「なんにしたって、騒音の元よ。あんなもんばっかり叩いてたら、そのうちに本物の不良になっちまうでしょうよ」
「それも隕石が叩きつぶしてくれたわけだけどね。あの子がタイコ、いえドラムっだったっけ? それを取り戻そうと思うんなら、地面を掘っくり返さなきゃだめだよねえ」
「あれから今日で2週間? え、まだ12日しか経ってないって? どうして、もっと早くに行けなかったんだっけ?」
「自衛隊が取り囲んでたんだもん、そばに寄れないじゃないのさ。あたしは、行ったんだよ。けっこう、そばまで見にさ。なんてったって、会長の高田さんに次いで、この中じゃ古株だろ? 様子を見に行くのが当たり前ってもんさ。ところがどっこい、バリケードなんか築いちゃってね、『ここから先、一般人は立ち入りを禁じます』だとさ。ばかにしてるじゃないか」
「まあっ、失礼ね。いいから、5.1ちゃんねるに書き込んじゃなさいな。そういう事はみんなで問題にしなきゃだわ」
「あたしもそう考えたんだけどね。だけど、あの連中だって、好きでそうしたわけじゃない、と思い返したわけさね。結局のところ、隕石が安全っていう保証はどこにもないわけだからさ」
「それで、今日の今日まで、ずっと調べたってわけね?」
「うん、そういうこと。昨日辺りから、自衛隊が撤退を始めたじゃないの。で、今日はもう、朝から通行止めを解除してさあ、居着いてた学者だのなんだのも、続々ときびすを返して行っちまったのさ」
「もう、誰も残っちゃいないのかい?」
「いや、いますとも。それどころか、見ものですよ。なんと、例の隕石が掘り出されてるっていうじゃないですか」
「そうそう、そうなのよ。それを引き上げるっていうんで、クレーン車がうちの前をバタバタと走っていくのを見たわよ。持って帰って、大学でじっくり研究するんだそうだ」
「あーら、あら。じゃあ、実物を見られるのはこれが最後の機会かもしれないわね。なぜって、あんた。大学なんてところはケチだから、一度しまっちまったもんは、決して出したりしないんだからね」
わたし達が着いたとき、いままさに、隕石をクレーンで吊り上げているところだった。
「思ったほど大きくないじゃないの。あれじゃ、うちの観音開きのタンスの方がよっぽど大きいわ」
「でも、きっとものすごーく重いんでしょうよ。でなきゃ、ここいら一画をぼっこりとへこましたりしないでしょうからね」
「ねえ、見て、あの隕石。なんだかヒビいってるじゃない。崩れて落ちるかもしれないわよ」
「おや、ほんとだ。あっ、ヒビが! あーあ、とうとう落ちた。あなたの言った通りになっちゃったわね」
「隕石、下に落ちて真っ二つだわよ。あら、やだ。わたしったら、今朝の玉子焼きを思い出しちゃったじゃないの。だって、まるで割れた卵の殻みたいなんだもの」
わたしは「卵の殻」を覗き込んだ。中は空洞になっていて、いましがたまで「何か」が入っていたかのよう。
「さて、会員の皆さん。こちらに集まって下さい」高田さんが号令をかける。「ここが一番インスタ映えするので、みんなして記念写真を撮りましょう。あとでネットに挙げるからね。さあ、集まって、集まって!」
わたし達は、隕石跡をバックに並ぶ。
「1番左の人は、もうちょっと中ほどへ――ええ、それでけっこう。後ろの人が隠れてしまうので、背の高い人と順番を入れ替わってもらえる? ありがとう。全員揃ってるか数えたら、セルフ・タイマーをセットしますからね。そのまま、動かずに頼みますよ。ひぃ、ふう、みぃ……29、30。あら、変ねえ。わたしも入れたら31人じゃないの。1人多いわよ」
わたし達は、互いに隣の人を確認し合う。
けれど、知らない顔など誰1人ないのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
