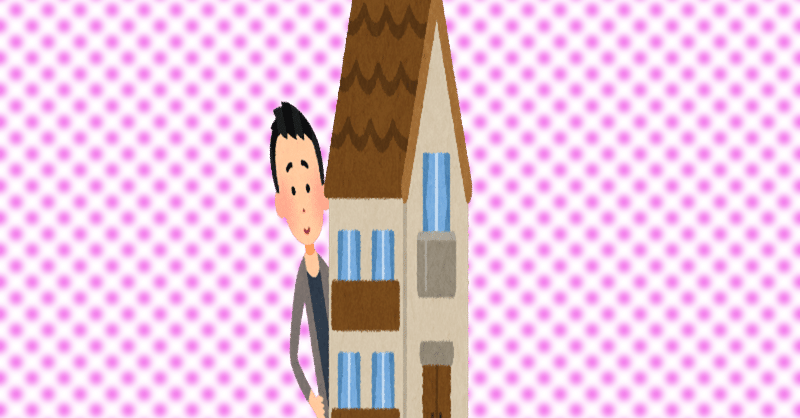
近所のノッポさん
掃除機をかけていると、開けっ放しの窓の外を影が行きすぎる。通りに面した部屋だから人の行き来はあるけれど、それにしては何かが変だ。
「ずいぶんと速かったなぁ。クルマなら、タイヤのこすれる音ぐらいするもんだし。それに、妙に縦長だった気がする」
あんまり気にかかるものだから、掃除機は放り出し、窓から顔を出して確かめてみる。
10メートルばかり先の角を、男が曲がっていくところだった。コンクリート塀が続いていたが、腰の辺りまでしか隠れていない。塀が低いわけではない、その人がおそろしくノッポなのだ。単に体格がいいのではなく、頭と爪先をヤットコでつかんで、無理やり引き伸ばしたかのよう。
「なんて、背が高いんだろ!」思わず、声に出してつぶやいてしまう。
町内に住んでいるのだろうか。これまでに、1度も会ったことはないけれど。
ベランダで、ポインセチアの鉢に水やりをしていたお隣が、そっと教えてくれた。
「あの人ね、2丁目の『ロング・ロング・ハウス』に住んでるのよ。とっても気さくでさあ、何度か遊びにお邪魔したことがあるわ」
「あ、知ってます『ロング・ロング・ハウス』。3階建ての、ピンク色をしたうちですよね」回りが地味な建物ばかりなので、とりわけよく目立っていた。
「あら、違うわよ。あそこのお宅、3階じゃなくって平屋なのよね。だって、ほらっ。あの人ってば、あんなにもノッポでしょ?」
そうだったのか。てっきり3階建てだとばかり思っていた。
「ねえ、むぅにぃちゃん。あんた、ちょっと行って、うかがってきたら? 『3丁目の中村さんの紹介』って言えば、お茶ぐらいはふるまってもらえるわよ」
「行ってみようかなぁ。掃除の途中だったんですけど、もう、それどころじゃなくって」わたしは正直に言う。
「うんうん、そうなさいよ。ほんっとに、いい人なんだから」
ノッポさんの名前は、高野伸行というそうだ。なるほど、名は体を表すかぁ。それに、まだまだ発展途上な含みまで持たせてある。
中村さんによれば、バウムクーヘンが大好物だという。途中にある老舗に寄って、ちょっと奮発するかな。
わたしはバウムクーヘンを手土産に、高野さんの家へ向かった。
例のピンクの家、言われてみれば、確かに造りがちょっと変わっている。3階辺りまで窓はなく、のっぺりと壁が続いていた。
扉もひどく縦長で、7メートルくらいはありそう。ただし、ノブはふつうの位置に付いてた。おそらく、来訪者に気遣ってのことだろう。中村さんの言う通り、親切な人物らしい。
呼び鈴を押す。奥の方で、ピンポーン、と音が鳴り響いた。
「はーい、どなたですか」すぐに応答があり、カチャッとドアが開く。中から、30代半ばの男が前屈みで現れた。
「こんにちは。あのう、3丁目の中村さんの隣に住む、むぅにぃという者ですけど」わたしは上目遣いに挨拶をする。大きすぎて、どうしてもそんな格好になってしまうのだ。それにしても、本当にノッポだった。3階にも達しようというこの扉ですら、窮屈だというのだから。
男はにっこりと笑みを浮かべた。
「ああ、そうでしたか。中村さんにはいつもお世話になっていましてね。先だっても、ズボンの膝っ小僧を繕ってもらったんですよ。さあさあ、こんなところで立ち話もなんです。中へ入りませんか?」
わたしは「お邪魔します」と言って、上がらせてもらった。
1部屋きりの吹き抜けになっていて、真ん中には特注サイズの揺り椅子がでんと置かれている。座が、わたしの背丈よりもまだ高い位置にあった。よじ登るだけでも骨が折れそうだ。
「どうぞ、そちらのソファにお掛け下さい」ソファは普通サイズだった。テーブルも、こちら側はふつうの高さだが、半分より向こうはせり上がって、壁のよう。1人テニスだって、できそうなくらいだ。
「あの、これ。よかったら、召し上がってください」来る途中で買ってきたバウムクーヘンを差し出す。
「あっ、これは、三角堂のバウムクーヘンじゃないですか! うれしいなあ、わたしはこれが大好きなんですよ。いやあ、感激だなあ!」まるで子どものように顔をほころばせた。こんなに喜んでもらえると、こちらまでうれしくなってしまう。
高野さんは、さっそくキッチンでバウムクーヘンを切り分ける。その片手間にお湯を沸かし、ティー・セットの用意までしてくれた。
「ダージリンにしますか? それとも、アッサムがいいですか?」
ストレートは苦手だったので、「じゃあ、アッサムでお願いします」と頼んだ。
わたしの側のテーブルに、アッサム・ティーと砂糖壺、それからミルクの入ったグラスが置かれる。
高野さんはと言えば、何も入れないダージリンだった。
「実は、午前中、高野さんが家の前を通りかかるのを見かけたんです」わたしは言う。「外を覗くと、信じられないほど背の高い人が歩いていくんで、本当にびっくりしました」
「ふふ、驚かせてしまいましたか。ちょっと、あの辺りまで仕事で呼ばれましてね」
「お仕事だったんですか」
「ええ、電気工事をしに。カラスの巣が原因で、漏電があったらしいのです。ほら、ご覧の通りノッポでしょう? ちょっと手を伸ばせば、梯子なしでも電柱に手が届くんですよ」
まさに天職だなぁ、とわたしは感心した。クルマの入れないような狭い所だって、高野さんなら身一つで取り掛かれるんだから。
部屋の片隅で、電話機が鳴った。高野さんはカップを置き、ちょっと失礼します、と言って受話器を取った。
「はい、高野ですが。あ、はいはい。公園の街灯の電球交換ですね。すぐに行って、済ませてきましょう。ええ、いますぐです」
どうやら、仕事が入ったらしい。
わたしは紅茶の残りを急いで片づけ、帰り支度を始める。
「今日はとつぜん訪ねてきてしまって、すみませんでした。でも、とっても楽しかったです」わたしは礼を言った。
「いえいえ、こちらこそバウムクーヘンをごちそうさまでした。近くなんだし、ちょくちょく遊びにいらして下さい」うどんのように細長い体を折って、ペコリと頭を下げる。
外へ出ると、もう夕方だった。後から、工具箱をぶら下げた高野さんも姿を現した。
並んだわたし達を夕日が照らす。高野さんの影は遠くまで伸びていた。
とてもとても長く伸びていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
