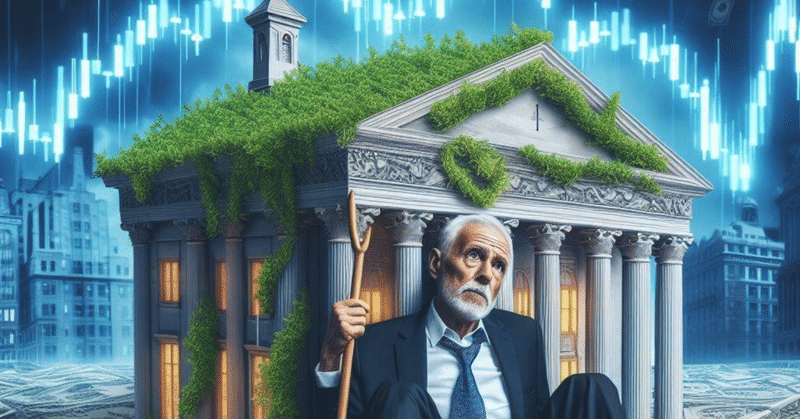
本日のメモ(【本日のメモ】を最後に書いたのは3年5ヵ月26日前)
↑が3年5ヵ月26日前のやつ。
日数の計算はこちらのサイトを利用した。
↑の売買手法と、記載されてるチャートの画像から、その内容を考察してみる。
このシステムは全体株価が下げる中で、逆に上がってる株を選んでいる。というのは、全体の流れに連れ安するだろう事(鞘寄せ理論)を想定し、上がった株を空売り仕掛けるのだが、その空売りを食い物にする勢力が売りの勢力を買い占める動きがあるとき、全体に連れ安する事なく株価が上値を更新してくる。
デイトレーダーはチャート等を使い独自の解釈から意識せずとも、その流れを掴もうしている。たとえば買った後に1分以内に撤退してしまうのは、株を空売りで仕掛けてる人も自分が食われている流れの変化に気付いてしまい撤退するからでその買い戻し圧力で価格を上げてしまう。その買い戻しの圧力は1分もあれば織り込まれてしまい、それ以上待っても積極的な新買い注文は来ず、株価は上には上がりにくいからで
ちなみに空売りを買い占める勢力はBNFのような資金力ある個人で、そいつらは半日から長くても翌朝までしか株を持たない習性がある。彼らが市場から逃げるタイミングまで株を持っていると、彼らの手仕舞い売りの圧力にさらされて株価は下がってしまう
このデイトレーダーの強みは、自分と同じやり方をする人間をnoteで布教して集めて、同じタイミングで買い注文を出させ流動性を確保して、手仕舞いの売り注文が確実に市場に届くように工夫してること。
※本人がそれを意図しているかどうか定かではない。投資で成功した人は自慢したくてノウハウを人に広めようとする傾向があり、また、それが更に強みになることもある。詳しく説明したら複雑になり過ぎるので省略するが彼もまた食う側でありもっと別の概念でトレードしている者(板トレーダー)を鴨にしている。本人に自覚があるかは定かではない
万が一買った瞬間に悪いニュースが出て、直ぐに売らなければならないとしても、同タイミングで自分が布教した買い手が少し遅れて買い注文をしているのなら、そいつに売ることで自分の約定分は確保できてるので売り逃げが可能である
小さな利益幅で抑えるのは、経験則等を元にしているのだろうか? その手の内を公表してしまうと、真似する人はそれよりも下の値段で注文しとくと、確実性ある売買が成立し、その分、この手法を紹介した者にとっては手仕舞い注文が通りにくくなるリスクが上がる。とはいえ、前述の板トレーダーを鴨る作用から、noteで手法を広める程にリスクは下がる。
まくど(MACD)や移動平均はテクニカル分析の世界ではトレンドフォローの概念によく利用される。つまり、価格が平均線を下回ったり、短期まくどが、長期まくどの下にくるとき、弱い相場と判断される、また、その判断によって実際に売りの注文が入り、価格を下げてしまう。その分析が正解かどうかは無関係にその分析を信じる者の影響力からトレンドが作られてしまう。
このデイトレーダーがマクどや移動平均を見ているのは、その指標を株価が下回るとしたら、その日は上値が期待できない可能性が高くなるので、株をチェックしている時間が無駄になるので、お休みするとか、別の株を調べるか、色々な可能性が考えられるが、少なくとも
マクどや移動平均に逆らうような売買をしないのが常識なのであるが、逆にその作用を利用して売買をしている勢力もあるだろう。
ちなみにRCIは株価の上下運動を極端にビジュアル化したものといっていい。規則的に直近の株価の天井と底がRCIに連動しているが、この連動性を期待して売買する勢力もある
その勢力でいうと14時頃以降に一回、売りのシグナルを発して損を被るだろうが、言い換えると、その勢力を食べてしまう勢力(大口の買い手)がいる場合、その買い支える作用で、まくどや移動平均が上向きになり、トレンドフォローの概念をチャート上に作り上げる事が可能で、その流れに乗れば儲かるという事で更にトレンドが形成されフォローされる。BNFのような相場の成功者はその流れに乗るし相場を作る側にある
たが、そういったテクニカル指標上の思惑が必ずもも作用しているとは限らない。翌日のギャップアップ(値飛び)現象からいって、その株には何らかのファンダメンタルズがある。例えば、市場関係者がアナリストレポート等を発行して、客に読ませて買わせる流れがあると翌朝の注文に客の買いが集中して値が飛んでしまう。レポートの影響力があるのなら、その後も継続的で積極的な上値を買ってくる動きもある訳で、その値動きを期待してデイトレードではなく、もっと長めに株を持つべき方が効率的と解釈するスイングトレードなる概念もある。
スイングトレードは一泊持ち越しから長くても一週間から二週間しかポジションを持たない。アナリストレポートが発行されるとしても熱心な個人投資家は遅くとも一週間以内に読みきりるからして、それ以上待っても買い手が市場にやってこないので上値が期待できない。
スイングトレードの強みは市場関係者の思惑を利用できる事にあるが、持ち越してるから寝てる間に震災やテロ等リスクにさらされる危険とも隣り合わせ。
デイトレードと比べて、どっちが良いかは完全に個人の趣味によるところが大きい解釈している。デイトレードの場合はチャートだけでなく板画面でのテクニカル分析があり、分析の領域を広げる事ができる。人によってはチャート見ないで板だけで売買をしてる人も希にいる(※ブログやSNSからの観察により)
だが、そういった板だけ個人も、トレードやってる内にチャートを見るようになる。好奇心からか、、皆やり方は微妙に違えど同じ様な概念で売買をするようになると思う
チャートは過去の値動きを記録しているだけだが、板は今ある注文の全てが画面に表示される。今以上の今が見え、あたかも未来の値動きを推理するのに役立つかのような思想、概念がある。
興味深いのはアメリカの株式市場に日本のような板システムがない事。個人は証券会社が予め用意している株式を証券会社が値付けした価格にて一対一で売買するという相対方式。、それにより日本とは全く株価の動きが異なるという。どう違うかは説明しにくいが、例えば、アメリカには値幅制限がない。株価が1日で二倍になったり、半値以下になったりすることが度々起きて市場が混乱する
混乱するというのは、その株の市場価値が適正である事を想定した場合に、似た業種の株式も同じような価格変化があるべきと想定する考え方により、関連株の値を変更したりと証券会社は忙しくなる。昔はその作業を手動でしていただろうが、今ではコンピューター、特にAIが適正な価格を算出して値を変更してたりするんではなかろうか。証券会社が自ら保有している株にどのような値付け原理を適用しているかはブラックボックスにて判らないもののも、チャート分析やテクニカル分析、あらゆる手法を取り入れているような気がするが、手数料収入でやっていけるのが証券会社なのだろうから、案外複雑なシステムは使われてないかもしれない
例えば、以下の本を買ってみると分かるが、「こんな単純な売買手法でお客さんのカネを運用しているのか!」と驚いて尻餅つきたくなるような、「あり得んだろ!」と思うものが幾つもある。
その手法の一例を挙げるなら
1「株価が4%上がったら買い」
概念としてはトレンドフォローであり「強い動きには何かそれなりの理由があるはず」
2「株価が月間で20%下がったら買い」
概念としては、いくらなんでも下がりすぎ。感情的になり売られ過ぎている。
3「株価が連続して3日下がったら買い」
概念としては、「いくらなんでも3日連続はありえない。相場の変動はランダムははずだ。」というランダムウォークな理論を支持する
こんな単純な手法で通用するのかと疑いたくなるものの、その本では実際に機能したと言わんばかりに統計的な数値(成功率)を紹介してくる。
拍子抜けする内容でその本を買ったら詐欺にあったと思うだろうが、、むしろそれがこの本の強みかもしれない。あまりに単純過ぎる概念なので誰も真似しない。真似されないからこそ、機能するのかもれない。なら今でも利用されている可能性がありそう?
というより、アメリカの金融市場が大き過ぎるのだ。お客さんのカネが預けられたとき、その担当者はそのカネを何に使っても許される。相場の動きががランダムならば、どんな売買手法を開発してもトータルではマイナスにらなない筈で、どんなにアホらしい売買手法も取り入れる事が可能である。アメリカは経済成長著しく、金融機関にはおカネが、ねずみ講の如く舞い込み、ちょっと損したくらいではネズミの資産で穴埋めできてしまう。
ヘッジファンドの売買手法はネットとコンピューターが広まりはじめた頃に運用されていた手法であるだろう。その頃の時代から見れば斬新な手法だったので評価されていた。AIがありきの現代からみると、単純過ぎるどころか原始人の発明かと思えるので、今はどのファンドもそんな単純な手法は使ってないと思うが、前述した様にアメリカ経済は成長率が著じるしい、ちょっと損したくらいではお客さんのカネで粉飾決算する余裕があるばす
もしもアメリカ大手の金融機関の自己投資部門が、前述の本ヘッジファンドの売買技術のような単純な手法を今でも使っていいて、損失を抱えていた場合
何らかの弾みで金融ショックが起きたとき、お客さんが資金を引き上げようとしてそれが出来なくなる、その時、ようやく事態が明るみになるような、そんなおざなりな事件がこの際起こらないとも限らない。
去年シリコンバレーバンクが破綻したが、その構造的原因はふわふわとして掴みどころの無いものだった。サブプライムショックのような明確な不原因がある訳でもない。専門家は金利差を理由にどうこう言うけど、結局はお客さんがシリコンバレー銀行から資金を引き上げたことを切欠にして業務不全を起こして破綻申告した。損失額はサブプライムショックの際に倒産した銀行の凡そ半分であるが、言い換えるのなら100年に一度だった金融ショック(サブプライム問題)なのに、その半額損失のシリコンバレー銀行は約50年に一回のショックを起こしている。
サブプライムショックは2007年からで、あれから20年経ってない。50年に一度のスケールでの金融不安が20年にまで短縮されている兆候がある共に、シリコンバレー銀行の倒産がまだこれから始まる連鎖倒産の一部分に過ぎないとしたら、これからアメリカで何が起こるのか…
悲観論ばかりに片寄るのは悪い癖だ。前向きに解釈するのなら、シリコンバレー銀行50年に一度の金融ショックが起きても特別経済にダメージはなかった。アメリカの経済力は今や100年に一度のサブプライムショックが再び起こるにしても、平然と立ち直る経済力があるかもしれない。実際アメリカが破綻してしまうと世界的な損失なのだから、都合が悪くなるとしてもアメリカを買い支える必要がある。それによってアメリカの価値は維持される
関連note
毎日、沢山の漫画に囲まれて楽しそうですね👍✨
— グヲタン(☆星クズ) (@guotan12) January 31, 2023
仕事しながら趣味も充実させて、時間の使い方が上手ですね!
漫画は紙にて環境破壊、ペット飼育の痕跡はペットフードに畜産動物が利用される件で命の差別(種差別)
そういう事をしてる人を羨ましいと思うのは、やくざに憧れてる不良少年と同じ心理のようなもの。
少年漫画とは関連性ないけど
、2024年もインフレ率がやや上昇する傾向が続くと予想される。しかし、これはFOMC関係者や市場が大方予想していることだ
つまり、インフレが想定され市場関係者は既に投資している。言い換えるとこれ以上の新規の投機資金は金融市場にやってこれず、資産価値が上がらない可能性がある。上がらないなら、下がる可能性も
◯アンチヴィーガンを斬る!
坂上忍等のボランティア(ペット愛好家)により最近ではペットフード需要が高くなり畜産利用が止められない時代に尚一層きていますが、最近ではペットフードが改良されいて、ヴィーガン用のもあるらしいです。つまり畜産動物を利用しなくても良い時代が到来しています。人類凄いっす!
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
