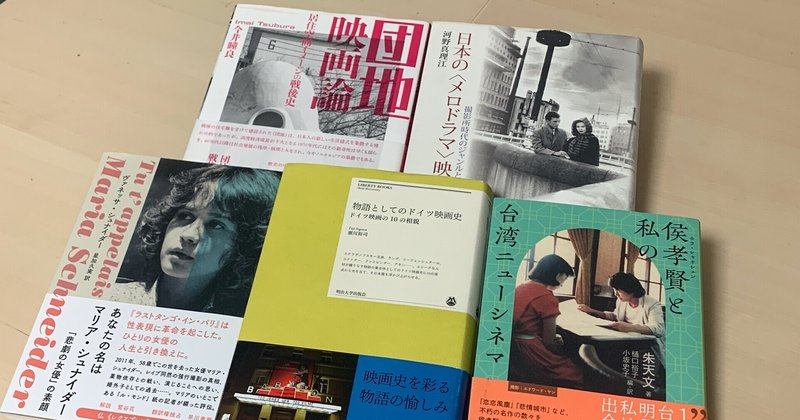
月例映画本読書録:2021年04月
今年、ぼくとパートナーのMは「毎月、その月あるいは前月に刊行された映画本を5冊読む」ことに決めた。
…ということで、毎月5冊最新の映画本を読んで、ぼく(=Y)とパートナーのMで短めな感想を書いて記録していくという企画の2021年4月分=第4回目である。企画開始の経緯などは初回である1回目に書いたので、未読の方はまずそちらをぜひ読んでみて欲しい──以後更新されていくの分も含めて、以下の”マガジン”機能で全てまとめておくつもりなので、こちらのページ↓を見ていただければ、常に”現状”の全ての回がみられるはず。
では、今月の5冊をはじめよう(並びは刊行順/感想は読了順)。
今回は、3月刊行のものor 4月刊行のものから。
・河野真理江『日本の〈メロドラマ〉映画』
森話社/2021年02月26日発売/288頁/3,800円+税
※2月26日発売の本ですが、Amazon表記が3/3になっており、今日の今日まで気づかず…例外としてご容赦ください。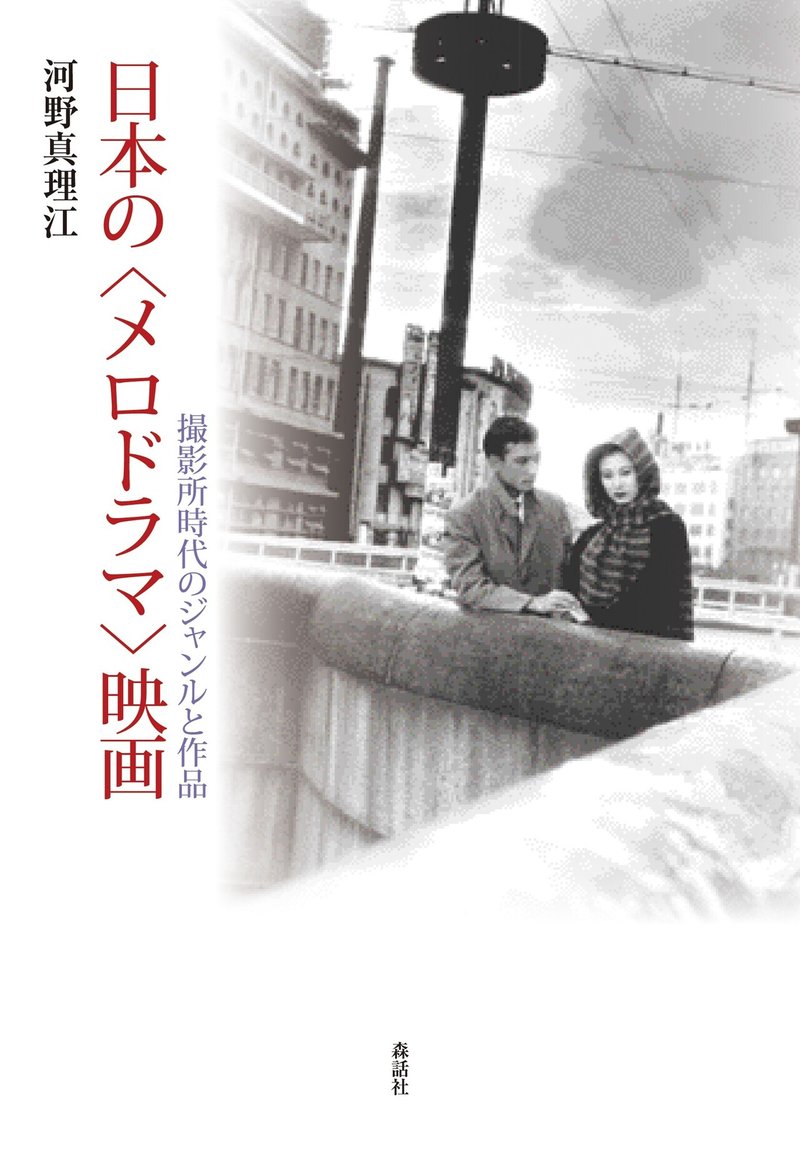
"メロドラマ"って何ぞ? と言われると、正直なところ困ってしまう。ピーター・ブルックスは名著『メロドラマ的想像力』(絶版…なんとかならないものか)で「強い感情への耽溺、道徳の分極化と図式化、極限化された存在状態、状況、行動。あからさまな悪行、善なる者たちへの迫害、そして、最後に美徳の勝利。誇張された表現。いわくありげなプロット、サスペンス、息をのむような運命の急変。以上挙げてきたことがメロドラマという言葉に含まれることがらである」と書いているのだが、正直なところ、恥ずかしながら厳密にはわかっていない気がする…たびたび便利ワードとして使っているにもかかわらず。本書は"日本の〈メロドラマ〉"と題されているように、上記のフィルムスタディーズにおける「メロドラマ」ではなく、その隆盛のずっと前から日本において浸透していた独自のジャンルとして作品群を取り上げ、つぶさに分析を加えつつ、別の経路を辿りつつも最終的には「メロドラマ」検討に回帰する…という必読の一冊。著者による関連論文「「メロドラマ」映画前史——日本におけるメロドラマ概念の伝来、受容、固有化」も一緒にどうぞ(ネットで読めます)。(Y)
松竹大船調のメロドラマに該当する作品に関する論文は多くあるし、実際に読んだこともあるが、日本における“メロドラマ“というジャンルの受容を研究するのは画期的なのではないだろうか。『君の名は』も『愛染かつら』も戦後の映画史を語る時にタイトルはよく見聞きするのに、その作品論や文脈を丁寧に説明されることは少なかったように思う。そして私もそれに囚われ、日本のメロドラマ映画を軽視していたと気付かされた。反省です。
また本著を読んで気付かされた点がもう1つ。第5章で触れられる増村保造『妻は告白する』が、当時の文芸メロドラマとしては例外的に男性批評家から礼賛された作品として紹介されている。個人的に『妻は告白する』の時評の良さがどこか腑に落ちないとずっと思っていたのだが(作品自体が嫌いとかは出ないです)、この章でメロドラマの文脈から作品を捉え直すことでとても腑に落ちた。同じように思っている人がいるかはわからないが、短いパートながら読み応えがあるので、楽しみに読み進めて欲しい。(M)
・瀬川裕司『物語としてのドイツ映画史』
明治大学出版会/2021年03月13日発売/410頁/3,400円+税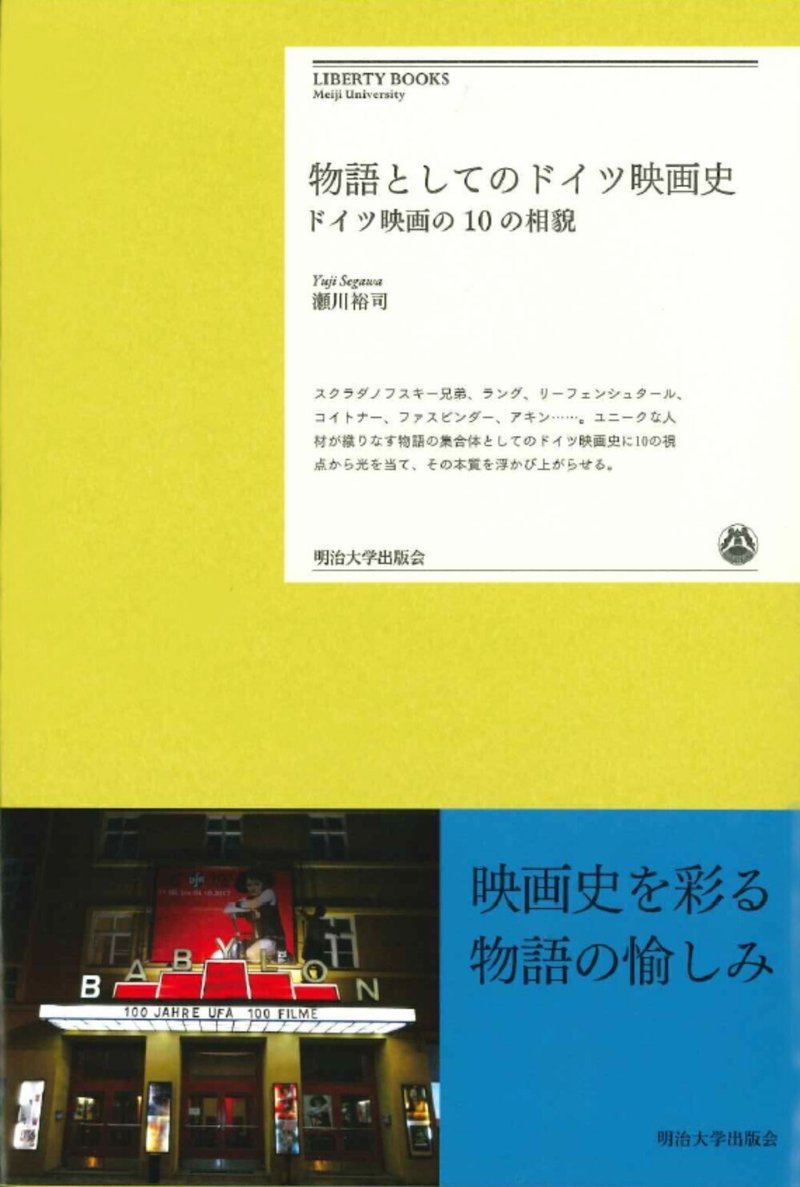
10つのトピックを筆者がのびのびと書いているような印象。固そうにも見える本だが、むしろ軽めな内容だと思う。
第1章のスクラダノフスキー兄弟(ドイツの映画機材発明者)に関する内容が特に刺激的だった。筆者が指摘するように、“映画史”で語られるのはリュミエール兄弟とエジソンばかりだが、それ以外の発明者の存在もやはり重要である。また、各国の映画前史と映画誕生時期・輸入初期の受容のされかたは1月に活弁本を読んだときにも思ったが、その国での映画製作や文化に面白い影響を与えていることもあるので、積極的に今後は調べてみたい。
またこれは本筋とずれるので最後に記すが、10章で2000年代のドイツ映画を語る際、移住者ではなく元々ドイツに住んでいた登場人物を“純粋ドイツ人”と説明上名付けていて、居心地の悪さを感じた。“純ジャパ“とかSNS上で使う人も多いですけど、怖い表現だと思います。10章は全体的に駆け足に近作を紹介していたのもあり、10章の内容がもう少し違えばもっと気に入る一冊だった。(M)
過去にも執筆を打診されたものの「編集者がイメージしているような一般的な形式の書籍を執筆する気には、どうしてもなれなかった」と自ら説明する著者が、満を辞して書いたドイツ映画史本。ここまで啖呵を切っているのだから、むろん"一般的な形式の書籍"ではない。著者曰く「従来の歴史記述では、中学校や高校の教科書のようなスタイルが標準的だと思われて」おり、過去から現在へ「それぞれの同時代的状況を概観して情報を並べるという書き方」即ち「〈年代ごとの現象を横切りしたもの〉」になるので「〈現象を縦切りにする〉視野が不足」してしまうのだという。そんな問題意識から出発している本書は「ドイツ映画とその歴史の全貌を人間くさい物語の集合体ととらえ、わが国ではほとんど知られていない映画人の物語に注目したり、(中略)過去になかった視角を設定して観察したり」する試み…らしい。加えて本書では、邦題fuckということで、作品題は基本的に著者の直訳題が使用され、初出時のみ括弧で本邦における公開題が添えられる。あゝ、なんてクセのある香ばしい前口上だろう。清々しい喧嘩口調…こういうのは好みなんだ、さて、いざ拝読…と頁を捲っていくと落胆が待っている。大抵の章で"縦切り"という名目で語られるのは、ひたすらに積み上げられた粗筋紹介と見覚えのない直訳題の列挙羅列のみである。教科書スタイルならどんなに面白く読めただろう。やはり教科書は侮ってはならぬということか。因みに本書、索引すら付いてないです。(Y)
・今井瞳良『団地映画論 居住空間イメージの戦後史』
水声社/2021年03月23日発売/318頁/4,000円+税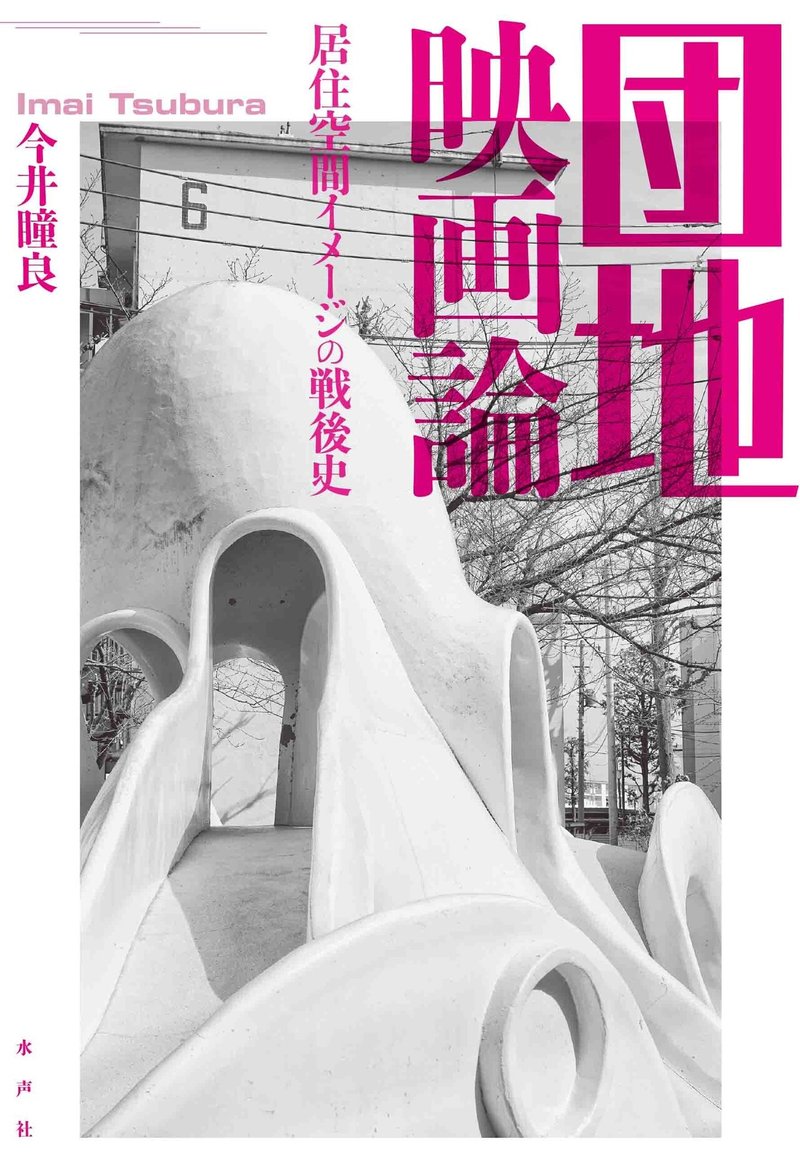
この企画をやっていると本の装丁を比べられるのが楽しいが、本著の装丁が個人的にかなり気に入っている。(モノクロの画像にこのピンクの文字なのがかっこいいポイントな気がします。)
私はなぜか大学の授業で一年間いろいろな団地映画を見て、分析する授業を受けており、「この作品はこんな読み解き方があったのか…」という楽しさが人一倍あったと思う。団地は映画に限らず、ファンも多く、いろんな読解がされている存在だと思うが、本著はフェミニズムやジェンダーの視点から作品を読み取っているのが特徴。団地×ジェンダーという掛け合わせ自体は目新しいわけではないが、ここまで体系的に時代の変遷と受容や作品の変化を分析していると読み応えがある。また、著者は学部が社会学系ということも影響してか、社会学的な観点の書籍の引用や社会背景の説明も詳しいのも面白いポイント。
作品と時代のターニングポイントはロマンポルノの箇所だと思うが、“団地妻”のイメージの源流について細かく分析しているので、ロマンポルノファンも楽しめるのではないでしょうか。(M)
映画における団地表象の変遷を辿る一冊。九章にわたり、かなり広範な作品を扱っているが、ロマンポルノのいちシリーズが"団地"イメージに大きな影響を及ぼしたことが判る第五章「日活ロマンポルノに現れた「団地妻」」がとにかく抜きん出た面白さ。各作品の丁寧な読み解きはもちろんのこと、最終的には全29作にものぼった同シリーズは、たびたびマンネリなどの危機に直面しつつも、その時々の機転と工夫で新たなアプローチを試みてきた…というプチ団地妻映画史としても読み応えがある。また、そもそもロマンポルノ自体、資料は充実してきているものの体系的な研究が不足しているという重要な指摘もなされ、まさに本書の白眉と言える章だろう。本書は同題の博士論文を大幅に加筆・修正して書籍化したものだというが、いくつかの書き下ろしを除く章の初出誌情報が巻末に記されており、太っ腹なことにresearchmapからベースの論文が大方読めてしまう。正直なところ、太っ腹すぎて気が引けるが、購入を検討している諸氏はまずこちらを読んでみるのも手。
最後に、余談だが念のため書いておくと…水声社はAmazonとの取引をしない方針を貫いている版元(至極真っ当な理由から…気になる方は調べて欲しい)のため、調べても出てきません。他の方法でお買い求めください。(Y)
・朱天文『侯孝賢と私の台湾ニューシネマ』
竹書房/2021年04月01日発売/296頁/2,500円+税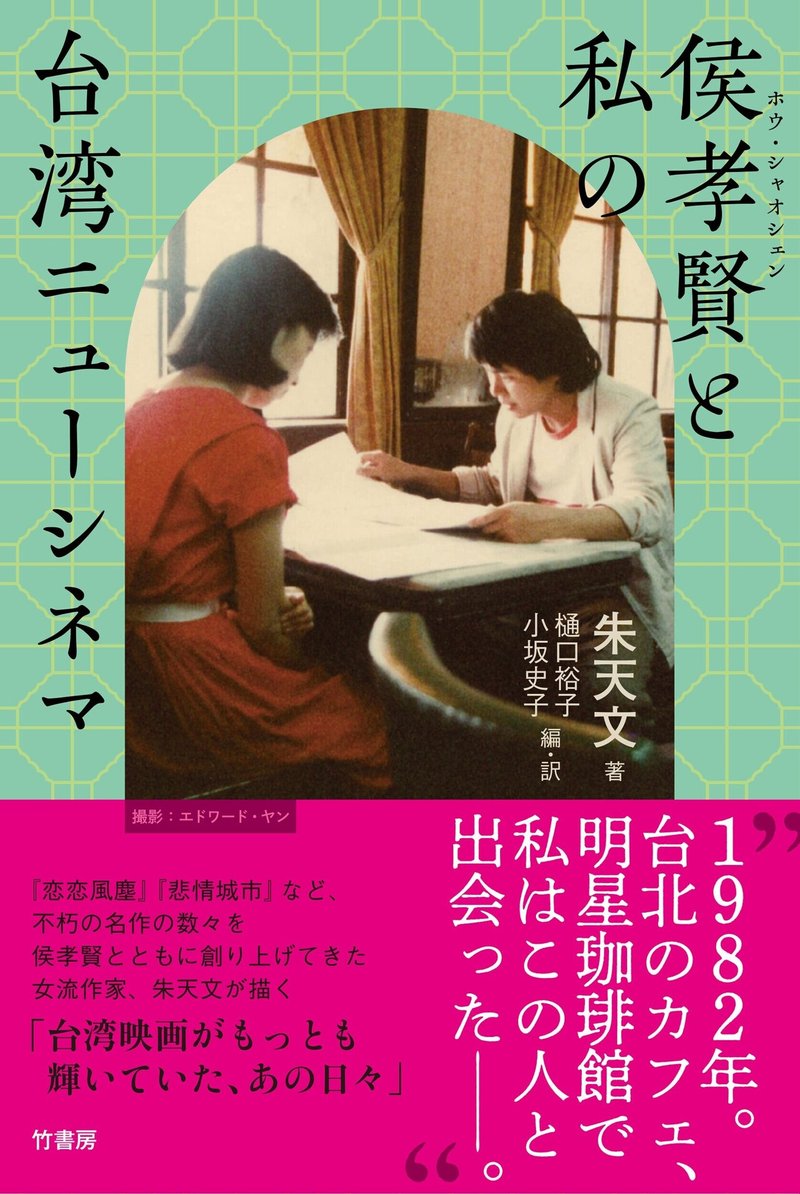
まず内容と関係のない小言で恐縮だが、私はこういう小言は積極的に言うべきという考えなので言わせてもらうと、帯文に「女流作家」と書いてあるのは”ご勘弁”という感じですね。(なぜか今月は小言が多い内容になっているが、そもそも私は小言が多いタイプです。どうでもいいですね。笑)
本題に入って紹介をさせてもらうと、本著は侯孝賢の脚本家でもある作家・朱天文のエッセイ集だ。画像もかなり多いので当時の雰囲気がよくわかるし、全体的にエモーショナルな仕上がりの一冊だと思った。
正直にいうと私はそこまで侯孝賢に好感がないので、本の読み方も穿ったものになっているかもしれないが、面白かったポイントは朱天文が侯孝賢の才能を信じ、好みながらも、その手法や映画論に対して時折懐疑的であるように見えたり、冷静な分析を行っている点。「長回しの問題はその長さでも緩慢さでもなく、得てしてそれが美学的スタイルの一つに過ぎないという点にある」など、かなり身も蓋もないような表現もあり、これが近くにいる作家のリアルな侯孝賢との距離なのかもしれないと楽しんだ。(M)
侯孝賢作品の脚本家として知られる作家・朱天文のエッセイ/対談/講演などをまとめたもの。"軽め"枠として気軽に選んだ本だったが、これが思わぬ拾い物だった。収められている文章は回顧して書かれたものではなく、どれもその時の"リアルタイム"のもので、侯孝賢作品の裏話には事欠かない──例えば『フラワーズ・オブ・シャンハイ』の阿片吸引描写はグレアム・グリーンの著作を参考にしたらしい──が、個人的に深く印象に残ったのは映画の具体的な逸話よりも、むしろその合間合間で語られる"行きつけの喫茶店"描写だった。1982年、明星珈琲館で初めて出会った二人は(表紙写真は『冬冬の夏休み』時だが、場所は同じく明星珈琲館)共同脚本をこの店で練り上げ、『童年往時』から『悲情城市』までは客中作という茶芸館で過ごしたという(「毎日昼食が済むと行き、夕方までそこにいて、外で食事してまた戻り、ラッシュアワーが過ぎてからやっと帰る」)。そして二人は今でもひっそりとしたチェーン店であるというダンテ珈琲に日々集まる。脚本を討論するか、あるいは夜まで各自の仕事をこなし、夜ご飯を食べ終わると解散するのだ。場所は変われど、行きつけの場所でのルーティーンの日々は変わらない。なぜだか胸を打たれた。(Y)
・ヴァネッサ・シュナイダー『あなたの名はマリア・シュナイダー』
早川書房/2021年04月14日発売/224頁/2,800円+税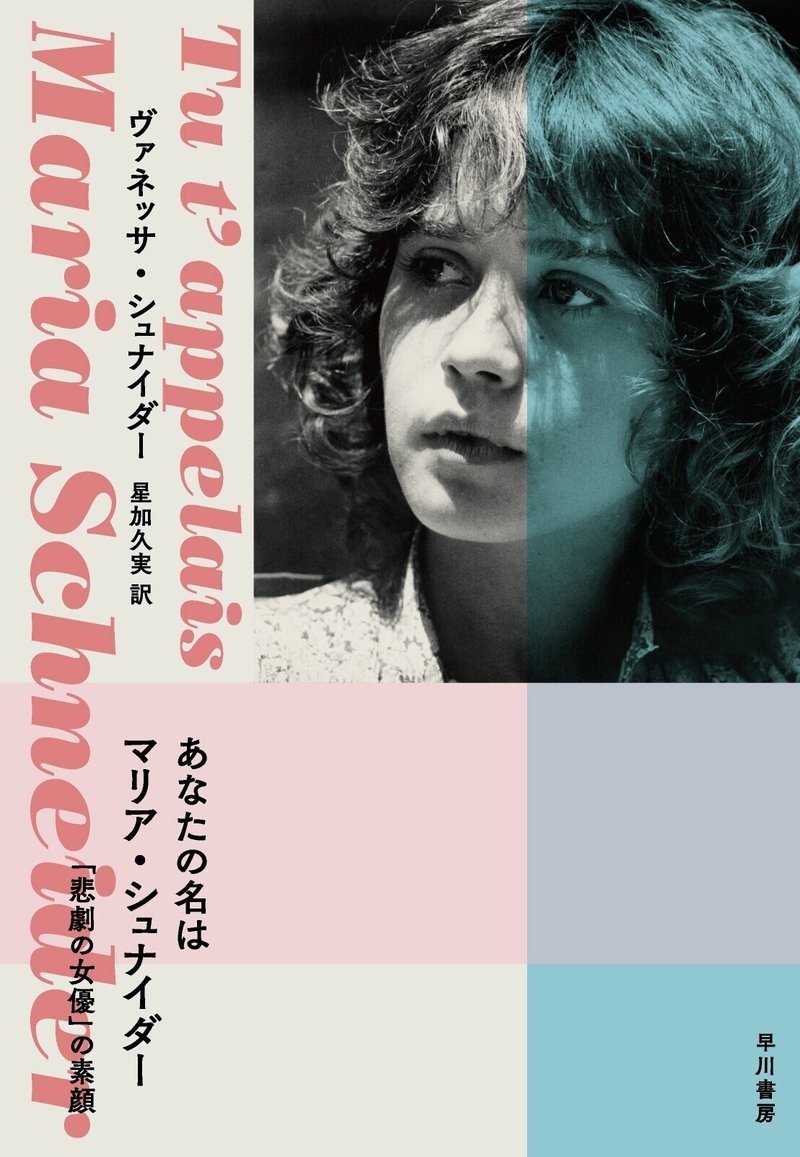
本著はマリア・シュナイダーの都市の離れたいとこでルモンドの記者をしているヴァネッサ・シュナイダーが執筆している。自伝小説など計7冊の出版をすでにしているようで、本著もエッセイ的な読み物の味わいもある。マリア・シュナイダーの人生についてももちろん知ることができるが、問題の多い親族を抱えた少女(ヴァネッサ)がいかに成長したかという点からも楽しめる。
『ラストタンゴ・イン・パリ』の事件が許されないものであることは本著を読む前から自明であるが、この本でさらに明らかになるのは”セックスシンボル”や”性的客体”とされた俳優の苦しみもまた根深いものであること。加害者でもあるマーロン・ブロンドも映画出演以降傷つき、マリアと文通していた事実も印象的だ。また、マリアと親交があったブリジット・バルドーや、鷲谷花の解説で触れられるビョルン・アンドレセンのエピソードもこの問題を提示している。(M)
従姉妹視点で描かれたマリア・シュナイダーの評伝。しかし正直なところ、良い評伝とはとても言えない。マリアの人生とはほとんど関係のない、著者のヴァネッサ自身の少女時代(マリアとは17歳差)の記述にも多くの頁が費やされているのである。もちろん、親族としてマリアと接した体験は”評伝”の強みにはなる。しかし、マリアとは凡そ無関係な日々は、本書の中で描かれるべきものなのだろうか。著者は何度も強調する──「私たちは、みんなとは違っていた」。確かに問題の多い家族ではあったようだが、結局のところ著者はただの”従姉妹”でしかない。もともと本書は、病に冒される前のマリアが著者に「(一人で完成できそうにないので)一緒に」と手助けを頼んだことを発端に動き出したが、肝心のマリアが企画を諦めたことで一度は頓挫したものらしい。著者が本書のなかで認めている通り、きっとマリアはこのような本が”他人”によって書かれることを望まなかっただろう…著者は「でも、私は語る。なぜなら、マリアと同じように、私にも何をする権利もあるからだ」と開き直っているのだが。「ここに語ることは、私の物語でもあり」…それは他所でやってくれませんか。(Y)
* * *
〈その他・雑記など〉
田房永子『大黒柱妻の日常 共働きワンオペ妻が、夫と役割交替してみたら?』は連載時から読んでいたが、田房さんの目の付け所のシャープさと、噛み砕いて表現する力のすごさが発揮されている1冊だと思う。
安野モヨコ『後ハッピーマニア』2巻。あの凄まじい『ハッピーマニア』の続編ということで、どんな内容になるのかビクビクしていたが(つまらないのでは…ではなくまた凶悪で最悪な一冊が放たれるのか…覚悟して読まねば、の気持ち)、各話本当に面白くて唖然としてしまう。そこそこ冊数もありますが、未読の方は『ハッピーマニア』から読んでほしい。損はしないです!あとnoteで公開されている『監督不行届』の文章版続編『還暦不行届』も良い。
またこれは今月刊行の本ではないが、『団地映画論』の中で言及があり、また『あなたの名はマリア・シュナイダー』の解説も務めていたという偶然もあり、2019年8月発行の『ユリイカ』京マチ子特集の鷲谷花「真砂サバイバル 『羅生門』における「ぐじぐじしたお芝居」とその放棄」も紹介したい。最初に読んだ時、自分が『羅生門』の評価に対して感じていた違和感を解き明かしてくれた巧みな内容に衝撃を受けた。『羅生門』を“強姦の映画”として正面から論じ、評論家から“悪女”とも評された京マチ子演じる真砂について捉え直していて読み応えがあるので、ぜひ読んでみてほしい。(M)
今月はそれほど読書進まず。『作業日誌』がバイブルの人々は皆読むべし…な中原昌也『2020年フェイスブック生存記録』(Kindleのみなのが悔やまれる)、Mの勧めで読んだ『大黒柱妻の日常』、そして同人誌『ATALANTE TRIANGLE』くらいか…ほかは読みかけばかり。すでに読み始めているのだが、来月取り上げる予定の遠山純生『〈アメリカ映画史〉再構築』は、本当に別格な凄みがある。必携です。(Y)
では、今回はここまで。
次回は5月31日更新予定です。
ここから先は
¥ 100
本文は全文無料公開ですが、もし「面白いな」「他もあるなら読むよ」と思っていただけた場合は、購入orサポートから投げ銭のつもりでご支援ください。怠け者がなけなしのモチベーションを維持する助けになります。いいねやコメントも大歓迎。反応あった題材を優先して書き進めていくので参考に…何卒
