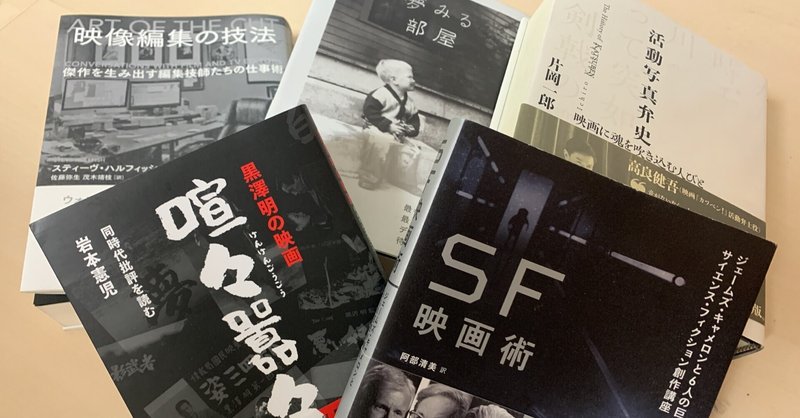
月例映画本読書録:2021年01月
今年、ぼくとパートナーのMは「毎月、その月あるいは前月に刊行された映画本を5冊読む」ことに決めた。
わざわざ「読む」と決めなくとも、常になにかしら映画本を読んでいる状態のほうが多いのだれど、毎回読後に感想を書くわけでもないし、否が応にも既に関心のある分野の書物に手を伸ばしてしまいがちである。毎月5冊…と決めたとしても、やはり"選ぶ"行為が介在する以上、偏りを避けることはできないが、それでも条件が固定されていることで網羅性は少しだけ向上するはず。いままでであればスルーしてしまっていたであろう本も多く拾うことができるだろう。周囲の評判が良いものを追いかけて買うのではなく、まっさらな印象で未開の"新刊"状態のものを選び、リアルタイムで読む楽しみも大きかろう。
…ということで、毎月5冊最新の映画本を読んで、ぼく(=Y)とパートナーのMで短めな感想を書いて記録していくことにした。単純計算では、年に60冊分の映画本を取り上げることになる。毎月少なからず刊行されていく映画本をまとめて紹介してくれる場はほとんどなく、故にそもそもぼく自身が一番「あったらいいなあ」と思っていたものだった。少しでも読んでくれる方の参考になれば嬉しい。
では、今月の5冊をはじめよう(並びは刊行順/感想は読了順)。今回は初回なので、昨年刊行のものor今月刊行のものから。
・ ジェームズ・キャメロン 『SF映画術』
DU BOOKS/2020年9月30日発売/304頁/3,200円+税
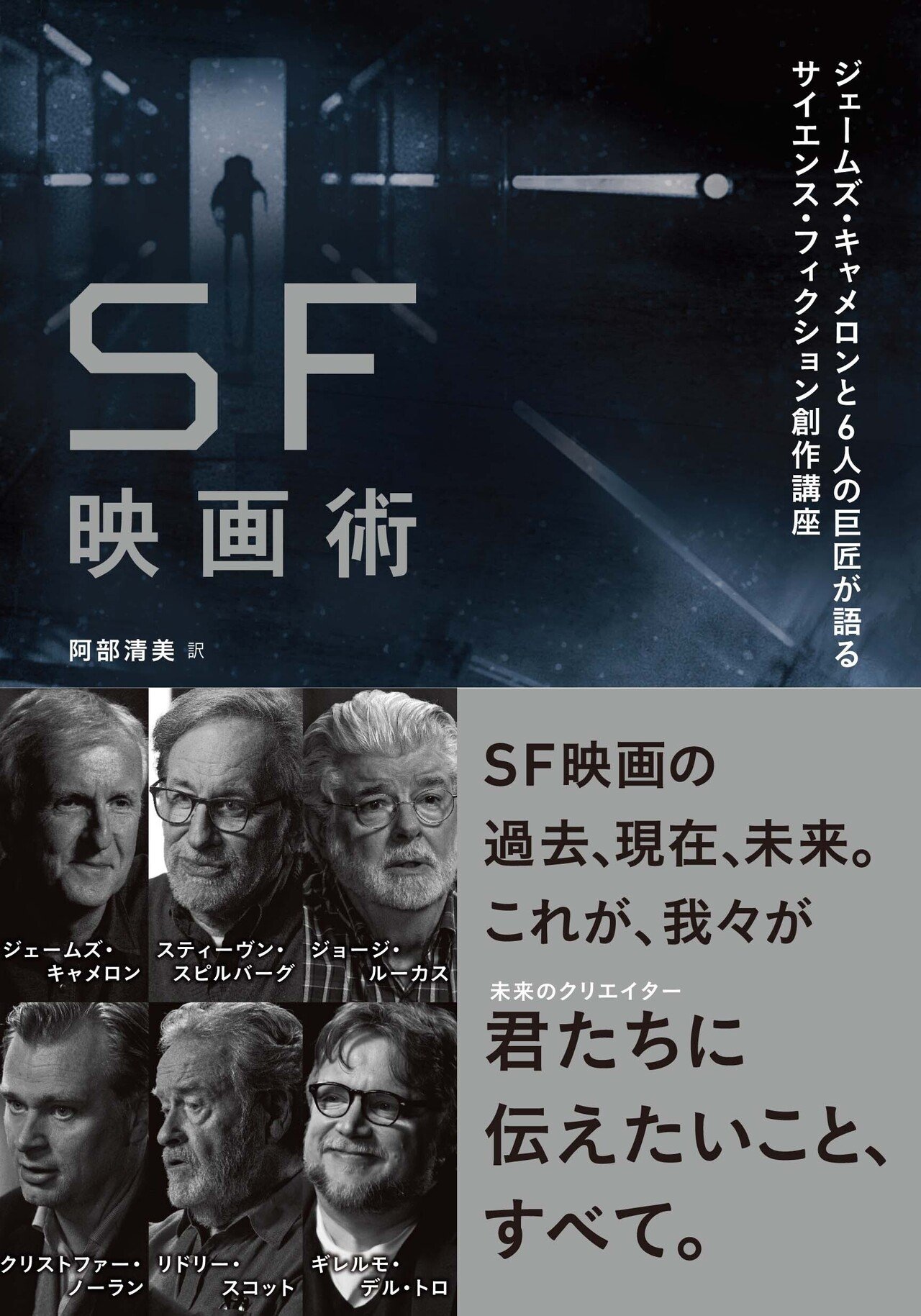
まず、ふんだんに掲載されている美しい図版は素晴らしいし、ちゃんと索引があるのもよい。しかし良くも悪くも、当初想像していたより"教育的"な本だったというのが一番の印象。スコット>デル・トロ>ノーラン>ルーカス>スピルバーグ>キャメロン…綺麗に後ろにいくほどほど面白い──いやむしろ、体感としてより正確な表現を試みるならば、前の内容ほど案外退屈。正直、SF映画を好んで見ている読者にとっては新鮮味のある内容とは言えないはず。何よりいちばん残念なのは、現代的な本とはとても言えない点。ゲストはみんな中年〜高齢者で、2000年以降にデビューした作り手は一人もいない。彼らは確かに偉大な存在なのだろうが…”いま”の作り手に話を聞くべきなんじゃないの?と思えてならない。シェーン・カルースやニール・ブロムガンプ、ダンカン・ジョーンズ、ジョシュ・トランク、スピエリッグ兄弟、アレックス・ガーランド、ライアン・ジョンソン…好き嫌いはさておき、2000年以降に頭角を現した才人はいくらでも浮かんでくる。とはいえ、SF映画の流れを大まかに総観できる…という意味では類書があまりないので意義ある一冊ではある。(Y)
ジェームズ・キャメロンがしんどい一冊。彼がインタビュイーになる1パート目以外、インタビュアーを務めるキャメロンだが、相手がいい話や面白い話をしても上手く掘り下げられない。それどころか、持論を長々と語り出す。ジェームズ・キャメロン様だから、それでも許されるのかもしれないが、それならば“対談”と銘打って欲しい。
キャメロンは人類の行く末を案じたり、現代社会に対して倫理を説いたりする。しかしそもそも、キャメロンの社会認識がアップデート出来ていないのでその説法も虚しい。「宇宙最強の力は母性本能」とか「人工知能は感情を持っていないといけない。愛や憎しみを抱いて初めて、人並みと言えるんだ」という発言は、ジェンダーの視点からSFを読み解く試みからは遥かに後退している。SF好きでない私ですら、もっと巧みに社会を捉え、製作されたSF映画や小説を知っている。キャメロンは必死に未来を説くが、彼が語れるのは残念ながら過去だけだと思う。
また、これはキャメロンがそうなので各章のゲストは単に引っ張られているだけかもしれないが、みんな人の善意や愛や、人間の底力を信じていて驚く。なぜそう信じるのかは、こういうときいつも語られない。全人類共通の大前提ではないだろう。黒沢清『散歩する侵略者』のラストのピュアさに乗れなかった気持ちを思い出した。(M)
・ デヴィッド・リンチ&クリスティン・マッケナ 『夢みる部屋』
フィルムアート社/2020年10月24日発売/704頁/4,500円+税
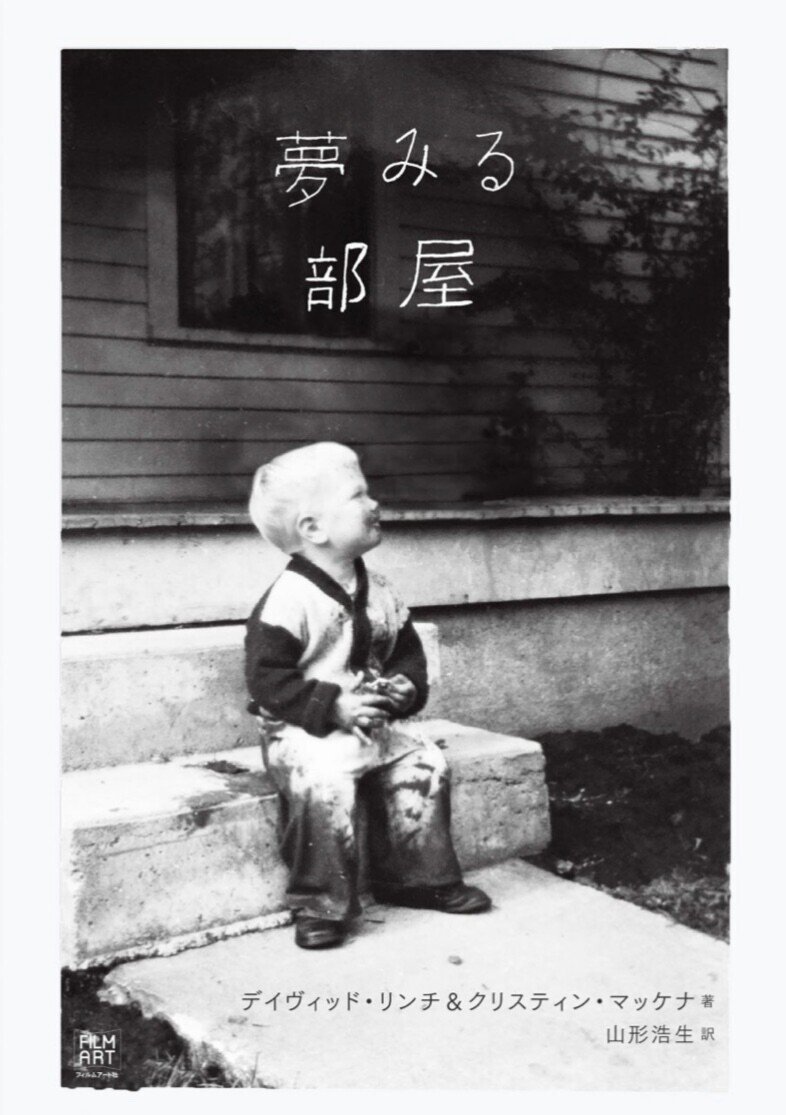
訳者の山形も指摘するように、リンチは評伝パートで語られたエピソードについて言及しない場合も多い。他人からするとそこまで重要ではなく思えるような些細な景色や会話を、鮮明に説明しているのが本著の特徴だ。自分に置き換えても、なぜか克明に覚えている出来事というのはあるし、何を覚え・忘れていくかという個人差は、人格の深い部分に結びついているという自分の“気づき”も含め面白かった。
また他の映画監督もそうである場合が多いが、リンチは“超・職場恋愛男”だと言える。仕事が人と知り合う最大のきっかけであるだけでなく、彼にとって創作活動と日常生活は地続きであることも、パートナー選びに大きく寄与している。評伝パートでは元妻たちがリンチとの出会いから別れまで、かなり赤裸々に語っている一方で、本人は殆ど詳細を語らない。私的なことであるから語る内容選択は当然自由であるが、元妻たちはその点について語らされている構図になってしまうのには切なさもある。リンチがいかにカリスマで、気配りができる人物であるかを知れる一方で、彼が譲らない部分や、なめらかにフェードイン・アウトする女性への関心の冷酷さも行間から読み解けるのがほろ苦い。( M)
マッケナが関係者の聞き取りを基に綴る”評伝”部とリンチ本人による”自伝”部が交互する構成。リンチ本人による映画舞台裏についての証言自体は多くあるものの、同時に『リンチ・オン・リンチ』などのような「自作を語る(=解説する)」側面は稀薄。どの企画がどのように実現した/実現しなかったか…といった”製”作背景は語られるが、”制”作の話はそこまで多くない印象。巻末索引を見れば一目瞭然のように、他作品への言及も控えめ。読みどころはやはり巻末解説で訳者山形浩生が指摘する通り、関係者とリンチ本人の記憶のギャップに尽きる。また、滝本誠の著書を耽読した経験がある者にとって、リンチ情報は知らずのうちに気づけば仕入れているもので、ぼんやりと知っていることも多いが、知らない情報が特に多かったのは幼少期の項。赤裸々に語られるガールフレンド事情が最高で、また映画の印象的な場面が実際の幼少期の経験に依っているという事実が驚き。(Y)
・ 片岡一郎 『活動写真弁史:映画に魂を吹き込む人びと』
共和国/2020年10月31日発売/573頁/6,600円+税
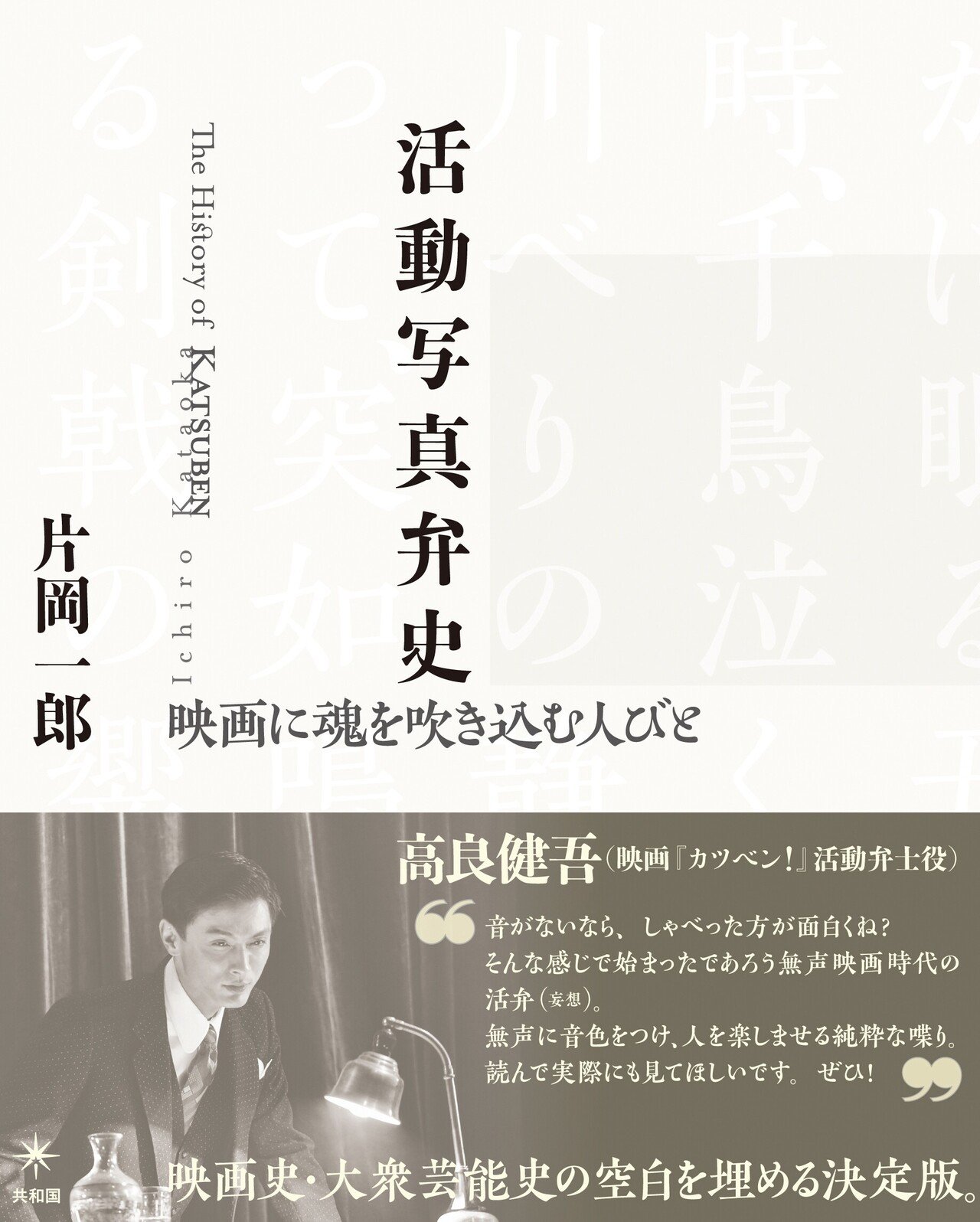
題名通り、無声映画期に活躍した映画説明者=活動写真弁士の起源から終焉までの”活弁史”を追いかける一冊。573頁もの大著だが、うち110頁は附録と索引──どのみち”大部”であることに変わりはないが。本書は弁士の成立過程や定着に多く頁が割かれていて、実際その部分も資料価値として計り知れないものがあるが、”読み物”としては後半部に位置しているトーキーの誕生以後のゆるやかな弁士消滅への過程が特出している。不当解雇に対するストライキや暴動が次々と起こり、仕事を追われて自殺者も出た──悲痛なエピソードがいくつか紹介されるが、その中には黒澤明の実兄・須田貞明の死も含まれる。また、トーキー流入後も共存を計って”音あり映画”に適応した話芸を模索した弁士たちの苦心や世界の弁士文化興亡事情など、興味深い話題には事欠かない。しかし唯一欠点を挙げるならば、あまり馴染みのない人名が多くの場合ルビなしで無数に登場することで、例外的な頻出者を除き、通読時に各々を読み分けることは難しい。せめて初出時には全人名にルビを振って欲しかったところ。(Y)
数々の名作無声映画が日本では説明・活弁付きで上映されていたという事実は、正直これまであまり想像できていなかった。しかし本著でその歩みを辿っていくと、あの映画にも、この映画にも説明がついていたんだなとイメージしやすくなり、とてもわくわくした。
私は落語が好きなので、弁士(と統一して記す)たちの芸への想い、あるいは私生活の放漫さ(皆ではないが)、ツメの甘さもありつつ連帯感が感じられるエピソードの数々に親近感を覚えた。
また、声色弁士の存在から純映画劇運動まで、様々なポリシーと共に映画や芸と向き合った人々の歴史を知ると、改めて映画の捉え方の多様さを感じた。昨年はヴェーラのサイレント映画特集に通い、初めて連日無声映画を見る体験をした。抽象的だが、それまでと違う感覚で映像を感受できた気がして嬉しく、いつもとは違う筋肉を使って映画を見る楽しさを覚えた。弁士の存在を想像すると、また新たな感覚で楽しめる可能性を感じたので、もっと理解を深めていきたい。(M)
・ 岩本憲児 『黒澤明の映画 喧々囂々──同時代批評を読む』
論創社/2021年1月8日発売/368頁/2,000円+税
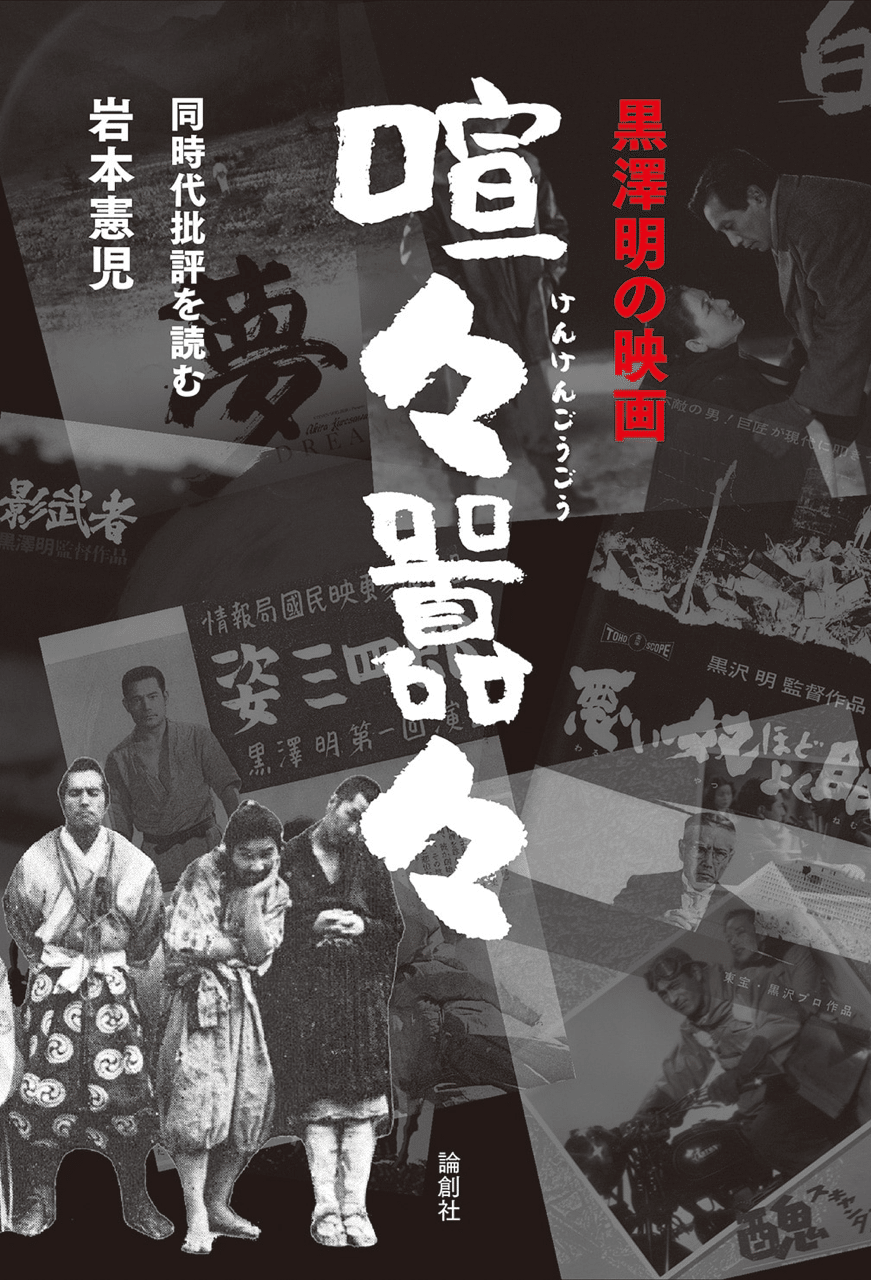
岩本の共著・監修の本はかなり読んでいるが単著をしっかり読むのは恐らく初めて。本著の感想を単刀直入に言えば、物足りないの一言に尽きる。今回のコンセプトは”公開時の映画評”を元に、評価の変遷を辿ることにあると思っていたが、映画評の引用がさほど多くないのが残念。時評の分析も、あくまで岩本の作品解釈の導入として利用される構成の章も多い。もっと言えば、時評の分析自体の雑さが気になった。第3章1960年代以降のパートは、黒澤より若い論者からの賛否が紹介されておりその内容は興味深いが、岩本はとりわけ“世代間の価値観の差”に各論の理由を早急に見出してしまう。
終盤では時評以外の批評も紹介されるが、ドナルド・リチーや佐藤忠男など「そりゃ読んどるよ!」な本を短く引用しているに過ぎない。時評を軸にした本は戦略的に書かれているか、とにかく資料がたくさんあって読み応えがないと厳しい。あるいは、論者特有の視点やジェンダー論的な別角度からの解釈をする場合とか…?(M)
「同時代批評を読む」とあるが、看板に偽りアリと言わねばならない。引用こそ多くされているものの、著者は客観的に「同時代批評を読」んでなどいないからだ。歪曲につぐ歪曲。公開当時黒澤に賛辞を送った者は先見の明の持ち主とされ、酷評した者は節穴…と基本的に位置付けられる。徹頭徹尾結論ありきであり、援用できる評を切り貼りして使いつつ、反対意見は「的を射ていない」と封ずるに終始する。くわえて、そもそも本書の”試み”を早くも序文で撤回する点──「第五章では晩年の三作品、『夢』『八月の狂詩曲』『まあだだよ』について、同時代の言説を追うことをやめて、筆者(岩本)が随想風に自由に論じていく」──には呆れて閉口するほかない。意味も説明もなく勝手に「同時代の言説を追うことをやめ」てんじゃねえよ!控えめに言って”詐欺”である。あまりに身勝手な”随想風”なる第五章の後、第六章では著者の黒澤論が展開されるが、第五章で掌を返され失望を味わった読者が、以降読み続ける意欲を維持していられるかは疑問というほかない。多数の資料を探す手間やコピー代を考えれば、2000円という価格は高くはないが、ならば同時代批評を転載しただけの資料本の方がはるかに喜ばしく、無害有益。(Y)
・スティーブ・ハルフィッシュ 『映像編集の技法 傑作を生み出す編集技師たちの仕事術 』
フィルムアート社/2021年1月21日発売/501頁/3,200円+税
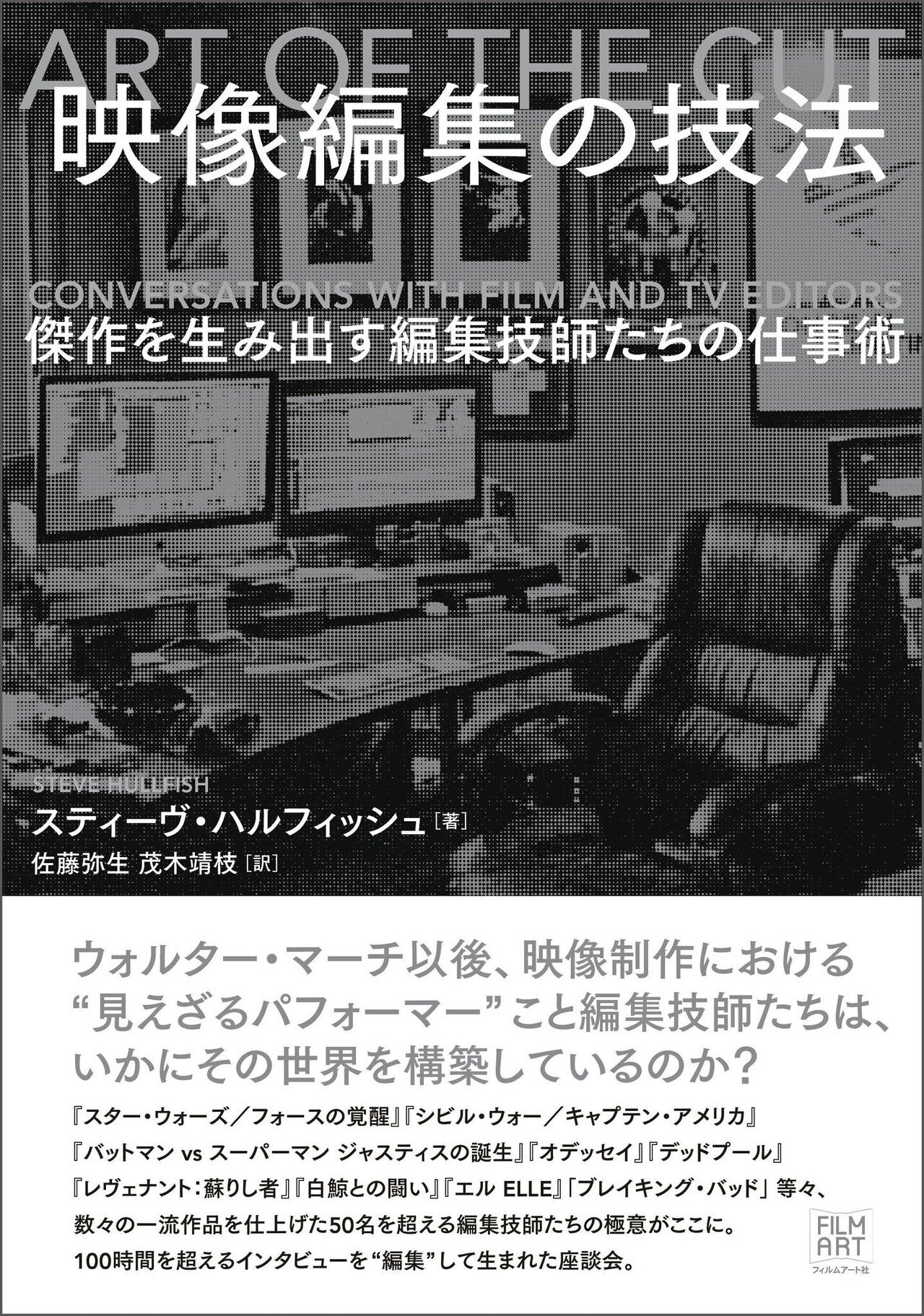
「編集者論を書く難しさ」をしばらく(Y)と話題にしており、その矢先に発売された本。本著は編集者論ではなく、一本の映画ができるまでの編集者の仕事を順番にまとめていく。著名な編集者達に同じ質問をぶつけ、回答の差異を眺めることが出来るのは面白いが、編集作業のまさに編集作業の部分の分量がさほど多いわけではないので、私と(Y)の関心とは残念ながら少しずれた本であった。またどうしても編集作業は”直感"や”感覚”で説明されてしまうが、本人達が感覚的だと思っているものは何か、という点をもっと掘り下げるべきだったと思う。(おそらく著者も編集経験者なので、その”感覚”を共有でき、納得してしまったのだと思うが。)
意外な面白パートとしては、編集者のいわゆる”処世術"的な心づもりが語られること。監督に意見をどうぶつけるか、監督が落ち込まないようにする配慮など…技術を提供するだけでなく、作品の完成まで色々気遣いをしなくてはいけない苦労が綴られる。心労がヤバそうすぎて、気の毒な気持ちになるなどした。(M)
映画における”編集”は、その重要度に反してあまりに批評/言及が追いついていない…という苛立ちが学生時代からあり、手に取った。登場するのが現役=デジタル時代の編集者なので必然的にツール関連の内容も多くなり、飲み込みづらい箇所も少なくないが、編集は”直感”に依るところが大きいというのが共通の意見のよう。第11章では、編集者が他人の編集作をいかに評価するのかが語られるのだが…「いつ編集を開始したのか、何に取り組まなければいけなかったのかなんて、わかりっこない」「オリジナルのデイリーを確認しないままで、その作品がどんな問題に取り組まなければならなかったのか、シーンを編集するのにどれほど困難だったかを知ることは誰にもできません」とのこと。編集について、いかに言語化すればよいか…という疑問は振り出しに戻ったが、読みながら考えが尽きない良い一冊だった。ただ『マスターズ・オブ・ライト』や『ファースト・カット』ではなく、『ディレクティング・ザ・フィルム』形式なのが少しつらい──読んでいる最中は、ひとつの話題について多くの所見が連続して楽しめるが、誰が何を言っていたかが記憶に残りづらいので。(Y)
* * *
〈その他・雑記など〉
今月、上記5冊以外に読んだ本では『人生の奇跡 J・G・バラード自伝』がダントツ。周回遅れで手に入れた、VHSについてのZINE『ばななぼーと』(vol.1~3)も素晴らしかった。現在の映画好きのVHS事情は、限られた市場を一部の事情通たちがひっそり楽しむ…という感じがして、(理解はできるのだが)たびたび発展性のなさに哀しくなってしまうので、勿体ぶることなく店名を明記する『ばななぼーと』は本当に読んでいて気持ちが良かった(潰れた店も多いようだが)。これだけVHS収集家がいながら、どこにもちゃんとした営業中VHS販売店一覧がないの、排他的すぎる…と最近、ネットやら街中でVHSを探している末端人間=ぼくは思う。今月、手に入って嬉しかったのは『ポランスキーのパイレーツ』『真夜中のニューヨーク』『グレゴア』…しかしデッキはない。(Y)
こうの史代『長い道』は浮世離れした雰囲気とリアルな空気感を絶え間なく行き来する一冊で、何度でも楽しく読めることだろう。『平凡倶楽部』が好きな人は気に入る内容なのではないだろうか。
穂村弘『図書館の外は嵐 穂村弘の読書日記』は、短いので少しずつ大切に読んでいるところ。まずタイトルがいい、とても好きだ。“読書日記”は、日記の側面と読書本の紹介・抜粋のバランスが悪いなと思う本もあるが、この本はどちらを期待しても満足できる内容。紹介される本のどこを切り取るか、という選択に日記性(そんな言葉はないですが)を感じるし、どの本も語りすぎず・語られなさすぎず、しっかり内容を想像できるので読みやすいし、実際にその本を手に取りたくなるのがすごい。
ゆざきさかおみ『作りたい女と食べたい女』は安心して読めるグルメ漫画。奥歯まで書き込まれる実食パートの食べっぷりは気持ちいいし、1人暮らし女性のつらさもさらっと描写されていてこれも気持ちがいい。私も結構料理はするし、お弁当もコロナ前は持っていっていたが、その時は中身を見られて話しかけられるのが嫌で警戒していたなぁ…。得意料理を聞かれて「タイ料理です」と答えると、絶妙に本格派っぽいので、その後面倒な詮索をされたり、“家庭的”とか言われないライフハックを身につけたり…。やれやれであるが、料理は楽しい。(M)
では、今回はここまで。
次回は2月28日更新予定です。
ここから先は
¥ 100
本文は全文無料公開ですが、もし「面白いな」「他もあるなら読むよ」と思っていただけた場合は、購入orサポートから投げ銭のつもりでご支援ください。怠け者がなけなしのモチベーションを維持する助けになります。いいねやコメントも大歓迎。反応あった題材を優先して書き進めていくので参考に…何卒
