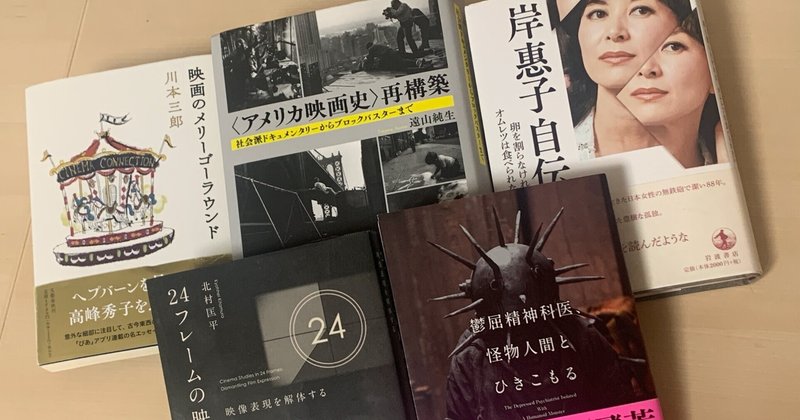
月例映画本読書録:2021年05月
今年、ぼくとパートナーのMは「毎月、その月あるいは前月に刊行された映画本を5冊読む」ことに決めた。
…ということで、毎月5冊最新の映画本を読んで、ぼく(=Y)とパートナーのMで短めな感想を書いて記録していくという企画の2021年5月分=第5回目である。企画開始の経緯などは初回である1回目に書いたので、未読の方はまずそちらをぜひ読んでみて欲しい──以後更新されていくの分も含めて、以下の”マガジン”機能で全てまとめておくつもりなので、こちらのページ↓を見ていただければ、常に”現状”の全ての回がみられるはず。
では、今月の5冊をはじめよう(並びは刊行順/感想は読了順)。
今回は、4月刊行のものor 5月刊行のものから。
・川本三郎『映画のメリーゴーラウンド』
文藝春秋/2021年04月14日発売/320頁/1,800円+税
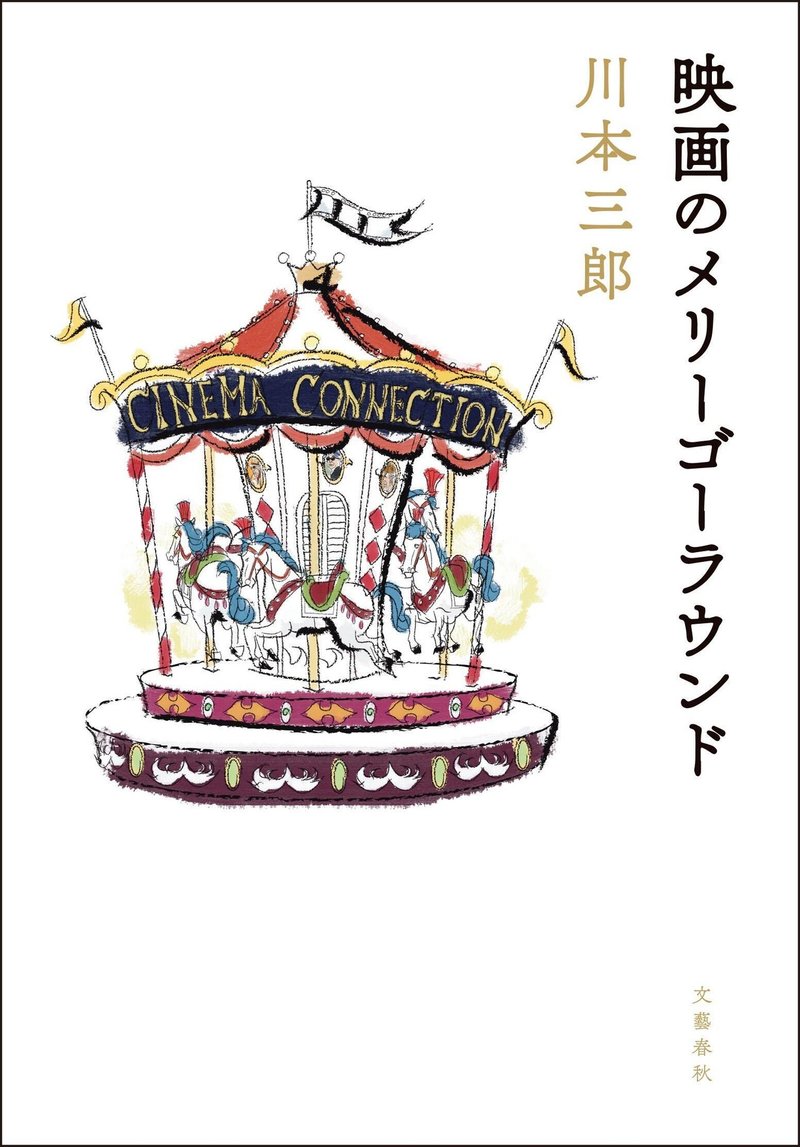
極限まで力の抜けた文章のリレー。読み進めていて、その様は幼少期に買った記憶はないのにもらったのか何かで家にあった、あの階段から落とすとどんどん落ちていくバネのおもちゃのようだと思った。通称・スリンキーと呼ばれているらしい。『トイストーリー』のあの犬の動態部分のバネといえばビンとくる人もいるだろうし、あと、なぜか理科の授業で地震の伝わりかた(縦波・横波)の説明にも用いられるアレだ。
スリンキーの例えが我ながら言い得て妙なので字数を割いてしまったが、要するにリレー形式で「○○が出てくる映画といえばこれもありましたね」と続けていく一冊。力が抜けた文章で、不思議なほどするすると読めるのでその読みごごちは面白いが、特段新しい発見がある本ではない。数多の映画をみてきた川本三郎なら面白いリレーになるだろう…という期待は禁物。
読んでいると、確かに自分一人で「あんな映画もあったな」と考えを巡らせてみても、その考えが小さな円になっていくというか、先細りする感じがあり、この本も正直同じ映画や同じシーンの話が何度も出てくる。やっぱり、外から刺激を適度に受けながら考え事をするのがいいのかもなどと、あまり本には関係ない結論に行き着いた。(M)
あとがきで著者自身が「映画の尻取り遊びの本である」と言明している通り、映画から映画へ、共通項を中継地点としながら横滑りしていく一冊。今月の中では”軽め”枠として選んだが、侮るなかれ、これはアタリ。”野心”を微塵も感じさせない肩の力の抜けきった文章で、映画が数珠つなぎにされていく。しかし、虚をつく斬新な視点や膝を打つような指摘は存在しない。あまりに軽妙がゆえに読んでいて意識させないが、ほとんどの記述がある種の”説明”である──この映画の監督は…この俳優は…脚本家は…原作は…この場面の音楽は…物語の舞台は…。豊かな”説明”が映画と映画を結びつける。読んでいるとその説明の鮮明さに、よくぞここまで覚えていて連関を拾い上げてくるものだ…と自分自身の記憶力の乏しさに情けなくもなるのだが、むしろ感動的なのは連想の見事な”縦横無尽さ”などではなく、偏りである。本書では、著者の映画的記憶を駆使すればいくらでもほかに選択肢=繋げ先があるであろう状況で特定の作品が何度も繰り返し言及される。”自由闊達”な想起の対極にある、その不自由さ/限界性にこそ惹かれる──どうしたって、好きな映画ばかりを思い出す。(Y)
・遠山純生『〈アメリカ映画史〉再構築』
作品社/2021年04月30日発売/724頁/6,300円+税
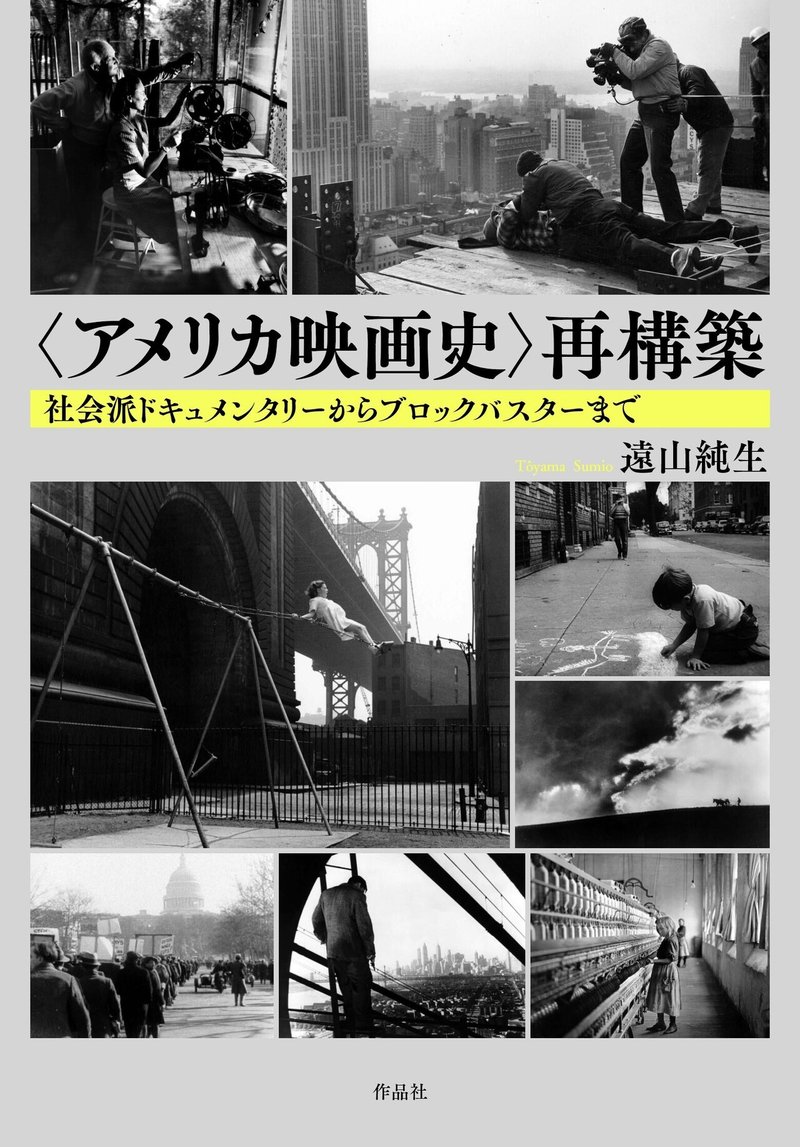
正統派な映画本の面構えだが、内容は異質と言えるかもしれない。“再評価”や“語り直し”というのは、常に批評の中で行われていることだが、この本はまさに“再構築”を行っている。本著を読み終えると、“再構築”などというのは易々と掲げられる目標ではなく、その言葉自体の重みまでも読む前と変えてしまうような労作だ。
この本の凄まじさは、それまで自分の中にあったた点と点が、確かに線になっていくところ。「この点とこの点がつながるんだ」という驚きと「つなげる根拠」の明瞭さに驚く。といっても、メジャーではない作品ばかりを突飛に繋げるのではなく、従来の映画史でも語られる監督(例えばエイゼンシュテインやヴェルトフ)から、日本ではあまり知られていない作品を丁寧に渡り歩いている。
個人的に嬉しかったポイントとしては、アニエス・ヴァルダの『ライオンズ・ラブ』の分析があること。後半に登場するが、それまでのアメリカ映画の著書中の文脈から考えると、また新たな気持ちで作品を捉えることができ、とても楽しかった。(M)
我々が知っている(と思い込んでいる)”映画史”は、一部で「カノン」と呼ばれる偏狭きわまりない一側面に過ぎない。しかし、いうまでもなく実際には幾重もの面/層がある。これまで本格的に語られずに来たのは、集団的惰性ゆえというほかない。本書は誰もが読み始めるや否や、すぐさま”別格”であることを感じ取るだろう。その手間、情報量、密度が捲るたびヒシヒシと伝わる──小手先・小細工はナシ、”愚直”といっていいほど徹底した調査に基づく記述の積み上げ。圧巻というほかない。撮影の映画史にして、編集の映画史にして、撮影機材の進歩史にして、注目されずにきた人的交流史…まさに”再構築”。認識が塗り変わる。映画史記述のみならず、画面を仔細に解析する作品分析も素晴らしい。万難を排して、他の有象無象を切り捨てて、いの一番に買い求めるべき必携の一冊。一読すれば、必ずや言及作品の数々を見てみたく/見直してみたくなるはず──ぼくは積んでいたエンゲル&オーキンのBDをやっと見た…ほんとうに素晴らしかった。これ以上の理想的な”効用”があるだろうか。唯一残念なのは人名索引がないことだが、もはや贅沢すぎる望みだろう。必要ならば、何度となく読み返しながら自分で作ってしまえばいい。暫定ベスト。抽象的な賛美ばかりになるのがもどかしいが、どうか許してほしい。(Y)
・岸惠子『岸惠子自伝』
岩波書店/2021年04月29日発売/350頁/2,200円+税
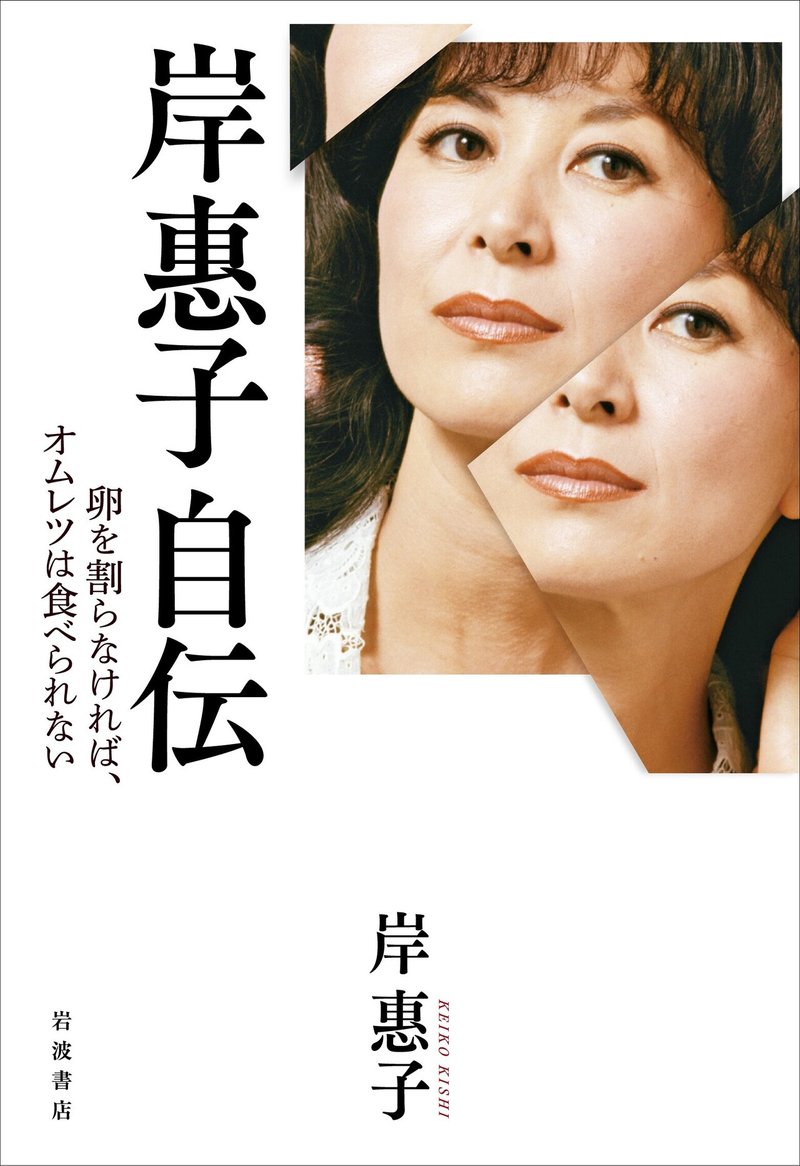
私は俳優のプライベート情報やゴシップに疎いので、今回も岸惠子が国際結婚していたことや、そのニュースの日本での受容に関しては初めて知った。
幼少期から現在までの本人の書きっぷりからは、パーソナリティがずっと一貫している・あるいは本人が一貫していると思っているのが印象的。愛嬌と野心があり、決めたことを力強く達成して行く様は、昭和を代表する女優らしさを感じる。また、久我美子らと会社を設立するなど、当時の俳優の置かれる立場から脱し、主体的に作品を選ぼうとする試みは重要な動きだっただろう。本人から語られるその歴史は貴重な証言だと思う。
ただ、後半になり本人がキャリアも年齢も重ねたパートになって行くと、首を傾げるような箇所が出てくる。フランス移住の経験を経て、各国へ赴きジャーナリストとしても活動した岸。ただ、各国や情勢への認識が安直な断定過ぎるというか、ちょっと偏見っぽいなぁと思う記述がちらほらと。無鉄砲な性格が魅力なのだと理解しつつも、地位のある大女優に振り回される人が当然いるだろうと、あまりその点は気に留めていない書きぶりにかえって想像が膨らんでしまった。(M)
思えば、ぼくは岸惠子のことを何も知らなかった。太平洋戦争末期、母親との約束「はぐれたら山手小学校の講堂」を厳守するために空襲の最中に防空壕を飛び出した──自分だけが生き残り、防空壕の人々は土砂崩れと爆風でほとんどが死んだという横浜空襲の体験。数学が苦手だったが、呼び出された数学教師の家で「人生は短いんだ。好きなことをやれ」と言われた高校時代。同級生に誘われて見た『美女と野獣』に啓示を受け、映画に魅入られると…その”同級生”の叔父は松竹大船撮影所所長の親友だった。親に内緒で撮影所に見学に行き、吉村公三郎に見込まれて(「女優になりたいと思いませんか」)ケーキを奢られ、そのまま研究生となって頭角を現し、進学を断念して女優業に打ち込むことになる。学業を諦めきれない岸が現場で教科書を読んでいると、高峰秀子に怒られる…「撮影所で読んでいいのは脚本だけよ」。なんて劇的な半生だろう。信じがたいほどドラマティックだ。これは面白い…ただし、前半までは。後半に差し掛かり、名声が確固たるものになってからの記述は、どうしても”誇るべき功績”の域を出ない。もちろんひとつひとつの”功績”は、誇るべきものなのだから、誇らしげに記述するのは問題ないが、それが面白いかというと…。加えて、ジャーナリズムに足を踏み入れてからの描写には違和感を覚える人も少なくないだろう。「イランやアフリカのことを書くなら、ちゃんとした知識を持たなきゃいかんよ。知識だよ、知識。岸クン」と言われた岸惠子は毒づく…「知識なんぞがあるならば、行かない、書かない、興味ない!」。いうまでもなく、このマンスプ野郎(政府関係者らしい)は最低の極みである。しかしこの岸の主張もまた、諸手を挙げて賛同してよいものにはどうしても思えない。(Y)
・北村匡平『24フレームの映画学』
晃洋書房/2021年05月17日発売/288頁/2,500円+税
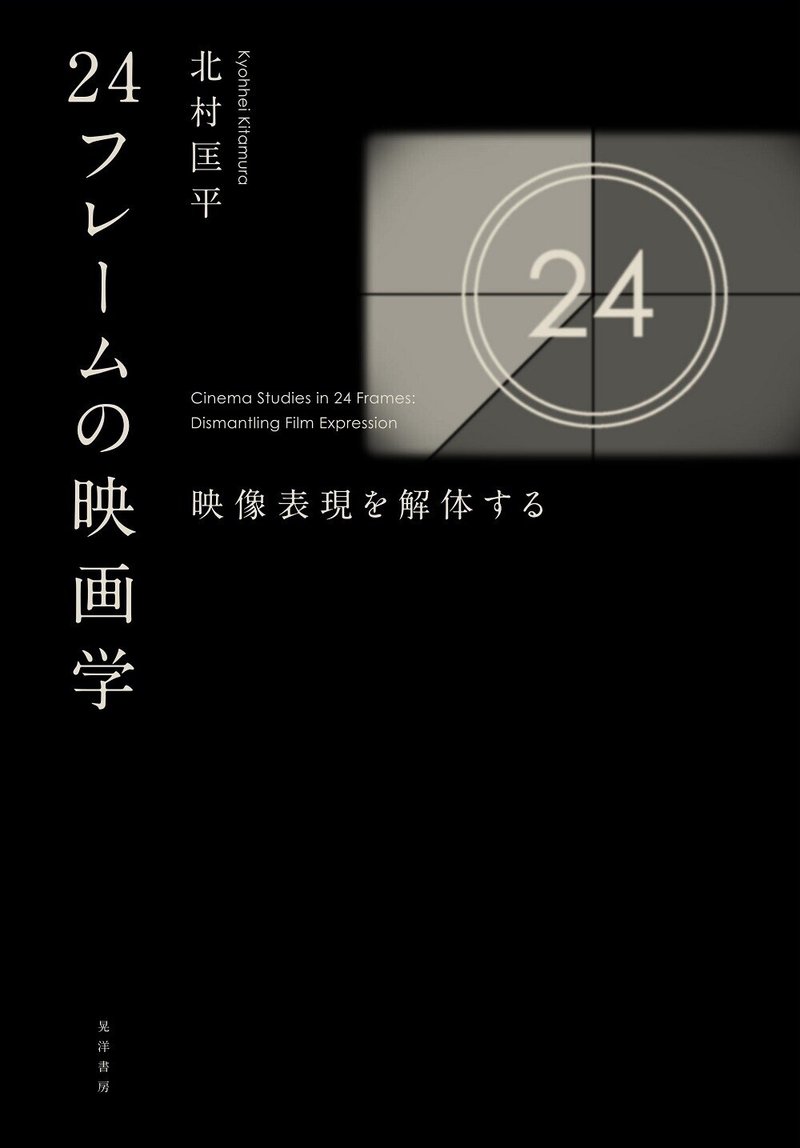
とにかく噴飯モノ。ここまで酷い映画本にはなかなかお目にかかれない。表紙を見れば「映像表現を解体する」「映画を計測する」などという魅力的な惹句が並ぶが、期待してはいけない。失望が大きくなるだけだ。「いつでも繰り返し観ることが可能になった」現代だからこそ「「記録と高解像度の解析力」に基づく新たな批評実践」即ち「映画の解剖学」が必要なのだ…と著者は序説で嘯くが、それは口だけのマニュフェストでしかない。DVDなどでの複数回鑑賞を前提とした方法論ながら、恥ずかしげもなく”24フレーム”などと掲げた題名からも、その安易さが伺えよう──信じ難いことに、序説における天晴れな大演説のあと本書からフレームレートについての関心を感じ取ることはできない。”計測”は単にASLのことを指していたらしい。様々な理論の引用で”説得力”の風味をまぶしながら、結局展開されるのは、徹頭徹尾退屈極まりないショット(ないしフレーム)分析に過ぎない。いや、ショット分析も有用な手段ではあるので馬鹿にしてはいけないが、ならば本書のアプローチは”ショット起こし”とでもいうべきものだ。ショット/フレームの連なりが(きっと一時停止を駆使しながら)まるで箇条書きのように文字起こしされ、そしてそこに浅薄な”意味づけ”が擦りつけられていく。これこそ著者が冒頭で批判する「強引な解釈や大雑把な分析」の何よりの見本だろう。書き起こしさえすれば何でも高解像度になるというわけがない。あまりに節度を欠いた今年のワースト。”もっともらしさ”に包まれた唾棄すべき一冊。(Y)
序説で北村は「私自身が映画の<教科書>は勉強にはなるが<説明書>を読んでいるみたいで引き込まれることがあまりなく、映画の<教科書>も体系的で堅苦しい感じがしてならないからだ」と記している。その気持ちに共感できる部分もあるものの、では本著はどのような内容かというと、堅苦しい感じはない一方で、引き込まれることもない。例えるならば、授業で配られる教科書のコピー。それも、教授が本を出すのが面倒だったのか見つからなかったのかわからないけれど、何年まえかに取ったコピーをまたコピーした読みづらいやつ。
例えば第1章は映画の黎明期から始まるが、そもそもこの内容であればなくてもいいように思うし、入れるのであれば工夫が必要だろう。リュミエール兄弟に関して突飛な意見を書けという意味ではなくて、“教科書的”な説明部分であっても、その人なりに史実が咀嚼されており、その考えがわかりやすい本など良い本はたくさんある。そういう意識があまり感じられないので、それであればわざわざ章立てをする必要はやはりないように思えてならない。(M)
・春日武彦『鬱屈精神科医、怪物人間とひきこもる』
キネマ旬報社/2021年05月21日発売/307頁/1,800円
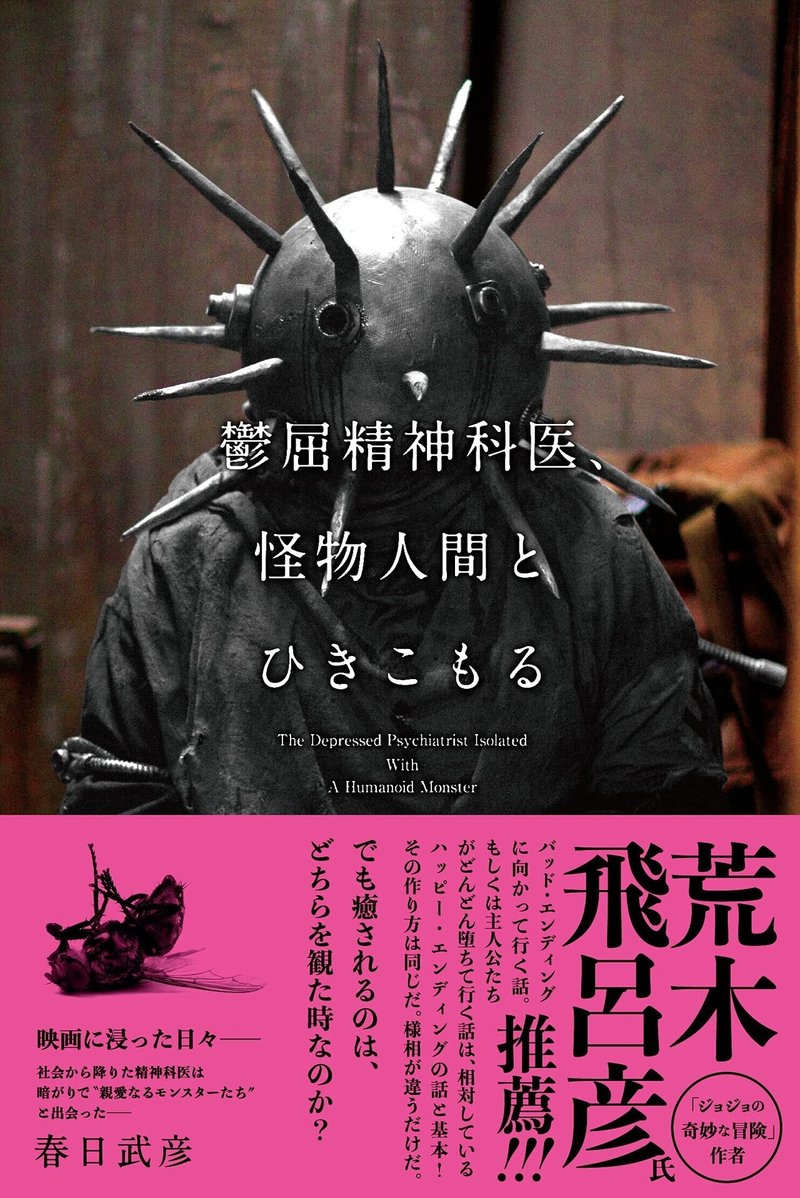
本書は著者が突如仕事の辞めて引き籠った数ヶ月間に見た”バッドエンドの映画”をめぐるエッセイ本。『蠅男の恐怖』に始まり、『レッドライン 7000』、『GERRY ジェリー』、『皆殺しの天使』、『メランコリア』、『ラルジャン』、『泳ぐひと』まで…これらは多くの言及作品の中から好みの作品を拾い挙げてみただけだが、この選定を眺めるとどうしたって期待は高まるもの。しかし、”映画本”としてはあまり期待し過ぎない方が良いかもしれない。むしろ”映画本らしさ”との距離にこそ魅力があるといっていい。著者は、画面に描かれていない人物の心中などに「なぜ」と思いを馳せ、鑑賞中の自らの感情の推移を丁寧に描写していく。自分語りも厭わない──「蠅男の魅力に気づかぬまま論理的矛盾ばかりをあげつらい嘲笑する連中のことを考えると、わたしの著作を決して評価しようとしない連中と彼らとが重なって見えてしまう」「妻は病院の外科病棟で働いているのにオレはこんなものをだらしない格好で観ているといった後ろめたさ(中略)こんなものを観ていては、妻に本当に申し訳なくなる」。ブニュエル『ブルジョアジーの秘かな愉しみ』については「つまらなかったのひと言に尽きる。全体にバランスが悪くて、この監督は技術的に未熟というか問題がある。すなわちアート以前の問題だと思った記憶がある」と一蹴。このフィーリング全開な語り口が潔い…どこか新鮮である。ただ、不可解なのは著者紹介がどこにもないこと。奥付にも、袖にもない。いや、たしかにこの本を手に取る人の大半は春日武彦を既に知っている人なのかもしれないけどさ……さすがにどうよ。(Y)
精神科医の著者が、仕事を離れていた数ヶ月に触れた映画や本、あるいはそこから連想される記憶について書かれた一冊。“怪物映画”とタイトルにあるが、それに該当しない作品の紹介も多く、登場する作品については著者が心惹かれた“歪さ”のある作品、と捉えるのがわかりやすいと思う。
作品の分析は著者の幼少期の体験や、ひきこもり期間の思考に大きく影響されていると言えるエッセイという感じ。数ヶ月の間、著者は引きこもって映画をただみたり、暗い部屋で電子タバコを吸うことに背徳感を覚えている様子で、様々なトリガーから「やはり自分は鬱屈しているな」と思いを巡らせたりする。その気持ちを否定したいわけでは全くないのだけれど、私はそういう気持ちに対して開き直っているタイプなので、どんどん「映画見ても、寝ても、別にいいんじゃないかなぁ。したいならええやん」という気持ちが強くなっていった。余計なお世話だと思うので、著者への投げかけではなくあくまで私の気持ちの話だが。
私も気持ちが落ちている時に歪だったり、バットエンドだったりする映画を見ることがあるが著者とは全く異なる理由から見ており、そう思う人もいるのかぁなるほどなぁとなった。(M)
* * *
〈その他・雑記など〉
季節の変わり目ということもあり、体調を崩したので読書はあまり捗らず。
発売は3月だが、オカヤイヅミの『白木蓮はきれいに散らない』を購入。中年の女性たちをこのように描く漫画を、少なくとも私はあまり読んだことがない。学生時代の友人がとあるきっかけから集い、現在の生活を見つめ直す…と書くと小説なんかではよくありそうなあらすじではあるが、それを魅力的に描き切るのがオカヤイヅミの魅力だと。同日発売だった『いいとしを』はWEBで読んでいたので購入していないが、こちらもとても面白いです!
そしてこれは4月に買っていて紹介が漏れてしまった一冊。かなり気に入っているので紹介。『ビリヤニ とびきり美味しいスパイスご飯を作る!』(監修:水野 仁輔 )である。私もYもビリヤニが好きなのだが、作ろうと思ったことはなかった。しかし本著はかなり丁寧に説明がされているのでチャレンジしやすいし、バリエーションのあるレシピが紹介されているので作り続ける楽しさに満ちている。個人的にビリヤニは食欲がないときでもガツガツ食べられるので、これから夏バテなどもしやすい時期にはおすすめの一冊。(M)
もはや遅滞が常態になりつつある。情けないかぎり。今月の遅れの原因もまた、予期せぬダウン=寝落ちによって土壇場で読書計画が狂ったため。その一方で、眠れない日はとことん眠れないわけだが。
今月は、ロマンポルノ関連書籍を集中的に漁ったり、文学フリマで購入した同人誌諸々──『霊障』(いずれ感想を書きたい)、『機関精神史』(學魔インタビューが最高)、『精神病院入院日記』、『本屋攻略読本』、『六出銀字最後の自戦記』などを読んだりしていた。ほかに印象的だったのは、大谷能生『植草甚一の勉強』、美内すずえ『ガラスの仮面』(途中)、眉月じゅん『九龍ジェネリックロマンス』あたり。漫画が多いのは、毎週火曜に一冊55円で借りることができる店が帰路にあるため。来月こそは遅れないようにしたい…いまは団鬼六『真剣師小池重明』とピンチョンを併読中。(Y)
では、今回はここまで。
次回は6月30日更新予定です。
ここから先は
¥ 100
本文は全文無料公開ですが、もし「面白いな」「他もあるなら読むよ」と思っていただけた場合は、購入orサポートから投げ銭のつもりでご支援ください。怠け者がなけなしのモチベーションを維持する助けになります。いいねやコメントも大歓迎。反応あった題材を優先して書き進めていくので参考に…何卒
