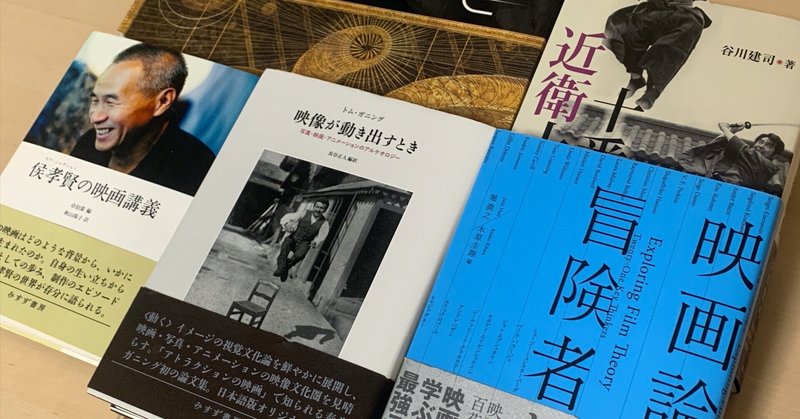
月例映画本読書録:2021年11月
2021年、ぼくとパートナーのM(山本麻)は「毎月、その月あるいは前月に刊行された映画本を5冊読む」ことに決めた。……ということで、毎月5冊最新の映画本を読んで、ぼく(=Y)とパートナーのMで短めな感想を書いて記録していくという企画の2021年11月分=第11回目である。
しかし、現在は2022年7月末だ。
情けないことこのうえない。昨年後半から、次第に滞りがちになったこの企画は、途絶したまま半年以上が経過してしまったのである。頸椎ヘルニアになったとか、かなり長いあいだ体調を崩していたとか言い訳は山ほどあるし、もうここまで後ろ倒しになってしまったのだから、潔く“現時点”の分から再び仕切り直そうかとも考えたのだが、いちおう毎月ちゃんと読んではいたので投げ出すのも後味が悪い。なので、周回遅れも甚だしいが、ひとまず無理のないペースで遅延分を更新していくことにした。「毎月ちゃんと読んではいた」と言いながらも、感想作業はほとんど未着手だったので、今さら書こうにも内容を覚えておらず、結果的にすべて再読を余儀なくされている。要は、そう易々と追いつくことはできそうにないわけだが、とはいえ、ひとつひとつ進めていけばいつかは辿り着くだろう。
企画開始の経緯などは初回である1回目に書いたので、未読の方はまずそちらをぜひ読んでみて欲しい。また、以後更新されていくの分も含めて、以下の”マガジン”機能で全てまとめておくつもりなので、こちらのページ↓を見ていただければ、常に”現状”の全ての回がみられるはず。
では、5冊をはじめよう(並びは刊行順/感想は読了順)。
今回は、2021年10月刊行のものor 11月刊行のものから。
・タニア・ラポイント『ドゥニ・ヴィルヌーヴの世界 アート・アンド・ソウル・オブ・DUNE/デューン 砂の惑星』
DU BOOKS/2021年10月22日発売/239頁/6,000円+税
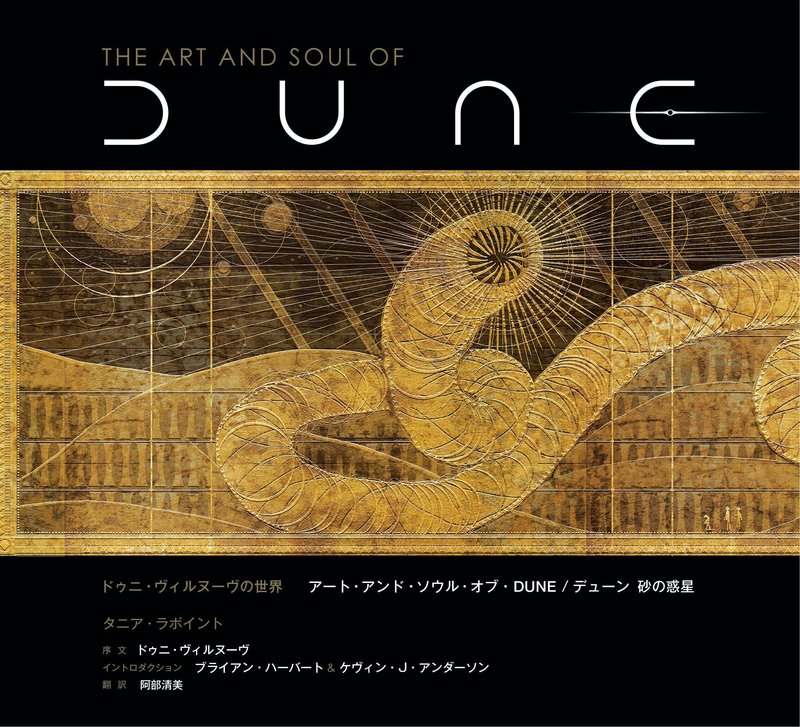
ドゥニ・ヴィルヌーヴ『DUNE』の主にアートワークを解説する本。画像を贅沢に使い、丁寧にアートワークを見せていく。映画を見終わった後にはやはり砂漠の広大さ、残酷さが強く印象に残っていたが、改めて見るとカラダンの静かで豊かな自然の美しさも引けを取らないインパクトだったのだな、と気付かされる。アラキスに移った後の彼らの心の中にもこの景色への哀愁があり、そして支えてくれる風景だっただろうと思う。またこだわりの部分としても語られるが、質感・経年を読み取れるアートワークだったことがよくわかる。
ただ、私は正直映画『DUNE』はイマイチだったと考えている立場なので、むしろこれだけの時間と知恵が集結したアートワークが、作品の仕上がりにおいて生かされていない、魅力的に写りきっていない部分があったということが気になった。特に、建築の造形に関してはゆっくりとページをめくり、目を配っていくと、経年を感じさせつつも壮大で美しいなと見入る部分が多くあった。そして映画の終盤、そこが戦場となり、一瞬で燃えて跡形もなくなってしまうことを思うと戦争のむごさが迫ってくるし、制作過程においてもかなりの時間をかけ用意した場所をそうして消し去ってしまうことができる作品の規模感にも感心するのだが、実際に映画を観た際にそこまでの迫力や説得力があったかと思うと、あんまりなにも思わなかったなー、という無味な感想が今度は迫ってきてしまった。また、これは公開時のガイド本的な出版物だから仕方ないのかもしれないが、ドゥニ・ヴィルヌーヴがまるで全知全能の監督かのように褒める内容ばかりが続くので、監督に関する記述やキャストのエピソードはあまり読み応えがないのも残念だった。(M)
このたび公開されたヴィルヌーヴ版『DUNE 砂の惑星』のメイキング本。この手の書物がおそろしいのは、もし映画が気に入ったのであればよいのだが、肝心の映画作品が受け入れられるものではなかった場合、突如として苦痛となる点にある。見終えてから購入の決断をすればよいのかもしれないが、限定部数だというし、そう思い通りにはいかないものだ。本書は“公式”資料本ゆえ、基本的には賛美一色。とにかく猫も杓子もヴィルヌーヴを褒めまくる──彼なら任せられる、彼と仕事がしたい、彼の発想は素晴らしい!という具合に。ひとりの“天才”に惹かれてスタッフやキャストが集結していくさまは、まるで『ホドロフスキーのDUNE』における“魂の戦士”のようだが、残酷なことに私はもうこの映画がどのような仕上がりになったかを知っているのだ。多くの関係者インタビューが収録されていて、一本の大作映画がいかに多くの工程を経て完成へ至るのかという、具体的生成過程について自分がいかに無知であるかを思い知らされ、その点では楽しめるのだが、魅力的な証言と見たばかりの落胆記憶が食い違い、虚脱の感は否めない。わざわざ試してみるまでもなく、作品に満足した人向けの本。(Y)
・堀潤之、木原圭翔編『映画論の冒険者たち』
東京大学出版会/2021年11月1日発売/312頁/3,800円+税
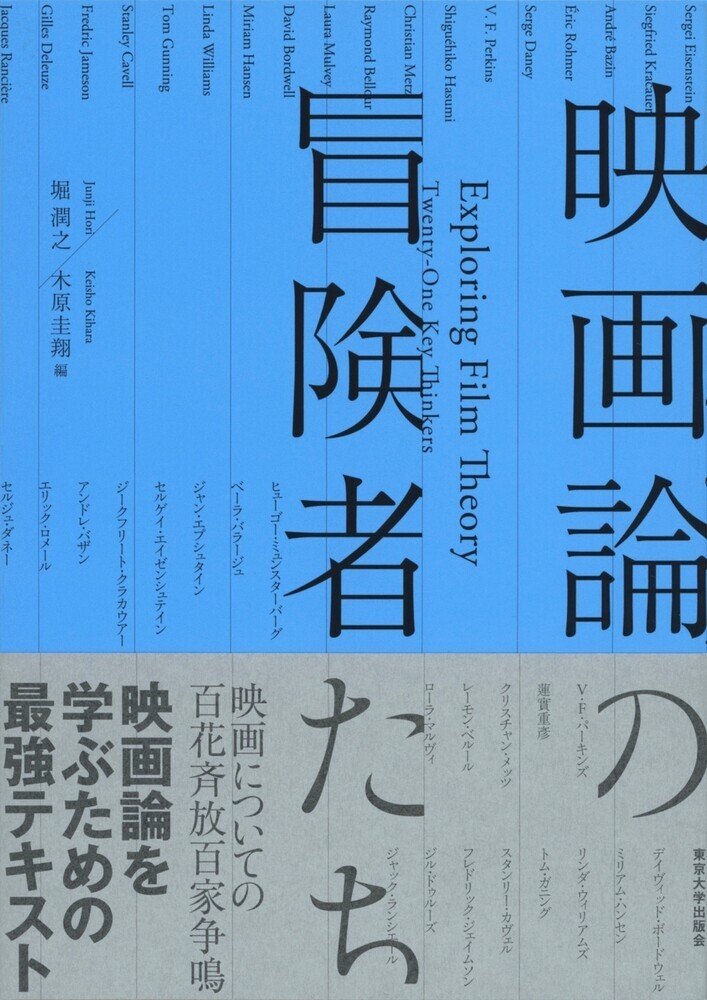
サイレント期から現代まで、様々な角度から映画を論じてきた21人を取り上げた一冊。実際に本著で紹介される論者の書物を手に取り、苦戦した経験もある身としては、気軽に手に取れる入門書の誕生は実に喜ばしい。(背伸びして手に取った本で苦戦する経験は大切ではあるが、それはまたそれとして)
またそれぞれの人物に異なる研究者が配され、編纂されている点も本著の特徴であろう。単なる概説ではなく、各々の解釈や自身の研究にまつわる関心も文章から読み取れるのが楽しい。そもそも、21人の選出自体も興味深く、エリック・ロメールがそのなかに入っていることに単純に嬉しくなったり。
個人的には以前読んだけれど理解しきれなかった/忘れてしまった内容の復習に極めて役立った。文献案内もそれぞれの人物ごとについており、この本をきっかけにさらに関心を深めていくことができる。編者の木原が記すように、学生の助けになる本だと思うが、普段批評に関心のある映画好きの方にもぜひおすすめしたい一冊。(M)
「映画理論家」21名の入門紹介本。“識者”ほど選定に文句もあろうが、それはそれでよいし、この書物もまたこれでよい。類書が溢れている状況ならばまだしも、たとえ“既知”の理論家が並んでいるのだとしても、行き届いた紹介は常に必要だ。じっさい、名前を知ってはいても、または著書を拾い読みしたことはあっても、あるいは通読したことがあっても、結局のところ、胸を張って「知っている」と言えるほど咀嚼できていないのであれば、入門に終わりはない。そもそも自らを「知っている」側と位置づけている者であっても、取り上げられている理論家すべてに精通している人は稀にちがいない。この本は、私のような門前の小僧へ向けた入門書でありながら、同時に「知ってるつもり」の自惚れをへし折り猛省を促す機能も果たすだろう。ほんらい入門書や紹介文の類いは、玉石混淆溢れているくらいでちょうどいい。だから、いつか第二弾、第三弾が出たらいい。もしくは、本書に啓発された者たちがいずれ別の仕方で編めばいい。そう思っている。特に愉しんで読んだものを三つあげるなら、須藤健太郎によるセルジュ・ダネー、長谷正人による蓮實重彦、木原圭翔によるスタンリー・カヴェル。どれも、読む前から好ましく思っていた対象であるから、そういった意味ではまだまだ読み直しの必要を感じる。(Y)
・谷川建司『近衛十四郎十番勝負』
雄山閣/2021年11月16日発売/488頁/3,000円+税
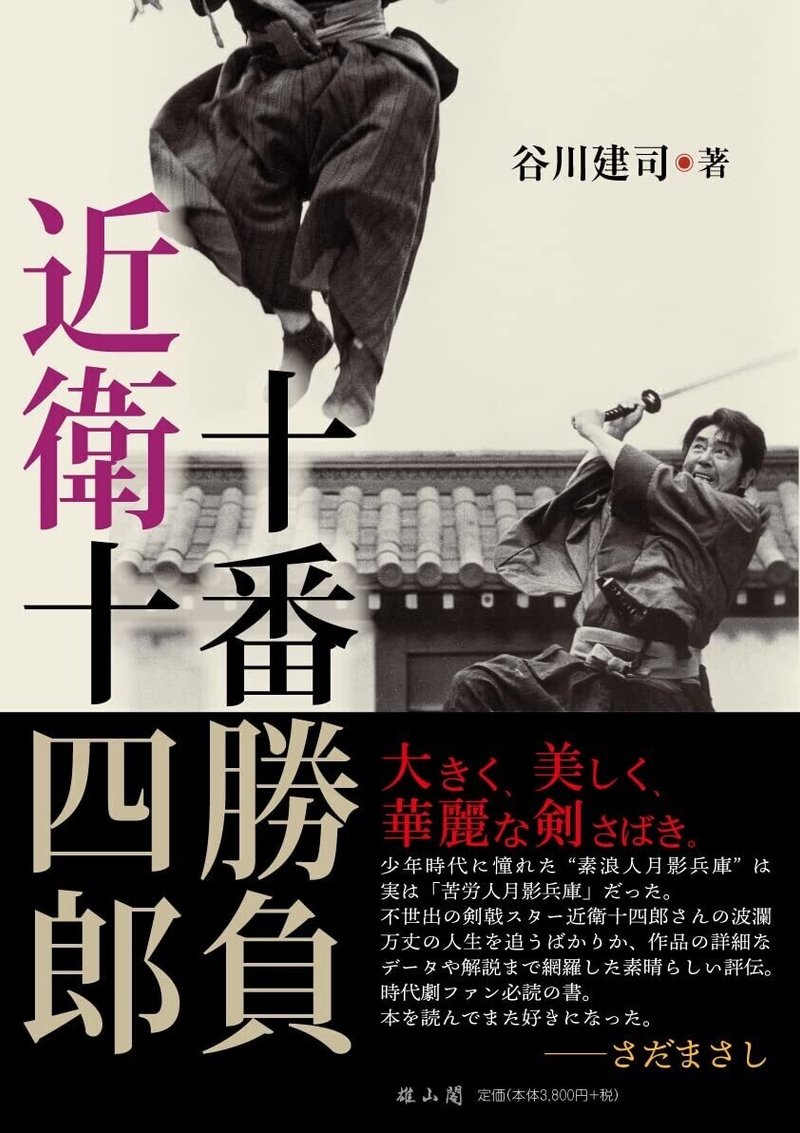
近衛十四郎の評伝と出演作の解説が載っている一冊。もちろん近衛十四郎の存在は知っており映画でみる機会もあったが、私生活やその活動遍歴に関する深い知識はなかったので、ここまで波瀾万丈な人生を送った人だということにまず驚いた。近衛が活躍していた世代の人であれば懐かしく振り返ることができ、知らない人はきっと驚きながら読み進められることだろう。
戦前戦後の混乱、映画の隆盛に翻弄されながらも、自らの芸を武器に道を切り開いていく。時代劇を見ていると、剣術と使い手が相関している場合は多いが、現実にもそんな人がいるのか、と思わされる事実の凄みがある。また作品解説も丁寧に書かれており、誤って流布している情報を訂正したり、そもそもネット上に情報が少ない出演作をフォローしているのでよいガイドにもなる。
ただ評伝は難しいな、と思うのがどこまでが事実を豊かに描写する範疇として許容でき、どこからが想像や創作になるのかということ。本著も流布してしまった誤った定説を丁寧に否定し、調査の蓄積を感じさせる記述がある一方で、やはりそのとき近衛がどう感じたかという部分に関しては著者の想像の側面があるのではないか、と思う。例えば、2人の息子が俳優になったことについて近衛が「親の跡をついでくれて、満足してますわ」といったエピソードについて紹介されている部分では、彼の喜びを他の俳優と比較して想像しており違和感を覚えた。片岡千恵蔵の2人の息子が子役として活躍しつつも大人の俳優にならなかったり、市川右太衛門の息子・北大道は活躍を続けているが1人息子であって、2人の息子が活躍を続けたことのすごさ、そして近衛が誇らしかったであろうと語るが、この部分は不要に思えた。近衛がそのように思うであろう資料があったのかも知れないが、本人が語った以上のことは推測でしかなく、彼の喜びについては読者の解釈に任せるので充分だったのではないだろうか。(M)
「近衛十四郎の全体像をきちんと把握したい」と考えた著者が、まともな評伝も出演作データをまとめたものすらないという現状のなか、書き上げたのだという一冊。厚さ480頁、価格4,000円超というボリュームだが、喜ぶべきか悲しむべきか、(少なくとも個人的には)目玉の評伝部は全体の三分の一程度。その後、30頁ほどの品川隆二/目黒祐樹インタビューを経て、残りの300頁弱はすべて作品解説(第二部「主要作品総覧」)に費やされる。ここが評価の分かれ目だろう。この作品解説部がまた特異な仕様で、計55作品を、著者の好みで5種類のベストテン(「Best of Best」「主演作品」「悪の魅力」「歴史上の偉人役を演じた作品」)+番外編に振り分ける形式で構成しており、“読みもの”としての面白味を付加する工夫なのは判るのだが、いかんせんこれが資料としての利便性を損ねている気がしてならない。製作年順で解説に徹するか、どうしても独自のベストがやりたいなら、それこそ独立した読みものとして章を立てるべきだったのではないか。全体としては、評伝部も面白かったが、ふたつのインタビューが特出している印象。ただ、内容以上に驚いたのは、本書の製作費の一部がクラウドファンディングで賄われているということで、しかも未だにそのサイトが残っているのだが、そこにはこうあるのだ──「目標金額を大幅に上回った場合には、著者印税のほうも出版社側に検討してもらいます(執筆のための取材・資料収集段階でかなりの出費でしたが、現状では印税無しという状況になっていますもので)」。あとがきには「上回った」とあったが、ぶじ印税は出たのだろうか。気になる。(Y)
・トム・ガニング『映像が動き出すとき――写真・映画・アニメーションのアルケオロジー』
みすず書房/2021年11月18日発売/368頁/7,200円+税
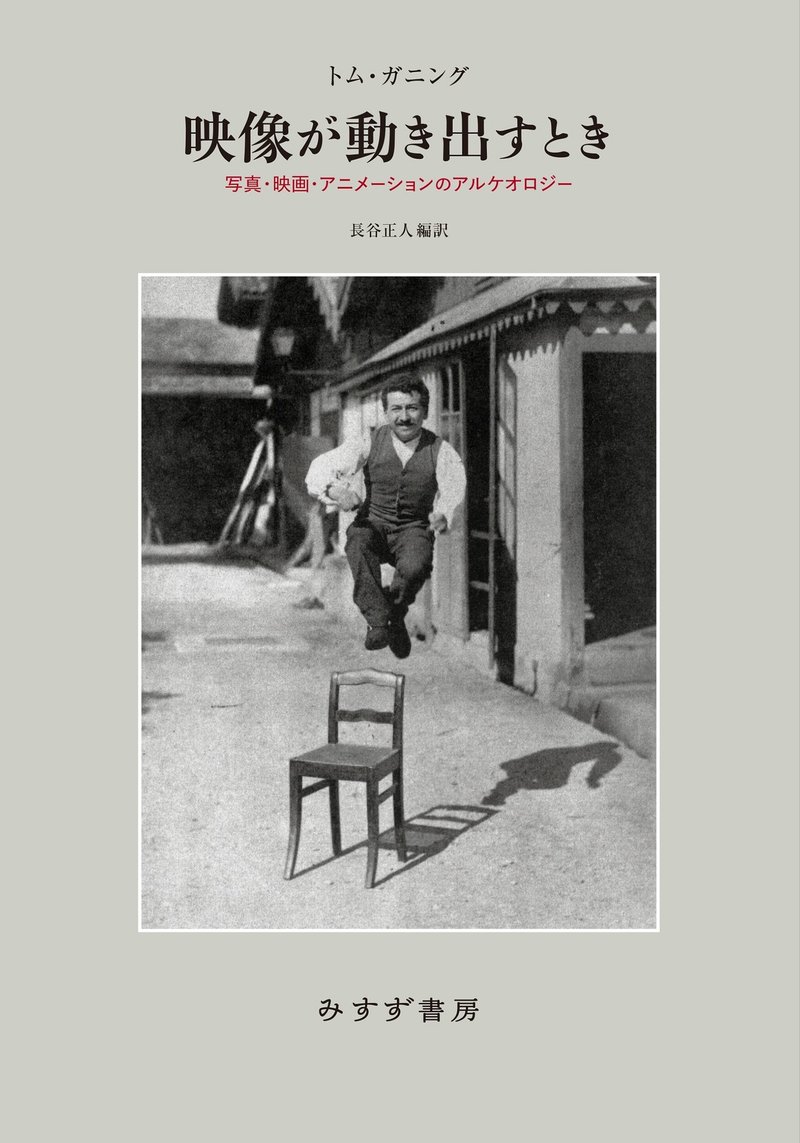
トム・ガニングによる待望の論文集。海外の出版状況に明るくないので「訳者あとがき」を読んで初めて知ったのだが、そもそも本書は「日本においてのみならず、英語圏においてさえ存在しなかった」文字通り「初」のガニング論文集なのだとか。正直なところ、二度ほど読んだ現時点でもなお、解ったなどと軽々しく口にすることのできない、一筋縄ではいかぬ一冊で、咀嚼するには時間をかけて幾度も読み込むことが必要だろう。とはいえ、小難しさに突き放されるような経験にもならないはず──途中で読み淀んださいは、いったん後半まで飛ばして、「柄にもないことだが、個人的逸話から」書き始められる、少々雰囲気の異なる筆致の「第9章 ゴラムとゴーレム」を挟むことを勧めたい──だ。ガニングは“ぽさ”を徹底的に拒んでいるように見える。抽象的な議論で煙に巻くことをせず、ひたすらに既知とされていたはずの原初的性質から問い直す。徹底的に具象、そのものと対峙し、安易に手っ取り早く結論を導き出そうとはせず、先行の言説を踏まえつつも、同時に自らの体験的な視点をわすれない。「私の課題は、私たちが経験するとおりにその知覚を記述することである」──そこに感動がある。間違いなく2021年最重要の一冊。
余談だが、本書に含まれていないガニングの重要論文「アトラクションの映画」は、本書企画の前身である『アンチ・スペクタクル』(もともとはガニングに限定されておらず、続編としての視覚文化論集が検討されていたのだ)に収められているが、現在は絶版である。復刊乞う。(Y)
トム・ガニングの論集は日本だけでなく英語圏においてもこれまで存在せず、今回が初の刊行とのことで、大変な労作である。海外の書き手の論集、と考えてもかなり貴重な企画だろう。映画の”動き”に注目し、またガニングが動きに注目したことに注目し、まとめられたのが本著というわけだ。
そして動き、ということにこだわった先にはやはり映画のデジタル化、またはアニメーションに関する捉え方の問題が生じてくるわけだが、その点についてもやはり”動き”を軸にしながら、これまでこちらが取りこぼしていたような論点も浮上してくるから楽しい。第3部の3章はどれもアニメーションやテクノロジーの進歩を議題にしており、例えば9章では『指輪物語』のゴラムから、モーションキャプチャーについて論じている。
その姿勢は柔軟にもうつるし、どこまでもガニングらしい…と安易にこちらが形容してしまいそうな一貫性もある、そのバランスも魅力かもしれない。内容としては固い章もあるが、ガニングが先行論文に皮肉とユーモアを含みつつ反論している点や、工夫された比喩に驚きながら読み進められるのも楽しい。まだ咀嚼しきれていない部分に関しては繰り返し読んで理解を深めたくなる文章の読み味、そして今後さらなる技術の進歩によって映画が変容することも予想される中、立ち返りたくなる重要な一冊だと思う。(M)
・侯孝賢『侯孝賢の映画講義』
みすず書房/2021年11月19日発売/344頁/3,600円+税
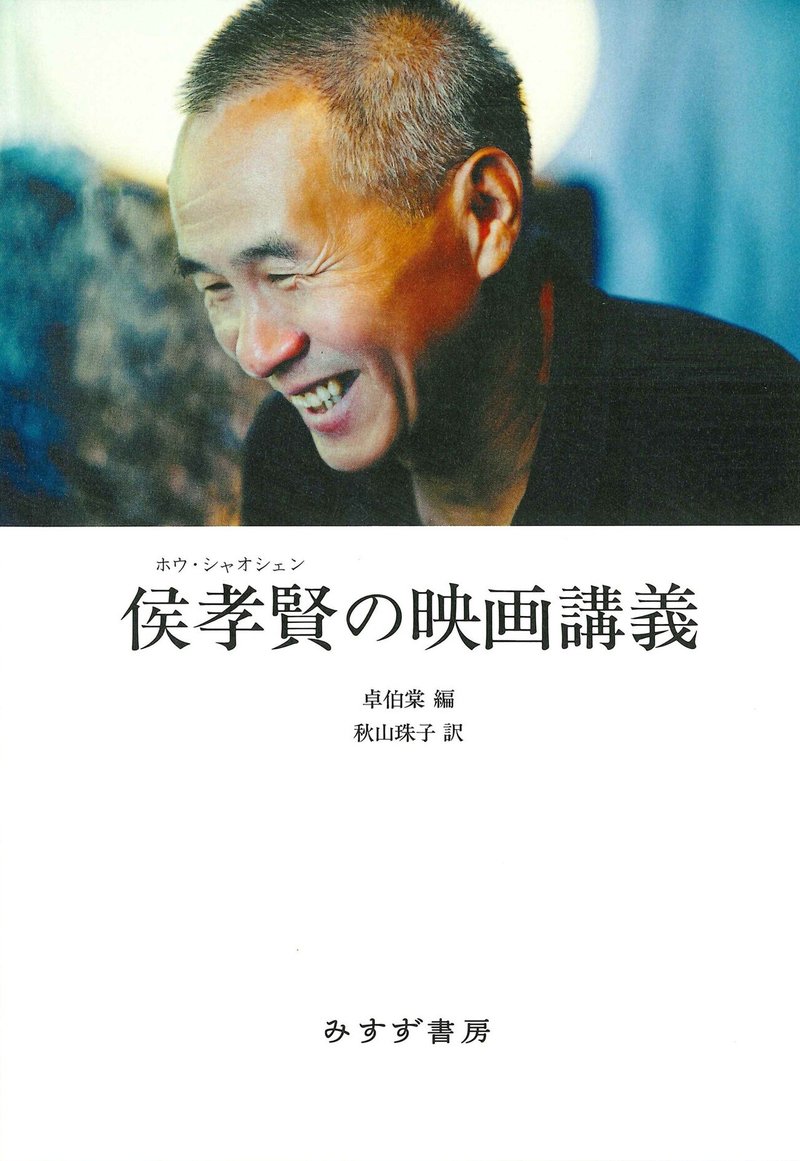
2007年に香港バプテスト大学で行われた、候孝賢(ホウ・シャオシェン)の講義録。私はこの講演を聴いたことはないし、むろん読むのも初めてなので、なぜか知っている内容が少なくなく不思議に思ったが、すぐにオリヴィエ・アサイヤスが撮ったドキュメンタリー『HHH』のなかで捲し立てていた話と重複が多いためだと思い至った。人前で講演をすることを苦手だ苦手だと随所で表明していながら、淀みなく原稿ナシで話し続けていること自体も可笑しいが、それぞれの話題が何度となく、ことあるごとに披露され、擦り尽くされてきた十八番なのだろうことが透けて見えて面白い。この手の「マスタークラス」企画の定めとして、内容の大半が監督作舞台裏エピソードで占められるが、個人的には“本題”以外の些細な箇所にこそ惹かれた──特に映画の好みについて。『カンフーハッスル』を「実に合理的」と評し、『ミュータント・タートルズ』について「第二作と第三作の武術シーンが大好き」と語る新鮮さ。『勝手にしやがれ』の革新性を褒めちぎったあと「私には、ゴダールの後期の映画はまったく見られない」と言い切るあたりも驚きつつ愉しい。とはいえ、今年刊行の候孝賢本としては『候孝賢と私の台湾ニューシネマ』のほうを推したいのが正直なところ。余談だが、訳者あとがきでさらりと触れられている「日本での出版に際して一部内容を割愛している」が気になる。(Y)
侯孝賢は正直あまり得意な監督ではないが、企画で2021年2冊目の侯孝賢関連書籍。関わりの深い朱天文の『侯孝賢と私の台湾ニューシネマ』は時代の回想録でもあり、侯孝賢のことを信頼して評価しつつも時に鋭い批判をする内容が面白かったが、今回は香港の大学で行った本人の講義の書籍化。2008年に香港、翌年中国で刊行されたものの日本語版ということで、本人の考えや映画を取り巻く状況も変わっているが、中国では版を重ねる好評っぷりということで、侯孝賢を知ることができる一冊と位置付けられていると思って良いだろう。
朱天文の本、あるいは本著に添えられた市山尚三による解題を読んで、周囲の侯孝賢という人物の捉え方を知ってから読むと、本人の講義も捉え方が変わってくるのが本著の不思議なところ。「見方によっては”いい加減”とも言えるような大雑把さは、侯孝賢と仕事をするうちに何度か遭遇した」と、市山はいくつかエピソードを披露している。そもそも、かなり感覚的な人物であることは本人の発言からも分かるが、一方で自分なりの論理を持っていることも分かる。それはときに、大雑把であったり突飛に周囲からはうつるものが含まれる。セルフイメージや作品の捉え方と周囲のギャップ、その差はどこか惹かれるものがあると思った。(M)
* * *
では、今回はここまで。
〈その他・雑記など〉欄は、更新が追いつくまでお休みです。
ここから先は
¥ 100
本文は全文無料公開ですが、もし「面白いな」「他もあるなら読むよ」と思っていただけた場合は、購入orサポートから投げ銭のつもりでご支援ください。怠け者がなけなしのモチベーションを維持する助けになります。いいねやコメントも大歓迎。反応あった題材を優先して書き進めていくので参考に…何卒
