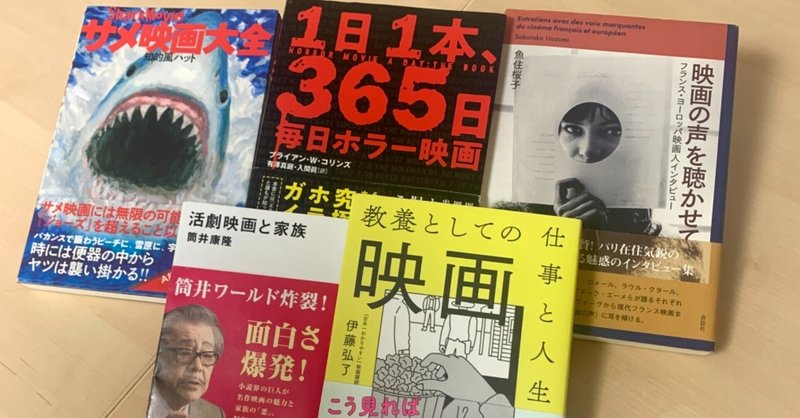
月例映画本読書録:2021年08月
今年、ぼくとパートナーのM(山本麻)は「毎月、その月あるいは前月に刊行された映画本を5冊読む」ことに決めた。
…ということで、毎月5冊最新の映画本を読んで、ぼく(=Y)とパートナーのMで短めな感想を書いて記録していくという企画の2021年8月分=第8回目である(先月に続き、毎月月末更新のはずが大幅に遅れてしまい情けない限りですが、9月末に帳尻を合わせる予定です)。企画開始の経緯などは初回である1回目に書いたので、未読の方はまずそちらをぜひ読んでみて欲しい。また、以後更新されていくの分も含めて、以下の”マガジン”機能で全てまとめておくつもりなので、こちらのページ↓を見ていただければ、常に”現状”の全ての回がみられるはず。
では、今月の5冊をはじめよう(並びは刊行順/感想は読了順)。
今回は、7月刊行のものor 8月刊行のものから。
・筒井康隆『活劇映画と家族』
講談社/2021年07月14日発売/176頁/840円+税

この記事の感想を書くとき、多くの場合文字数を削るのに苦心する傾向にあるが(大まかに決めた上限があるため)、今回ほどあっさりとした感想に落ち着く本は珍しい。本著は一言でいうと筒井康隆が映画のあらすじを書き連ねているだけの本であり、筒井の独自性であるとか、文章の魅力は感じられない。長々と作品の筋の説明ばかりが続き、時折山田宏一などの批評の引用があるとはいえ、それもとってつけたような引用であり、内容としては物足りない。
タイトルにある”家族”というのは、実際の血縁関係だけでなく擬似家族であったり、制作現場の密な関係性をもすくい上げる目的があったよう。しかし、そのテーマでの筒井の解釈がわかるような作品解説はないし、取り上げられる作品も『リオ・ブラボー』など、すでに作品中のコミュニティについて幾度も語られているような作品も多い。また、そもそも”家族”というテーマが大きすぎ、さらに前述のように解釈を広げているので、テーマとしてのまとまりがなくなるのも当然のことと思える。
それから、わざわざ指摘するのが気が滅入るが『マルタの鷹』のメアリー・アスターの年齢や容姿にことさら触れ、「美女ではあるものの御歳すでに三十五歳」とか「姥桜」「やや老け顔」と記しているのにゲンナリ。(M)
”小説界の巨人”に向けて不遜なことを書きたくはないが…わずか176頁の新書にもかかわらず、無限地獄の苦行読書だった。読んでも読んでも終わらないこと終わらないこと。惹句にある「名作映画の魅力(中略)を絶妙な筆致で描き尽くす」は「絶妙な筆致」部分以外、ある意味正しい。要は、文字通り映画の最初から最後までが律儀に逐一「描き尽く」されているだけで、基本的には長すぎる粗筋に終始している。時折、思い出したように他者の言説や作品情報が挟み込まれるが、ほとんどの文章はまるで作品を流しながら、一時停止しつつ書き起こしたかのよう。作品を見ていなければ、いかに展開が律儀に書き起こされていても読んでいて面白くはないだろうし、作品を見ていても無用の長物というしかない。「精緻な分析など自分には不向きであることもわかった」「評論家ではなく小説家なのだと思い知らされもした」「結果として主に筋書きを書くだけになってしまった」と反省(?)が綴られている「あとがき」が唯一の救いか。(Y)
・知的風ハット『サメ映画大全』
左右社/2021年07月15日発売/240頁/2,000円+税

サメ映画の紹介本で、紹介作品は100以上。帯には「サメ映画には無限の可能性がある。『ジョーズ』を超えること以外は」とやや結論めいた一文が入っていることからも分かるように、手放しで賞賛される作品は本著の中でもかなり限られている。厳しい戦いに挑んだ本とも言える。
次第にサメ映画、ひいてはパニックムービーのNGパターンが見えてくる。多いのは主題(サメ)そっちのけで登場人物の恋愛を描くもの、そして1番ひどいのは大事なサメがそもそも全然出てこない作品…。見るのはもっと辛いだろうが、読むのもちよっと辛いくらいだ。
あらすじも似たようなものが多く、正直なところ読後の各作品の印象がどうしても薄くなってしまった。サメ映画好きであればそうならないだろうけれど。日本ではみられないサメ映画を紹介するコラムなどは有益で、その他も短いコラムが挿入されてはいる。ただ、紹介作品の比較などボリュームのある批評がないのはやや物足りなく感じた。本著のようにジャンルを限った作品解説本は『いとしの〈ロッテン(腐った)〉映画たち』のように、ある程度読み応えがある記事があると良いなと改めて。(M)
そもそも映画ガイド本で”通読”に耐えうるものはそう多くないが、本書も残念ながらきびしい一冊。”サメ映画”という題材選択からして、限定的ジャンルであるがゆえに各レビューの内容が似通ってしまいがちなうえに、文体自体もわりと累計的なパターンの繰り返しで、バラバラに読めば気にならないのかもしれぬモヤモヤが増え続ける。各作品頁は「あらすじ」と「解説」から成るが、(映画の筋書きに左右される「あらすじ」は脇に置くとしても)キモであるはずの「解説」部の文章の多くが箇条書き的な文章構成で、作品情報や著者の雑感を段落別に羅列している感が否めない。さほど多くはない文字数の中で重複する記述(たとえば『ロスト・バケーション』評での「禍々しい巨体は、まるでナンシーと母を襲った死の象徴」「作中に登場するホオジロザメはいわばナンシーと母を責め苛んだ死の概念そのもの」)や、やたらと頻出する「〜めいた」という表現、最後の一段落で”気の利いた”締め括りの一文を拵えようという執心(たとえば『PLANET OF THE SHARKS 鮫の惑星』評では「あえてサメを選ばずともサルを観た方が無難だろう」)なども読む上でかなりノイズになる。また、無い物ねだりかもしれないが、”大全”を謳うならば、短めのものでも構わないので「サメ映画通史」のようなジャンルの変遷を辿る論考がひとつは欲しかったのが正直なところ。文句が多めになってしまったが、とはいえ、サメ映画を見たくなったときに作品選びの参考にするには十分有用ではある。(Y)
・ブライアン・W・コリンズ『1日1本、365日毎日ホラー映画』
竹書房/2021年07月21日発売/624頁/3,400円+税

1日1本ホラー映画を見て感想をアップするブログの単なる書籍化ではなく、著者が月ごとにテーマを決め、365本の映画を選んでいる。内容も当時のレビューの抜粋のみでなく、現在の著者の考察も記されており、時間の経過による作品の評価の変化や後日談が語られるのが面白い。
ただ、本著の1番の魅力は豊富な作品紹介部分ではない。1日1本ホラーを見た著者が、365本の映画の選定や加筆に際し、自らの経験を追体験するドキュメントであることだ。本著の作成にあたり再見した作品も多いようだが、視聴がかなわない作品も当然あるだろう。内容を覚えていない…なんてこともやはりあり、そんなとき著者はその”サッパリ思い出せない”さまを素直に記しており、思い出せない理由の説明が詳細だからおかしい。言い訳めいていて「どうなの?」と思う人もいるかもしれないが、それは違う。著者自身がブログ、あるいは本著の制作のドキュメンタリー性を自覚しており、むしろあえて細かく言い訳をしその面白さに花を添えているのだと思う。
そして、1日1本のブログを辞めた理由や妻子とのエピソードも短くだが記される。著者は例えば『シネマニア』に出てくる人々ほどは映画に生活を振り切っておらず、日常生活を維持しながらいかに趣味を深めていくか…という痛切な悩みも垣間見える。「僕は冗談ツイートで創作エネルギーを使い果たし、レビューを書くときにそれがあまり残っていない」なんて一文もあって、そこには可笑しみと切実さが凝縮されていると感じた。(M)
ここ最近、3冊のガイド本(来月分も含む)を連続して読んでいたが、めっぽう面白かったのは本書のみだった。著者のブライアン・W・コリンズは(書名の通り)「1日1本、365日毎日ホラー映画」を見てレビューする習慣をブログ「HMAD」上で6年間(=約2500本)継続し、それが”書籍化”されたのが本書…なのだが、「手をかけてレビューを整理するにしても、読者がすでに無料で読んだものに料金を請求することなんかできない」という著者の、単なるブログ書籍化を回避しようとする強固な意思/工夫がとにかく素晴らしい。まず本書は、彼の6年間=2500本の鑑賞歴の中から選び抜いた365本を、毎月1テーマ×12ヶ月に分類し、ひめくりカレンダー式に1日1本割り振ってある構成。そしてその各作品は(作品情報は当然として)「うろ覚えのストーリー」「レビューの抜粋」「さらなる考察」の項目で成り立っている。「レビューの抜粋」は当時のブログからの引用だが、それ以外の二項目が本当にユニークで、作品を見直さずに書かれたという「うろ覚えのストーリー」はほんとうに必要最小限(『ぼくのエリ』の場合は「孤独な少年が、ヴァンパイアになってしまった謎めいた少女と恋に落ちる」のみ!ほかも大抵はこの分量)だし、書籍化に際して作品について新たに書き下ろされた「さらなる考察」は”考察”と銘打ってはいるものの、とにかく自由。もちろんその作品について新たな知見が披露される場合もあるにはあるが、なにせ著者は殆どの選定作品を改めて再見していないため、少なからず内容を忘れてしまっていたりする(正直に忘却告白が綴られる)し、作品を見た当時の状況──場所や時期、当時のコンディションや自らの生活について──が赤裸々に語られもする…さしずめ、作品を起点にしたエッセイといったところ。この潔さに胸を打たれる。とことんパーソナルに振り切っていて、義務感による事務的執筆とはどこまでも無縁。決まり切った形式(字数はさまざま)もなければ、締切に追われて慌てて見て書いてもいない(見直してさえいない)。プロの小手先仕事(ままあることは誰にも否定できないだろう)の対極にある、アマによる「完璧じゃないかもしれないが、ジャンルへの本物の思い入れと愛によって作られたもの」。レビュー自体は、脚本や描写(特殊メイクの出来など)への言及がほとんどで、いわゆる”演出”については感覚的な記述が多いが、膨大な鑑賞量の蓄積が(多くを忘れたとしても)がもはや統計学的説得力を備えていて物足りなさを感じさせない(「このジャンルで〇〇が〇〇する展開があったのは〇本くらい」)。作品ガイドとしても面白いが、それ以上にひとりの映画愛好者の変則的な生態記録として楽しんだ。「Twitterを多用し始める前のほうが自分のレビューがずっと面白いことに気がついた」…なんて誠実で耳が痛い話だろう。(Y)
・伊藤弘了『仕事と人生に効く教養としての映画』
PHP出版/2021年07月29日発売/368頁/2,050円+税
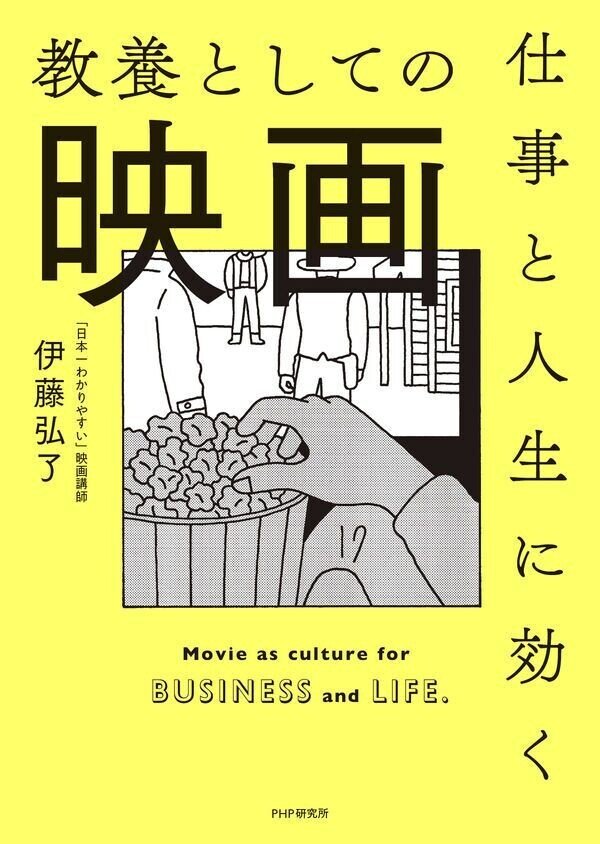
本著はビジネス書という看板で間口を広げつつ、映画の具体的な分析や鑑賞方法も紹介し”実用性”のある構成を目指している。しかし、率直な感想としては要素を詰め込みすぎて煩雑に思えた。また黒澤、溝口、あるいはヒッチコックに代表される紹介部分も、語られ尽くした文脈をなぞるだけの印象である。既存の文脈や語られてきた映画論を、”ビジネス”思考という実は曖昧で汎用性が高い視点に引き寄せ、あたかも分かりやすく・新しさも交えつつ語っているかのように見せているにすぎないのではないか。
また、基本的には著者を模したイトウ先生という人物が20代前半と思しき男女に講義をするかの体裁で進行するが、この形式が極めてノイジーである。そもそも想定読者が”ビジネスパーソン”なのであれば、両人物が若者と思しき人物である必然性もないだろう。
女性のキャラクターは1時間以上の視聴に耐えられないという設定の一方、口調は「〜わ」などいわゆる古風な女口調で初めは違和感を覚えるが、次第にそもそも2人とも性格設定にブレが出てくる。女性キャラクターは前述の設定があるにもかかわらず、ヒッチコックは何作か見たことがあると言うので混乱する。あるいは小津の世界的評価を紹介した後の男性キャラクターの「同じ日本人として誇らしいや」という発言、あるいは鑑賞メモの項目としてどの出演俳優を記すかという説明の際には「主人公とヒロインは外せないとして」などの記述もあり、筆者のバイアスを感じてしまった。(M)
刊行予告(当時は「読むだけでアート思考が身に付く「映画の教養」」/「ビジネスに活かす教養としての映画」という仮題)の時点から、すでにヒヤリとしたものだったが、じっさいに読んでみると予想を上回る酷さで慄いた。「映画研究者=批評家としての立場から、私は「映画を意識的に見ることは、人間としての能力の底上げや人生の向上につながる」という確信」を抱いたという著者が、映画の歴史や実際の作品分析を”ライト”に紹介しつつ、その”効用”をしきりに訴えているのだが、根拠薄弱な精神論/ありきたりな綺麗事が並ぶばかりで、読む限り「人生に効く」かは大いに疑問(”効く”必要があるか否かはさておき)。そもそも、本書で示される肝心の作品分析の多くは著者独自のものではなく、説得力を他者の研究に丸投げした流用紹介の”借り物”でしかない(本書の序盤で「学問の水準は集合地の力で上がっていくものです。本書でも、すぐれた研究成果は積極的に紹介させてもらいます」と断りがあり、その考え自体には同意するが)。そんな著者が「映画を見ると得をする」と熱っぽく語る──著者をモチーフにした「イトウ先生」が架空の若者男女ふたりに向けて語りかける問答=”講義”形式になっている──ようすは、正直なところ、ここまでくるとかなり痛ましい。映画を愛好した著名人/文化人を”証拠”として引っ張り出しつつ「一言で言えば、映画を見続けていると、人間としての魅力が増す」と言い、「映画はあなたをこう変える」と示された挿絵の横には箇条書きで「想像力が豊かになる」「観察力が高まる」「雰囲気のある大人になる」「ファッションセンスがよくなる」などとあって唖然とするほかない。そのうえ、観賞後のアウトプット法が指南される終盤では「小津作品ツイートが「バズった」理由」などという立項まであり辟易した。このように、苛立たしい箇所を挙げ始めればキリがない本書だが、一番の驚きは終盤で示される著者の映画鑑賞記録ノートの写真である。掲載されているのは1ヶ月+数日分のみだが、少なくともこの期間は規則正しく1日1本しか見ていないようで目を疑った。もちろん私は、本数至上主義ではないし、他人の鑑賞量をとやかく言えるほどたくさん映画を見ているわけではない。けれど、映画の研究者であり、「映画を見ると得をする」という主旨の書物の著者がこの様子では”効能”の程度も知れたものだろう。重版がかかり大変好評とのことだが、それを受けて今後類書が増えたりしないことを祈るばかりだ。
余談だが、「映画研究者の初の単著」という事実が信じられない(信じたくない)本書について、Twitterなどで感想を調べてみると、ひたすら嫌気が差してくるのでぜひお試しを。若手研究者たちが肩を並べて賛辞を表明し、エールを送っている。心の底から悲しくなった。ほんとうにこれでいいのだろうか。(Y)
・魚住桜子『映画の声を聴かせて フランス・ヨーロッパ映画人インタビュー』
森話社/2021年07月30日発売/416頁/3,200円+税
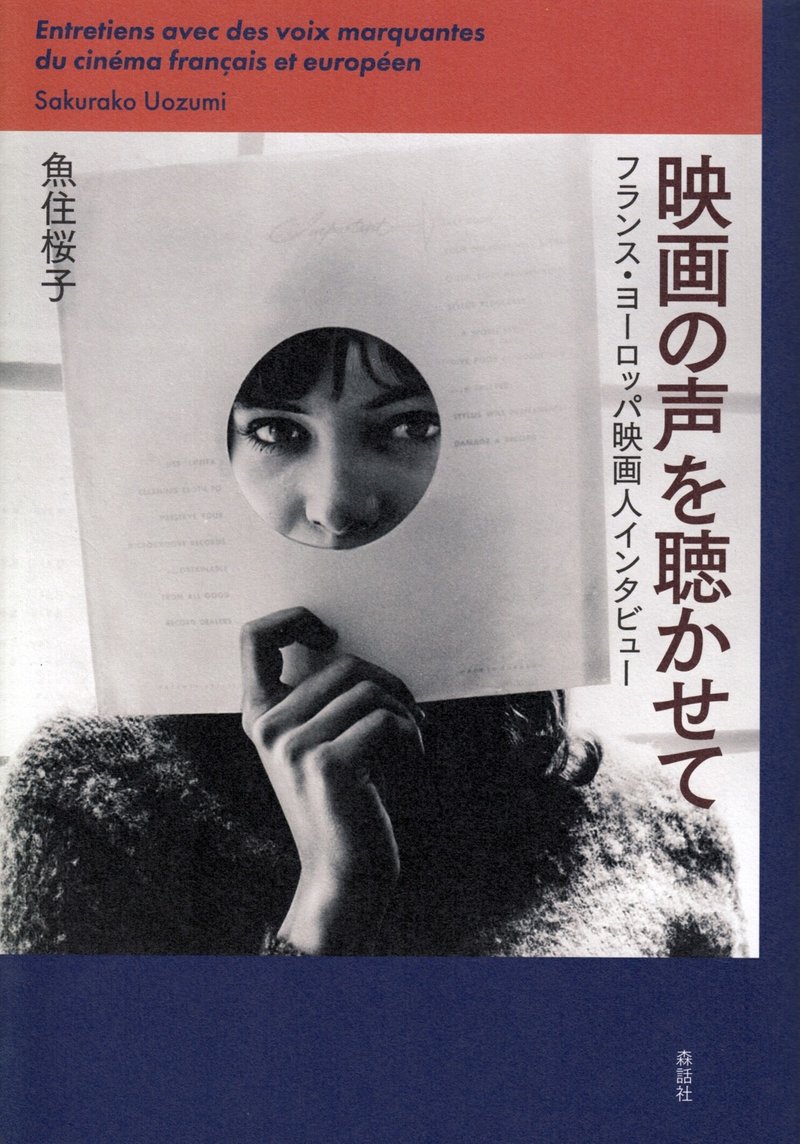
2004年よりパリ在住の著者による映画人インタビュー集。収録されている総勢29名のインタビューは、当然ながらそれぞれ分量に差があり、時に物足りなさを感じることもあるだろう。加えて、正直なところ、限られた時間で割と広範な話題を満遍なく聞いている=ひとつひとつの発言への掘り下げ不足感は否めない。だが、撮影監督たちに焦点が当たる第6章「天才カメラマンのまなざし」などは各人のボリュームも多めで興味深い発言も多々あり必読といえる。特に、「全く俳優の演出を知りません」「彼のような偏屈な人間」「怠け者で、サボってばかりいる」というラウル・クタールによる辛辣なフィリップ・ガレル言及は爆笑もの。その一方で(人柄については「頑な」と評しつつも)俳優から素晴らしい演技を引き出すガレルの演出について証言するレナート・ベルタとの差異を考えると(協働時期の違いもあり)面白い。日本における海外映画人へのインタビュー本というと、どうしたって山田宏一や蓮實重彦の仕事を思い浮かべてしまうが、彼らと比べるのは誰にとっても流石に酷だ──しかし、そうと判りつつも比べずにはいられないもの。本書についても、じっさい遠く及ばないのが事実ではある。しかし、同時にもはや彼ら二人が新たにインタビュー本を出すことはない(であろう)現在、これだけの人数/ボリュームの”新規”インタビュー──(雑誌初出のものもあるが)収録されているインタビューは2007年〜2020年に行われたもの──を読むことができるのは極めて貴重。多くのインタビューの末尾には「〇〇は、〇〇年〇月〇日、〇歳で逝去した」という一文が入る──ぎりぎり間に合ったものばかり…晩年の証言集としても必携。(Y)
本著は読む前の印象と比べると、ライトな一冊だった。主に著者のインタビューがやや掘り下げ不足な点が気になり、購入検討者が特定のインタビュイーのファンである程度本人の発言を追っている人物であれば、内容に物足りなさを感じる可能性がある。また元々のインタビュー掲載時の発注がどのような内容だったか不明なため、どこまでが著者のこだわりかはわからないが、そのヌーヴェル・ヴァーグへの執着に違和感を覚える部分もあった。
例えばフィリップ・ガレルへのインタビューでは「ヌーヴェル・ヴァーグの精神を引き継ぐ、確固たる意志と純粋さがあります」と著者は述べるが、果たしてヌーヴェル・ヴァーグの精神とは何かと考えあぐねてしまう。(もちろんこの本はヌーヴェル・ヴァーグが何であったかという問いを含む一冊ではあるが)。あるいはピエール・ロムへ「ヌーヴェル・ヴァーグと呼ばれた映画作家との仕事がなかったことについて残念に思わないか」という趣旨の質問をする。一方で、ブレッソンの『白夜』やユスターシュ『ママと娼婦』への質問は、両監督の人となりや現場の様子を簡単に書くのみで、具体的な撮影に関する言及が少なく、作品のファンとしてはただ残念に思った。
ただ、ピエール・ロムへの質問からも分かるようについドキッとする話題(例えば監督とスタッフの仲違いやスキャンダルについて)にも切り込んでいるのは面白い。また撮影監督へのインタビューが充実しているのも素晴らしく、特にヌーヴェル・ヴァーグの監督と仕事をした数名が、フィリップ・ガレルの欠点を指摘しつつも、彼との仕事は刺激のある経験だったと語っているのが興味深かった。(M)
* * *
〈その他・雑記など〉
重版も早速かかっているらしいが、真造圭伍『ひらやすみ』がよかった。気のいいフリーターの主人公が、仲良しな”ばーちゃん”(お婆さん)の死後、平家を相続する話。家賃を毎月支払わねばならない立場としては羨ましい限りだが、その羨ましささえ乗り越えればあとは楽しめる一冊。主人公の従姉妹(美大1年目)もその平家に住むことになるので、共同生活ものでもある。主人公は本当に気のいい性格で、おおらかに日々を過ごしていて、これはある種の才能というかカリスマ性を感じる。本作の舞台は阿佐ヶ谷だが、同じく阿佐ヶ谷が舞台の『A子さんの恋人』のA子さんも奇しくもそんなカリスマ性がある人物で、その残酷さも魅力だったので『ひらやすみ』もそんな話が出てきたら面白いなと思っている。
『現代思想2021年9月号 特集=〈恋愛〉の現在』は菊地夏野の「「逃げ恥」に観るポストフェミニズムーー結婚/コンフルエント・ラブ/パートナーシップという幻想」という論考目当てで購入。『逃げるは恥だが役に立つ』をポストフェミニズムの観点から語る試みは、しばしばあったように思うが、その中でも抜きん出て読み応えがあった。連ドラと今年放送されたスペシャルドラマの違いにも言及しているのが興味深く、またスペシャルドラマ版を読み解く試みは原作者の海野つなみと脚本を務めた野木亜紀子の差異を考えるきっかけにもなるだろう。(スペシャル版は原作に途中までは忠実な一方で、コロナの現実を盛り込んだ展開はオリジナルであり、そのパートに関する菊地の言及は必読)。(M)
読書近況は先月に引き続き、変わらず買い集めてはいるものの読み進めずにいるというのが現状。8月は7月分を慌てて読んでいて、9月は8月分を読んでいた…なさけない。とはいえ、予定通り9月分で遅れを取り戻すことができそうで安心している。当初の予定通り、9月分は9月末に更新予定。副反応でダウンしている最中に『キネマ旬報』原稿準備のために、いまおかしんじの日記ブログをすべて一気に読んだのだが、ポール・トーマス・アンダーソンが『絶倫絶女 おじさん天国』を見て面白がっていた…という記述があって驚いた。いまおか監督はかつてキネ旬のお気に入り監督三名選出企画でもPTAを挙げていたし、『ろんぐぐっどばい』はどこか『インヒアレント・ヴァイス』を思わせもしたから。(Y)
では、今回はここまで。
次回は9月30日更新予定です。
ここから先は
¥ 100
本文は全文無料公開ですが、もし「面白いな」「他もあるなら読むよ」と思っていただけた場合は、購入orサポートから投げ銭のつもりでご支援ください。怠け者がなけなしのモチベーションを維持する助けになります。いいねやコメントも大歓迎。反応あった題材を優先して書き進めていくので参考に…何卒
