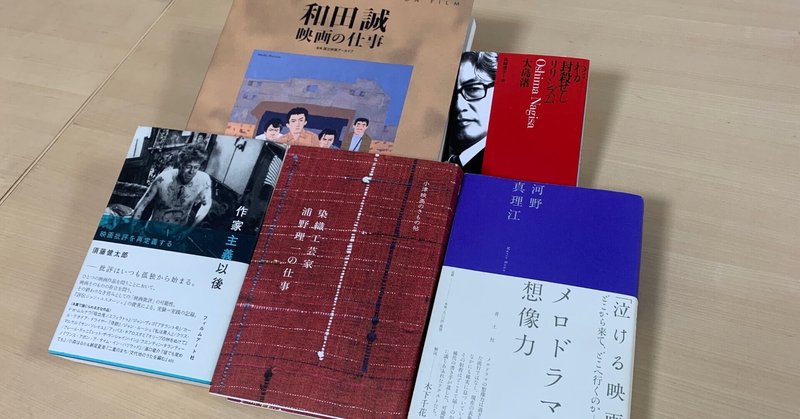
月例映画本読書録:24年01月
2021年のこと。新刊映画本情報が少なすぎるという苛立ちから、私(=髙橋)とパートナー(=山本麻)は「毎月、その月あるいは前月に刊行された新刊映画本を5冊読む」ことに決め、「月例映画本読書録」と題してクロス(ショート)レビュー方式で紹介していく……という習慣をnoteで始めた。しかしながら、情けなくも掲げられた「月例」の言葉むなしく、1年と経たずに更新遅滞が常態化し、ついには途絶えてしまったのだった。にもかかわらず、なぜかずっと変わらず毎月5冊を選んでは買い求め、必死になって読んでいる。そろそろ潮時だろうと決意を新たにしたわけでもないのだが、相変わらず新刊映画本をめぐる状況に物足りなさを感じ続けているのもあって、今年はようやく再開することにした。
……ということで、2024年1月分である。企画開始の経緯などは初回(2021年)に書いたので、未読の方はまずそちらをぜひ読んでみて欲しい。また、以下を見ていただければ、常に現状の全ての回がみられるはず。
では、今月の5冊をはじめよう(並びは刊行順/書籍ごとの感想は読了順)。今回は、23年12月 or 24年01月刊行のものから選んでいる。
⚫︎織田桂 取材・文・編集『染織工芸家 浦野理一の仕事 小津映画のきもの帖』

2023年12月12日発売/336頁/価格 3,600円+税
染織工芸家・浦野理一の仕事を小津映画を軸に、写真をふんだんに掲載し紹介する贅沢な一冊。小津映画の着物については中野翠が『小津ごのみ』でファッションの章を設けたりとすでに書かれているものがあるが、映像や図版ではなく生地を撮影した写真をみてみると、模様の繊細さや質感が分かりやすく新たな発見があった。例えば『彼岸花』で山本富士子が着用した藍型鹿と鶴の印華布は大きなスクリーンで見ない限り模様が鮮明には認識できないと思うが、拡大された写真で見ると鹿の模様が小花になり、一部が朱色になっているかなり凝った色使いであることを知った。コラムや説明は多くはないが、着物を吟味し撮影に使う贅沢さは写真を眺めるだけでも十分伝わってくる。
また、雑誌『ミセス』等では香川京子や司葉子が浦野の着物で登場し、当時の女性の着物への関心の高さがうかがえるが、何より驚くのは幸田文全集と浦野がタッグを組んだプロモーションだ。布ばりに使用された格子は幸田格子と呼ばれ『彼岸花』でも田中絹代が着用しているが、この造本を「粋な着物のような美しい造本です」と広告で宣伝し、なんと全集の定期購読者を獲得した書店には反物のプレゼントまでしたという。作り手からその受容までをまとめた内容になっており、日常的に着物を着る機会がある観客が小津映画を見てどんな感想を抱いたか、想像が膨らむ。(山)
昨年刊行された『Fashion in Film』(ボーンデジタル)──内容自体は悪くないが編集が杜撰きわまりない代物──を読んだときにも感じたことなのだが、私は映画を見ていて衣装について考えることがほとんどない。だから着物のこともよくわからない。にもかかわらずこの本は、小津安二郎監督作『東京暮色』から『秋刀魚の味』に至る6作品で女優の着物を手がけた(本書では取り上げられてはいないが中村登『辻が花』や番匠義彰『恋とのれん』にも関与した)染織工芸家・浦野理一を紹介する一冊なのだから、本来ならば門外漢として頭を抱えるほかないのはずなのだが、さにあらず、意外なほどに楽しめた。いうまでもなく本書の主役は浦野なので小津に関する内容はあくまで一部に過ぎないが、そこには小津から浦野へ宛てた手紙や場面毎の衣装イメージ要望書、そしてもちろん着物の布が示される。たとえば女優が着物を身につけた場面/現場の写真や掲載された布は、要望書と見比べることで発注がどのように結実したかという製作の一端を覗く面白さを味わわせてくれる。本書は決して読みものが分量的に充実した書物ではない。が、少量ながら冴えている。いくつかの寄稿を除き、ほとんど署名はない。書き手は誰だろう? きっと誰もがそう思うはず。答えは奥付にある──「取材・文・編集:織田桂」。本書の版元「katsura book」の代表だ。ひとり出版社の門出(2冊目とのことだが)を言祝ぎたい。(髙)
⚫︎大島渚/高崎俊夫 編『わが封殺せしリリシズム』

2023年12月21日発売/288頁/価格 1,000円+税
編集者・高崎俊夫のファンである。にもかかわらず、あろうことか2011年に清流出版から刊行された氏の編著『わが封殺せしリリシズム』を読まずにきてしまった。大島渚に対して格別の思い入れがあるわけではないからか(余談だが好きな作品を3本選べば『御法度』『マックス、モン・アムール』『日本春歌考』ということになる)後回しとなり続け、文庫化にまで追い抜かれて今年ようやく重い腰を上げることができたというわけだ。本書には作品評から俳優論、追悼文や弔辞まで幅広い文章が3章にわたって収められているが、私が特に胸打たれたのは特定の人物についての言葉、すなわち追悼やポルトレだ。大島は対象となる人物を言葉を尽くして説明しようとしない。読み手に判らせようともしなければ、決して自身が理解しているふりもしない。あくまで他者として、特権的な瞬間の印象を記述するに留める(印象的体験を回想するさいの「忘れがたいシーンがある」という表現に顕著である)。たとえばビートたけしの衣装合わせ、デヴィッド・ボウイが口にした挨拶、佐藤慶の美しい筆跡という具合に。あるいは砂糖、会議、利根川など……自立したエピソードが、どういうわけだかその人物を浮き上がらせる。思えばこれは、第1章に収められている『夜の鼓』評や、新録された『旅芸人の記録』評の見事な画面描写にも通ずるかもしれない。喜ばしい文庫化である。この機会に読むことができて良かった。(髙)
大島渚が人の心を掴む力に長けた人物であることは知っていたが、文章にも人たらしっぷりがにじみ出ている。それを体験するのが本著を読む何よりの面白さだったかもしれない。ディティールの描写で引き込み、人物評や追悼文であれば、辛辣で率直な相手への吐露があり、同じように自らの弱い部分も開示する。例えば、寺山修司の追悼文では、最期の日々を回想した末に「そして私は生れてはじめて自分の泣き顔をテレビの中に見た」と記す。客観的な視点と感傷、そしてナルシズム。この波に揺られていると、あたかも本心を打ち明けられたように錯覚し、これまでよりもずっと大島を親しく感じる。鮮やかで洗練された手つきはちょっと怖いくらいだ。
ざっくばらんな面白さという点では、第1章の俳優論が魅力的。独自の観点で俳優を観察し「高峰秀子が信頼される人間を演じて成功したのは、彼女が負うて来た全人間的な生活の重みがその人間達のそれをはるかに超えていたからです」「仲代達矢をよく訓練されたシェパードだと言いましたが、よく訓練されたと言っても俳優の場合、それは同時に自分が自分を訓練したということにほかなりません」といった文章からは、俳優自身の人生の歩みやそれによって高めた内なる強度を重視し、常に問うていることがよく分かる。この考えが基盤にあるからこそ、非職業俳優の起用など独特な配役が功を奏した作品が多くあるのだろう。(山)
⚫︎国立映画アーカイブ 監修『和田誠 映画の仕事』

2023年12月21日発売/144頁/価格 3,200円+税
近年和田の仕事をまとめた書籍の刊行が続いている。和田誠の仕事とともに映画に親しんできた人からすれば自明なことだろうが、後追い世代なのでこんなにも鋭い分析眼を持ち、アウトプットし続けた人がいたんだといちいち驚かされる。和田の文章はあらすじ一つとっても誰かの借り物の言葉ではなく、和田の身体を通して出た言葉、という感じがするが、イラストの仕事も新鮮さに満ちており、和田がどんなふうに対象を捉えているか想像しながら眺めるのが楽しい。ルイス・ブニュエルの手に浮かぶ血管に注目するのかという驚き、まるで見得を切るかのように手を前に出したグロリア・スワンソンを下からあおりぎみ描き、迫力を誇張する納得感。あるいはゴジラの動きと身振りがリンクするように並べられた本多猪四郎のイラストの切り口のスマートさ。
偉大な人物を形容するとき、「(映画)愛」といった言葉が安易に使われていると思うことがあるが、和田誠に関しては、そう呼ぶことしか出来ないような映画への執着、格闘の歴史があることがこの本を一冊読むだけでありありと浮かび上がってくる。膨大なイラスト、デザイン、装丁の仕事から音楽や監督業までをまとめつつ、日記や収集したフィルム、ポスターの紹介、また『快盗ルビイ』のスタッフ似顔絵は今回長谷川隆が割り出し名前付きで掲載されるなど、細かいこだわりも嬉しい。(山)
「実は見たことない映画」があるように「実は読んだことない映画本」というものもある。考えてみると、私にとっては長いあいだ和田誠の著作がそれだった。きちんと出会うのが遅かったのだ。まず「山田宏一と仲が良いイラストレーター」として、次いで「『麻雀放浪記』のすばらしい監督」として記憶され、ずっとそのままの期間が続いた。失礼ながら相手目当てに対談本は幾つか読んでいたはずで、装幀本も多く手にしてはいたから存在は認識していたはずだが、なぜだか単著へ手を伸ばすには至らなかった。『お楽しみはこれからだ』もつまみ読みこそしていた気がするが、「台詞ねェ……」と斜に構えていたのだろうか、結局読まずにきた。恥ずかしながらようやく、この人凄いんだ、となったのは、わりと小賢しくなって(しまって)から。『お楽しみ…』も、数年前の愛蔵版復刊によってようやく通読を果たし、その凄味を痛感した。だからまだまだ私は和田誠入門の途上にある。まさに、お楽しみはこれからなのだ。展覧会図録でもある本書の文章量は決して多くない。だから読もうと思えば1時間もかからない。けれど、紹介される仕事の数々を眺めながら、書棚からあれを取り出しこれを取り出し捲りつつ、お次は作品を見直しつつ、とするうちに不思議と時間は過ぎてゆく。読んでいなかった『銀座界隈ドキドキの日々』を読んだ。幾度となく読んだ『新人監督日記』を再読した。久しぶりに山田宏一のことをたくさん考えた。『にっぽん脚本家クロニクル』や『ええ音やないか』をぱらぱら捲った。頁と本棚を行き来する。巻末の長谷川隆(『熊谷照明学校』インタビュアー)による寄稿がいい。すぐさま『熊谷照明学校』も見た。そういう読書だった。(髙)
⚫︎河野真理江『メロドラマの想像力』

2023年12月25日発売/352頁/価格 2,600円+税
メロドラマを軸としつつ、自分の直感や疑問と向き合い、ふさわしい言葉に落とし込むべく手法にも工夫を凝らした濃密な一冊。試写の克明なレポートから始まる『ホットギミック ガールミーツボーイ』論、残暑にアテネ・フランセへ赴かず、騒音に悩まされつつ敢行された論考のためのペドロ・コスタ再見の質感。これらは余談ではなくむしろ文章の核となる観賞体験記になっており、自分の心のうごきは何によってもたらされるのかというあくなき探求、主観的で私的な感覚をどう他人に伝えるかという模索を続ける著者の立場をシンプルに示している。
あるいは渋谷実の『母と子』についての論考では、著者が感じた違和感から出発し、公開時の評論の鮮やかな分析からダイナミックな展開をみせる。まず作品を暫定的に松竹大船調の女性映画の慣例から逸脱した疑問符付きの“女性映画?”として扱い、“お妾映画”の系譜に連ね捉えてみることで、この上なく残酷な真の姿を浮かび上がらせる。タイトルは『母と子』とあるが、彼女たちは大企業の専務らしき父親からすれば取るに足らない“オンナコドモ”であり、父の若い部下からも出世に利用できる存在としてあつかわれることに触れ、日中戦争が激化する1938年に公開された、国家組織的な空間から女性を排除した男性映画であると指摘する。さらには『日本の<メロドラマ>映画──撮影所時代のジャンルと作品』の『猟銃』等を扱った6章のように、男性の批評家中心に形成された公開時の時評を取り上げ、同時代の女性映画とは異なる“オンナコドモ用のお涙頂戴のメロドラマ”らしくない、見所のある映画として高い評価をうけた事実にも切り込んでいく。
また細部の楽しみとしては、独自のたとえによって著者が感じた微妙なニュアンスを共有しようとする試みがある。キネマ旬報の星取り表担当初回で、著者が『孤狼の血 LEVEL2』評にて「白石和彌はいつも、頑張ってるね、という感じの映画を撮る」と書いていたときには、短文故に際立つ辛辣さに、全然好きではない監督なのに、つい白石和彌の気持ちになっておののいてしまったくらいだが、『ホットギミック ガールミーツボーイ』の主人公を『寝ても覚めても』のヒロインを「一六倍くらいサークル・クラッシャー気質にした感じの女子」と説明するような比喩の模索には、友人とカフェで特定の映画の悪態をついていたら「これだ!」としか思えない比喩(ほとんどが揶揄)がおりてきたときのような中毒性があり、硬軟どちらの文章にもこの妙味が顔を出すのが河野印なのかもしれない。(山)
『キネマ旬報』2021年10月下旬号の片隅で訃報を目にして言葉を失ったときのことは忘れられない。むろん私は単なる読者に過ぎないが、その年の2月に刊行された初単著『日本の〈メロドラマ〉映画』の格別な面白さに愕然としたばかりであったからだ。今回取り上げる本書『メロドラマの想像力』は、著者の既出原稿を編んだ遺稿集である。『ユリイカ』などに発表された論考もあれば書評もある。いずれも当然ながら加筆はされていない。まずなにより、本書の魅力を私的な逸話も交えつつ慎ましく端的に繙いた木下千花の巻末解説がすばらしい。とくに俳優論における映画的身体をめぐる記述を批評史に位置づける「からだと身体」が圧巻。また「第二部後半や第三部に顕著なように、撮影所時代の日本映画という専門から離れて「お題」に応えて書けば書くほど、河野さんは書き手としての声を獲得」したという指摘にも、本書を読んでいるさなかの言語化しがたい感銘の核心を言い当てられたような思いがする。もちろん博論本と響き合う第一部も、第二部前半の俳優論も清順論も渋谷実論も頗る面白いのだが、それ以降で言及される作り手=「お題」が、個人的に気が進まない対象ばかりであるがゆえに、より一層、そのつど異なる鮮やかな対峙、対処に魅せられるとでも言えばよいだろうか。取り上げられるのは(映画作家に限定して挙げてみても)大林宣彦、北野武、岩井俊二、山戸結希、ペドロ・コスタ、ソフィア・コッポラ──このなかで好きと言えるのは北野武だけだ。たとえば『ヴァンダの部屋』についての「ジャンル映画研究者としてのわたしはまず考える。この映画をどのようにカテゴライズすべきか?」、『ホットギミック ガールミーツボーイ』についての「確実なところから紐解いていくことにしよう。ジャンル映画という見方に立つと」という斬り込み方からは、まるで作品を前にして動き始める思考の流れ、ジャンルのフレームを通して作品を開く批評の生成過程が見え(始め)てくるようである。だから著者は、メロドラマに見えない清順映画に敢えて「メロドラマであるという前提」という視点から、同性愛表象に「(『おっさんずラブ』について)ゲイ・ドラマではないし、そして実のところBLドラマですらない」という切り口から分け入ることになるのだなと。また、見る主体として自ら感じたことを軽んじることなく、印象から作品へと遡行していく態度にも、胸を打たれた。泣いた立場から大林を、わからなかった感覚から山戸を批評するなんて。 本当に格好いいのだ。2023年刊行されたなかで最も重要な一冊と言っていい。まだまだ余波のなかにいる。(髙)
⚫︎須藤健太郎『作家主義以後 映画批評を再定義する』

2023年12月26日発売/448頁/価格 3,700円+税
『評伝ジャン・ユスターシュ』の鮮烈が未だ記憶に新しい須藤健太郎の評論集。一、二、三段組が入り混じるほんのちょっと晶文社ヴァラエティブック風(四六判ソフトカバーだが)であらゆる論考(に限らず講演や対談まで)が収録されて400頁を超えるボリュームであるが、語弊を恐れず正直に記すならば、読んでいるあいだ、少々の物足りなさがつきまとう。しかしそれは不満ともまた異なる感覚である。おそらくこの不足は、映画の捉えがたさに起因するものだろう。本書のなかで須藤は、批評家ないし研究者として映画に精通しているかのような振る舞いは決してしない。むしろ些か不恰好なほど率直に、不安や迷いを滲ませる。言葉を追いかけるうちに染み入るのは、精緻な分析や画面の読解ではなく「と、そんなことを考えながら映画を見ていると」、「いったい、どういうことだろう」「思い至る」「いや、少し冷静になって考えてみると」「ラストショットを前に、私は戸惑いを覚えた」「いや、こちらが勝手な思い違いをしているのかもしれない。あらためて冷静に考え直してみたい」「なおさら何か隠された意味でもあるんじゃないかと勘ぐりたくなってしまう」などという尽きることのない逡巡、鑑賞の思考である。たとえば須藤は、ある映画について「なんとも掴みどころのない厄介な映画である」と記しているが、読み終えると頻繁な惑いの記述に「全部じゃないの?」と感じるかもしれない。そして、きっと全部そうなのだ。映画というものは、得体の知れない、容易には捕まえられぬ、わからないものである。まさに「映画とは何か。それは永遠の疑問符のなかにある」のだ。だからこの本には答えが(目指されてい)ない。どの作品も、決して言い尽くされていない。閉じられていない。作品を自ら仕立てた論に従属させるのでなく、ゆらめく作品のほうへ身を任せる。徒手空拳であることを受け入れる。「この映画のそういった奇妙な作りについてみなさんと一緒に考えられればと思ってやって来ました」──著者がそう言ってくれるから、読む者の思考も滑らかに動き始める。必ずしも価値判断に「ノれる」わけじゃない(あたりまえだ)のに、点数を取り除いた状態で総覧されることで全く異なる読み心地へ生まれ変わっている『キネマ旬報』星取評の通読を最も刺激的に感じられたのも、意外かつ愉しい発見だった。(髙)
はじめ『作家主義以後』というタイトルは内容に対し大きすぎる看板に思えた。しかし全てを読み終えてみると『評伝ジャン・ユスターシュ 映画は人生のように』がなるべく先入観を与えないよう副題はタイトルから想像できる最低限の情報──映画監督の評伝であれば映画とその人生について書かれていること──で構成したと著者が説明するように、今回のタイトルもあくまで書き手が作家主義以後にいる、という現在地を簡潔に示す言葉を選んだように思えてくるから不思議だ。最初そう思ったのは、特に1章はパンフレットやDVDのブックレット用の解説の役割を担う、映画を見終わってから間を置かずに読むことを想定した文章が中心だったことも大きい。続けざまに読むとどうしてもするすると上滑りしてしまって内容を咀嚼しきれなかったのだが、読み進めると文章の掲載先によって説明の詳細さの使い分けがあることがわかった。
意外な面白さがあったのは『キネマ旬報』の星取りをまとめた章。率直な価値判断が述べられ、今の自分が感じたことを記そうとする意識が窺える。あるいは5章では2023年のユスターシュ特集にさいし自分の論文を振り返り、不十分だった点など現在の考えをまとめ、『ジャン・ドゥーシェ、ある映画批評家の肖像』のトークを終えての感想が掲載されている。一つの対象を著者が反芻する、その過程をめぐるようで楽しい。(山)
〈その他・雑記など〉
丸2年。長いことさぼっていたが、ようやく再開することができた。今回も幾度か「今年も無理かも、来年からにしようか」と思いかけ、手をつけたり中断したりを繰り返し、結果的に初回から(1月末に更新すべきところ)さっそく遅延という有様。ではあるものの、ひとまず更新できただけで良しとしたい。
そもそもこの試みを始めたのは、①なにか新刊映画本を買おうと思うが、懐はさびしく、絶対にハズレは引きたくない。 ②とはいえ書評で扱われるまで待ってはいられぬ、ひとまず面白いのか否か、ざっくりで構わないから刊行されてすぐ知りたい。 ③長文を読むのは億劫なときもあるので、あるていど短い文章で、あけすけに判断を示しているものが読みたい。④だれかやってくれないだろうか。……という学生時代の他力本願な望みを自分自身でやってみようという思いつきがきっかけだったのだが、今回は特に久しぶりなこともあって、即時性に欠けるばかりか、自ら設けた字数制限も平然と超過してしまっている。そのうえ全体的にぼんやり、そしてしんみりしすぎている感もある。リハビリ期間、ということで。(髙)
毎月の映画本クロスレビューが滞っている間に、好きだった漫画がたくさん完結し悲し、入れ替わるように好きな漫画が増加し嬉しという感じの時間を過ごしておりました。比較的最近読んだところだとオカヤイヅミの『雨がしないこと』、田沼朝『いやはや熱海くん』、雁須磨子『ややこしい蜜柑たち』が特によかったでしょうか。特に意識せず並べた3作だったけれど、全て「好意ってなんだろう」という素朴な疑問と好意(あるいは恋愛)の暴力性に真っ向から向き合っている作品といっていいかもしれない。あと岩浪れんじ『コーポ・ア・コーポ』が一旦終わってさみしいけれど『セーフ・セックス』がこれまた面白いという喜びもあり。実写版『コーポ・ア・コーポ』をやると知ったときは本気かいなと思ったけれど、中条役を東出昌大にした人には拍手を送りたい、まだ映画は見れていないけれど…。(山)
* * *
では、今回はここまで。
次回は2月末頃に更新予定です。2023年の映画本全般に関しても、いずれ振り返る機会を作りたいと考えております。
本文は全文無料公開ですが、もし「面白いな」「他もあるなら読むよ」と思っていただけた場合は、購入orサポートから投げ銭のつもりでご支援ください。怠け者がなけなしのモチベーションを維持する助けになります。いいねやコメントも大歓迎。反応あった題材を優先して書き進めていくので参考に…何卒
