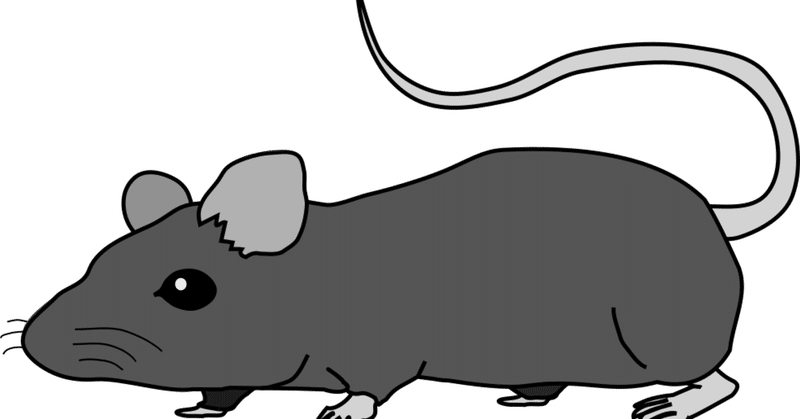
【定例討論会】#5「動物実験の賛否」
定例討論会が何かわからない方は、マガジンの説明欄を参照してください。
今回は動物実験の可否について、一応ディベートという形式で行いました。一応、というのも陣営が一方に偏ってしまったため、立論→反駁という流れが少し難しくなってしまいました。そこで、今回は少し変わった形でまとめることになります。
基礎知識
化粧品メーカーが相次いで開発段階での動物実験を廃止するなど、動物実験をめぐる動きが世界中で大きくなっている。この背景にあるのは動物の権利(アニマル・ライツ)運動の広まりがある。この運動の特徴は、動物にも人権と同じような動物の権利があると考え、動物の利用を厳しく制限する点である。
こうした運動に対して、動物実験を行う研究者たちは、医療などにおける動物実験の必要性を訴える一方で、三つのR(動物実験の削減、洗練、代替)などを軸とした動物福祉(アニマル・ウェルフェア)の取り組みを進めてきた。(『科学技術をよく考える クリティカルシンキング練習帳』より抜粋)
上に挙げた引用を理解していただければ、概ね大丈夫でしょう。
その通り、過去から現在に至るまで、様々な動物実験が古今東西で行われてきました。いくつかの実験は理科の教科書などでも確認できます。例えば、1780年頃、イタリアの解剖学者のガルバーニはカエルに二つの異なる金属をを接続して、カエルの筋肉が痙攣することを発見しました。ガルバーニはこの際、異なった結論に達したものの、その後、ボルタがこれを応用し、ガルバーニ電池を生み出しました。
また、人体実験もしばしば行われてきました。有名なもので言えば、例えば免疫の発見が挙げられます。
イギリスの医師ジェンナーは、一度牛痘に罹った人が天然痘に罹患しないことを観察し、牛痘の膿を接種するとことによって、天然痘を予防できることを発見しました。
現在では、私たちの生活に溶け込んだ技術や知識は、このように動物実験や人体実験の成果であることがこれ以外にも往々にして存在します。
しかし、動物実験や人体実験は多くの倫理的な問題を抱えています。
動物は基本的に苦痛を感じる能力を持った存在と考えられます。
(前略)つまり、そうした能力を持った動物を研究に用いるということは、動物に対し身体的のみならず心理的な悪影響を与えることになる。さらに、そうした研究対象に対し仮に配慮もなしに実験操作を加えることが許されるとなると、ヒトを含めた命ある存在の扱い方自体に混乱を引き起こす。研究に用いる動物への倫理的配慮の必要性は、動物を実験に用いることが残酷だとか可哀想だといった擬人主義による感情論のみならず、わたし達ヒトが知り得た動物に関する科学的知識からも導き出されるものである。
また、日本生理学会様のサイトも大変参考になります。
ヒューマン・ライツとアニマル・ライツ
人間(ホモ・サピエンス)には、人権があり、それは現代社会の基礎をなす倫理的な原理だ。しかし、こうした権利は人間にしか認められていないのは奇妙なことである。動物には人間と同種の権利があり、実験などにみだりに使ってはならない。
人権の歴史は、たえずその範囲を拡大し続け、現在の枠組みになった。これを踏まえると、動物の権利を認めることも自然な流れといえるだろう。つまり、動物の権利を認めることは、人権からもう一歩拡張したものだといえる。
アメリカ独立宣言には「全ての人間は生まれながらにして平等」だという記述が見られます。しかしその実、完全な権利が認められていたのは白人成年男性のみでした。
特に、アメリカでは黒人は長い間、虐げられてきた歴史があります。
また、社会学の領域ではこのような場面で、サバルタンという言葉がよく出てきます。
サバルタンとは、「自らを語る声を持たない従属させられた社会的集団を意味し、とりわけ植民地主義の文脈で、周縁化された先住民や奴隷を指す用語」です。
サバルタンは自ら語ること(自分の権利を主張するなど)が原理的に困難です。そこで、どのように語るかという言いますと、社会運動等で動的、戦略的な行動で訴えるか、より良い代弁者を探すしかありません。そして、その代弁者はサバルタンの酷い扱いに同情し、権利の獲得がやっとできるようになります。
これは、動物の権利にも当てはめられるのではないでしょうか。語る力を持たない動物に代弁者である私たちが同情し、彼らにも権利があることを主張するのです。
ですから、権利の拡大が動物に及ぶことはありうる話なのではないでしょうか。
しかし、様々な論説を実際に適用できるかは怪しい部分もあります。
人権拡大の歴史と動物の権利保証の関係は別々に考えるべきである。人権の範囲はあくまでホモ・サピエンス内でとどまっており、その他の動物の権利に及ぶものではない。もちろん、無益な殺傷は論外であるが、ワクチンの開発といった大きな利益が見込めるものならば、積極的に用いるべきではないか。
「人権」は人種や民族、性別を超えて誰にでも認められる権利のことを指しますが、当然その字の言う通り、人の権利なのです。それが、その他の動物までにも及ぶのは過剰で、私たちの生活にも大きく支障をきたす可能性があります。
アニマル・ライツといっても、人権で保障される生存権も動物に適用するには、さすがに無理が生じます。
肉食はカニバリズムのような異端者の各印を押され、車でうっかり轢いてしまおうものなら、数年間の禁固が待っています。
また、人間以外の動物といっても、その範囲はどこまででしょうか。愛玩動物といったものは、もちろん適用されましょうが、哺乳類の中でも、特に害獣とされるもの、我々が日常的に殺傷している蚊やゴキブリを省く正当な理由を用意できるのでしょうか。
確かに、人権はホモ・サピエンスという種に限られたものですが、果たしてこの枠組みは権利を持つもの、持たないものを分ける根拠になりうるのでしょうか。
例えば、全遺伝情報であるゲノムでは、ヒトとチンパンジーで99%は一致すると言われている。言語能力も今では、多くの動物にかなり複雑な情報伝達の方法が存在していることがわかってきている。このように、人間と他の動物の間に倫理的に本質的な違いがあると、生物学に基づいて主張するのはどんどん難しくなっている。
文化人類学では、人間とその他の動物を分ける大きな特徴として、言語がよく取り上げられます。私たちの扱う言語に見られる様々な特徴をその他の動物のコミュニケーションには見られないのがその理由なのですが、一方でその他の動物にも複雑なコミュニケーション手段を用いる動物が少なくありません。特に研究が盛んなのがシジュウカラという鳥です。
また、さらに限界事例と呼ばれる人々にも焦点を当てなければなりません。
以上のように、人間とその他動物の区別として「ある能力の有無」を挙げると、人間にも、精神障害者や赤ん坊といった、その能力を持たない個人がいます。
能力を根拠にこのような線引きを行うことは、いささか危険なのです。
おわりに
いかがでしたか。今回はいつもより少し短いです。
賛成派と反対派で、倫理的な違いと生理学的違い、人と動物の間の種の違いと権利を認める度合いの違いの齟齬がありそうだと感じました。
人間とその他の動物においては確かに、種の違いと生理学的な異なりがありますが、倫理的な違いが権利を認めるかどうかにかかっていると反対派は考えていると感じます。
書籍紹介
デボラ・ブラム(2001)『なぜサルを殺すのか―動物実験とアニマルライト』白揚社
今回の議論をやるにあたって筆者が読んだ本ですが、ルポ形式で結構面白かったです。動物実験をめぐるいざこざの歴史がよくわかる一冊だと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
