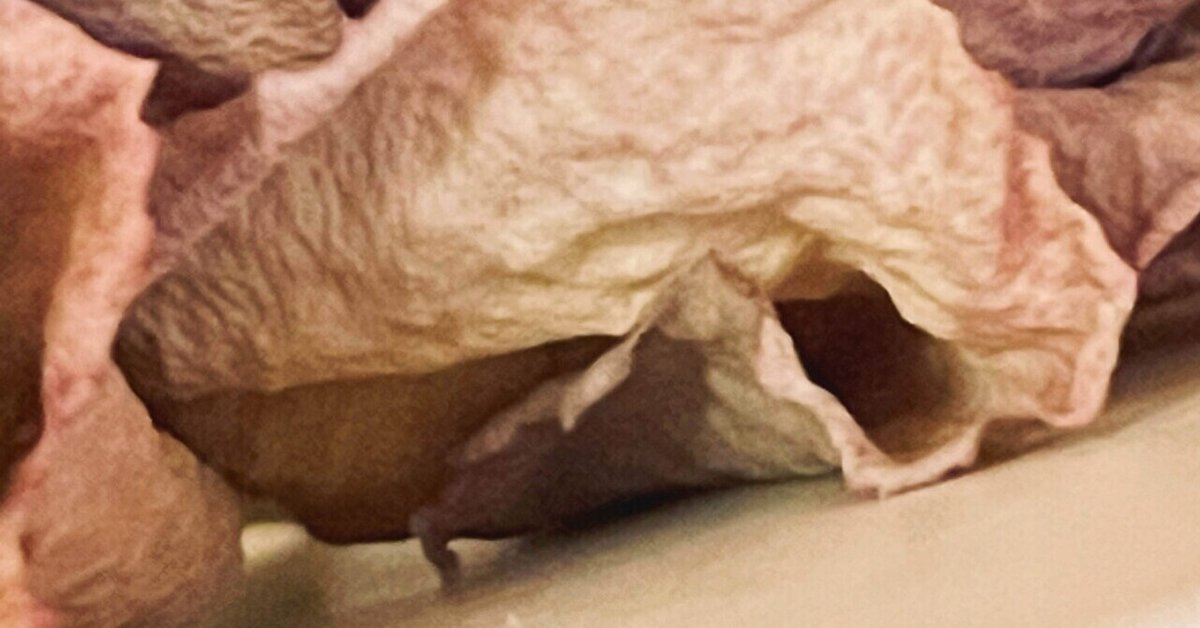
未完
『こころ』のオチが、「実は全部遺書でした」だと知ったとき、悲しさよりも憤りが勝ったことを思い出した。私はそれまで芥川の遺書だけを信じて、それだけが真実であることを願って生きていたから、露骨な罪悪感と、愛だのなんだのと言って死んでいく様は無様だとしか思いたくなかった。先生の朗読は、いつも文章の全てを肯定するから嫌いだ。もっと嫌悪しながら読んでほしい。
段々と、隣の教室の騒がしさが気になった。驚きというか拒絶に近い叫び声が聞こえる。なんというか、異様だ。
ざらざらとした感触が胸に込み上げてくる。なんでかはわからなかったけど、抱き抱えられながら去っていく葵を見てやっと確信した。穏やかな顔をしていた。
誰もいない。換気扇みたいな、空気が振動しているだけの音が耳の中にいる。懐かしい匂いがする。私が生まれてから一番最初に嗅いだ匂い。病室。
葵がここに運び込まれてからどれくらい経ったかは覚えてない。医者に、なんか色々言われたけど覚えてない。ただ、もう助からないということは覚えてる。私たちは今、二人とも制服で、不可逆性の命の消費に抗うこともしないで、空気を共有しあってるだけ。葵の親指に貼ってあった絆創膏が剥がれていて、小さなかさぶたが姿を見せている。他の指に比べて少しだけ長くなった爪はちょっとずつ滑らかじゃなくて、代替品でしかない存在の上でも必死に伸びてる縦の線が、そこに神経が通っていないことを教えてくれる。左手。手首。腕。肘。腕。肩。胸。首筋。喉仏。口。鼻。目。前髪。前髪は私だけ揺れてる。
いつかの約束。学校から直で病院に来て正解だった。リュックの内ポケットに入ってる筆箱と、弁当袋に押し曲げられているスケッチブックを取り出す。病室を歩き回って、両手で四角を作りつつ画角を決めた。無難かもしれないけど、頭が右奥、足が左前。椅子を動かして、HBの鉛筆を動かす。
葵の顔は教室の入り口から見えたときから何も変わっていなかった。口角なんて上がってないのに、不機嫌にも悲しそうにも見えない。
全部沈んでいる。いつもは気づかなかった葵の重さ。
「細いのに、鉛みたいに重そう」
声に出してみても返事はなかった。
星が死ぬときに爆発するって話は私が教えた。あのとき葵はちょっと嬉しそうな顔をして、すぐに怒ったような顔をして、また笑った。理解できなかったけど、今なら少しだけわかるような気がする。葵は爆発なんてしないでほしい。するならせめて、死んだ後にして。鯨みたいに重そうに。
影を描き終わってハッとした。葵はもうすぐ死ぬ、それがすごく嫌だと思った。抱きしめようと思っても壊れてしまいそうでできない。触れたら全部終わる気がする。泣くたびに、いけないことをしている気分になった。
あれからスケッチブックを持って美術室に通うようになった。〇〇号のキャンパスに、あのとき描いたスケッチを貼って絵の具を塗っていく。病室には万緑の葉を生い茂らせて、揺らして、湿らせて、風を吹かせた。
私が葵の臨終で感じたことの全部、脳みその奥の方で描いた。ときどき叫んだり、ペンキを投げ飛ばしたりしてもいい。その方がいい。そうやって私たちは、感性を肯定してきた。君は感性。夏の病室で死に続けている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
