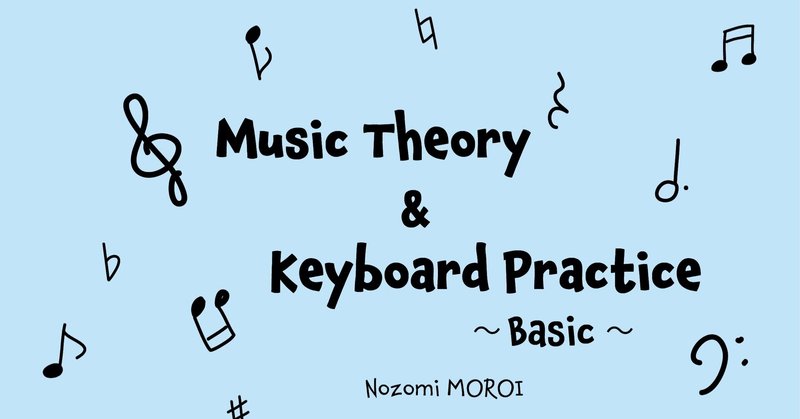
【3】 No.1 アヴェ・マリア
「顔合わせ」である初回。
まず「アンケート」と称し、
・これまでの鍵盤楽器の経験
・好きな音楽のジャンル
・他の楽器の演奏経験
・簡単な音楽に関する質問
(楽語、コードネーム、音階など)
→その場で採点をして、ひとりひとりと会話。名前も覚えます。(覚えようとします。。。)
やっている間にアンサンブルの譜面(このブルグミュラー:アヴェ・マリア)を配って(今回は教科書)見ていて貰ってました。
むり〜〜〜〜やら、私すぐ弾けるもん、と弾き始める人やら色々出てくるので観察しながら、採点を終えます。
そこまでのまとめとして、「色んな人がいる」ということを話し、
ひとつのチームとして、みんなでやっていくことを宣言する!
まず、パート分けをするときに、列ごと、コースごとなど色々あるが、
鍵盤の人たちに負担が重くなるように(!)
余裕のありそうな人たちにはあなたたちが弾けば音楽が進むよ〜とおだてる。
ヘ音記号読めません→じゃあト音記号のところに移動
もうむり〜な人には、2番のパートのAの部分はaとgisしかないので、ここをやらせる、とか。
最初から最後まで弾かせなくても、3つに分けてリレーしてもよいし。
大事な事は、「A durなんてどうしよう、難しい」ではなく、
「なんとわたしは今日A dur の曲を弾いた」です。
これをみんなの力でどうにか美しい音楽にする!
ということを体験して、目的は「みんながいればなんとかなる」
ということです。
みんなの音が軌道に乗って前進する様になったら、
そこで強弱と流れのことを軽くアドバイスして、
その質感と量感と高める。
軌道に乗ってくると放っておいてもそれぞれに上手く弾きたくなり
練習を始めて調子が上がってくるものです。
同音を3つ連打することがモチーフの要になっていますが、
そこも言える感じなら言う。
特にシンコペで同音を連打するところは楽譜は難しく見えるけど
ちょっと半拍遅れているだけだよ〜〜〜〜みたいなことを言うとなあんだ、となります。
先生は「ファシリテーター」であれ。
実は以前は「エーデルワイス」でやっていました。
著作権の問題が難しいので、曲を替えましたが、
この曲はオープンキャンパスなどでも取り上げており、
ハモると美しいので心がひとつになりやすいです。
そうそう、大事な事。
A durの曲なので、スケールのA durのページも開いて、見せたりしてください。
また、これからコードの勉強をするための助走なわけで、
ざっくり言うと、4のパートはベース 123のパートで和音が成り立っている、
ということをさらっと意識させてください。
ここからは和声的な分析の楽譜になります。解釈はいろいろあると思いますが、分析初心者にもわかりやすいように、調の移り変わりの視点から書いています。
また、最初から分析までやる必要はありません。先に進んで該当の進行が出てきたら、このアヴェ・マリアに戻って和音進行の話をするのが良いと思います。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
