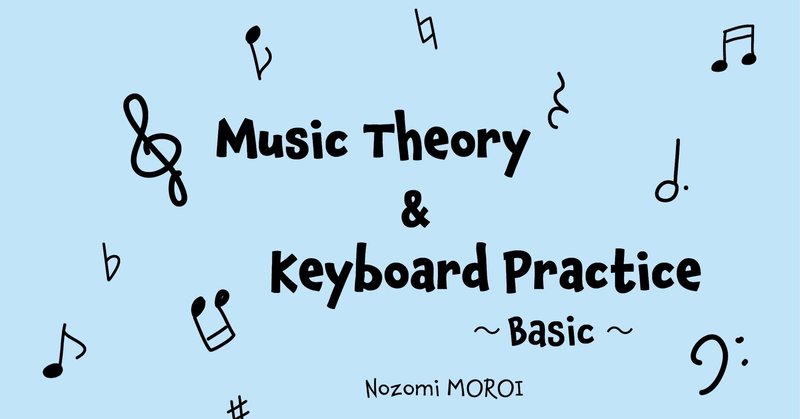
【6】No.4 Music Theory 03 音階・調性
音階・調性は音楽で一番大事なことでありながら、学生が一番面倒に感じてしまうことですね。
本当は一番鼻歌で歌ってできることであり、いつも音階の音の順番が変わっただけのメロディーを感じ取れているので、難しくもなんともないわけですが、、、。
長調の音階は 日本語!と思っている ドレミファソラシド ですから、
まあ、親しみが持てるでしょう。
短調が3種類あるだけですでに面倒くさくなるので、そもそもなんで3つあるのか、という説明をしてしまった方が速いです。どこが半音どこが全音とかそういう問題ではない!
自然短音階 調号通りで自然だね〜。 でもちょっと違和感
和声的短音階 長調でシ→ドと第7音が半音上がって主音に入る。つまり導音から主音。ならば短調でもそうしてしまえ。ということで第7音を半音上げてしまった和声の都合短音階。自然短音階の違和感は半音上がって主音に入っていないからだ。これこそが我ら日本人もドイツ和声がすっかり定着していて、和声的短音階の方が自然に感じているからこその学生の大混乱なのである。
旋律的短音階 いいね、いいね、解決がスムーズになった、、、と思ったら、第7音を含むメロディーがへんてこりんになってしまい、ハーモニーはいいのにメロディーは異国のものになってしまった〜、これはまずい〜と調整。半音上げたら今度そのひとつ下の第6音からの距離が離れた〜。第6音も半音上げてしまえ〜。
なだらかになった〜。旋律の都合じゃ短音階。帰りは主音から第7音なので導音問題はもう関係無い、めんどうくさい、重力に逆らわず下がってしまえ、自然のままでよい〜な下り。
と私は覚えております。。。。
固有和音については、また次回。。。
P.13の短調のポイント

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
