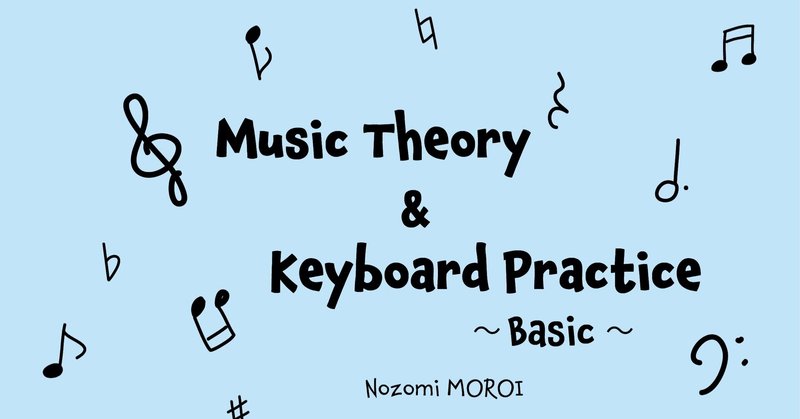
【14】No.9 Music Theory 08 コード進行④ ⅠーⅣ/Ⅴ7ーⅣー○ⅣーⅠ
P.34 の解答例です。
開始の和音は右手の転回形を様々な位置からスタートし、すらすら弾ける様にしましょう。どの位置から弾き始めても「ドーシ♭ーラーラ♭ーソ」を一緒に歌うと良いでしょう。

ここからはP.35の楽曲についてです。
17小節目は左手がありませんが、これは表小節でAのコードでベースはラがある感じです。
18小節目から左手が入ってきますが、後から弾くラの音がベース音であり、17〜24小節はずっとラの上にコードが乗っています。
続いて【四度五度→Ⅳ度→○Ⅳ度】の後、Ⅰ度の2転に入ってそのまま終止のカデンツに繋がります。ここではド→シ♭→ラ→ラ♭(レ→ド♮→シ→シ♭)というラインをベースがやっています。
同主短調から借りたⅣ度(準固有和音)はⅡ度のこともよく見かけます。
その場合ベースはやはりラ♭(ハ長調の場合)になります。Ⅳ度とベース音は同じになりますね。
【35】に楽譜を掲載しています。
内容:コードネーム、和音記号、解説
P.35「コード進行④
P.38「音程①1,2,8度」
P.43「音程②3度」
P.45「音程③4度」
の楽曲の楽譜に和音記号や説明を書き込んだものは【35】からお求めください(有料)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
