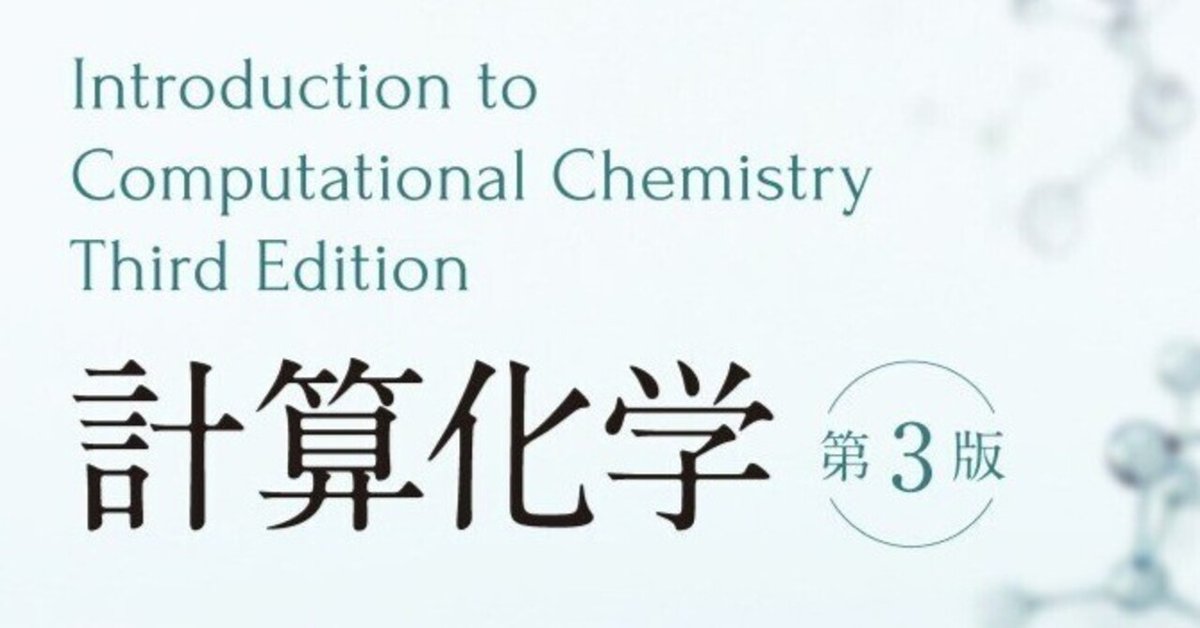
バイブルがついに翻訳!――近刊『計算化学(第3版)』監訳者あとがき公開
2023年3月下旬発行予定の新刊書籍、『計算化学(第3版)』のご紹介です。本書は、計算化学分野の世界的名著Frank Jensen “Introduction to Computational Chemistry, 3rd Edition (Wiley, 2017)”の全訳です。
「監訳者あとがき」を、発行に先駆けて公開します。

***
監訳者あとがき
「計算化学」が書名に現れたのは、1988年に出版された『計算化学ガイドブック:3大分子計算プログラムの解説』(Tim Clark著、大澤映二ほか共訳、丸善出版)が初めてのようです。実際、このころから経験的/半経験的/非経験的分子計算プログラムが化学研究の道具の一つとして、また、これらを駆使して「化学」の課題を解くことが「計算化学」の研究として認知されるようになったと記憶しています。一方、可視化技術の発展とともに分子動力学法に注目が集まり、「分子シミュレーション」という用語も広く使われるようになりました。さらにGaussianプログラムにDFT法が導入された1993年以降には、大きなメモリを備えた計算機の高速化・低廉化によって分子計算プログラムの適用規模が拡大し、国内外のアカデミアだけでなく民間企業でも、それらを利活用する実験化学者が増えていきました。こうして化学研究に不可欠な手法となった「計算化学」は、1998年、Walter Kohn博士とJohn A. Pople博士がノーベル化学賞を受賞されたとき、長い伝統をもつ「化学」の一分野として、ようやくその地位を確立したのだといえるでしょう。
ちょうどその年、本書の原著であるIntroduction to Computational Chemistryの初版が出版されました。ノーベル賞によって計算化学に注目が集まる中、多くの化学者が入門書として購入したのではないでしょうか。しかし、計算化学未経験の実験化学者にとって、読み進めるのはかなり難しかったはずです。なぜなら、この本には、理論や計算技法をよく知っているFrank Jensen博士が、実際に分子計算プログラムを実行した結果に基づいてコメントしている箇所が多いためです。英文は訳せても、意味は不明だったのではないかと思います。また、多少癖のある英語の説明を日本人が正確に理解するのは、計算化学に限らず、どの分野においても難しいことです。そのような意味で、日本語に訳された本書は、計算化学未経験者や初学者であっても、理論を理解しながら、結果の解釈の仕方に慣れながら、読み進めることができると思います。学部化学系コースで物理化学や量子化学をしっかりと学んだ大学院生向けの教科書としても最適だと思います。
原著が出版されて以降、多くの計算化学者がその内容構成を好意的に受け入れてきたと思います。とくに、次世代の計算化学者を育成するという視点で本書の各章を見ると、計算化学を学ぶうえで重要な学修項目がほぼすべて網羅されていることに気づきます。また、計算化学を実際に適用し、その結果を解釈するために必要な知識や知見がとても効率的かつ効果的に修得できるよう、適切にまとめられています。その意味で、計算化学をきちんと体系化した初めての教科書だといえるでしょう。
(中略)
監訳者として、いくつかの点についてコメントしておきます。
本書では、人名に関してはできるだけカタカナにせずに、アルファベットのまま表記することにしました。英語の学術論文をよく読んでいる学生にとっては、そのほうがよいと判断しました。一方で、頭字語や略称でよばれる方法論や手法で、いまだ日本語の専門用語が決まっていない用語については、そのもとになった英文名称をできるだけ日本語に翻訳するようにしました。それは、すでに英語読みが定着している用語に対しても、あえて翻訳することで、その方法論や手法をよりイメージしやすくなることを期待しています。しかしながら、それは英語読みするのをやめようとか、本書の呼び方を定着させようという意図があるわけではありません。なお、「理化学辞典」(岩波書店)や「化学辞典」(東京化学同人)などで訳語が掲載されている専門用語については、できる限りそれらに従っています。
頻出する英単語のいくつかは意図的に訳語を統一しました。たとえば“technique”は、通常「技術」と訳していますが、「○○法」と訳せるところの一部では「技法」を採用しました。また、“surface”については、「曲面」と表記している教科書も多いですが、本書では原則「面」と訳しています。ただし、「表面」とするのが適切な場合はその限りではありません。
最も悩んだのは、“property”に関連する用語の訳語として「物性」を使うかどうかです。「物性」とは、マクロな物質固有の性質や物理量(実験値)を意味し、日本語の教科書などではよく使われていますが、英語訳が定まっているわけではありません。また、原子・分子レベルの性質、あるいは電子論から導かれる物理量に対して使うことには違和感があります。そこで本書では、“property”に関しては、原則「特性」という訳語を採用することにしました。
翻訳にあたり、訳者一同は、原著者の意図や真意をできるだけくみ取りつつ、なるべく平易な言葉を用い、理解しやすい文章になるよう努力したつもりです。また、教科書としての利用を重視して、各章で現れる同じ用語や表現が訳者間で異なっていた箇所は、監訳者として統一するように努めました。力至らず不備な点も多々あると思います。そのような箇所を見つけましたら森北出版にご連絡ください。本書がさらによいものになるようご協力いただければ幸いです。
(以下略)
***
オーフス大学 フランク・ジェンセン(原著)
豊橋技術科学大学 後藤仁志(監訳)
横浜市立大学 立川仁典(監訳)
横浜市立大学 長嶋雲兵(監訳)
豊橋技術科学大学 五十幡康弘(共訳)
長岡技術科学大学 内田希(共訳)
岐阜大学 神谷宗明(共訳)
横浜市立大学 北幸海(共訳)
北海道大学 小林正人(共訳)
京都大学 佐藤啓文(共訳)
筑波大学 重田育照(共訳)
京都大学 砂賀彩光(共訳)
北海道大学 武次徹也(共訳)
神戸大学 常田貴夫(共訳)
北海道大学 長谷川淳也(共訳)
東京都立大学 波田雅彦(共訳)
茨城大学 森聖治(共訳)
世界中で親しまれてきた計算化学のバイブル、待望の翻訳!
全19章、900ページ超の大ボリュームで、力場法、分子軌道法、密度汎関数法など、多岐にわたる手法を網羅。各手法の基礎理論だけでなく、手法どうし、あるいは手法内でパラメーターを変更した場合の計算結果も詳細に提示されているので、GaussianやGAMESSを使う際の手法選択のよりどころになるでしょう。
大学院生や研究者の方のリファレンスに最適な一冊。
[原著]Introduction to Computational Chemistry, 3rd Edition (Wiley, 2017)
【目次】
第1章 序論
1.1 基本事項
1.2 系の記述
1.3 基本力
1.4 運動方程式
1.5 運動方程式の解法
1.6 変数分離
1.7 古典力学
1.8 量子力学
1.9 化学
第2章 力場法
2.1 はじめに
2.2 力場エネルギー
2.3 力場パラメーターの作成
2.4 全原子力場の違い
2.5 水モデル
2.6 粗視化力場
2.7 計算上の留意事項
2.8 力場の検証
2.9 実践的考察
2.10 力場法の利点と限界
2.11 遷移構造モデリング
2.12 ハイブリッド力場の電子構造法
第3章 Hartree–Fock理論
3.1 断熱近似とBorn–Oppenheimer近似
3.2 Hartree–Fock理論
3.3 Slater行列式のエネルギー
3.4 Koopmansの定理
3.5 基底関数近似
3.6 変分問題の代替定式化
3.7 制限Hartree–Fockと非制限Hartree–Fock
3.8 SCF法
3.9 周期系
第4章 電子相関法
4.1 励起Slater行列式
4.2 配置間相互作用
4.3 CIによる電子相関とRHF解離問題の説明
4.4 UHF解離とスピン混入問題
4.5 大きさに対する無矛盾性と大きさに対する拡張性
4.6 多配置自己無撞着場
4.7 多参照配置間相互作用
4.8 多体摂動論
4.9 クラスター展開
4.10 クラスター展開法,配置間相互作用法,摂動理論の間の関連性
4.11 電子間距離をあらわに考慮する方法
4.12 計算効率を改善するための技法
4.13 電子相関法についてのまとめ
4.14 励起状態
4.15 量子Monte Carlo法
第5章 基底関数系
5.1 Slater型軌道とGauss型軌道
5.2 基底関数系の分類
5.3 基底関数系の構築
5.4 標準的な基底関数系
5.5 平面波基底関数系
5.6 グリッド基底関数系とウェーブレット基底関数系
5.7 フィッティング基底関数系
5.8 計算上の問題
5.9 基底関数系の外挿
5.10 複合的外挿法
5.11 等電子対反応と等結合反応
5.12 有効内殻ポテンシャル
5.13 基底関数重ね合わせ誤差と基底関数不完全誤差
第6章 密度汎関数法
6.1 軌道を使わない密度汎関数理論
6.2 Kohn–Sham理論
6.3 縮約密度行列法
6.4 交換–相関孔
6.5 交換–相関汎関数
6.6 密度汎関数法の性能
6.7 計算の考察
6.8 密度汎関数理論とHartree–Fock理論の違い
6.9 時間依存密度汎関数理論(TDDFT)
6.10 アンサンブル密度汎関数理論
6.11 密度汎関数理論の問題点
6.12 最終考察
第7章 半経験的方法
7.1 2原子微分重なりの無視近似
7.2 微分重なりの中間的無視近似
7.3 微分重なりの完全無視近似
7.4 パラメーター化
7.5 Hückel理論
7.6 強束縛密度汎関数理論
7.7 半経験的方法の性能
7.8 半経験的方法の利点と限界
第8章 原子価結合理論
8.1 古典的な原子価結合理論
8.2 スピン自由度を考慮した原子価結合理論
8.3 一般化原子価結合理論
第9章 相対論的方法
9.1 Dirac方程式
9.2 Dirac方程式とSchrödinger方程式の関係
9.3 多電子系
9.4 4成分法の計算
9.5 2成分法の計算
9.6 相対論的効果
第10章 波動関数解析
10.1 基底関数に基づく電子密度解析
10.2 静電ポテンシャルに基づく電子密度解析
10.3 密度分布に基づく電子密度解析
10.4 局在化軌道
10.5 自然軌道
10.6 自然軌道解析における計算上の考慮
10.7 解析例
第11章 分子特性
11.1 分子特性の例
11.2 摂動法
11.3 エネルギー微分法
11.4 応答方程式法および伝播関数法
11.5 Lagrange法
11.6 波動関数応答
11.7 電場摂動
11.8 磁場摂動
11.9 幾何学的摂動
11.10 時間に依存する摂動
11.11 回転および振動補正
11.12 環境効果
11.13 相対論的補正
第12章 概念の例示
12.1 構造の収束性
12.2 全エネルギーの収束性
12.3 双極子モーメントの収束性
12.4 振動数の収束性
12.5 結合解離曲線
12.6 変角曲線
12.7 問題のある系
12.8 C₄H₆異性体の相対エネルギー
第13章 最適化技法
13.1 2次関数の最適化
13.2 一般的な関数の最適化:極小点探索
13.3 座標の選択
13.4 一般的な関数の最適化:鞍点(遷移構造)探索
13.5 制約付き最適化
13.6 大域的極小化とサンプリング
13.7 分子ドッキング
13.8 固有反応座標法
第14章 統計力学と遷移状態理論
14.1 遷移状態理論
14.2 Rice–Ramsperger–Kassel–Marcus理論
14.3 動力学的効果
14.4 統計力学
14.5 理想気体,剛体回転子–調和振動子近似
14.6 凝縮相
第15章 シミュレーション技法
15.1 Monte Carlo法
15.2 時間依存法
15.3 周期境界条件
15.4 シミュレーションからの情報抽出
15.5 自由エネルギー法
15.6 溶媒和モデル
第16章 定性的理論
16.1 フロンティア分子軌道理論
16.2 密度汎関数理論から導き出される概念
16.3 定性的分子軌道理論
16.4 エネルギー分割解析
16.5 軌道相関図:Woodward–Hoffman則
16.6 Bell–Evans–Polanyi原理/Hammond仮説/Marcus理論
16.7 More O’Ferrall–Jencks図
第17章 数学的方法
17.1 数値,ベクトル,行列,テンソル
17.2 座標系の変換
17.3 座標,関数,汎関数,演算子,超演算子
17.4 規格化,直交化,射影
17.5 微分方程式
17.6 関数の近似
17.7 Fourier変換とLaplace変換
17.8 表面
第18章 統計とQSAR
18.1 はじめに
18.2 統計処理の基礎
18.3 二つのデータセットの間の相関
18.4 複数のデータセットの間の相関
18.5 定量的構造–活性相関(QSAR)
18.6 非線形相関法
18.7 クラスタリング
第19章 おわりに
付録A 記号
付録B 変分原理
付録C 原子単位
付録D Z-マトリックスの構築
付録E 第1量子化と第2量子化
監訳者あとがき
索引
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
