
「週刊少女コミック」の萩尾望都 Ⅱ 『萩尾望都初期作品集』上 宝の山だ
1、昔のマンガが今の雑誌に?
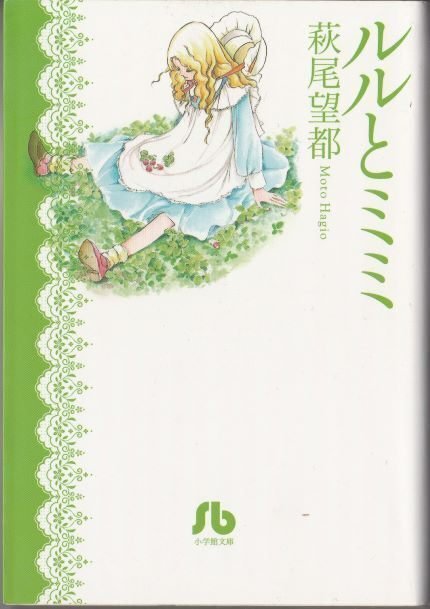
小学生のころ、妹が買った「週刊少女コミック」をパラパラめくっていたら、萩尾望都の短編マンガが載っていた。作品はもう覚えていないが、ドタバタコメディだった気がする。
お話が、他の少女マンガのラブコメのようなウエットな感じがなくて乾いている、キャラクターがクール(ハリウッド映画のコメディみたいとか言われたと思う)。ただ絵はちょっとだけ古い感じがした。
そしてページの枠に、こういう文字が書かれていた。
萩尾望都初期作品集。
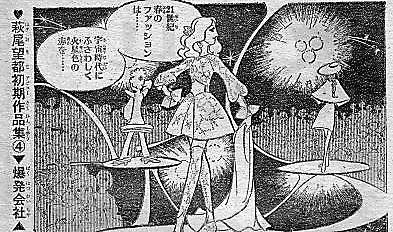
萩尾望都がデビュー当時に描いた作品が、再録されていたのだった。
『ルルとミミ』でデビューしてしばらく、萩尾望都の発表の舞台は「なかよし」(講談社)だった。その当時のマンガが『萩尾望都初期作品集』という名目で「週刊少女コミック」に連続して再掲載された。
萩尾望都のデビューが、少女マンガ雑誌の中でも低年齢層向けの「なかよし」というのは、意外というか今では信じられない。雑誌のカラーと合わなかっただろうなと思うけど、実際描いても描いてもボツになってたらしい。
その後「少女コミック」(小学館)に移籍したことで、才能を十分に表現する場所を与えられた。
そこら辺は『一度きりの大泉の話』(萩尾望都)『少年の名はジルベール』(竹宮恵子)を読むと書いてある。

マンガの中身は外国を舞台にしたコメディが多くて、日本の女の子を主人公にした、同じ雑誌の他の作品とちょっと違う感じだったと思う。
ただ、それよりも当時気になったのは「初期作品集」という文字。特に「初期」の上に《デビュー》とルビが振って有る、
昔のマンガ、それもデビュー当時の作品が今の雑誌に載ってる? 雑誌というのは新しいマンガをよむモノでしょ、古い作品はコミックス(単行本)で読むのがあたり前のはず。
デビュー当時の作品なら、絵もお話も今より未熟な筈、それがわざわざ再録されてる。
「おかしい、ありえない」子供だったけど、そういう気持ちになった。
デビュー作『ルルとミミ』が1969年、それが「週刊少女コミック」に再掲されたのが1973年、だから4年前の作品

”4年前”はこの歳になると最近なんだけど、当時小学生だった自分には大昔。
マンガというのはそういう子供に向けた、良く言えば時代の変化流行を敏感に取り入れるもの、悪く言うと読み捨てるものだったから、4年前のマンガは昔のマンガという感覚だった、だからちょっと絵が古いと思ったのだ。
そういう当時の自分からみて昔のマンガが、周りを新作に囲まれて雑誌に載っているのが不思議だった。
この人のマンガは、他の読み捨てられるマンガと違うのかもしれない。
すくなくともこの雑誌では、そういう扱いを受けている。
萩尾望都という名前を意識した最初だったと思う。
2、小学館に移籍

その後、萩尾望都が少女マンガの神様になったので、『萩尾望都初期作品集』に対する違和感もあまり無くなった。
ただ、マンガファンになってから気が付いたのだけど、デビュー当時の講談社「なかよし」に掲載された作品が、小学館「週刊少女コミック」に再掲されている。出版社が違うのになんでと、ぼんやりと思っていた。
『一度きりの大泉の話』によると、講談社でボツになった原稿を竹宮恵子に送ったところ、そこから小学館の山本順也氏に紹介されたという。
「萩尾さん。講談社でボツになったという原稿を私(竹宮恵子)に送れば、小学館の山本順也さんに渡してあげる、小学館の雑誌の『少女コミック』は今、新しい描き手を探しているから」
一方、大牟田から。桜台の竹宮先生宛に講談社のボツ作品を送りました。(中略)
竹宮先生はそれらの原稿を読んだ後、山本順也さんに渡してくれました。本当にお世話をかけたと思います。ありがたかったです。
ほどなくして山本さんから「全部買ってやる。すぐには載せられないが、おいおい考える」との返事がありました。
結局、萩尾さんはその後も同じようにボツになってしまうことが何度かあり、私は、「Yさんに相談してみれば?」と小学館に作品を持って行くように誘った。
これはあとからだれかに聞いたことなのだが、Yさんは彼女の作品を見るなり「ボツになった作品は、小学館がすべて買い取ります」と言ったそうだ。
少女マンガファンならともかく、そうでは無いだろう大人の男性が、この時点で萩尾望都の才能を見ぬいて、さらに「全部買ってやる」と即決したのはスゴイ。実際、講談社の編集者には見抜けなかったワケで。
ただ、ここで萩尾望都も竹宮恵子も、山本順也氏が「ボツになった作品を全部買う」と言った、とだけ書いてる。
しかし、『萩尾望都初期作品集』で再録されたのは、「なかよし」その他に一度掲載された作品で、ボツではないんだけど、それはどういうことなんだろう。
ボツになった作品だけではなく、掲載された作品の権利も買い取ったということなのだろうか。
その後、萩尾望都は講談社から小学館に移籍する。
『ケーキ ケーキ ケーキ』を描き終えた頃、講談社の編集者に会い、小学館に移ろうと思っていることを話しました。
担当編集者からは「あなたはあまり『なかよし』に合わないと思うし、他にないかなあと考えていたんだよ、小学館は良いかもしれないね」とすんなり了解していただき、ほっとしました。
こうして萩尾さんの小学館デビューが、あっという間に決まった。
「ほらね、やっぱり!」と、私は、ライバルと認める仲間が受け入れられたことに心から満足しつつ、同時に「すごいな。そんなことってあるんだ!」と素直に驚きもしていた。
作家の人が出版社と揉めて、版権を引き上げて別な出版社に移るみたいな話は、聞いたことが有るけど。作家が移籍したら、作品の権利も一緒についていくものなのか?
萩尾望都竹宮恵子、あるいは出版に関わるひとにとっては、あたり前すぎることなので書いていないのだろうか。そこの疑問は解消されてない。
3、宝の山だ

小学館に移籍してから、順調に作品を発表する。
萩尾望都は、短くても良いなんでも良いから毎月描かせてくれと言う。
とりあえず、小学館に行って山本さんに「どんなのでも良いから仕事をください」とお願いしました、カットでもなんでも、できれば毎月仕事をください、8ページでも16ページでも良いから。
頼み込んで、細かい仕事を拾っていたような書き方をしている。
これが竹宮恵子から見ると、山本順也氏のほうから特別扱いにしてるように見える。
特にYさんが直接仕切る『別冊少女コミック』では、「何ページであろうと、萩尾には自由に描かせる。ページ数が少なかろうが、多かろうが、とにかく毎月、萩尾だけは載せる」という方針を立てていた。
山本順也氏は実際、どの程度萩尾望都を特別だと思っていたのか。
こういう証言があった。
講談社でボツにされたコンテを萩尾望都が持ち込んできたとき,編集者の山本は「宝の山だ,次の時代に活躍する」と大きな驚きを感じたと伝えられています。
かなり入れ込んだのだろうというのが分かる。
一方萩尾望都にとっての山本順也氏は、
アラン・レネの特集もやっていたので観に行きました。言葉にならない思い、伝わらない思いを何とか告げようと傷ついた二人の人間が見つめ合っていました。あまりに悲しくて長い溜息ばかりが漏れました。どちらも素晴らしい映画でした。改めて山本さんの美意識の確かさに感心しました。
山本さんは褒めもしないし、作品に注文もつけない。しかし、しっかり読んでくれていて、小学館に移って以来、信頼のできる編集者さんでした。
仕事相手として信頼できるだけでなく、美意識、感性が合うと感じている。
萩尾望都は、山本順也氏とは相性が良かったけど、他の編集者とはそうでも無かったらしい。
実際、時々他の編集さんから「山本さんが言うから萩尾さんを使っているんだよ」とか、「萩尾さんの作品乗っけて良いのかって編集部内で言っているんだよ」など、お荷物になっているようなことを聞いていたんです。
昔は、大学出て出版社に入って、少女マンガ雑誌に回されるとガッカリするという話があった。
少女マンガ好きだった当時の自分には、その感覚が分からなかった。
今考えると、出版社を志望するのだから多くが文学青年だろうし、小説家の担当になりたかっただろう。『あしたのジョー』や劇画ブームがあって「大学生もマンガを読む!」と言われてた時代だから、せめて少年(青年)マンガ雑誌だったらやる気を出したかもしれない。
少女マンガは少年マンガのさらに下と言う感覚があったから、当時の編集者(の男性)が、少女マンガに熱意が無かっただろうというのは、今ならわかる。
そうなるとマンガの評価は、読者の人気、雑誌の売り上げだけになる。
アンケート調査の順位が良くなかったという、当時の萩尾望都を、お荷物と考えてもおかしくはない。
講談社「なかよし」の編集者も、同じ感覚だったのだろうけど作品をボツにしていた。
そんな中で、萩尾望都マンガを「宝の山」と感じた山本順也氏との出会いは、奇跡のようなものだったのだな。
萩尾望都が信頼した、山本順也氏の美意識の確かさから来るものか。
仕事として、与えられたことだけをやっている他の編集者とは、違う目を持っていた。
これが無ければ萩尾望都は、70年代の前半一時期作品を発表してそのまま消えた、幻のマンガ家になっていたかもしれないなと思う。
(そしたら多分、今、山田玲司のYoutubeできたがわ翔に「『萩尾望都』っていう変わった名前のマンガ家がいたんです、これペンネームじゃなくて本名なんですよ。マンガ家や一部のマニアには注目されてたんだけど、すぐにいなくなっちゃって」とか言われてただろうな。)
続く
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
