
『海街diary』は何故”名作”なのか① -吉田秋生作品の思い出-
吉田秋生作品と私
1、『少女たちの覚醒』

ちくま文庫「現代マンガ選集」の少女マンガ編、作家恩田陸が選んだ【少女たちの覚醒】と言う本、”現代マンガ”という括りなのに、選ばれているのは殆ど1970年代の作品と言う偏った選集。

70年代って、いわゆる「24年組」とそのフォロワーの人達が活躍し「少女マンガ」に限らず、マンガ表現を革新した時代。少女マンガが時代の最先端だった。
1963年生まれの恩田陸がその時代に思春期を過ごし、その時代の少女マンガに今でも特別な思い入れが有るのは、すごく良くわかる。
でも70年代って殆ど半世紀前なワケで、全然「現代マンガ」じゃない。
その選集の中で唯一”現代”の作品として選ばれてるのが、『海街diary』第一話「蝉時雨のやむ頃」(それでも2006年作品)。
”他が70年代の作品なのに、なぜコレだけ今の作品?”と思う。
その理由を恩田陸は
当時私が読んでいた少女漫画が目指していたもの、あるいは当時私が少女漫画に求めていたものの完成形がこれなのではないか、と思ったからだ。
『少女たちの覚醒』より恩田陸の解説から
と説明している。
確かにヒット作で映画にもなったし、自分も大ファンなのだが、そこまで言う作品だろうか?とはおもう。
しかし、その理由はともかく「海街diary」と言う作品を入れたかった、その気持ちはちょっと分かる気がする。
2、吉田秋生の”新しさ”
1970年代、萩尾望都竹宮恵子に代表される”24年組”によって少女マンガが革新された。その一つが男性(少年)を主人公にしたマンガを描いたこと、男ばっかりで女性がほとんど出て来ない作品もいくつも有った。
70年代後半にデビューした吉田秋生も、男性が主役のマンガを描いたけど、それまでのマンガとは違う点が二つあった。
1、アメリカを舞台にした
2、リアリティのある男の子を描いた
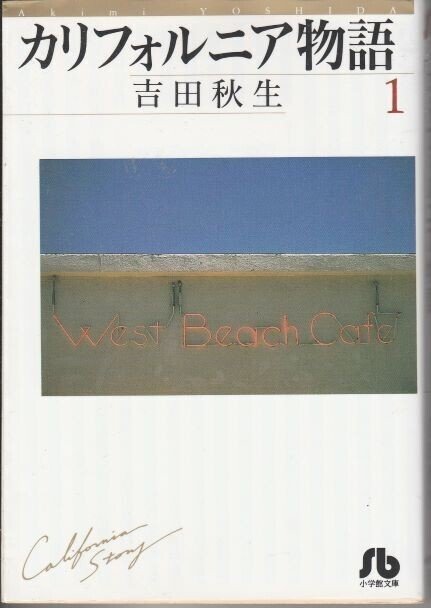
1、は『カリフォルニア物語』、それまでの少女マンガの外国と言えばヨーロッパだったのに対しアメリカが舞台。しかもヒッピーというか、比較的底辺あるいはドロップアウトした若者を主人公にした。
それは”アメリカンニューシネマ”の影響と当時から言われていて、当人も認めている。
少女マンガで外国を舞台にする場合は、読者女性の”憧れ”を描くワケだから、なるべく現実(日常)とは距離が有った方が良い。
アメリカは、映画TVドラマやニュースで情報が沢山有ったし、何よりも米軍基地が日本各地に有ったから、日本でよく見かける「外国人」(「外人」というのが適当な気がする)は基本アメリカ人だった。
アメリカは”憧れ”を持つには、自分たちに近すぎる感覚が有った。
だからそれまでの少女マンガは、アメリカはあまり舞台にせず日本と距離が有るヨーロッパを舞台にしたし、登場人物も中流以上(貴族階級というのも良く有る)にした。
アメリカを舞台にし、底辺の若者を主人公にした『カリフォルニア物語』は、それまでと違う、少女マンガに、よりリアルな舞台を持ち込んだ感じがした。
2、は『河よりも長くゆるやかに』

若い男の子の生理感覚を、リアルに描いていると、当時言われた。

24年組その他の”少年”主人公は、自分達日本人の日常とは関係ない”憧れ”の存在だった。又当時女の人には”女だからダメ”と言われて出来ない事が多かった、なので少年を主人公にする事で、代わりにやりたい事をやり、言いたいことを言わせるようにした、つまり自分の分身。
それまで少年を主人公にした少女マンガの”少年”は「頭で想像した”憧れ”であり、理想の”自分”だった。
その少女マンガの世界に、吉田秋生は”自分の周りにいる”男の子を観察、あるいは”自分の付き合った”経験から描いている感じが有って、それが新しい感じがした。

あと、遠い異国の憧れじゃない、自分の隣にいるリアルな”外人”である米兵。

それは少女マンガが80年代になって、より身近な物語を求めるようになっていった時代の流れと合っていた。70年代に人気のあった作家がパワーダウンした80年代に、次々と話題作を発表するようになる。正しい方向性だった。
世の中的にはそうなのだけど。自分にとっては、そこで描かれたような、いわゆる”普通の男”は周りに山ほど居て、そういうのとは別な物が見たくて現実離れした少女マンガを読んでいたのに、そこでも「リアルな男」を見せられるのかとあまり嬉しくなかった。そして又そういう吉田秋生作品が、特に上の世代のマンガ好きの男に評価が高いのも面白くなかったな。
なので、吉田秋生のマンガ、読めば「面白い」のは確かなんだけど、無条件に「好き」とは言えない気持ちが有った。
だから80年代になって、徐々に少女マンガ全体を読まなくなった。
【少女たちの覚醒】で70年代少女マンガを選んで、80年代以降は選ばなっかった恩田陸も、同じような感覚が有ったのでは。
3、『吉祥天女』の居心地の悪さ

吉田秋生作品には語りづらいところ、居心地の悪いところが有る。その中でも特に『吉祥天女』は男には辛い作品だな。
男の持つ暴力性。女性を無理やりモノにしようと言う肉体的な。社会の中心に居る男たちの、その力によって女性を従わせようとする権力的な、様々な暴力性。今では、そんな物をストレートに表に出す男達は居ない。当時でも良くない事、時代遅れな事では有った。それを閉鎖的な田舎町を舞台にする事で、「女に舐められるのは許せねえ」みたいな事を露骨に言葉にし、女性をレイプしようとする不良グループや、女性を政略の道具として利用する、旧家や建設会社一家等、土地の権力を描くことで、男の暴力性を描いている。
そういう世界で、主人公小夜子を肉体の力や権力で支配しようとする男たち、彼女は頭脳と不思議な能力で男たちに逆襲する。

その復讐劇、男に嫌な思いをさせられたことのある女性から見たら痛快なのかもしれない。
女の人にとっては、男の暴力性は100%自分の外側に合って、理不尽に自分を傷付けようとするものだから、無くなってくれた方が良い。
でも男にとって、その暴力的な衝動は自分の内側にも存在する。女性に意見されてムカッとしたり、自分に肉体的社会的な力が有ったらイイ女をモノにできるのに、みたいな感覚は有る。それをストレートに出すことを気にしないか、そうじゃ無いかの違いだけで、内面に違いが有る訳じゃ無い。
『吉祥天女』を読みながら、暴力的な男どもが小夜子に逆襲されて破滅していくのは当然だと思いつつ、その男に対する怒りあるいは冷たい視線に居た堪れない気持ちになる。
中島みゆき「ファイト!」と言う曲の中で
”あたし男だったらよかったわ 力づくで男の思うままに ならずにすんだかもしれないだけ あたし男に生まれればよかったわ”
と言う部分が有って、この曲の他の部分は傷つけられた側と自分を一体化して”ファイト!”と拳を突き上げる事が出来るのだが、ここにくると、どうしても自分は傷つける側になるので口ごもってしまう。
作中の同じようなセリフ。

この作品に居心地の悪さを感じている人が、自分以外にも居る。
文庫本2巻の解説の呉智英。
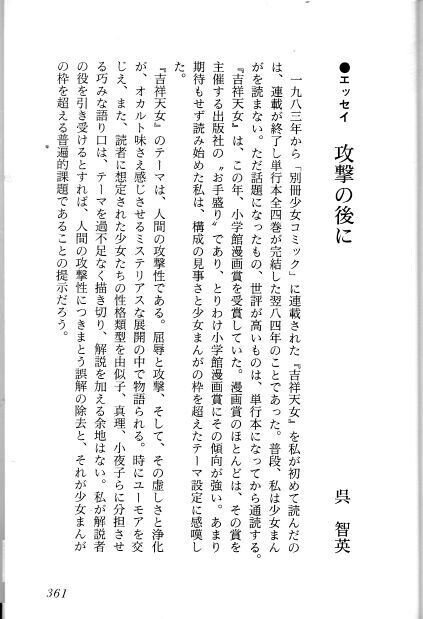
男の攻撃性を、”遺伝子”と言うか、自然科学的な理由で説明する考え方を否定したうえで。旧ソ連(ロシア)によるシベリア抑留の話を始める。
ソ連の捕虜収容所で日常的に絶え間なく行われて居たのは、女性看守による性的虐待である。・・・・・・
男女平等を謳う共産主義思想により社会進出を果たし、かつ銃まで手にした女たちは、・・・それまで因習と迷信の中で男にしか出来ないと思われてた強姦を、彼女たちはやすやすと成し遂げたのである
今のウクライナ侵略でもロシアは、戦争とは直接関係ないレイプ虐殺拉致略奪をしているので、成る程そんな事が有ったのかと納得はできる。
”男の暴力性と思われている物は、男の肉体のせいじゃない。女だって権力を持てばするんだ”と言っている。それはそうかもしれない。しかしその後に「小夜子に”凌辱”された男性達」も、とソ連の女性看守と、小夜子のやった事が同じであるかのように、書いてる。このマンガの中で小夜子は、彼女に惹かれる男たちの性欲を操って破滅させるという、古典的な悪女のキャラで、ここで書かれている、ソ連の女性のやった事とは違う。なので説得力が無い。
普通に読めば関係ない、ソ連の女性兵士の例をワザワザ出したのは、呉智英がここで指弾される”男の暴力性”に、居心地が悪い気持ちが有ったのだ。なので、それを何とか相対化しようとしたのだなと、最初読んだ時に思った。
マンガをダシにして、あまり関係ない持論を語るのは、自分の本などでやるのは自由だけど、それは『吉祥天女』というマンガの「解説」か?と同時に思った。今回見返すと、解説では無くエッセイと逃げている。
4、その後

80年代になると、少女マンガもファンタジーより現実の女の子のリアルを描く方向に行った。女じゃなく年齢も上になった自分には、感覚が合わなくなったので、徐々に読まなくなった。
その後の吉田秋生作品は『BANANA FISH』『YASHA-夜叉ー』は、後からマンガ喫茶で読んだくらい。面白かったが、今時の若者のリアル路線から離れて完全なエンターテインメント路線に行ったなと思った。同時に大友克洋風キャラから、いかにも少女マンガな美少年キャラを出すようになった。『イヴの眠り』は本屋で『月刊フラワーズ』を立ち読みしたが、アクションマンガで女の子を主人公にするのは、ちょっと無理が有った感じ。
その『月刊フラワーズ』での次の作品が『海街diary』(やっと辿り着いた)。

しかし最初の頃の記憶はあまり無い。最初は地味で印象に残らなかったからか。本格的にハマったのは、海猫食堂のオバチャンが余命何カ月で、という辺りからだった。
この作品は本当にハマった。雰囲気が実にいいのだけど、それって具体的に何なんだろう。何が良くて「好き」になった?
続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
