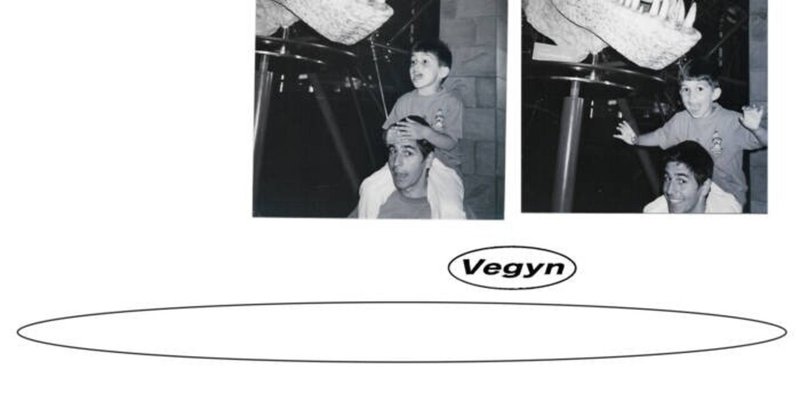
エレクトロニカは何を夢みたのか?⑦/エレクトロニカの後を埋めるOPN、そしてVegynで感じたエレクトロニカの残像
※有料に設定していますが全文読めます。
エレクトロニカの後を埋めるサウンド
2004年ごろにエレクトロニカのムーブメントが収束した後、継続して活動を行う人も少なからずいたが、リスナーの多くは離脱していった。そんな中で00年代後半に登場し全方向にエクスペリメンタルな音楽を奏でていたキーパーソンがチャック・パーソン名義で作品を発表していたダニエル・ロパティンだったと思われる。彼の活動の最初期は、2010年代初頭のYoutubeカルチャーとして台頭したヴェイパーウェーヴの始まりを告げた2010年のアルバム「Eccojams」があり、このアルバムの元になったデモ音源「Collected Echoes (2004-2008)」が、タイトルにあるようにエレクトロニカが終わった2004年以降のシーンを示唆するように思えてこの流れで考えると面白い。
Chuck Person/Collected Echoes (2004 - 2008)
ただしヴェイパーウェーヴ自体は90年代のヒューストンのヒップホップシーンから生まれた、チョップド&スクリュードというレコードの回転数を落としてサンプリングしたダウナーでドラッギーな手法を用いていて、エレクトロニカとは無関係なジャンルである。2016年にバリー・ジェンキンス監督の映画「ムーンライト」のサウンドトラックで取り上げられて、再び注目を集めていたのも記憶に新しい。
ロパティンはジャック・パーソンと並行してワンオートリックス・ポイント・ネヴァー(以下OPN)を始動させ、以降こちらのユニットを中心に活動を行なっている。OPNの音楽はとにかく掴み所がなく、タンジェリンドリームのような電子音やドローン、ノイズ、ここ数年ブームとなっているニューエイジも含んだ如何とも形容しがたい音を奏でている。そんなOPNが2010年にメゴ(エディションズメゴ)からアルバムをリリースしていた。
Oneohtrix Point Never/Returnal
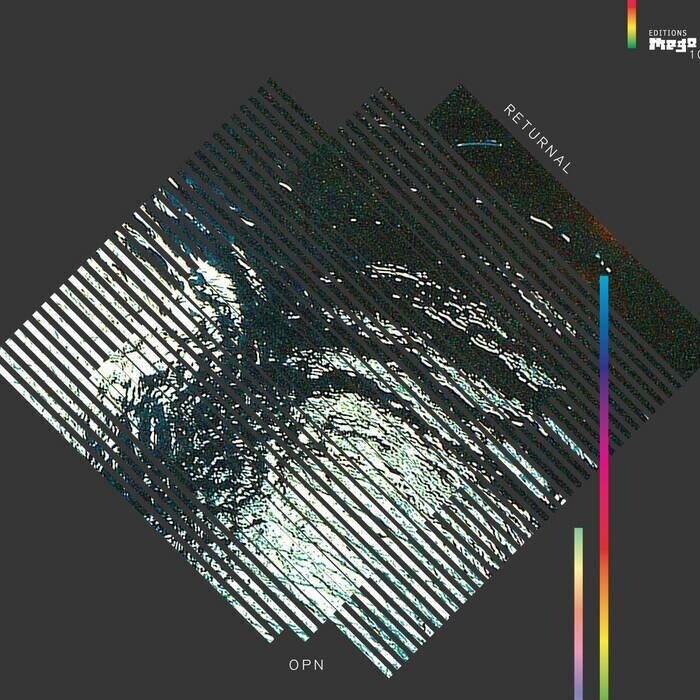
冒頭の「Nil Admirari」はグリッチというよりもハーシュノイズに近いサウンドではあるが、その後の「Describing Bodies」や「Stress Waves」ではグラニュラーなアンビエントドローンが奏でられてる。エレクトロニカで括るにははみ出るものも多いが、フェネスのサウンドのその先にあるサウンドを提示した一枚とも言える。実際にフェネスもリミックスで参加している。
OPNはその後ワープと契約し現在に至るが、他にもサントラも手がけていて、サフディ兄弟による映画「グッドタイムズ」では80年代風のシンセのシーケンスが走り、「アンカット・ジェムズ」ではニューエイジなアルバムを制作している。ブルックリンをベースにしている事もあり、東海岸ベースなのにやってることは西海岸のニューエイジカルチャーが濃厚という変わった感覚を持ち合わせているが、その感じが今のアメリカっぽい感じがある。
ヴィーガンに感じられるエレクトロニカ
Vegyn/Only Diamonds Cut Diamonds 2019年
2016年にリリースされたフランク・オーシャンの「ブロンド」と「エンドレス」に参加し注目を集めたサウスロンドン出身のヴィーガンことジョー・トーナリー。その後2019年にアルバム「Only Diamonds Cut Diamonds」がリリースされ一部で話題になっていたが、最初に耳にした時にかつてあったエレクトロニカの雰囲気があり驚かされた。と言ってもジェイペグマフィアが示しているように、彼のベースはどちらかと言えばヒップホップがベースにあって、回転数を落としたスクリューによるサンプリングなど、ヴェイパーウェイヴやチルウェイヴ(どちらも10年代前半には収束したがチルな感覚は10年代を通して続いていた)といった10年代のサイケデリックカルチャーを締めくくる一枚であったと感じられる。翌年の2020年はコロナ禍で音楽界隈は活動自粛の最中での表現にシフトしてしまったため、10年代のチルな感覚は分断されて別の次元にシフトしてしまった。本来であれば2020年はチルムーブメント以降の新しい波が現れるタイミングだったと思うが、社会的な変化によるパラダイムシフトが起こってるため、今後の流れは大きく変わってくるのではないかと思う。
ヴィーガンのこのアルバムは厳密にはエレクトロニカとは言えないが、これまで紹介してきたグリッチやクリックの範疇から漏れてしまったポストロックとエレクトロニカの中間に位置する音楽を感じさせる。
ここではグリッチ/クリック、マイクロサウンド、フォークトロニカの範囲で収めきれなかったアルバムを紹介して終わりたいと思う。具体的にはポストロックとエレクトロニカの中間に位置するような人たちを取り上げたい。
Mouse On Mars/Niun Niggung

エレクトロニカというにはポストロック寄りだし、ポストロックというにはサンプリングや打ち込みの比重が高い。生演奏主体であるけれどフォークトロニカとも違う。これまでの明確に細分化されたジャンルから漏れてしまう筆頭がマウス・オン・マーズだと思う。クラウト・ロックからノイエ・ドイチェ・ヴェレのラインの延長線上にいるバンドでくくる方が正しいのではないだろうか。しかしその一方でこのアルバムは、エレクトロニカの時代の空気もふんだんに内包している。Vegynを初めて聴いた時にこのアルバムを真っ先に頭に浮かべた。
細野晴臣/スケッチショーファンは「Pinwheel Herman」のポップネスに胸を打たれてほしい。
To Rococo Rot/The Amateur View
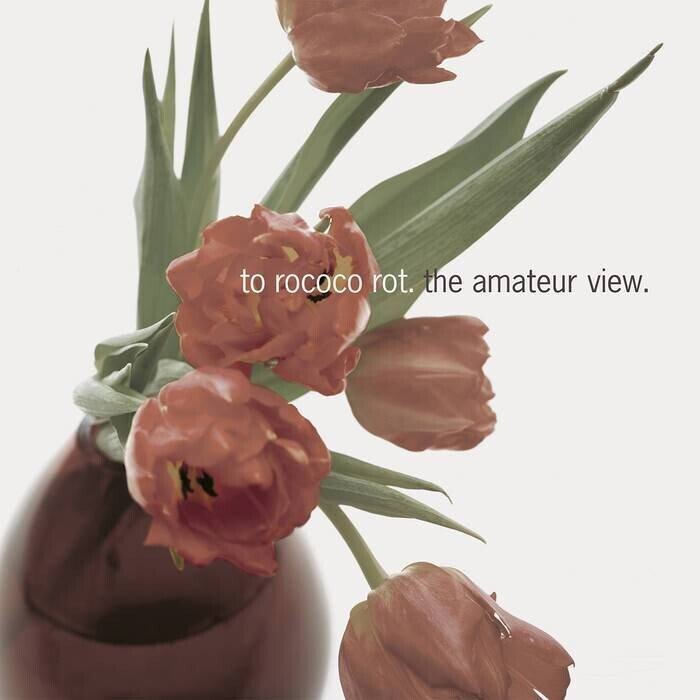
トゥ・ロココ・ロットもポストロックとエレクトロニカの狭間にいるバンドで、グリッチなサウンドを差し込みながらも、基本はジャジーなポストロックではあるが、ヴィーガンに通じるある種のロマンチシズムを感じさせる。シンセサイザーのシーケンスとリズムを刻むハイハットを軸にアブストラクトなメロディーが印象に残る「Die Dinge Des Lebens」を聴けばわかると思う。
Four Tet/Pause
一般的には次作の「Round」をフォークトロニカと扱うべきなのかもしれないが、時代の空気としては「Pause」の方がポストロック/エレクトロニカに近い雰囲気を持っている。音から判断すれば「Round」はフォークトロニカから脱却し始めていてレアグルーヴ回帰な側面があったのに対し、「Pause」の方がここで取り上げている狭間にあるサウンドに近い。
Max Tundra/ Some Best Friend You Turned Out To Be
マックス・ツンドラも扱いに困る人で、生演奏とサンプルのスライスというバトルズ以降では当たり前になったスタイルの先駆けとも言える。ポストロックとも言えるけれど、エレクトロニカの感覚も持ち合わせている。今振り返られにくい人でもあるのだけれど、ここのあるキテレツなサウンドは楽しめると思う。
scratch pet land/Solo Soli iiiii
どちらかと言えばチップ・チューン(ファミコン音源を使った音楽)で語った方がしっくりくると思うのだけれど、ここにもエレクトロニカ以降な感覚がある。アドヴェンチャータイムにも通じるコケティッシュな感覚がある。
Marumari/The Wolves Hollow
アメリカのカーパーク(最近ではトロ・イ・モアのリリースで知られている)からリリースされていたマルマリも形容しがたい音楽性を持っている。打ち込み主体ながらエレクトロニカ以降の感覚を持ち合わせている。
Manitoba(Caribou)/Start Breaking My Heart

現在もカリブーとして活動を続けるマニトバ。ハウス/2ステップを感じさせるこのアルバムもエレクトロニカの香りが散りばめられてる。ヤン・イエリネックと並べて紹介するべきアルバムではあるものの、エレクトロニカの濃度の差でこちらで取り上げた。近々20周年盤がリリースされる模様。
suppa micro panchop/goo
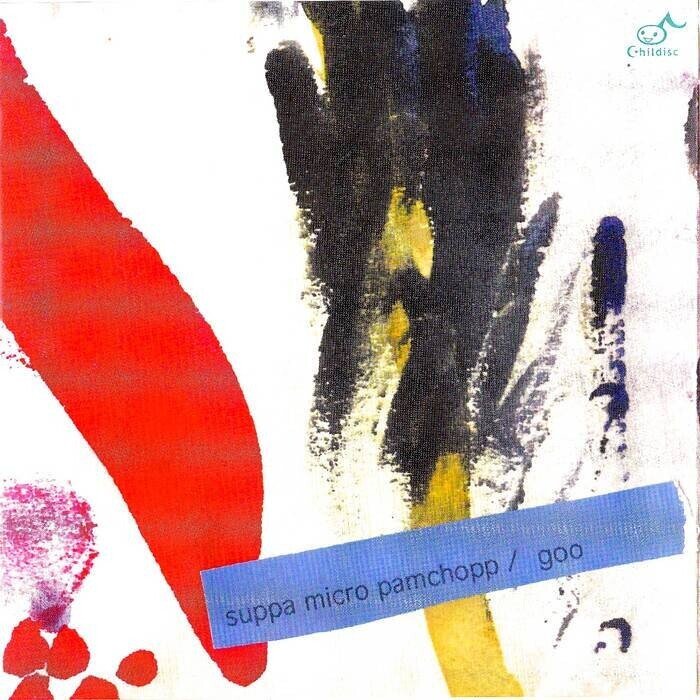
竹村延和のチャイルズビューからリリースされ、現在はツイッターで一大インフルエンサーとして影響力を誇るスッパマイクロパンチョップのアルバム。チャイルズビューらしいおもちゃ箱をひっくり返したようなサウンド(定型型かもしれないけれど)の妙が繰り広げられている。あえて言及するとこれまでレイ・ハラカミを取り上げなかったのは、エレクトロニカという枠で彼を取り上げるにはいささか枠が狭すぎるように感じた。逆にスッパマイクロパンチョップを取り上げたのは、このエレクトロニカの時代に寄り添ったアルバムを作っていた事に他ならない。キャリア全体を見ればどちらもエレクトロニカの枠には収まらないのだけれど。
次回は主要レーベルのまとめを簡単に。
今後の活動資金のためのサポートもよろしくお願いいたします。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
