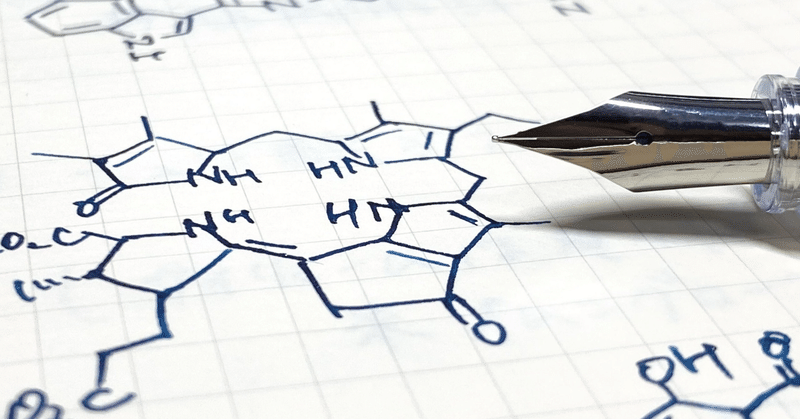
文章術の本は生成AIで無効化される?
◉佐々木俊尚さんの、興味深い指摘がありました。有料記事ですが、無料部分だけでも読み応えがありますし、そこの指摘を元に、アレコレと文章術について、思うところを。
ヘッダーはnoteのフォトギャラリーより、万年筆と化学式ですが、テーマに合ってるように思うので。
◉…▲▼▲▽△▽▲▼▲▽△▽▲▼▲…◉
■文章の巧拙とは?■
まず、文章の巧拙という点で、誤解というか、混乱があると思うんですよね。上手い文章とはなにか、と問われて即答できる人、いますか? あんまりいないと思うんですよね。漠然としたイメージとして、なんとなく三島由紀夫のような美文調の文章とか、そうでなければ夏目漱石や森鷗外などの、文豪の書くような高尚な文章が、上手い文章と思っていませんか? そもそも、高尚って何ですかね? そのレベルにも達していなくて、誤字脱字がない文章が上手いと、単純に考えている人もいますね。
あるいは、用字用語の誤用とか。ハッキリ言いますが、誤字脱字や用字用語の誤用は、文章の巧拙とは、ほぼ関係ないです。夏目漱石とか、当て字を使いまくりですし、生原稿段階では誤字脱字や誤用なんて、ボロボロありますしね。だから、宮沢賢治の『雨ニモマケズ』が〝日照りか日取り〟かで、論争になるわけで。以前にも指摘しましたが、文章の上手さってザックリと思いつくだけでも、コレぐらいは人によって思い浮かべるイメージが、違うと思うんですよね。
①広告文的な、人々の印象に残ったり想像を刺激する上手さ
②説明書的な、情報を誤解なく精確に読み手に伝える上手さ
③詩文的な、視覚的イメージや経験・記憶を刺激する上手さ
④詞文的な、リズムや口に心地よい語呂の良さを選ぶ上手さ
⑤落語的な、セリフの選択と各キャラ性を演じ分ける上手さ
⑥論文的な、ロジックの厳密さや記述ルールに沿った上手さ
⑦檄文的な、感情を揺さぶり読んだ人間の行動を促す上手さ
⑧小説的な、作品世界に引き込む語り口や人物描写の上手さ
⑨脚本的な、小説的な要素を時間軸に沿って構成する上手さ
⑩散文的な、上記の要素を過不足なく持った総合的な上手さ
さて、佐々木俊尚さんが指摘する、生成AIによってカバーされるのって、主に②と⑥になるでしょう。
■情報と感情の狭間■
現実的に、小説や脚本において重要視されるのは、②と⑥以外の部分になります。なぜなら、これらの表現ってのは、人間の感情を動かすモノだからです。感情を動かすのは、感情です。海原雄山が山岡士郎に繰り返し言いますね、「人間の心を感動させのは、人間の心だけだ」と。まぁ、人間は美しい風景を見ても、可愛い動物を見ても、心が動くんですが。そこでこう断言しちゃうのもまた、心を動かす言葉になり得るんですよね。
修飾語の位置が被修飾語との距離を近くするとか、作家でもついやってしまいがちな部分は、文章の上手さではなく。情報が正確に伝わっている、ということです。実はこの〝感情と情報〟ってのは、作話講座でもかなり重視しています。感情を伝える場面と、情報を伝える場面の、バランスが悪いと、感動できる文章にはなりづらいんですよね。これは、詩でも散文でも同じです。俳句の実相観入という考えも、自分の解釈では「風景や情景を描写することで、感情を揺さぶる」という面があります。
古池や 蛙飛びこむ 水の音 松尾芭蕉
これは、最近造成されたわけではない池にカエルが飛び込む音がしましたという、情報を伝えているだけではなく。カエルが飛び込む音が聞こえるほどの静けさ、そして寂しい風情。その部分をAIで表現できるかと言えば、難しいでしょうね。情報から沸き立つ感情。ここを理解するには、AIにいったいどんな学習をさせればいいのか? 門外漢の自分には、ちょっと思い浮かびません。人類の集団的無意識のようなモノを、未来の量子コンピュータがモデル化できるなら、あるいは可能かもしれません。
■本末転倒な方法論■
小説の場合は詩文より、もうちょっと情報の方が多いのですが。これは、脚本や漫画原作も同じです。というか、梶原一騎先生はハッキリと、ビルの鉄筋のようなモノだと、仰っています。コンクリートや外装、内装は漫画家次第と。でも、そのト書きと情景描写とセリフの情報から、実は漫画家は感情を読み取り、その感情を揺り動かす絵で、行間を埋めていると言えます。横浜・黄昏・ホテルの小部屋…と情景を重ね、男女の別れの風景を喚起させ、感情を動かす。実は、文章読本はこの部分を説いてるのに、技巧の説明に終始するという面が。
なぜ、どれもこれも「文章読本」と名乗っているのか。わけわからないし不思議ですが、どれを読んでも「名文から学べ」「簡潔で美しい文章を書け」といった話が並んでいます。これらの「文章読本」が書かれたのは戦前から1970年代ぐらいまでで、文学の全盛期でした。みんなが小説を読み、作家に憧れ、作家は現代のお笑い芸人さん並みのタレント人気を誇っていました。テレビがそれほどの大きな影響力を持っていなかったころには、映画と並んで小説がエンタメの中心地だったのです。
モテるための本を開いたら延々と、異性に嫌われないための身だしなみや喋り方のマナーが書かれてる。たしかに、それは大事ですが。嫌われないと好かれるの間には、大きな壁というか断絶があります。嫌われてしまっては、絶対に好かれることはないから、まず嫌われない方法を。それは解るけれど、アバタもエクボという言葉もあるように。好きになってしまったら、嫌われる要素が吹っ飛んでしまうのも事実。だから、好きになって貰うハウツーを教えろと、読者は思うわけです。
漫画家になる方法を聞きにいったのに、フォロワーを増やすノウハウを教えられ、気がつくと漫画を書く気がなくなってしまっていた、この事例も本質は同じかと。
■人の話を聞け■
でも、現実には、そういう感情を揺さぶる言葉って、日常生活では、そんなに必要ないです。CLIP STUDIO PAINTのセルシス社の推計で、商業プロの漫画家の総数は全国で3000人から6000ぐらいだとか。アニメーターの総数も4500人から6500人ぐらい、小説家も2000人から4000人ぐらいではないかと、以前に推測しましたが。医師免許を持つ人間が、全国に約34万人いることを思えば、文章読本で開陳されてる知識って、ハイアマチュア用で数千人レベルにしか、理解して使いこなせないモノです。
それよりも、医者は100倍ぐらい多く。でも、医者の使うカルテの正確な記述方法なんて、一般人には不要です。そう、過去の文章読本は、マウンドからキャッチャーまで届く投げ方を学ぼうとしたら、いきなりメジャーリーグでタイトルを獲るのに必要な投げ方を説かれたようなモノで。ビジネスや日常のコミュニケーションに必要な文章が求められるわけです。それはほぼ、正確に情報を伝える技術とイコールです。何がどうして、どうなった。そういう基本的な文章力は、AIが得意とするところでしょう。
そういう時代背景があり、小説の名文を目指す人はとても少なくなりました。代わって台頭してきているのが、ビジネスの場面などでの実用的な文章スキルを求める声。論理的な文章のための「文章読本」というと、以前は新聞記者本多勝一氏の「日本語の作文技術」(1976年)ぐらいしかありませんでした。しかしいまでは、美文や名文よりもきっちりと論理的な文章が求められるようになっています。
ところが、そういう正確な文章って、究めれば究めるほど、辞書的な文章になります。もっといえば、法律の文言や条例の文言に近くなります。でも、あの文章を、上手い文章とは思いませんよね? 実際は、かなり上手い文章なんですが、それは情報の正確な伝達に、全振りしてるから。でも、そういう弁護士や裁判官が書く、正確な文章の書き方は面倒くさいので、学ぼうとはしない。手っ取り早く、人の心を動かす文章=感情を動かす文章を学ぼうとする。文章読本が、三日坊主を量産するベストセラーになりがちな、理由です。
1978年末(SFM1979年2月号掲載のDP。←ここ重要)以前のヒットした(←ここも重要)女性ペア物のスレッドなんですが、なぜか、それ以降の作品のことを教えてくださる方がおられます。それだとコメントのしようがないんですよね。おおもとの投稿も読んでください。よろしくです。お願いしますね。
— 高千穂遙 (@takachihoharuka) September 9, 2023
高千穂遙先生は、自身の『ダーティペア』以前に女性コンビのバディ物SFはあったのか、なければ自分が元祖かもという、興味からX(旧Twitter)で聞いているのに、78年以降の作品を挙げる。これ、嫌がらせでなければ機能的文盲、悪くても人の話をちゃんと理解できない人です。でも、こういう人ってゴロゴロいます。たぶん、こういう人は生成AIも使いこなせない。まず、正確に読み取れないと、正確な返しや言葉のキャッチボールはできないという。それができたところで、野球以前にちゃんと走れるレベルの話なんですが。
どっとはらい( ´ ▽ ` )ノ
売文業者に投げ銭をしてみたい方は、ぜひどうぞ( ´ ▽ ` )ノ
