
90なんちゃって図像学(5,6) 紅葉賀巻⑫ 出掛けられない源氏🌺

・ 和みたくて西の対へ
じっと物思いに沈んでいるばかりで、気持ちが晴れそうもありません。
若紫の顔が見たくなって、東の対を出ます。
少し寝乱れたままの髪に寛いだ袿姿で、ゆかしく笛を吹き鳴らしながら廊を行きます。

・ 可憐な女君
西の対まで行って居間を覗くと、女君は、先程の露に濡れた撫子のような風情で脇息に寄りかかっていて、大層愛らしく可憐で、愛嬌がこぼれる様子です。
帰邸したのに、すぐにこちらに来ないのを恨めしがって、拗ねているようです。
そっぽを向いているので、端の方に座って、「こちらにいらっしゃい」と言っても知らん顔です。
…………………

🌷🌷🌷『拗ねている若紫』の場の目印の札を並べてみた ▼

・ 拗ねている
🌺①「入りぬる磯の草のように」「あまりお会いできないから」
と口ずさんで口元に袖を当てている様子にも才気が目立って、愛らしいことです。
「おやおや、そんなことをおっしゃるようになったのね」
🌺②「でもね、興に任せて心ゆくまで逢う なんて見苦しいことですよ」「何事もほどよくする嗜みが大事なのです」
などと言い聞かせます。
それから、女房に筝の琴を出させます。
・ おままごとのような楽興の時
📌③「箏の琴は、中の細緒が切れやすいのが面倒だな」と言って、平調に下げて調弦してから、試し弾きにちょっとだけ鳴らします。

平調におしくだして調べたまふ かき合はせばかり弾きて さしやりたまへれば
それを姫君の方に押しやると、もう拗ねるのをやめて、可愛らしく弾き出します。
筝の琴を弾くことがとても好きなのでしょう。
小さな体で左手を差し延べて弦を押さえ揺す手つきがとても可愛らしく可憐です。
源氏は笛を吹きながら教えます。
とても利発で、難しい調子も一度で覚えてしまいます。
源氏は、何事にも才長けて、理想通りになっていることが嬉しくてたまりません。

笛吹き鳴らしつつ教へたまふ いとさとくて かたき調子どもを ただひとわたりに習ひとりたまふ
大方 らうらうじう をかしき御心ばへを 思ひしことかなふと思す
『保曾呂惧世利』という曲は、曲名は妙ですが、源氏が素晴らしく笛を吹くと、姫君の琴が後をついて合わせます。

おもしろう吹きすさびたまへるに かき合はせ まだ若けれど 拍子違はず上手めきたり
未熟ではありますが、拍子に間違いはなく、姫君には楽才もあるようです。
…………………
📌 保曾呂惧世利とは、雅楽の高麗壱越調の長保楽の破のことだそうで(?????)、以下の動画の2分直前に笛が始まります。
残念ながら十三絃琴とではありませんが、源氏がまず笛を吹き始めた感じを想像します。
こんな舞に付く曲だそうです。 ↓

https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc22/sakuhin/bugaku/s4.html
…………………
・ 出られなくなった源氏
暗くなってきたので、灯りを灯して、一緒に絵など眺めます。

🌷🌷🌷『一緒に絵を見る』の場の目印の札を並べてみた ▼


…………………
📌 源氏と若紫が一緒に絵を見る場面がそこまで特異的なのかどうかわかりませんが、絵だけでなく筝も側にあることが特徴的なのかもしれません。
…………………
出掛けると命じてあったので、供人達の用意の声が聞こえます。

「雨がふりそうでございます」
など言う声が聞こえると、姫君は気配を察していつものように心細くなって塞ぎ込んでしまいます。
絵を見るのもやめてうつ伏してしまっているのが可愛くて胸を締め付けられるような気がします。
髪が見事にこぼれかかっているのを撫でながら、
「私がいない時は寂しいの?」と尋ねると、頷きます。

他なるほどは 恋しくやある と のたまへば うなづきたまふ
「私だって一日あなたに逢えなければ辛いのだ」
「あなたがまだ小さいうちは私も安心していられるから、まずはひねくれて恨む人たちを怒らせまいと思ってね」「あれこれ煩わしいことがあって、暫くはこのまま夜歩きすることにもなろうけれども」
「あなたが大人になれば、もうどこにも行かないよ」
「人から恨まれまいと思うのも、長生きして、あなたと好きなだけ一緒に居たいと思うからなのだ」
細やかに話して聞かせると、恥じらって何もお返事しません。
そしてそのまま膝に寄りかかって眠ってしまいました。
源氏は、いじらしくてたまらなくなって、
「今夜は出掛けないことにする」と声を立てます。
側の者たちは立って行って、それからお膳などを持ってきました。
姫君を起こして、「出掛けないことにしたよ」と言うと、御機嫌を直して起きました。
一緒に食事をします。
姫君はそれでも心配そうにしていて、ほとんど食べないで、
「本当にお出掛けにならないの?」
「それならそのしるしに、ここで寝てくださらなくてはいや」
と不安そうです。
源氏は、どんなに恋しい人の所にも、こんな人を見棄てては行けないと思います。
・ 人の噂
こんな風に引き留められることも多いので、漏れ聞いて左大臣家に御注進する者もいます。

さやうにまつはしたはぶれなどすらむは あてやかに心にくき人にはあらじ 内裏わたりなどにて
はかなく見たまひけむ人を ものめかしたまひて 人やとがめむと 隠したまふななり
心なげにいはけて聞こゆるは など さぶらふ人びとも聞こえあへり
「どなたなのでしょう」「全く失礼な話ですわ」
「今まで御噂も聞いたこともないような方で、そんな風にまとわりついて戯れていらっしゃるなんて、あまり御身分も品もなさそうな方ですわね」
「宮中などでちょっとお見初めになったような方を大仰に扱われて、でも見るに堪えないような方でいらっしゃるから、人の咎め立てを避けて隠していらっしゃるんですわ、きっと」
「ものの風情もわからない幼稚な方だそうじゃありませんか」
など、女房たちは噂し合っています。
・ 帝のお叱り
そういう人がいるということが帝の御耳にも入ります。

おほなおほな かくものしたる心をさばかりのことたどらぬほどにはあらじを
などか情けなくはもてなすなるらむ
「気の毒に、左大臣が嘆いているそうだが」
「子供の頃からずっと、あなたをこの上なく大切に世話してきたあの人の気持ちがわからない齢でもあるまいに」
「どうしてあの人の娘御にそんなに薄情な扱いをするのか」
とお叱りになります。
源氏は、恐縮した風でいるばかりでお返事もできません。
帝は、左大臣の娘が気に入らないのだろうと、源氏を責めるよりも、源氏を可哀想に思されます。
源氏が可愛くてたまらなく遊ばされるのです。
御注意はあったものの、「宮中の女官にせよ、そこここの女房にせよ、誰それと特別な仲であるなどの好色がましいような噂も聞かないのに、どう隠れ歩いてこのように人に恨まれることになっているのだろう」と、間近な者にふとお洩らし遊ばされることもおありなようです。

🌺①「入りぬる磯の草のように」「お会いするのが少なくて」
‘’潮が満ちれば隠れてしまう磯の草のように、お逢いできる時間は少なくて恋しがっている時間ばかりが多うございます‘’
📖 潮満てば入りぬる磯の草なれや見らく少なく恋ふらくの多き
(万葉集 詠み人知らず)
🌺②「逆に、この歌のように、みるめにあく なんて見苦しいことですよ
‘’ 伊勢の海女が朝夕に潜って採るという海松布のように、満足のいくほどに逢えればいいのに ‘’
(📖伊勢のあまの 朝な夕なに かづくてふ みるめに人を あくよしもがな」(古今集 詠み人しらず)
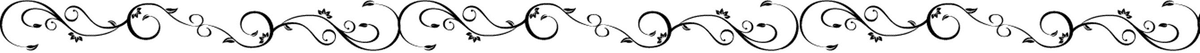
📌③ 中の細緒の堪へがたき
若紫の弾いている十三絃琴の『中の細緒の堪へがたき』 とは、どういうことなのか、基礎知識がなさ過ぎて、全然わからないのですが。
平調というのが、他の調子に比べて非常に張力の低い低音の調子のようにも思えなかったのですが。
絃がいっぱいある中で真ん中辺りは張りにくいというのか、
中ほどには細い弦を用いるで切れ易いというのか。
ともかく、源氏は、この楽器は中の細緒が面倒だと言いながら、調弦してやったということらしい、とだけ何となく。

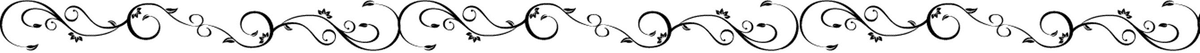
📌 この章の書き出しでは、源氏が覗きに行った時に、露に濡れた撫子の風情でいたのは、女君だと書いてありました。
拗ねてぐずる子供っぽい描写のところで呼称が姫君に戻ります。
源氏18歳の年の3月末に若紫を初めて見た時には、雀が逃げて愚図っている幼い子でした。若紫は10歳。
今は、源氏19歳の年の恐らく4月。若紫は11歳。
お誕生日がわかりませんが、小学校2年生から3年生に成長していく過程を見ている感じでしょうか。
現代でも、その頃に幼女から少女に変わる感じがあるのかもしれません。
そんな時から囲い込まれて、今か今かと性的な目で見られ続けているということが痛ましくてならないのですが、1000年前の道徳を論じるのは不遜なのかもしれず、源氏物語内でのこのことに関して意見を持つのは手に余ることだと思っています。
泣き寝入ってしまった幼い若紫に胸の締め付けられる思いでいる源氏には、親を亡くした寄る辺ない孤児同士としての深い共感、同情があるのだということは忘れてはならないと思っています。
眞斗通つぐ美
📌 まとめ
・ 拗ねている若紫
https://x.com/Tokonatsu54/status/1711313094075625890?s=20
・ 一緒に絵を見る
https://x.com/Tokonatsu54/status/1711314809445335087?s=20
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
