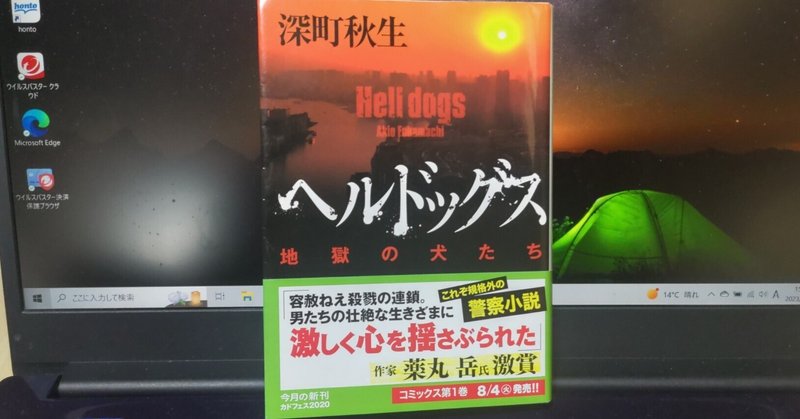
3/10 『ヘルドッグス 地獄の犬たち』を読んだ
購入したのはこの文庫版が発売されてすぐで、その後映画化が発表され、公開されるまでには読めるかなーと思っていたが間に合わなかった。そして映画も、なんやかんやで結局観逃がしてしまった。いつかどこかで観れたらと思う。
のっけから凄惨な殺戮劇が展開されて、主人公の兼高も躊躇なく人を殺し、容赦はないのだと知る。囮捜査や潜入捜査が違法でやっちゃいけないこととされているというのが、理解はできるがいまいちピンとはきていなかったのを、ピンどころかガツンとこさせられた。なんかこうして文章にしてみると自分が間抜けに思えてくるが。
馳星周『不夜城』を読んでいたので、黒星とか蛇頭とかいう単語がいきなり出てきてもなんのことか理解できた。ノワールの教養が高まっているのを感じる。ただ『不夜城』は、主人公がどの陣営とも仲良くできないはぐれ者の悪党であるために、出会う人々すべてに対し猜疑と敵意がひしめいていたが、今作は警官という出自の男がヤクザの世界に潜り込んでいるためか、猜疑や敵意以外の情も多分に盛り込まれている。血のつながりではない、流血のつながり――とは、西尾維新の『戯言』シリーズにおける殺し屋一賊を表す言葉だが。あの世界においては異端とされる集団だったけど、実のところ現実の世界においては、そう珍しくもない集団なんだよな。今更そんなことに気づくとは、これまた間抜けな話。
ヤクザの食事、ヤクザのビジネス会議、ヤクザの葬儀など、密着ドキュメントのようにヤクザの生態が描かれるところがとても興味を引かれ面白かった。ヤクザにとっての礼節とは、根底に暴力があるからこそ、そこにどれだけ礼節を搭載できるのかというのがステータスになっているのだと理解できる。物理攻撃タイプなのに魔法攻撃も結構いけんのか、みたいな。抗争で事務所によく籠るし出前もろくにとれないので料理上手のヤクザが育つとか、宴会もよくやるのでカラオケの上手いヤクザが重宝されるとか、愛嬌のある面も見せてくるが、それも暴力という基礎あってこそ。暴力を根底に敷くと、いろんなものがシンプルになる。人が暴力を求めるのは、暴力がシンプルだからなのではなく、暴力によって複雑なものがこそぎ落とされた世界がシンプルだからなのではないか。だから世界の複雑さを吞み込めない者は暴力に頼り、暴力を好まない者というのは、自分が呑み込める範囲の複雑さの世界を好んでいるに過ぎない。
終盤、自分の組長(※)を殺した後の顛末は、重く冷え冷えとして辛い。ヤクザという血と情の掟に縛られた生き物の厄介さを存分に描いていながらも、やっぱり室岡のようなキャラクターには愛おしみを覚えてしまう。フィクションのキャラクターという、絶対にこちらに危害が及ばない対象だからではあるが……。
十朱の秘められた信念を垣間見せる言葉や、阿内のヤクザそのもののような言葉など、どいつもこいつも最期の一言まで大変に魅力を感じさせてくれる。すべてを看取って、すべてを裏切り、己の掟だけを首輪に狂犬の道を歩む男は、地獄の果てで自らを何と名乗るのか。面白かった。
※……余談だけど、作中のルビ技術として、話者によって「オヤジ」や「アニキ」と読んでいる語が違うのがとても上手くて面白かった。兼高なら土岐、熊沢なら十朱、など。映画だとアニキオヤジが飛び交っててわけわからんだろうな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
