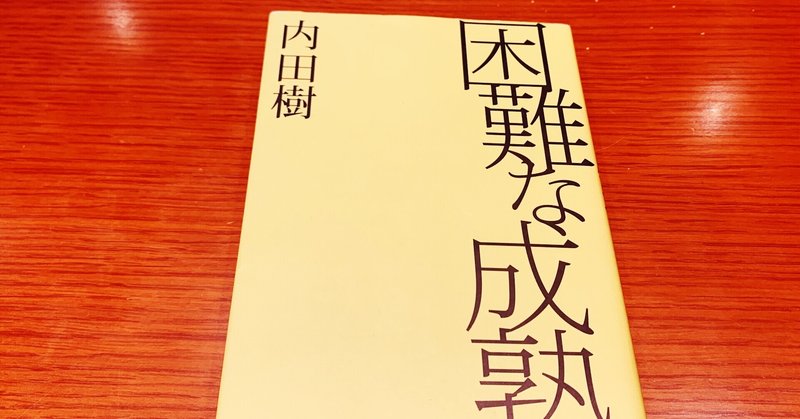
読書録/「困難な成熟」(内田樹・著)
「困難な成熟」を読み終えての、読書録といきたいところだが、自戒の念に駆られることや反面教師にしたいことが多い。
もちろんそのための一冊としても良書なのだけど、そこに焦点を当てて読書録を書くと、ぼくの文章力では単なる自己啓発本と捉えられかねない気がする。
背筋の伸びる一冊であり、あるいは自己啓発本と同じ括りで手に取る人もいるかも知れないが、もっと違う側面もある。殊、自分のことにとどまらず、この本はもっと普遍的なことについて言及しているが、とはいえ筆者のいち意見というところを重ね重ね強調しており、かえって納得させられてしまう。個々の人間の振る舞いから世の中の乱れや歪みに至るまで、的確にツッコミを入れてくれる本だという説明が一番しっくりくる気がする。
ということで、このエントリでは「困難な成熟」の主に第1章と第5章を使って、日本の政治にツッコミを入れていきたい。
因みに、第2章は仕事との向き合い方、第3章はお金との付き合い方、第4章は嘘や教育の話を中心にコミュニケーションの心構えの話で、読めば読むだけ金言が出てくるわけですが、耳が痛いので棚上げしていきます。
「責任を取ることなど誰にもできない」
「まえがき」でこの本を手に取った読者へのお礼も早々に、『第1章の最初の「責任を取ることなど誰にもできない」だけ読んでいってください。』と先を促される。
のんびり最初から最後までページを手繰りながら読書することが多い僕ですが、「著者がそう言うなら」と第1章を開いてみる。
件の一節を読み始め、ページを捲ったところで、
「責任を取るということは可能でしょうか?」
答え、「不可能です」
以上。おしまい。
と、なかなかに刺激的な断罪である。
最近は何かと政治家の不祥事につけ、「今辞めることこそが無責任。自分の責務を全うすることで、責任を取りたい」みたいな「責任を取る」ための謎のロジックが横行していて、非常に腹立たしい。
そう考えると、刺激的と言ったが、この断罪こそが正しい姿だと思う。
まず辞める。その上で粛々と生き、(或いは罰を受け、)その中で赦しを得ていく、というのがあるべき姿のように思う。社会的地位が確保されたところに留まりながら、なぜ「責任を取る」事ができると思っているのか?
数ヶ月、無給だの減俸だの言われたところで、そもそも目障りなんだよ、というのが国民の本音だろう。
政治家はのうのうと居座り続ける一方で、なぜかそれ以外の人たちはネット上で過剰な私刑を受けている。これも強く頷きたくなる一節だが、著者曰く、これも強く頷きたくなる一節だが、著者曰く、
正義の起源は生身を備えた他者の具体的な受苦に対する「共感」。観念的な「悪」を憎んで正義を発動させたりすると、だいたいろくなことになりません。「見たこともない人の苦しみへの想像的共感に基づいて、会ったことのない知らない人に罰を与えようとする」はあまりしないほうがいい。
いや、政治家が誹謗中傷を受けていない、というわけでもないが、まぁ単純に図太い人間の集まりなのだろう。
そこに居座り続けられる鈍感さこそが当人をその地位に押し上げたのかもしれないが、その過程で市民的な倫理観がすべて剥がれ落ちている。
そういった人にこそぜひこの一冊を読んで頂きたいように思う。
『第1章「社会の中で生きるということ」』の中では、「真実」と「方便」の件もまた痛烈だ。
ルール(法律や道徳)はどれも「他者と折り合って暮らすための方便」。「方便」とは仏教用語で、「人を真実に導くため、仮に採用された便宜的・迂回的な手段」のこと。(中略)ルールをめぐる混乱には2種類あり、ひとつは「真実」と「方便」の区別がつかない人が「方便」の部分を金科玉条のように守ろうとすることから起きる混乱。ひとつはどうせルールなんか方便なんだからとその制定時点での「真実」が何であったかを検証しなくなることで生じる混乱。
最近では特に気候危機や原発に関する報道で、「真実」を追求する問いに対して、日本の政治家がよく「方便」を口にしているのが目につく。
無論、その方便では真実に導けないのだが、それにしても明らかに意図的な混乱というか、倒錯が当たり前のように展開されている。
私たちは誰を「愛する」のか
10月末の衆院選を前に父親と政治の話をしたことがありました。互いに好きなスポーツの話を除けば、普段からさほど話す方でもない父親と、ほとんどしたことのない政治の話を。
普段から、政治家、主に与党議員の不祥事などのニュースを見るにつけ、文句言ったりぼやいたりしているから、少なからず与党に不満を持っていると思っていたら、いざ選挙となると自民党を推しているらしい。曰く、「若い人が変わらないと、ホゲホゲ」「自民党の団結力がゴニョゴニョで、とにかく日本には不可欠」ということでした。
今、若い人が政治を変えていくとしたら、たぶん自民党の「団結力」をとき解いていくことに他ならない、と思うんだけど、どうなんでしょう。ちょうどその、父親世代が抱く自民党の「団結力」への幻想が何たるか?を第5章は教えてくれている気がする。
現代日本の用語法では、排外的な人は自分のことを「愛国的」であると名乗ることが習慣化しています。このような人は「愛国的」というのではなく、むしろ端的に「ゼノフォーブ」「外国人嫌い」と呼ぶべきだろうと思います。ゼノフォーブの攻撃対象には「外国人に対して過度に宥和的な同国人」も含まれます。そもそも彼らが「非国民」とか「売国奴」と呼び、攻撃対象とするのは同国人です。外国人よりも同国人に対する憎悪のほうがはるかに大きいことさえある。
父親から、特に排外的な思想についての話を聞いたことはないが、共産主義批判のようなことは聞いたことがある。
父親の話を聞くと、要するに、バブル崩壊以前の時代への懐古、奴隷労働を是として突き進んだ社会全体の当時の雰囲気、その時代のアンチテーゼとしての共産主義への負の感情が綯い交ぜになっていて、「団結力がオッタマゲ」ということのような気がする。
とにかく現政権がどれだけ悪事を働いても、自民党が大正義というところは変わらないようだ。自分の家族の生活にとって自民党に関わることは強いて言うなら近所付き合いくらい(主に父親の)で、既得権益なんて全く関係ないのに。
どうやら、今回の衆院選で自民党議員が口にしていた、共産党が与党になることへの警鐘を地で信じているようだ。
「ゼノフォーブ」の採用する社会理論は「私たちの社会の不調は、私たちの社会に入り込み、国富を収奪し、国威を損じている外国人たちである。だから、彼らを組織的に排除しさえすれば、私たちの社会は原初の清浄と豊穣を回復するであろう」というものです。この理論を徹底させた実例としてナチス・ドイツの反ユダヤ主義があります。
「父さんよ、今の自民党の方がよほどかつての共産主義的な性格を持っていることに気づいてくれ」という切実な願いは、おそらくこの先も届くことはなく、切実さだけが増していく。
「愛国心」は必ず国民の統合に失敗します。それは愛国心の純度を「非国民リスト」の長さに基づいて考量したからです。「許せないやつ」の数が多ければ多いほど、愛国的情熱の純度が高いというルールでゲームを始めてしまった。(中略)排外主義的愛国心は必ず国民的な統合に失敗する。(中略)では、いったいどういう愛国心が持続可能で、統合可能なのか。その基盤となるのは「私とは考え方も感じ方も違う人間たちとも、私は共同的に生きることができる」という「他者を受容する能力」です。
かつての政治は大企業や一部の宗教団体を囲って利益誘導すれば、或いは少なくとも一定のマジョリティが幸福を享受することになって、それで良かったのかもしれないけれど、現状はその既得権益を受ける側がかなり限られてきているし、そもそも今の政治の在り方が前時代的なそれでいいはずがない。
そして、話題は領土問題に移り、この本の中で最も感銘を受けたメタファーがこれです。
どこの国でも、領土問題の炎上と鎮静は政権の安定度と相関します。領土問題「から」話が始まるのではありません。領土問題は両国それぞれの統治がうまくいっていないことの帰結なのです。そのことを棚に上げてこの問題を論じる人は、なみなみと水の入ったコップにさらにひとしずく水滴が落ちたせいで水が溢れた時に、「この一滴こそが水が溢れた『原因』である」と言っている人によく似ている。
領土問題はともかく、この「なみなみと水の入ったコップに落ちたひとしずくの水滴」の喩えは、資本主義社会に蔓延るあらゆる社会問題をカバーできる批判として懐に忍ばせておきたい。
原発も盛り土も過労もメンタル疾患も気候危機も、全部そうだ。もうすべてがとうに限界を迎えていることに気づくべきで、その意味では変わるべき人たちには、大人も子どもも老いも若いも関係ない。選挙の度に若者の投票率が問題になるが、責任転嫁も甚だしいように思う。まず、社会が弱者ーつまり、日本在住の外国籍の人たち、貧困や障がいに苦しむ人たち、そしてまだ投票権すら持たない次世代の子どもたちーへの救済と包容力を持つこと。そのための政治の在り方を考えて投票する人が過半数にならない限り、日本はどこまでも沈んでいくんだろうなぁ。。。
「愛する」という行為は理解と共感の上にではなく、「理解も共感もできないもの」に対する寛容と、そのような他者に対する想像力の行使の上に基礎づけられたほうが持続する。そういうことです。
とまぁ、政治への苛立ちを露わにしてきたが、この本の半分以上は自分の実生活への向き合い方を考えるためのインスパイアとなる素晴らしい本です。どうぞ、ぜひご一読ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
