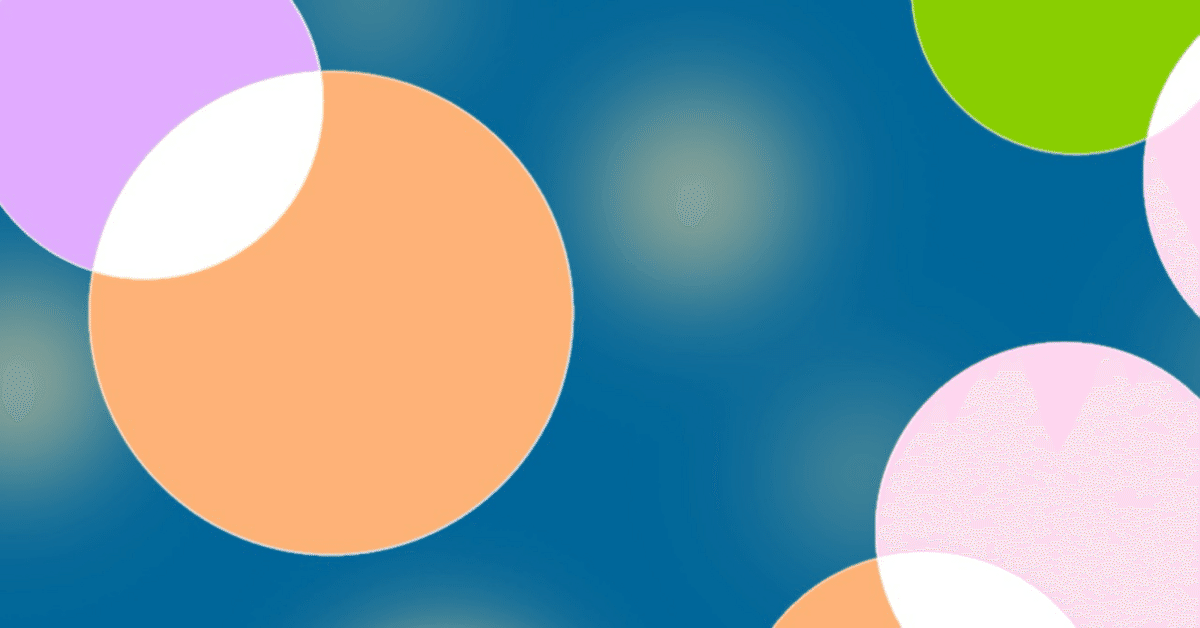
【短編小説】最期の10分間
ボクは、同居人のあの男が嫌いだ。
一緒に外出している時はボクの呼びかけを無視して、他の奴らに作り笑いを向けてヘコヘコしているし、かと言ってひとたび家に帰ればボクに気持ち悪い笑顔で近付いてきてベタベタするし。
毎日同じご飯しかくれないし、おやつはたまにしか買ってこない。撫で方も無骨で雑で慣れていない感丸出しの癖に、ボクの呼びかけには普段の低い声からは想像出来ない程の裏声で応えて、これまた気持ち悪いことこの上ない。
「ブルー」
なんだよ。ボクは眠いんだ、少し放っておいてくれないか。
適当に返事をして再び眠りに就こうとすると、またあいつの声がした。
「なぁ、ブルー…」
なんだよってば。というか、あのおぞましいくらいの裏声はどうした。逆に寒気がするからそんな声を震わせるな、いつも通り呼べよ。
と、鼻先に温かい水が零れる。どうやらあいつは、まどろんでいるボクを見下ろす形でボクの名前を何度も呼んでいたらしい。
なんだお前、泣いていたのか。仕方ないな。ほら、いつもみたいにまた泣き止ませてやるから顔近付けてこい。
そう。それでいい。
ちゃんと拭ってやるから。本当、見かけによらず泣き虫だよな、お前。おちおちゆっくり寝てもいられないよ。
これからも、ボクがずっとお前の面倒見てやるから。だからもう泣くな。
「は、はは…
俺が泣いてると、いつも顔面パンチかましてくるよな。きっと慰めてくれてるんだよな…優しいなぁブルーは…っ」
泣きながら笑うって、お前変なところで器用だな。ああ…何だか気が抜けてきた。
『にゃあ…』
自覚していたより掠れた声で一鳴きする。今のでどっと疲れちゃったよ。
少しだけ寝るわ。
起きたらまた、遊んでやるから…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
