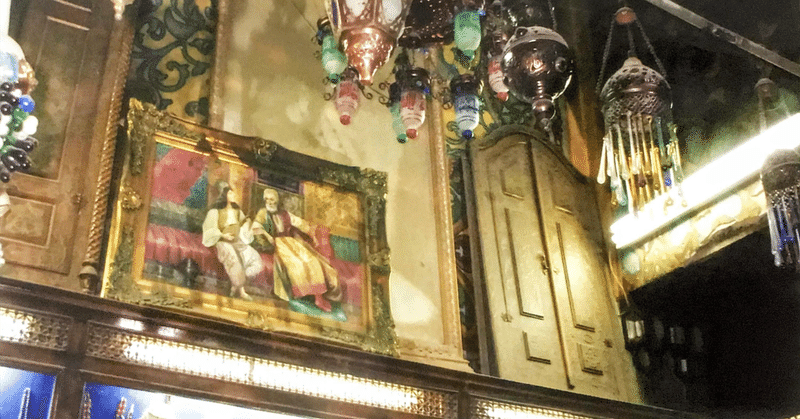
オリエント・中東史㉚ ~ウラービーの乱~
1869年、フランス人レセップスが主導して開削を進めたスエズ運河が、10年にわたる難工事を経て開通した。地中海と紅海を結び、東西航路に革命的な効率化をもたらした運河の開通だったが、一方でその開削の過程には、多くのエジプト農民の無償労働と2万人にも及ぶ死者の累積があった。しかもエジプトは運河建設の資金調達のために発行した外債の支払いのために財政破綻し、運河経営の主導権は株式買収の形でエジプトからイギリスへ移り、結果的に英国によるエジプトの半植民地化を促進することになった。こうした中でエジプトでも反帝国主義の民族運動が起こった。後にイランのタバコ・ボイコット運動を指導することになるパン・イスラム主義のウラマー(イスラム法学者)であるアフガーニーの影響を受け、1881年に陸軍将校のウラービーが「エジプト人のためのエジプト」をスローガンに掲げて革命を起こしたのだ。
アラブ民族の独立と立憲政治の樹立を目指すウラービーは、議会制の導入・外国軍の撤退・自国軍の増強などを主張し、英国への従属に陥っていたエジプト副王政府を動かして憲法制定にまでこぎつけた。だが、翌年に英国が軍事介入して運動を鎮圧。ウラービーは逮捕されてセイロン島へ流され、エジプト初の「革命」は「反乱」として処理された。その後、エジプトは英国の軍事占領下に置かれ、実質的な植民地としての保護国化へと向かうのだが、ウラービーの蒔いた種は、20世紀におけるアラブ民族独立運動へとつながっていった。
ウラービーの乱と同じ頃、日本でも自由民権運動が始まっていた。欧米列強との不平等条約の改正を国是として掲げる日本にとっても、エジプトの革命とその失敗は他人事ではなかった。明治政府で大臣秘書官として欧州視察に随行した柴四朗は、帰途にセイロン島に立ち寄ってウラービーと面会し、帰国後に東海散士の筆名で政治小説「佳人之奇遇」を著した。彼は作中でウラービーの口を借りて、外債に絡め取られた植民地化の危険性に警鐘を鳴らしている。20世紀初頭の日露戦争における日本の勝利は、列強の一角である大国ロシアをアジアの小国が打ち負かしたということで、中東地域の民族運動にも大きな刺激をもたらしたが、当の日本はアジアに対して列強と同様の植民地政策に乗り出し、日清・日露の両戦争を経て急速に帝国主義国家への傾斜を強めつつあった。帝国主義諸国の利害の対立と激化する民族主義運動は世界各地で加熱し、戦争の世紀と呼ばれた20世紀の惨事を連鎖的に引き起こしていくのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
