
最古級の大名庭園

東京都の文京区にある、小石川後楽園です。
寛永六年(1629年)、水戸藩邸の中で造られ、非常に広大で格式の高かった庭園です。
そして、現在に残る最古級の江戸の大名庭園でもあります。
園内に入ると、

大きな池の後方に、東京ドームが見えました。
かつては、水戸藩邸の書院があった所に建っています。
現在、小石川後楽園は2万坪の広さを有していますが、今は無き水戸藩邸は、小石川後楽園を含めるとかつて8万坪以上の広さがあったようです。
この小石川後楽園は、池のまわりを一周しながら、移りゆく風景を愛でる日本庭園です。
園内を1周すると、景色が驚くほど変わっていきます。

巨木の森

水面に小石がちらばる川。京都の嵐山がモデルになっています。

朱色の反り橋が架かっている、懸崖( けんがい )の渓谷

円月橋( えんげつきょう )、水面に映る姿を合わせると円に見えます。
後の世に、徳川幕府八代将軍・吉宗公の財力と権力をもってしても、同じ精度の石橋が作ることができなかったという脅威の石造技術です。
駒場 嘉兵衛( こまば かへえ )という石工によって作られたと伝わっています。
いかにも中国趣味なのは、当時の水戸藩のブレーンでもあった朱舜水( しゅしゅんすい )と、彼を重用した二代目水戸藩主・水戸 光圀( みと みつくに )の意向によるものです。

水戸藩邸の、書院庭園の中島に生えている松


おおらかな曲線を描いた、池の汀( みぎわ )

丸石が敷き詰められた、池の汀( みぎわ )に並んだ飛石


池に浮かんだ、木々の茂る島

大きな池は、琵琶湖を表現しているとも、大海を表現しているとも云われています。
そんな小石川後楽園で、

東京都さんが主催する通訳案内士養成講座で、案内をさせてもらいました。
参加者は40名以上、園路が狭かったので案内がスムーズにできない時もありましたが、みなさんの眼差しと姿勢に圧倒されました。
案内人冥利につきる一時でした。
それから午後に、会場をうつして、


日本庭園の歴史と変遷の、2時間の講義をさせてもらいました。
小石川後楽園は、たくさんの手入れが潤沢に行われていることもあり、年々魅力的になっていることを感じます。
その庭園を、これからたくさん訪れるであろう海外の人々に通訳案内士さんたちが案内をされることを思うと、すごくワクワクしました。
ここから先は
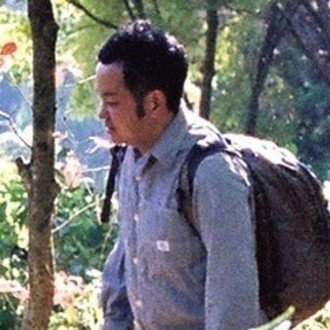
forest forest
今までのアーカイブはコチラ→ https://www.niwatomori.com/forest_forest_map/ 森の案内人・三浦…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
