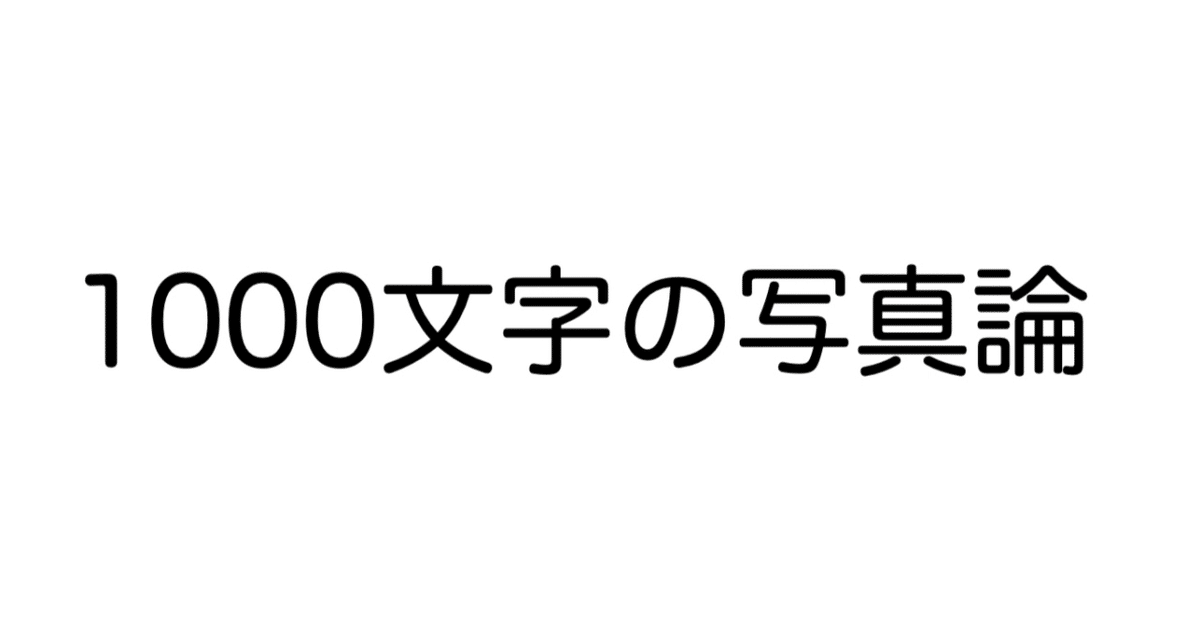
1000文字の写真論
4 写真の土壌、「平面」と「枠」
前回、写真の描写には「制約」があり、よく考えれば「土壌」といわれるものではないかとして筆を置きました。今回はその点を考えてみます。
写真には確実な制約がまずあります。それは、実際に私たちが立体のものとして見たものが「平面」に置き換えられているということです。もちろん3Dカメラというものもありましたが、補助装置に助けられての「立体感」でした。またホログラムというものもありますが、これは「平面写真」に光の位相情報を加え「立体的に見せる」というものです。では平面、二次元としての写真は私たちにイメージとしてどんなことをもたらしているでしょうか。
みなさんの部屋のテーブルにメロンが一つ載っていると想像してください。1メートルほど離れて写真を撮ります。写真には。メロンがある程度「丸いもの」として写ります。しかし、これはただの円のような「形」ではなく立体的な「形態」として認識できるはずです。さらにそのメロンの前後に「奥行き」も感じられますと、その部屋の空間がイメージとして表されていきます。
平面化することでモノとモノ、モノと場の関係を私たちが経験やイメージを総動員して細かく読み取っているのです。平面化は「制約」でありながら、ここを豊かにしていくことで、その産物である写真表現はとても実りあるものになってきます。「土壌」としたのはそういう未来への可能性として考えていただきたいからです。
また写真の平面化は「枠(フレーム)」を伴っています。しかしそれは単に物理的に閉じ込めただけのものでなく、枠外の世界、動き、広がりをも想像させるものであるということを忘れてはなりません。もちろん写真プリント上の枠だけでなく、カメラのファインダーという枠もここに重なります。
写真表現をより自由度の高いものとして考えていくためには、この枠を「絵画」のキャンバスと同じようなものとして捉えなくともよいのではないかということもいえます。「映画(動画)」ほどではないが常に変化をもたらすものとして認識していくことで生き生きとした現実も手に入れることができるかもしれません。特にスナップショットはその点に支えられた一つの方法でしょう。
写真の土壌をさらに豊かなものにするための「時間」と「焦点」については次回にお話ししましょう。

古くから様々な読者に支持されてきた「アサヒカメラ」も2020年休刊となり、カメラ(機材)はともかくとして、写真にまつわる話を書ける媒体が少なくなっています。写真は面白いですし、いいものです。撮る側として、あるいは見る側にもまわり、写真を考えていきたいと思っています。
