
『天晴!な日本人』 第86回 「グレート・エンペラーと称された、偉大な明治天皇」(1)
<『天晴!な日本人』、発売中です!>
拙著、『天晴!な日本人』、発売中です!
おかげさまで「じっくり、堅実に」売れているとの連絡が編集者よりありました。
皆さんのおかげです。感謝しています。
今後も、アマゾンのレビューへの投稿も待っています!よろしく!

<本文>
<新しい天皇像を創る!>
今回の『天晴!な日本人』は、これぞ明治を象徴する、というより、「明治そのもの」の明治天皇、その人です。
明治天皇は1852年(嘉永5)年9月22日、太陽暦では11月3日に、第121代の孝明天皇の子として出生しました。母親は権典侍の中山慶子です。
慶子は権大納言の中山忠能の2女でした。典侍は、宮中の女官、大納言は律令制度下の大臣の代理であり、権は「副・次」を表しています。早い話が母は側室とも言えるでしょう。子孫を絶やさないため、側室制度があったのです。
明治天皇の名前は睦仁、幼少時は祐宮と言いました。現在の天皇は浩宮と呼ばれていましたね。1852年といえば、ペリー来航の前年です。その時に、外国人、外国、「大・大・大キライ!」の孝明天皇の親王として生まれたのでした。
孝明天皇、非公式では、あの、したたかな岩倉具視の謀略で毒殺されたことになっていますが、これ、真実です。徹底した攘夷論者だったので、岩倉にとっては邪魔だったのです。
そうして、1867(慶応3)年に睦仁親王が践祚、即位します。数え16歳でした。
当初は、おしろいを塗り、眉を描いているお公家さんのような柔弱な天皇でしたが、
「帝は、よろしく英雄でおわしまさねばなりませぬ」
という西郷や大久保の意向で、質実剛健の元・武士たちが側近、侍従として仕えるようになり、天皇の教育も従来とは一変したのです。
天皇は、戊辰戦争の折り、宮殿内に砲弾が流れてきて、炸裂しただけで気絶した人でした。当時は、それが普通だったのです。天皇に勇敢さや、武士の精神など不要でした。
1615(元和元)年に出された『禁中並公家諸法度』という17カ条の法令で、天皇と公家は厳しく統制されていて、天皇の権威も半ば形式上のものになっていました。法令では、天皇がすべきことを、学問・和歌・有職故実(過去の歴史や儀礼を学び継承する)の3点に限定していたほどです。
政治の天才、徳川家康は、権力は徳川幕府に、権威は形式として天皇に、と考えて法令をだしていますが、幕末になるまで、外出すら自由にできなくされるほど、権威も形だけのものになっていたのです。
それを転換したのが、明治維新で創られた新政府で、自分たちの統治の正当性、正統性を担保するために、天皇を担いだのでした。しかし、まるっきり利用しようとしたのではありません。
実際に天皇に本当の権威を持ってもらおう、政治権力は政府が持って、新しい国を創ろうとしたのです。そこで西郷、大久保は宮中改革から始めました。
薩摩出身の村田新八を宮内大丞、今の局長に据え、同じく薩摩出身の吉井友実を送り込み、侍従には熊本藩士だった米田虎雄、土佐藩士だった高屋長祥を入れ、従前の華族の多くをクビにしました。
そうして、次侍従の北条氏恭、高島鞆之助を侍従にし、剛健清廉の側近たちに、代えたのです。
その上で、孝明天皇の女官として権勢を誇っていた女たちを、ことごとく辞めさせ、残った女官を皇后の下に配属させ、彼女たちの権勢をないものとしました。
さらに、若い天皇の教育係として、元田永孚の他、数名を任命し、日本の歴史、『論語』『日本外史』などを講義するようにしたのです。
元田は熊本藩士出身で、後に明治憲法を起草する秀才の井上毅と同じく、勝海舟が、西郷以外で凄い奴と賛辞を贈った思想家の横井小楠の弟子でした。
こうした教育が始まったのは1871(明治4)年6月頃からですが、翌年5月には山岡鉄舟が加わり、1カ月半後には山岡を侍従番長、現代なら侍従長としています。
「当代第一の豪傑が、よろしゅうございましょう」という西郷の勧めでした。
天皇は負けず嫌いな性分で、侍従らと相撲を取ると、勝つまでやめないので、みんな、わざと負けてやる中、山岡は、その巨体で平気でぶん投げ、信頼を勝ち取っています。
山岡の他にも、土佐藩士の佐々木高行を侍従にするなど、周囲を剛直な武士たちで固め、天皇の気風を変えるのに成功したのです。
天皇は乗馬も愛し、精神と共に肉体の鍛錬と軍事にも目覚め、統率者としての自覚をも抱くようになっていきました。特に西郷を愛し、西郷の言葉は金科玉条のごとく胸に刻み、守っています。
ある時、落馬して、「痛い」と口にすると、痛いなど口にしてはいけません、と西郷に叱責され、爾後、終生、痛いとは口にしないどころか、態度にも出さなくなったのです。天皇は、一に克己、二に忍耐の人となりました。
ここから先は
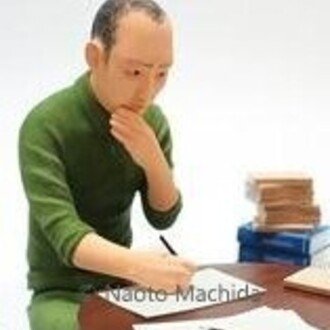
無期懲役囚、美達大和のブックレビュー
書評や、その時々のトピックス、政治、国際情勢、歴史、経済などの記事を他ブログ(http://blog.livedoor.jp/mitats…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
