
『天晴!な日本人』第52回 神算鬼謀の奇才、天才参謀の秋山真之 (4)
八代六郎大佐は、何をしても、八代なら仕方あるまい、と上官が諦める、勇壮で豪快な人です。
真之は、こんな上官であっても戦術の話となると遠慮なく論破しますが、八代は、怒りながらも真之の実力は認めます。
1903(明治36)年春、八代は真之の花嫁を見つけてきました。宮内省御用掛の稲生真履の三女、季子です。
結婚式は同年6月2日、海軍士官・高等文官の親睦を図る社交の場でもある水交社で行われました。真之36歳、季子21歳です。
季子、しっかり者で清楚で美女、良い妻でした。
真之の講義、その一節を紹介しますが、これが軍人の言葉か、というほどのものです。
「戦果はあたかも、草木が春夏に生い茂って花開き、その花散りて後、秋冬に果実を結ぶが如く、戦闘前半期に収め難く、多くは後半期の終わりに多大の収穫あるものなり。この前半期は概して決戦の時期に属し、あたかも春花の爛漫たるが如く、彼我相撃ちて、戦闘の光景、最も激烈を極む」
こんな調子で続くのですが、美文調で、これが戦術の講義かというものです。
真之は、「戦略、戦術の要訣は天、地、人の利を得るにある」と語っています。
天は時、地は場所、人は人の和です。戦闘での攻撃方法には、正法(正攻)と奇法(奇襲)があり、奇法によって効果を発揮するとしていました。
しかし、いつも奇法でいくことはできず、正をもって戦うことの利も説きます。
最終的には、
「戦士たる者は、いよいよ戦場に立つ時は、生死の念を去り、毀誉褒貶にとらわれず、無我の境地に立ち、時相を達観せよ」
と己の信念を用いて締めくくるのが秋山流の講義で、私も聴いてみたかったです。
毀誉褒貶とは、非難と賞讃です。
戦いの場に立てば他者の評価などに囚われず、無我無欲の境地で、目前のことをよくよく見よ、ということですが、生きている間、ずっとこの境地でいることが望ましいのです。
さらに真之は、兵器・装備の進歩の速さを説き、常に研究を怠らないことを奨励します。
こうした優れた講義をしている間にも、ロシアとの関係は風雲、急を告げてきます。
1900(明治33)年の「義和団の乱(北清事変)」以来、満州に居座ったロシア軍が、当初の協定を守らず、撤兵を拒否していたのです。
ここから先は
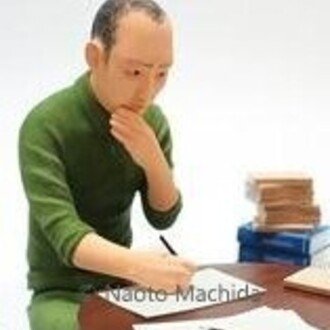
無期懲役囚、美達大和のブックレビュー
書評や、その時々のトピックス、政治、国際情勢、歴史、経済などの記事を他ブログ(http://blog.livedoor.jp/mitats…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
